wallpaper:1
あなたは「恐怖症」というものをご存知だろうか。
有名なものでは「高所恐怖症」や「閉所恐怖症」、ちょっと変わったものでは「ピエロ恐怖症」などというものも存在する。
人間誰しも苦手なものはあると思うが、それによって引き起こされる症状が重度の場合に恐怖症となるようだ。
ところで、恐怖症を発症するのには個人的な理由があることも珍しくない。
一種のトラウマと言ってもいいかもしれない。
wallpaper:1
wallpaper:1
これは、少し変わった恐怖症をもった知人の話である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
nextpage
約束の時間の10分も前に駅に到着した私は、缶コーヒーを買うべく駅構内のコンビニに立ち寄った。
クリスマス間近という事もあってか、行き交う人々はカップルが多いように見えた。
もっとも、イメージからそう見えているだけかも知れないが。
コーヒーを購入した私はそのまま待ち合わせの方の出口へと向った。
予報ではそれほど気温が下がらないと聞き防寒対策を怠った私は、思いがけず冷たい風に顔をしかめた。
薄いコートの前を閉じ、ひとまず風が当たらない場所を探そうとしたところで、人ごみの中に見知った顔を見つけた。
約束の1時にはまだ10分も前だったのだが、どうやら向こうも早く来たようだった。
声をかけようと口を開きかけたが、年甲斐もなくイタズラをしたい衝動に駆られ、正面ではなく後ろから忍び寄った。
「......やあ、久しぶり」
声をかけるまで本当に気付いていなかったようで、その女性は文字通り軽く飛び上がった。
予想よりも良い反応に可笑しさがこみ上げる。
だが、様子がどうも変だ。
向こうも笑ってくれることを期待していた私は、彼女の眉が釣りあがっているのに気付き慌てて謝る羽目になった。
彼女は私の中学時代の友人である。
近況報告会として久しぶりに会うことにしたのだが、どうも私の悪ふざけが最悪の再会にしてしまったようだ。
私はなんとか謝りつつ、目的地のカフェへと向かった。
カフェに着いた時点でようやく許しを得た私は、そんなに怒るとは思わなかったと笑ってみた。
すると、思いがけない返答が帰ってきた。
彼女は誰かに追いかけられるのはもちろん、自分の後ろをついて来るように歩かれたり、すぐ後ろに立たれたりすることにすら恐怖を感じるという。
もちろん赤の他人が何もしてこないのは百も承知だが、それでも耐えられないのだそうだ。
もしや、とも思ったが本人曰くストーカー被害にあった経験はないらしい。
結局思い当たるフシも無く、その後話題は中学での思い出へと変わっていった。
自分ではそう忘れっぽい方ではないと思っていたのだが、人の記憶とは何と雑なものか。
話せば話すほど忘れていた思い出が鮮明に浮かび上がってきた。
そんな私たちの懐かしの話題が尽きることは無く、気がつけば日も傾き始めていた。
nextpage
それはレモンティーを飲み干した私が、そろそろ店を出ようかと考えていた時だった。
話も一段落して、紅茶をかき混ぜていた彼女がふと思い出したように口を開いた。
「そうだ、ケンくんって覚えてる? ほら、2年の時同じクラスだった」
「健......ああ、うん覚えてる」
「それがさー、なんかあの子.............」
言いかけて、彼女は紅茶から顔を上げたままの状態で固まった。
目を見開いたまま窓の一点を見つめているようだったが、あたかも時が止まったかのようにティースプーンを持ったままの手もピタリと静止していた。
あまりに突然の異様な挙動に戸惑った私は、咄嗟にかけるべき言葉が見つからなかった。
「お、おい、どうした?」
口が小さく動いているのが分かる。
視線は相変わらず窓の外の何かに釘付けになっているようで、私もすぐにその視線の先を追いかけた。
ーしかし
燃える陽に照らされた道路は、特に何の異常もないように見えた。
赤信号で停車中の自動車と、奥の十字路を行き交う人々。向かいの雑貨店も通常営業中である。
ただ何と無く、そのとき彼女は何かを「見て」しまったのではないかと予想した。
すぐそちらの方に考えが及ぶのは、オカルト好きの私の悪い癖だ。
彼女には霊感はないはずだが、もしそうだとしたらその類が大の苦手だった彼女ならあり得る反応だ。
まだ見えるかも知れないと、じっと目を凝らす。
青信号に変わって発進した車
駐車された赤いマウンテンバイク
テナント募集中の雑居ビル
目に留まるのははごく普通の日常風景だ。
事の真相を確かめようと彼女に向き直り、私は更なる驚きに見舞われた。
彼女はつい2分前とは打って変わって、青い顔をしたまま俯いていた。
心なしか手が震えているように見える。
何がなんだかさっぱり状況の掴めない私は、そのただ事ではない雰囲気に、ひとまず自宅まで送る事にした。
救急車を呼んだ方がいいかとも思われたが本人が大丈夫と言うので、店を出たところでタクシーを捕まえた。
夕暮れ時の市街はあっという間にその光度を落とし、対照的に信号機の赤が煌々と輝きだした。
私のコートを余分に掛けた彼女は、運転手に目的地の住所を告げ、私に何度か礼と謝罪を言うとしばらくじっと固まっていた。
見れば、唇も色を失っている。
耐え難い何かに耐えているのが伝わってきたものの、今はそっとしておいた方が良いという結論に至り、夜の気色を帯び始めた街並みを何となく眺めていた。
眺めるとはいっても先の出来事に対する疑問に頭を支配されてしまっており、流れて行く風景など全く見えてはいなかったが。
そして恐らく、その対応は正しかったのであろう。
しばらくして幾分落ち着いた様子の彼女が、車内の重い沈黙を破った。
「......さっきは驚かせてごめん。ビックリしたよね」
「いいよ、それより具合は?」
「うん、結構良くなった。ありがとう」
「また辛くなったらすぐ言ってくれよ?」
コクリと小さく頷く彼女に私はどうにか、何があったのかという言葉を飲み込んだ。
今じゃなくていい、何も今じゃなくても。
また落ち着いたら話してくれるだろうし、下手に詮索しない方がいい話かも知れない。
そう考えあえて聞くのを避けたのだが、実は聞かなかった理由はもう一つある。
状況からして、既に一つの納得のいく結論を得ていたからだ。
それは霊的なものなどではなく、ずばり
ー生理痛である
男の私には詳しいことは分からないが、それなら突然の体調不良の理由がつくし、進んで理由を話したがらないのも頷ける。
もしかしたら今日は初めから無理をさせていたのかもしれない、と勝手な推測で勝手に申し訳なく思っていたところ、そんな気持ちを知ってか知らずか彼女が静かに口を開いた。
「やっぱり、気になるよね? 何があったか」
「まあ......でも無理に言うことはないぞ」
「いや、ううん、言わせて」
「分かった。聞こう」
ふーっと一つ息を吐くと、何かを決意したかのように話始めた。
「......道路にさ、自転車が停めてあったの分かった?」
......自転車?
言われて見れば、道端に赤いマウンテンバイクが停まっていた気がする。だがそれとこれと何の関係が......?
「うーん......あのマウンテンバイクみたいなヤツか?」
「そう......」
一呼吸空けて、こちらを見た彼女と目が合った。
ー実はね、マウンテンバイクがどうしようもなく怖いんだ。
真顔でそう言い切った彼女は少しだけほっとしたように見えた。
だが対する私には、全くもって意味が分からない。とても冗談を言っているようには見えないが......。
ただ、私の論理的推察が大外れだったということは理解出来た。
頭上に巨大な疑問符を浮かべた私を見て、彼女はぽつりぽつりと話し出した。
ー笑われると思って、誰にも相談したことは無かったんだけどね
マウンテンバイクを見ると、すぐに気分が悪くなって吐き気がしてくるんだ......
でもそれは、私がマウンテンバイクで大怪我をした事があるからとか、つい事故を想像しちゃうとか、そういうんじゃない
子供の頃からずっとそうだったんだ
もし見ちゃってもこれほど具合が悪くなったことはなかったんだけど...
......何て言うのかな......ただ、ただ怖いんだ
理由とか、自分でも全然分からなくて
......ふふっ、変だよね
私でも何言ってんだろうこの人、って思うもん
自嘲気味にそう笑った彼女の様子からは、今まで本当に苦しんできたのであろうことが伝わってきた。
それは決して冗談や悪ふざけではない、リアルな恐怖だった。
「......大変、だったな...」
全く予期しない展開に、月並みな言葉しか返せない自分に腹が立ったが、それでも彼女は嬉しかったようだ。
「......ありがとう......笑わないで聞いてくれたから、嬉しかった。それに他の人に話せてなんかスッキリした」
その特異な悩み故、今まで相談もできずに一人で苦しんできたのだろう。
そう考えるといたたまれない気持ちになり、話を聞いた縁で相談相手になろうと申し出た。
ところが丁度そのとき彼女のマンションに到着してしまい、結局深い話は出来ずじまいだった。
また何かあったら連絡をするということで、彼女は私に礼を言うとそのままマンションに消えていった。
nextpage
......マウンテンバイク恐怖症。
確かに普段の私なら笑って流していたかもしれない。
だが今の私には笑い飛ばすことなど到底出来なかった。
とはいえ心の何処かで、そう大した問題では無いだろうと思っていた自分がいたのも事実だ。
そのとき私は、そこに哀しい真実があるなどとは到底知る由もなかったのだから。
nextpage
彼女から連絡があったのは、それから一週間後の事だった。
着信があったのは確か、午後5:40ごろだったと思う。
開口一番、電話が繋がるなり彼女は震えた声でこう言った。
ーわかった......全部、分かった
と。
nextpage
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「その」日も、私は学校が終わるなり急いで家に帰った。
家といっても自宅ではなく少し離れたところにある祖母の家だ。
共働きの都合上、どうしても金曜日の午後は家が空いてしまうようになった。
まだ小学校低学年の娘に一人で留守番させるという訳にもいかず、金曜に限って私は祖母の家にお世話になっていた。
祖母はいつも私を歓迎してくれたし、好きなお菓子も買ってくれた。
私はそんな優しい祖母が大好きだった。
しかし通っている小学校とは違う学区内ゆえ、その近所では友達が出来なかった。
祖母と外で遊ぼうにも散歩以上のことは不可能で、子供の私にとっては正直少し退屈だった。
だが、ある日そんな私にも遊び相手ができた。
それは祖母の家の近所に住んでいた、中学生のお兄さんだった。
散歩の途中で知り合って以来、彼は私と遊んでくれるようになり、唯一の遊び相手であった彼と遊ぶことが私の大きな楽しみだった。
彼は小さい私を本当の妹の様に接してくれたのだが、私の知るその姿はいつも一人だった。
そして、彼はいつでも家にいたのだ。
まだ幼かった私には不登校が何を意味しているのか、良く分からなかった。
私にとってはただ、楽しく遊んでくれる存在だったのだ。
一週間に一度、金曜の午後に彼と遊ぶ。
そんな生活が始まって、約半年が過ぎたある日。
その日、彼は出てきてくれなかった。
次の週も、その次の週もまた。
遊ぶことは叶わなかった。
そして、その翌週。
wallpaper:1
wallpaper:1
「その」日がやってきた。
季節柄もうずいぶん気温も下がり、日が短くなっていた。
日が暮れたら家に帰らなくてはならない。だから、彼と会えるのは学校が終わってから日が暮れるまでの間だけだ。
彼に会いたい一心で、集団下校の班を振り切って帰り道を駆けた。
その日はなぜか会えるような予感がしたから。
冷え切った空気が容赦無く顔に当たって抜けていった。
息を切らしながらもどうにか祖母の家に到着した私は、荷物を置くのももどかしくそのまま彼の家に走った。
頭上では冷たく澄んだ空が、傾き出した陽によって徐々に赤らみ始めていた。
程なくして彼の家が見えてきた。
ーしかし
やはりそこには私を待つ彼の姿は無かった。
期待の分だけ、落胆は大きい。
もしかしたら嫌われてしまったのかもしれない
もう遊んではくれないのかもしれない
すっかり沈んだ私はインターホンを押す気にもなれず、諦めて帰ろうかと後ろを向いた。
丁度その時。
ーカチャ.......
控えめに扉を開く音が聞こえた。
驚いて振り向いてみたが、薄赤い光を帯びた玄関は無言のままだった。
すると
ー............パタン
今度は静かに扉を閉める音が聞こえた。
ここで私は、ある可能性に思い至った。
それは玄関と丁度真反対にある勝手口だ。
私は一度だけその家の裏側を見せてもらったことがあった。
陽当たりは悪くないものの、通りからは死角になる場所であった。
そこにあるのは物置と、彼のお気に入りの自転車だけだ。
きっとそこに彼がいる
やっと会えるんだ
私は期待に胸を膨らませ、家の脇を通り抜けて裏口に向かった。
あの角を越えれば、また......。
満面の笑みで裏口に辿り着いた私を待っていたのは、物静かな少年ではなかった。
それは想像を絶する光景だった。
wallpaper:61
ー赤
そこには、夕陽のそれを超える鮮烈な赤があった。
すなわち、血の赤。
あれほど会いたいと願った彼は、赤の中心でうつ伏せに倒れていた。
彼の周囲は浸み出し、飛び散り、広がり、塗られた赤色で溢れている。
そして彼の下敷きになった白いマウンテンバイクには、鮮血がまだら模様を描いていた。
彼の手はまるでマウンテンバイクにすがるように、痙攣しながらその車体をきつく握りしめていた。
鮮明な視覚情報が最初に脳になだれ込み、次いで鼻につく鉄のにおいを感じた。
「......う.........あ............」
まさに心臓が止まる程の衝撃を受けた私は、その地獄絵図から目をそらすこともできなかった。
平衡感覚を失い気が遠のいていく中で、夕陽に灼かれたその強烈な赤さだけがいつまでも目に焼き付いていたのだった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
nextpage
その自殺現場は自宅にいた少年の母親によってすぐに発見され、彼は病院に救急搬送された。
ーしかし少年は助からなかった
そして現場を目撃した幼い少女もまた、心に深い傷を負った。
まともに会話ができるようになるのに丸2日を要したという。
彼女の両親は心のケアに尽力し、なんとか忘れられるようにと願った。
人間は極度の心的外傷を負うと、自己防衛本能によりその記憶を封印することがあるという。
その少女もそうだった。
おぞましい記憶を封印し、日常生活に全く支障のないレベルにまで回復した。
ーだが
強烈な赤と血塗られたマウンテンバイクのイメージは、消し去ることが出来なかった。
「赤」と「マウンテンバイク」
それらは恐怖の記憶を呼び起こすトリガーとして心の内に残り続けたのだった。
nextpage
wallpaper:1
以上が、彼女を苦しめたマウンテンバイク恐怖症の真相である。
彼女が母親に恐怖症のことを打ち明けたところ、母親は真っ先にこの出来事に思い至った。
辛い記憶もいつかは話さなければならない。そう思っていた母親が真実を話し、そして彼女は全てを思い出したという。
現在はその記憶と向き合い、乗り越えようと努力している最中らしい。
nextpage
もしかしたら、あなたの周りにも変わった「恐怖症」を持つ人間が居るかもしれない。
もし出会ったならどうか、配慮ある言動をお願いしたい。
そこには想像も出来ないような理由が、隠されているかもしれないのだから............




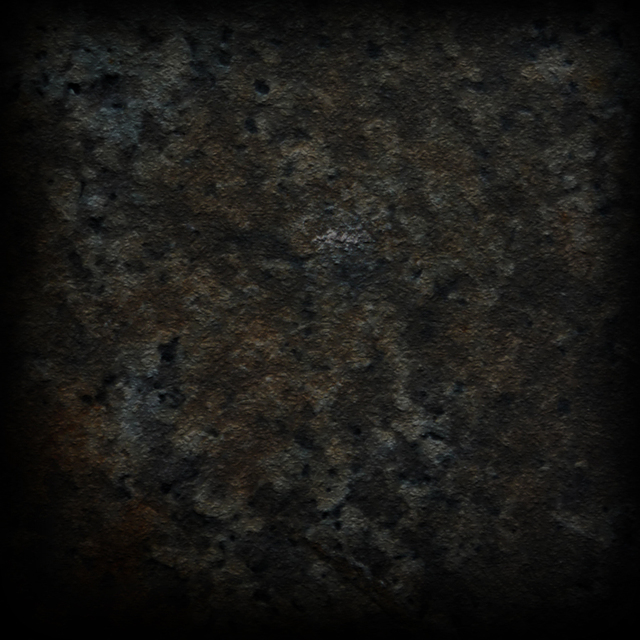
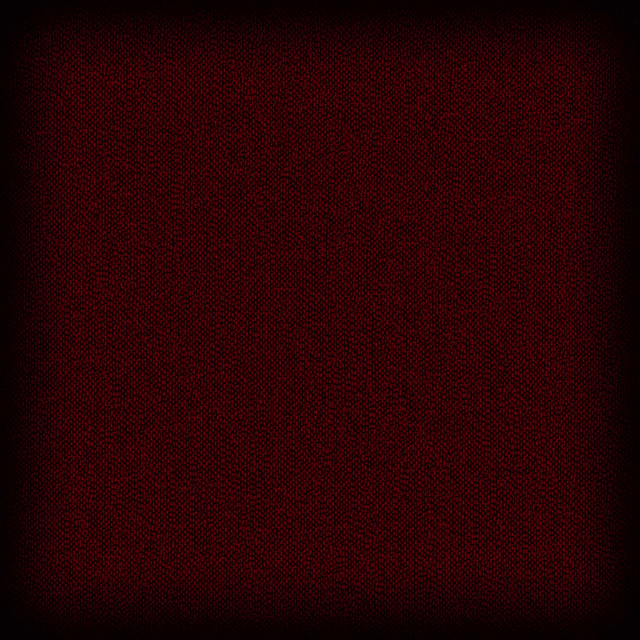
作者ダレソカレ
こんにちは、ダレソカレです
新年いかがお過ごしでしょうか
またもや長文、さらに読みにくい文になってしまいましたが、暇つぶしに読んで頂けたら嬉しいです
タグ、コメント、怖い等大歓迎です
2014年も皆様にとって良い一年になりますように
追記
コメント、怖いを下さった方々、誠にありがとうございます。心より感謝申し上げます。(コメント欄でのお返事という無礼をお許し下さい)