同じ会社で働く真弓は私と同期だ。背が高く、モデル並みにスタイルがいいのだが、性格は引っ込み思案で暗い。職場でも特別に仲がいい人間はいないらしく、孤立している。
真弓は俗に言うスマホ依存症だ。仕事中、パソコンと向き合っている時も、トイレに行く時も、昼休みもスマホをずっと弄っている。仕事が終わればまずスマホを確認し、その足でエレベーターに向かう。
そんな彼女の様子を横目でチラリと見たことがあったのだが、どうもメールを打っているようだ。
暗い性格の真弓に、彼氏がいるのだろうか。あんなにもスマホと睨めっこしているのだから、きっと彼氏と連絡を取り合っているに違いない。彼氏と別れたばかりの私は、女としての軽い嫉妬を感じるようになっていた。
ある日のこと。私と真弓は夜遅くまで二人で残業をしていた。ふと見ると、やはり真弓はパソコンから目を離し、スマホを弄っていた。
「……ねえ、真弓。スマホは仕事が終わってからでもいいんじゃない?」
真弓のデスクに向かって声を掛けた。真弓はゆっくりと顔を上げ、パソコン越しにジッとこちらを見た。
「ごめん。でも、どうしても返さなくちゃならないメールがあって」
「どうせ彼氏からのメールでしょ。仕事が終わってからでいいじゃない。今はとにかく次の会議で使う資料をーーー」
「そうじゃないの」
私の言葉を遮るように言うと、真弓はカタンと立ち上がった。そして足音も立てず、静かに近付いてきた。目を見開いて。
「二年前の、夏のことよ」
二年前の夏のこと。真弓には付き合っている男性がいた。彼は大のオカルト好きで、毎年夏になると心霊スポットに出掛けることが趣味だった。
その日も彼氏に付き合わされ、とある小さな町にあるトンネルへと車で向かっていた。そこは地元では有名な心霊スポットであり、夜な夜な子どもの声がするとか、悲鳴が聞こえたという噂が絶えないのだという。
真弓は心霊やオカルトが苦手だった。だから本当は行きたくなかったのだが、彼氏があまりにもしつこく誘うので、とうとう根負けしたのだった。
しかし。いよいよトンネル付近に近付いてきたところで、真弓は早くも弱音を吐いた。
「やだ。やっぱり行かない。怖いもん。帰ろうよ、ねえ」
「何言ってんだ。もう着くよ。目と鼻の先だぜ?」
「やだ!私、やっぱり行きたくない。ここで停めて。車の中で待ってるから、行くなら剛だけで行って」
「ったく、仕方ないな」
彼は舌打ちすると、車を路肩に停めた。トンネルまであと五十メートルあるかないかといった距離だった。
助手席で震える真弓を尻目に、彼は「すぐ帰ってくるから」とだけ言い残し、車を降りた。真弓は小さく頷いた。
彼がトンネルに向かってから三十分が経過した。まだ帰ってこない。何度か彼の携帯に電話してみたのだが、留守番サービスに繋がるだけだ。
一時間が経過し、二時間が経過し……真弓はだんだん不安になってきた。幾ら何でも遅過ぎる。すぐ帰ってくると言っていたのに……。相変わらず、電話にも出ない。だが、自分でトンネルまで行って中の様子を確かめる気にはなれなかった。
三時間が経過した。彼は帰ってこない。とうとう真弓は警察に通報した。
駆け付けた警官らに付き添われ、真弓はトンネルまで向かった。トンネルの前に立つと、中からゴウゴウと風の唸るような音がする。一寸先も真っ暗で何も見えない。空間にポカンと空いた異次元に通じる穴を想像し、真弓は背筋が寒くなった。
トンネル内を捜索したが、彼は見つからなかった。結局、ただの失踪ということで話は片付けられてしまった。苦虫を噛み潰したような顔をしている真弓に、一番年嵩の警官がこんな話をしてくれた。
ーーー今から十年くらい前のことです。近所に住む子どもらがね、このトンネルでかくれんぼして遊んでいたんですよ。
都会と違って、近くにゲームセンターもなければ公園もない。このトンネルは随分昔に閉鎖されたんだけれども、子どもらにしてみれば恰好の遊び場だったんでしょうね。
だがね、遊んでる最中に落盤があったんです。あっちゅう間のことでねぇ……ドーンと大きな音がして。慌てて駆け付けたんだけれども、間に合わなかった。可哀想に……一人も助からなくてね。
それからですよ。トンネルの近くを通りかかると、子どもらの声が聞こえてくるようになってね。「もういいかーい」、とか「もういいよー」ってね。
急な事故でしたからな。きっと子どもらは自分達が死んだことにも気付かず、今もまだトンネルの中で遊んでるのかもしれません。
あなたの恋人も、もしかしたら子どもらに魅入られてしまったのかもしれませんねぇ……。
そこまで話し終えると、真弓は長い長い溜め息をついた。
「彼がいなくなってすぐのことよ。メールが来たの」
差出人は彼だった。彼は無事だったのかと安堵しながらメールを開く。そこにはたった一言、こう書かれてあった。
“もういいかい“
はじめはふざけているのかと思ったが、日に何度も同じ内容のメールが届くようになった。真弓はそのメールが届く度、速攻で返信した。
“まーだだよ“
「……そう返信しないと、彼が迎えに来ちゃいそうな気がするの。一日中落ち着かないのよ。トイレに行ってても、食事をしていても、仕事をしていても、ひっきりなしにメールが届くんだもの。分かる?彼が来ちゃうのよ。だから私、スマホが手放せないの」
真弓の手の中にあるスマホが鳴った。真弓は「ほらね」とでも言いたそうな目で私を見た。
「じゃ、私はまだ仕事があるから」
真弓は踵を返してデスクへと戻った。話をしている間、真弓は一度たりとも瞬きをしていなかったことに私は気付いた。
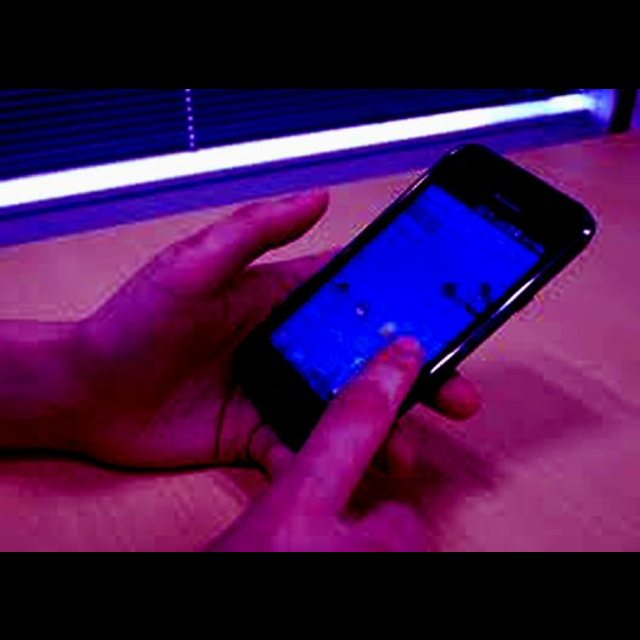





作者まめのすけ。-2