僕は相手と顔を合わせて説得したいと思った。
顔を合わせて話し合えば、相手はきっと理解して受け入れてくれるはずだ。
そして、僕たちを祝福してくれるはずだ。
◇
その日、たまにコーヒーを飲みに行く喫茶店は客がまばらだった。
店員が注文したアイスコーヒーの入ったコップを三つ置き、頭を深く下げて立ち去った。
「この店のコーヒー、おいしいんだよ」
僕はコップにガムシロップとミルクを注ぎながら、正面に座る角田に話しかけた。
「優子もここのコーヒーをお気に入りなんだ。だよね?」
僕はコップの中をストローでかき混ぜながら、隣に座る優子に話を振った。
優子は僕をジロッと見たが、僕と同じようにガムシロップとミルクをコップに注ぎ、いつもより短めにかき混ぜてからストローに口を付けた。
角田はガムシロップやミルクを入れずにストローに口を付けた。
「角田君はブラックでコーヒーを飲むんだね」
今度は笑いながら話しかけたが、角田はちらっと優子を見ただけで、それ以上の反応を示さなかった。
僕は春の柔らかな日差しが注ぐ窓の外に視線を逃した。
しばらくして、優子から膝を叩かれた。
喉が渇いていたのか、角田のコップにはコーヒーが半分しか残されていなかった。
「それでね、角田君。僕は角田君をここに呼んだのは……」
「優子さんを諦めてくれという話ですよね?」
角田が震えた声で言った。
僕は優子と顔を合わせる。
優子の僕を見る目が苛立っていた。
「はっきり言ってしまえば、そういう話だ」
「どうして僕が優子さんを諦めなくちゃいけないんですか?」
「それは優子から角田君に伝えた通りだ。僕と優子は結婚を前提とした交際をしている。僕と優子の家族も僕たちの交際を認めてくれているんだ」
優子から同じ職場で働く角田から交際を申し込まれたと相談を受けたのは数か月前だ。
相談を受けた僕は当然のように断るように伝えた。優子は当然のように断ると答えてくれた。しかし、角田は引き下がらなかった。
優子は上司や同僚にも相談し、相談を受けた上司や同僚は角田を諭してくれたらしい。しかし、角田は優子を諦めなかった。
そんな中、優子が自宅アパートの付近で角田を目撃したと僕に言ってきた。実は本当に角田だったのかがはっきりしていない。角田がそれを認めなかったからだ。
そこで僕は角田を呼び出すことにした。怖がる優子の不安を払拭させるため、そして、角田に諦めるように説得するためだ。
今日が初対面とは言え、角田は僕より年下だ。優子から教えてもらった通り、言葉は悪いが、青白い顔をして弱そうな男だ。これなら時間を掛けずに説得できそうだ。
「だからといって、僕が優子さんを諦める理由にはなりませんよ」
「角田君、僕の話をよく聞いて。僕と優子は結婚を前提とした交際をしている。僕と優子の家族は僕たちの交際を認めている。それを聞いて、諦めない理由なんてあるのかい?」
「……」
角田はストローを強く噛みながらコーヒーを飲んだあと、黙って僕を睨んだ。
優子が僕の耳元で、気を付けて、と囁いた。
僕は優子に頷いてから、角田に話を続ける。
「客観的に現状を見てみよう。僕が角田君から優子を横取りしたら、僕に非がある。でも、今回の場合はどうだい。立場がまったく逆じゃないか。角田君が優子に交際を申し込んだとき、すでに優子は僕と交際していた。それでも僕に非があるのかな?」
「……じゃあ、僕に非があるというんですか?」
「そこまで強く責めるつもりはない。ただ、冷静に現状を判断して行動をしてくれ、とお願いしているだけなんだ。そうでないと、お互いが不幸になっちゃうよ。そうは思わないか」
「……」
「僕は優子を愛してる。優子も僕を愛してくれている。わかってくれないかな」
ここまで言えば、みなまで言わなくても分かってくれるだろう。
僕は角田が頭を下げ、優子を諦めると決心してくれると信じた。
しかし。
「なら、僕からも訊いていいですか?」
角田が目を剥いた。
隣に座っている優子が小さく悲鳴を上げた。
僕は安心させるように優子の肩を叩いた。
「なんだい?」
「丸木さんが優子さんを愛しているという証拠を見せてくれますか?」
僕の名を呼んだ角田の声が上擦っていた。
「証拠って……いま説明した通りだよ」
「それでは納得できません。丸木さんが優子さんを愛しているという証拠を見せてください」
僕は思わず苦笑した。
こいつは苦し紛れに何を口走ってるんだろう。
往生際が悪い奴だ。
「僕は角田君の前で優子を愛していると言った。それ以上の証拠はないよ」
「僕はそれを証拠だとは納得しません。だから、丸木さんが優子さんを愛しているという証拠にはならないんです。つまり、丸木さんは優子さんを愛していないんです」
こいつ、何を言ってるんだ?
「ちょっと待ってくれ。角田君が納得しようしまいが、僕たちは愛し合っているんだ。優子だって僕を愛してくれている」
「だったら、優子さんが丸木さんを愛しているという証拠を見せてください」
角田が不敵な笑みを浮かべて優子を見た。
優子は怯えながらもはっきり断言した。
「私は丸木さんを愛しています」
しかし、角田は不敵な笑みを浮かべたままだった。
「では、その証拠を見せてください」
「だから、私は丸木さんのことを愛して……」
「言葉だけでは証拠にはなりません。つまり、優子さんも丸木さんを愛していないということになりますね」
こいつと話をしていると頭がおかしくなってくる。
「角田君、あのね、それは君が納得できないから僕たちの愛を否定しているだけだよね?」
「だったら、二人が愛し合っている証拠を見せてください」
「だから、さっきから何度も……」
「証拠を出せないなら、二人は愛し合っていないということになりますね」
なんなんだ、こいつは。
優子が断っても、優子の上司や同僚が諭しても、角田が引き下がらなかった理由を垣間見た気がした。
「いい加減にしろよ。お前が納得しようがしまいが、僕たちには関係ないんだ」
「もう帰ろう。相手にしても時間の無駄よ」
優子が立ち上がって僕の腕を引っ張った。
しかし、僕は立ち上がらなかった。
ここまで馬鹿にされて、角田に背を向けて帰るわけには行かない。
「なら聞くけど、角田君は僕たちが愛していない証拠を出せるのか。証拠を出せるわけがないだろう。そうと違うか?」
「そんな言い方は有り得ないですよ」
「なんでだ?」
「だって、僕が証拠を出すまでもなく、丸木さんと優子さんが愛してないということがわかったんですから」
「なにを証拠にそんなことを断言できるんだ?」
「二人が愛しているという証拠を出せなかったじゃないですか」
「だったら、なにを証拠にすればいいんだ?」
「それは僕が考えることではないですよ」
のらりくらりと逃げやがって。
こいつはサイコパスか何かか?
なんで僕たちがこいつに納得させるような証拠を見せなくちゃいけないんだ?
僕は角田を威嚇するように感情に任せてテーブルを叩いた。
店員や客の驚いた視線が僕に突き刺さるのを感じた。
しかし、角田は可笑しそうに笑っただけだった。
「なにがおかしい?」
「丸木さんが優子さんを愛さなくてはいけない証拠を見せてください」
「これ以上の証拠はないと言ってるだろう!」
「では、丸木さんが優子さんを愛さなくてもいいわけですよね」
角田はそう答え、ストローを使わずにコップに口をつけてコーヒーを飲み干したあと、優子をじっと見つめた。
「僕が優子さんを愛してはいけない証拠を見せてください」
「だから、彼がさっきから……」
「丸木さんは優子さんを愛していないと判明しました。だって、愛しているという証拠を出せなかったんですから。なら、僕と優子さんが愛し合ってもいいじゃないですか。横取りしたわけじゃないんですから」
もう我慢できない。
これ以上、この場に留まると角田を殴ってしまいそうだ。
今度は俺が優子の腕を引っ張った。
「いいか、これ以上、僕たちに付きまとうな! お前が納得するような証拠がなかろうが、僕たちは愛し合ってるんだよ!」
「その証拠を出せますか?」
「うるさい!」
僕は愉快そうに笑う角田に怒鳴りつけ、優子を連れて席を立った。
◇
それから数日後の優子からの連絡に僕は驚かされた。
角田が勤め先に退職願を提出した日の翌日から行方不明になったというのだ。
優子は単純に喜んでいたが、僕は不気味さを感じた。
角田が唐突に退職願を提出したのはなぜだ?
行方をくらませた理由はなんだ?
◇
角田が行方不明になって数か月がたった。行方の手掛かりは何もつかめていないらしい。
優子は角田のことを話さなくなっていた。僕も角田のことを口にしなくなっていた。
しかし、記憶から角田を消すことはできなかった。
なぜなら今後、角田が僕たちの前に姿を現さない証拠がないからだ。(了)



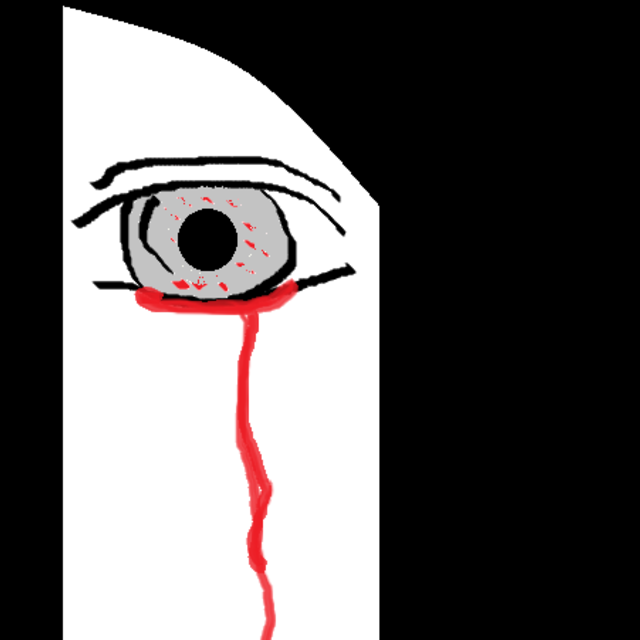
作者退会会員
こんばんは、シタセキです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
四作目となる今作は心霊ホラー要素がない物語となりましたm(__)m
次作も読んでいただけたら幸いです。