大学4年生の時の話である。
nextpage
当時私は、配属された研究室でおそらく他の生徒以上に、研究に没頭させられていた。
院生のいないこの研究室で、身の程知らずにも先生が外国企業から調査研究を受けたのだ。
人手なんてある筈も無い。
先生自身も、大学の講義で講師としての仕事があるのだ。
なのに、そんな依頼を受けてしまった。
nextpage
「君には外国の企業から受けた調査依頼内容を、卒業研究の課題として行って貰いたい」
笑顔でそう言い放つ先生の顔を、今でもよく覚えている。
そのことを伝えられたのは、研究室配属が決まってしばらく経った、3年の秋学期だった。
研究内容を聞かされた当時は、なんとなく凄い研究が出来そうな予感に心が躍った。私は座学が苦手だったが、実験は好きで、他の生徒よりも早く正確にこなせる自信があった。
同じ研究室に配属されたメンバーのうち、他にあと3人もの人間が、同じ研究を合同で行うというのも心強かった。
nextpage
しかし、今では後悔している。
先に述べたように、人手がいないのに受けたこの依頼。調査研究費を貰ってまで受けたこの依頼を、私たちは先生に代わって達成しなければならない。そう、達成しなければならないのだ。
この依頼は調査研究費を貰っている以上、れっきとした仕事である。相手の企業が望む結果が得られるまで、実験を続けなければならない。
nextpage
一番の問題は研究内容だった。
与えられた依頼は、日本では一般に知られてもいないマイナーな食材の、発酵による健康機能の向上である。
ただし、その食材が持つ健康機能値は消して高いとは言えなかった。
元々弱い健康効果を、実用的なレベルに上げろという無茶ぶりが、この調査研究の内容だった。
考えてもみて欲しい、0.1は例え5倍したところで0.5なのだ。5倍もしてまだ半人前、それなのに、私たちが行った実験では最大でも1.35倍の効果上昇が限界だった。
狙っていた健康効果の発酵による効果上昇なんて、その程度しか上げられやしない。正直これならば濃縮した方が手っ取り早い。
当然、いくら実験を繰り返しても先方の望む結果なんて得られるわけがなかった。
おまけに先生は非協力的で放任主義だった。
分からないことがあるからと、先生に質問をしても、憮然とした顔で過去の卒業生の実験レポートを見ろとしか答えてくれない。そして過去の先輩の実験レポートは驚くほどに出来が悪く、結局自力で論文を漁る羽目になった。
欲しい結果は得ることが出来ず、先生すらあてにできない、おまけに発酵の影響で研究室内は臭い。
モチベーションもそよ風に飛ばされる劣悪な環境だが、それでも辞めることは許されない。
卒業研究としてこの実験を行っている以上、達成しなければ単位が貰えないからだ。
卒研は大学を卒業する為に取得しなければならない必修科目のひとつだ、つまりこの単位は絶対に落とせない。
強制的に無理難題をこなさせるとは、全く鬼畜もいいところである。
nextpage
だけどそんな楽しくない実験もついに終わりが来た。
依頼主が求める結果が得られたわけではない。単純に、私たちが卒業の時期になったのだ。
一足早く、2月の終わりから始めたこの調査研究は、望む結果が出ないからと、測定法を変え発酵に使う菌を変え、最終的に1チームで5パターンの実験を、条件を変えながら繰り返し行った。
いくら向こうの企業が求める結果が得られなかったとしても、これだけやって単位が取得できないなんてことがあったら大問題だ。
私たちの卒業研究の最終結果は、あらゆる切り口の膨大なデータから、対象の食品の健康効果は発酵によって向上するということを証明・確立させるものとなった。
そして、当たり前だが卒業論文の文章量が異常に多くなった。
結局、一番に実験を開始したはずの私たちの卒論提出は、提出期限ぎりぎりの2月7日の23時となってしまった。
nextpage
明日2月8日は、午前10時半からパワーポイントを用いての卒論発表が予定されている。
私は、同じ研究室の他の人たちより1桁多いページ数の卒論を20分かけて印刷しながら、ここから片道2時間かけて帰っても時間の無駄だと判断し、1人研究室に泊まる決意を固めた。
どの道、とっくに終電は逃しているのだ。
研究室に泊まるのが1人ぼっちの理由は、4人いるこの研究チームの内、私以外は皆女性だからだ。
みんな遅くまで卒論作成を手伝ってくれたが、最後まで残るのは男性である私1人でいい。
既に今日になってしまった明日の発表を控え、私はエアコンも付けずに研究室で横になった。もうすっかり慣れた発酵臭に包まれながら目を閉じる。
思えば、丸1年近くこの研究室を利用してきたが、この場所に泊まるのは初めてのことだった。
nextpage
○○○
nextpage
目が覚めたのは、初めて体験するほどの異常を感じたからだった。
手元のスマホで時間を見ると、午前2時50分を示していた。丑三つ時といえば丑三つ時だと、やけにはっきりとした頭で思った。
nextpage
とにかく、喉が渇いた。
自分が今まで生きてきた中で、断トツで一番の喉の渇きを感じていた。
小学生の時に熱中症で倒れた時でさえ、こんなに喉が渇いたことはなかった。
疲れた状態で、かつ寝るのに適さない場所で寝ていたから盛大に大口を開けてイビキを立てて寝ていたのだろうかと心配になったが、例えそうだとしてもこの喉の渇きは異常だった。
そもそも、流行中のインフルエンザ対策に装着していたマスクによってある程度保湿されるのだから、3時間も経たないうちにここまで乾燥するはずがない。エアコンだって点けていないのだ。
なのに、まるで砂漠の真ん中で丸3日も水分を摂取していないかのような渇きようは、異常以外の何物でもなかった。
堪らず並べた椅子の上に寝転んだ状態から起き上がった。すると丁度左手側にある机に手をついて起き上がったのだが、その小指の背にやわらかいペットボトルの冷たい触感が伝わった。
こんな場所に飲み物なんて置いていただろうか?ついさっきまで本当に寝ていたのか怪しいほどはっきりした頭が疑問を覚える。
こんなに喉が渇いているのに素直に水分を認めない思考回路に、説明のつかない違和感を自覚しながら、上半身だけを起こして手元の円柱形をしたプラスチック容器を手に取る。
やけに太い、そして重い。
頭で違和感を感じてその容器を見る。研究室の電気は消していたが、廊下の電気が漏れ出てその物体が何であるかは直ぐに判別がついた。
油性ペンで「廃液」と書かれた1リットルのプラスチック瓶を、私は手に持っていた。そしてあろうことか、その廃液に満たされた瓶のキャップを今にも開けようと手を捻りかけていた。
それこそまるで、ペットボトルの水を飲もうとしているかのような動きだった。
意識的に手を止めなければいけない、強制的な無意識の行動。いくらこんなにも喉が渇いているとはいえ、明らかに人体へ影響がありそうな物体を飲もうとするだなんておかしい。
流石に危機感を覚え、早くこの喉の渇きを沈めなければいけないと思った。
立ち上がり、部屋の電気を点ける。そして研究室に設置されている冷蔵庫の元へ向かった。
そこには他の研究室メンバーが常蓄している緑茶があると知っていたからだ。はたしてそこには正真正銘ペットボトルのお茶が入っていた。
それを手に取る。勝手に飲んでしまうのは申し訳ないけれど、今はそれどころでは無い。後ろめたさを感じながら、先ほどのプラスチック瓶にしたようにそのキャップを捻ろうとして些細なはずであることに気が付いた。そのペットボトルは未開封だった。私の手は止まった。
どうしようもなく喉が渇いて苦しいのに、目の前に飲める水分があるのに、未開封だから申し訳ないという罪悪感にその手が止まり、冷蔵庫に戻してしまった。
不気味に冴えた頭が思いついていた。開封済みの液体は他にもあるじゃないか。
私は再び実験机に戻った。そして、今度は茶色の褐色瓶を手に取った。
褐色瓶にはジメチルスルホキシドと表記がされている。
もはや訳が分からない。
私の頭は悲鳴を上げた。ひどく混乱していて、それなのに冷静に物事を判断していた。
ジメチルスルホキシドは実験で使っていた試薬だ。こんなものを飲めるわけがない。手元の瓶の中で液体がちゃぽんと揺れる。
体はいつまでも渇いている。それでもこんなものは飲むことが出来ない。廃液だって飲むことが出来ない。お茶も飲んではいけない。
体がおかしくて、頭もどこかおかしくて、意識と無意識がわからなくなって、アリジゴクの巣に引きずり込まれるようにもがけばもがくほどに怖くなった。
nextpage
コンコンコン、
唐突な物音、私の心臓は飛び上がった。
部屋のどこかから聞こえる音は、昼間もたまに聞こえる実験機器から立つ物音だった。
普段なら気にも留めないこんな音が、この時ばかりは恐ろしい。
だけど思い出した。
私はカバンの中にエナジードリンクを入れていた。ただただ感じる恐怖に動けない体がやっと動いた。
いつまでも手に持っていたジメチルスルホキシドを机に置いて、急いで鞄を開けた。
そこに今日卒論が終わらなくて徹夜するときのために買っておいたエナジードリンクがあった。
私はそれを飲む。
まだ喉は渇いていたが、幾分かマシになっていた。
混乱が落ち着き始めつつあるひどく冴えた頭が、どうしてあの場所に廃液が置かれていたのか考えた。
少なくとも、普段あの場所に廃液は置かれていない。
考えれば考えるほどまた訳が分からなくなってくる。
ジメチルスルホキシドは融点が低く、18度で凍る試薬だ。2月のエアコンのついていない部屋でどうしてちゃぽんと音がするのだろう。背中がだんだんと寒くなってくる。
分からない。
分からないことが多すぎることがひどく恐ろしい。
冷たく冴えた思考が、次から次へと巡って跡を残す。
きっと私は、あの時冷蔵庫に開封済みのお茶を見つけても、他人の飲みかけだからといってまた褐色瓶に手を伸ばしていたのではないだろうか。
分からない、自分の体が、頭が、思考が、無意識が、
思考の砂に埋もれる傍らで、まだ半分残るエナジードリンクの缶がひとりでに倒れた。
薄緑に透明な液体が、泡をたてて床に広がった。
喉の渇きは未だ残っている。




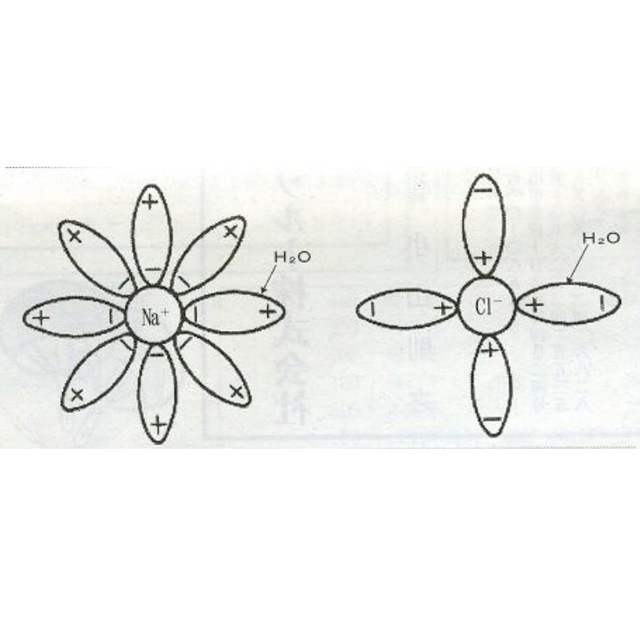
作者ふたば
※実話です。
最後までお読みくださった方々ありがとうございます。
誤字脱字、日本語間違いなど御座いましたら、お気軽にお申し付けください。
…知っていますか、2月8日って「ふたばの日」なんですよ。(去年から決まった)
本当なら、違うお話を投稿するお話だったんですよ、他にもやりたい事があったんです。
なのに、こんなこんなで、色々不十分でしょうがなく奇妙に冴えた頭で研究室のパソコンからこんな怪文を打っているんですよorz
あ、もともと投稿する予定だったお話はちゃんと後々投稿します。(←誰も覚えてない)
それではあと2時間後に予定があるのでこの辺で失礼致します。