客室へ向かう間も俺の心臓の鼓動は高鳴り続ける。
一体どんな奴で俺はどんな言葉を掛ければいいのか、彼女(夜川さん)は「大丈夫」と言っていたが、そう述べる根拠がまるで見えてこない。俺は全身から汗が滲み出ていた。
客室の前へ辿り着く。中からは何も聞こえない、俺はドアを二回ノックし、汗ばんだ手でドアノブを回す。
ガチャ
「し、失礼します。」
緊張のせいか、ぎこちない挨拶になる。客室の中は観葉植物の甘い香りが漂ってるが、それでこの緊張感が緩和されたりはしない。そして例のおとぎ話に出て来そうなベッドの上に緊張のあまりか多少身を固くして彼(中尾 末広)は腰を下していた。黒の短髪で真面目そうな雰囲気は出ているが、多少鋭い眼光で、目が合うと睨まれてるような感じにも見える。
コイツも緊張しているのだろうが、俺もかなり緊張を露わにしていると思う。言葉が詰まる、まず第一声が重要だ。なにか言わなければ.....
「こ、こんかい中尾さんの実行を担当させて頂く沢辺と申します。」
思うように口が動かず、ぎこちない喋りになってしまった。
すると中尾は「実行.....さっきの女性の方が行うのではないのですね。」
ここでは自殺幇助の事を(実行)と言うように夜川さんから教わっていた。中尾は初めて聞くような顔をしているが、どうやら察してくれたようだ。
「はい、今回僕がさせて頂きます。」
「そうですか。まぁ、誰でもいいんですがね.....」
会話がなくなった。普通ならここで自殺理由を尋ねたくなる所だが、そこは夜川さんに止められている。俺の時もそうだったが、おそらく自分と向き合う時間を与え、改めて考えさせるのが目的だろう。中尾は多少投げやりな雰囲気を醸し出しているが、俺がここですぐに実行をしようとすれば思考の時間を取るのだろうか。
そう考えてる間にこの空間に変な間が出来てしまった。考えても仕方がない、気は乗らないがやるしかないな。
俺は「で、では早速実行を行いますね。まずベッドに横になって下さい。」と、ぎこちない喋りや動きで手順を踏んでいく。
中尾は指示通り黙々とベッドに横たわった。
「では、安楽薬を腕に点滴しますので針を通させて頂きます。」
中尾は静かに腕を差し出し「どうぞ」と言わんばかりの雰囲気を出していた。緊張しているのは伝わるが、まだいまいちこの中尾という人間がみえてこない。一体今なにを考えているのだろうか。そして俺は中尾の腕に針を刺す。
いまだ中尾からの反応はなにも伺えない。
「で、では点滴しますね。」
後は安樂薬を流すボタンを押すだけだ。しかし、俺の手はボタンを押すことを拒むかのように震え出す。ここで押せばコイツは死ぬ、俺の手によって天へ召される。そんな思いが頭の中を駆け巡らせる。
「どうしたんですか?」と中尾が声を出した。
「........」
俺は言葉に詰まる。
「あの、早くしてもらえませんか?」と中尾は急かすような言葉を発する。
「.....くないのですか.....?」
気付けば俺は、自分でも聞こえないような小さな声で囁いていた。
中尾は多少苛立っているかのように「え?」と疑問を投げてきた。
次の俺の動き一つでコイツは今感じてる、嗅覚、味覚、聴覚、触覚、視覚が全て失うことになる。コイツは意識してるのだろうか。自分の死と今向き合っているのだろうか。このまま実行に移してもいいのだろうか。そんな感情が自分の中で強く轟く。そして俺は、俺にはあの時犇々と感じた想いをそのまま投げかけた。
「怖くないのですか......?」
「え?」と再び中尾は疑問を投げる。
「死ぬの....怖くないのですか?」
「.......」
一瞬の間が空いた。
そして中尾は少し肩を怒らせながら口を動かす。
「怖くないのですか?って......怖いに決まってるじゃないですか!でも、もう決意したんですよ!だから.....だからその決意が鈍らないうちに早くして下さい!」
声を荒げて俺にそう言った。
俺は中尾の言動で少し踵を返した。そして思った。俺はあの時、いざという時に怯え、狼狽え、泣き喚いた。そして、あの時初めて自分の死と向き合ったように感じた。そのうえで俺はあっさりと「生きる」を選択した。死にたいという意志の一貫性をすぐに崩壊させたのだ。それに比べるとコイツはなんて勇ましく、固い意志を持っているんだ。俺は自分の弱さを、自分の愚かさを罵られているような感情に陥った。
そして、俺は自然とあの禁断の言葉をうっかり口走ってしまった。
「理由は.....理由はなんですか....?」
「.......」
長いようで短い間を空け、中尾が視線を落とし、小さく囁く。
「志望校.....落ちたんですよ......」
separator
「末ちゃんはホントに頭がいいね~」
母に毎日のようにそう言われて育った。
母だけではない、親戚や先生、クラスメイトも口を揃えて僕を「頭がいい」と持ち上げてくれた。僕は必死だった。周りの期待に応える為、毎日必死に勉学に励んでいた。塾や参考書の類は母に頼めばすぐに用意してもらえる。父は優秀な人だった。だが、僕が幼い時に癌で亡くなった。今は父が経営していた会社を母が受け継いでいる。部下が優秀なので母はなにもしなくても懐にお金が入る。
そのお金で僕の教育費をまかなって貰えているので、環境は完全に整っていた。だがそれがプレッシャーでもあった。父が優秀だから、その遺伝子を引き継ぐ僕に母は大きな期待を抱いていた。しかも僕は一人っ子なので、分散することなく母は僕だけに目一杯の力を注いでくれていた。
「お父さんのように優秀な人になってね」これが母の口癖だった。
甘えと思うかもしれないが、僕はこの整った環境で今にも圧し潰されそうなプレッシャーと日々奮闘していた。周りがカラオケやボーリング、ゲームセンターへ行ってる時、僕は塾へ行った。周りが漫画や小説を読んでる時、僕は参考書を読んでいた。周りもそれを察し、僕を遊びに誘うことはしなかった。本当はみんなのようにしたかった。もし「みんなでゲーセン行くんだけど今日ぐらい塾サボって一緒に行かない?」と誘われればすぐに行ってたかもしれない。
そのくらい僕は周りが羨ましかった。別に誰にも縛られてるわけではないが、僕は母が言う「優秀」の道を自ら歩いているつもりだった。
だが、ある日、一人のクラスメイトに言われたあの一言で僕の中の「優秀」はあっけなく崩壊した。
その日、クラスで流行っていたテレビドラマの話題が飛び交ってる中、そのクラスメイトの女の子は熱が入っていたのか傍で参考書を読んでいた僕にこう話しかけた。
「中尾くんはあのドラマ観た?あっ、中尾くんは真面目だからそんなの観ないか。」
僕は胸を締め付けられる想いだった。「真面目だから」その言葉が脳裏に焼き付いて離れない、何度も頭の中で再生される。その「真面目」にはどんな意味が込められているのか。どこか見下すようなその言葉、「この人は勉強が唯一の生き甲斐だから私達の言葉が理解できるはずがない」と言われてような気分だった。この中学という狭い檻の中で勉強ができる者が中心に立つことは決してない。いつも中心にいるのは勉強ができなくても運動ができる者、ひょうきんな事を言って人を笑わせられる者、または少しグレていて大人っぽい魅力をひき出している者がいつも中心になっている。
僕はこの一言を聞くまで辛い思いはあったが、自分や母の「優秀」を信じていた。でも結局は勉強が出来たところで周りと同じ立ち位置には立たせてくれない。それどころか「アイツはガリ勉だから」と感じさせるような蔑んだ目で見られる始末。
その日の帰り道、僕は目を伏せながらいつもと同じ道を歩いてる。そして、自分の信じていた「優秀」を考えた。優秀とは一体誰が判断するのか。いくらテストで良い点を取っても周りに認めてもらえなければ何の意味もない。本当に自分は一体何の為にここまで必死に努力していたのか、なにもわからなくなってしまっていた。
そして僕はその日を境に勉強に全く身が入らなくなった。やらなければ、やらない分だけ成績は下がり、ついには周りに「中尾なら大丈夫」と言われ続けていた志望校も落ちてしまった。
皆、手のひらを返したような目で僕を見る。母には「きっと私の教育方針が間違っていたんだわ、ごめんね....」と少し哀れみのある目で言われた。
それから僕は学校にいても期待されていた分、肩身が狭くなってしまい、部屋に引きこもるようになった。
あれから数カ月が経ち、僕も皆と同じように高校に通わなければならないというのに、いまだに部屋に引きこもったままだ。本当に自分はなにがしたかったのか、もう涙すら浮かんでこない。
そんな時、あのホームページが目に止まった。ふざけた作りで「理由問わず安楽死したい人大募集!」と記載されている。僕は全く信用していなかったが、エントリーした。もうどうでもよかったんだ。別にこれが嘘でもホントでも僕は死ぬつもりだった。どうせこの世に希望なんてないんだ......。
すると、翌日電話があった。元気な女性の声で「いつこちらに来られますか?」と尋ねられた。僕はこれが嘘であってもその足でどこかで死ぬつもりだったので「2日後の19時頃でお願いします」と自殺の道具を集める為に余裕をみて答えた。19時にしたのもできるだけ学生の姿を見たくないからだ。見ると自分が本当に哀れに感じる。
そして僕は、この2日間であらゆる道具をかき集めた。といってもそんなに多くの道具を持っていく訳にはいかず、結局、首を括るロープだけカバンにしまった。方法は色々考えたが、自殺後に注目を浴びたくなかったので飛び降り自殺は論外だ。「あの子、志望校を落ちたから自殺したらしいよ」と周りが騒ぎ立てるだろう。電車に飛び込む自殺は、これまで良くしてくれた母に迷惑が掛かる。結論、僕は人気のない山奥で首吊り自殺を選んだ。
幸い、母は仕事中の為、抜け出すのは容易だった。いくつかの小銭とカバン、小雨が降っていたので傘を持ち、家を出る。道中は思っていたより時間が掛ってしまい、結局到着したのが19時を少し過ぎた辺りになってしまった。
(自殺村)と消えかかった字で書かれている看板の前で佇んでいると、村の中から「夜川」と名乗る女性が出てきた。僕はまだ半信半疑だったが、言われるがままに「客室」と呼ばれる部屋へ案内された。そして、おおかたの説明を受け、その女性は席を外した。
しばらくして男性が部屋に入ってきた。何故か緊張した面持ちでその男性は「沢辺」というらしい。言葉に間があったり手順がグダグダになったりで僕は多少イラついていた。そしてついに声を荒げ、怒鳴りつけてしまったのである。
それから、自分でも二度と思い出したくない記憶を何故かこの男性に喋ってしまった。
separator
「志望校.....ですか......。」
「はい......。」
「.......」
沈黙とした重い空気、屋根を打つ雨音だけが室内に響き渡る。
咄嗟に質問してしまったが、その後の言葉を一切考えてなかった俺はまたも言葉が詰まる。この年代の悩みはよく考えれば大体想像がつく、俺のような人間関係や、家庭環境、恋愛、そして勉強のことが候補に挙げられる。だが、いざその問題に直面しても掛ける言葉が出ない。普段なら「まだ若いから人生これからだよ」など表面上だけの言葉を掛ける所だが、この場所と状況ではそんな安い言葉は何の意味も持たないだろう。
重い空気の中、先に言葉を発したのは中尾だった。
「僕は....それが全てだったんです....。」
さきほどまでの険しい表情とは打って変わって視線を落とし、どこか寂し気な表情で中尾は言った。
「母や周りに期待されて、そのプレッシャーに圧し潰されてしまったんです。本当に情けないと思います。でも、もう覚悟は決まってるので早くボタンを押して下さい。」
また険しい表情に戻り、急かすように中尾は言った。
「.........俺はイジメだった。」
「え....?」
「俺の場合はイジメだった。それが原因でこの村に来たんだ。」
俺はいつの間にか口調が変わり、どこか遠くを見るように中尾に語りだした。
「嫌味に聞こえるかもしれないが、俺はそこそこ有名な高校に少しの勉強で入れた。でも、そこからが地獄だった。成績は常にトップクラスだった俺は正直周りを見下していた。「なんでコイツ等はこんなことも出来ないのか。」と、そんな態度をよく思わなかったのか、俺はイジメの標的にされた。最初は軽い無視程度だったが、段々エスカレートしていき、暴行を始め、様々な嫌がらせを受けてきた。本当に辛かった......。」
中尾は視線を落とし、黙々と俺の話に耳を傾けていた。
そして俺は話を続けた。
「そんな状態になっても俺は、まだ他人を見下していた。「高校生にもなってこんなレベルの低い事しやがって」とか「こんな有名な高校にイジメがある時点で学校側に問題があるんじゃないのか」と俺はいつも物事を他人のせいにしてたんだ。そして俺はこんな世の中なら、無い方がいいじゃないかと思い、自殺を選んだ。でも、どうしても死ねなかった、怖いという感情が勝ってしまってたんだ。それはこの村に来ても変わらなかった。ボタンを押される直前、俺は狼狽えてしまった。でもその時初めて、「ああ、俺は生きたいんだ」と実感したんだ。」
ここで俺は拳を強く握り、かぶりを振る。
「いや、あの時気付いたんだ。死はみんな平等に訪れるもの。上も下もない、人生も一緒なんじゃないかって。俺は他人を下に見ていた、見下すことで自分を評価し、優劣を判断してた。でも他人は俺を上に見たりはしない。今までの俺の考えが無駄だったということだ。だから俺は、すぐには無理だが、少しずつ.....少しずつ、このくだらないプライド無くして生きていこうと決めたんだ。」
少し間を空けた後、中尾が重い口を開く。
「そ、そんなのアナタの考えでしょう......僕には何も関係ない.....」
「そうだな。でも俺は今日、自分より上に見える存在を目の当たりにしたよ。」
「だからアナタ考えはもう.....」
「そいつは俺と違ってしっかりとした決意を持ってここに来た。俺と違って最後まで堂々と自分の命と向き合った。俺と違って自分の意志を強く持っていた。」
俺は中尾に視線を向ける。
「俺は、そんなお前が誇らしくみえた。」
「......」
中尾は無言で視線を落とし、強張った頬を少し緩め、肩の力を抜いて何かを諦めたかのように呟く。
「........わかりました。」
その後、自ら点滴を外して持参していたカバンをゆっくり背負い上げ、部屋を出る姿勢をとった。
「もう、死ぬはいいのか?」
「......はい。」
「外まで送るよ。」
俺は中尾と共に部屋を出て、村の出口に向け歩き出す、雨はすっかり止んでいた。お互い無言で歩き、出口に差し掛かった後、別れを告げた。俺は中尾に背中を向け、村の自室へ戻ろうした時、
「あ、あの沢辺さん!」
今までで一番大きな声量で中尾に呼び止められ、俺は振り向く。
「初めてでした.....初めて勉強以外で他人に褒められました....だから.....ありがとうございました。」
中尾は少し気恥ずかしそうに俺にそう言い、一礼して村を後にした。
「「ありがとうございました。」ですって。」
すぐ後ろで囁くような声が聞こえる。
「夜川さん、居たんですか。」
彼女はニヤニヤして肘で俺の腕を小突きながら言う。
「沢辺さん、凄いじゃないですか!」
「い、いや僕はただ.....」
ここで俺は思い出したかのように、ばつの悪い表情に変わる。
「夜川さん、すみません。理由、訊いちゃいました。」
俺は多少の叱咤があると覚悟して告白した。
「まぁ、今回は結果としていい方へ事が進んだので、いいんじゃないですか。」と彼女は優しい笑顔で俺にそう言った。
しかし今回たまたま上手く事が進んだが、もしその「理由」が俺に受け止めきれないレベルのものであれば、はたして俺はどうしてたのかと今になって不安になる.....しかし、その感情よりも俺は今、一人の尊い命を救えた事で胸が一杯だった。この村で働く意味を少し理解できた気がした。
そして「あっ、夕食がまだでしたね。」と彼女が呟いたので、少し遅めの夕食をとってその日は終えた。
separator
~数日後~
俺は、もうお馴染みの村掃除を行っていた。すると、自室の掃除を行っていた彼女が外に出てきた。
「沢辺さん、沢辺さん、新しい志願者です!」
俺は自然と表情を顰めて「も、もう来たんですか!?」と訊く。
彼女曰く、こんな隙間なく志願者が来ることは珍しいらしく、彼女自身も驚いている様子だった。
俺は彼女の部屋に行き、PCのディスプレイを見せてもらう。
磯部 アリス(25)女
電話番号 080-〇〇〇〇-〇〇〇〇
続く


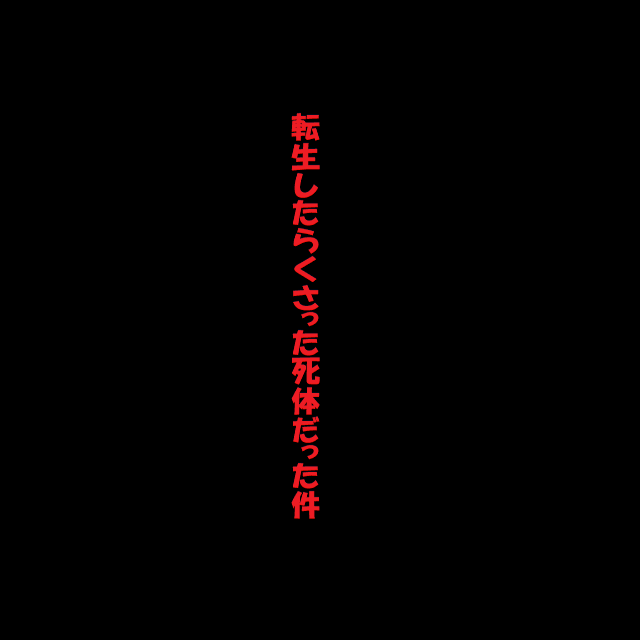
作者ゲル
3話目になります。読んで頂ければ幸いです!
https://kowabana.jp/tags/自殺村