小学校のときからナマコというあだ名を付けられた私の名前はマナコだ。
人が嫌いになってからは専ら人以外の動物を好むようになり、
大学でアニ研(アニマルの方)に入ったのをきっかけに、県内で有名な動物園のインターンに参加させてもらうこととなった。
そこは山の麓に土地をこしらえた、自然と一体になった動物園だ。
選ばれたのは私一人で、とても電車で通える勤務体制ではないので寮を手当てされていた。
nextpage
しかしいざとなると、退屈だった。
職員に付きっきりで動物のウンチクを聞かされながら体調を記録するのみ。
エサをあげたり、掃除をすることも、触れることさえもできない。
ここの動物たちは手入れがとても細かいらしく、臭いがほとんど感じられなかった。その秘訣も教えてもらえない。
炎天下でただ観察するだけなら家でナショジオでも見ていた方がマシだ。
そんなことを考えるのは贅沢だろうか、と行ったり来たりしつつ、
1週間が過ぎてから園長に相談した。
nextpage
そして以前と変わらず、太陽に服をびしょびしょにされている私がいる。
「ナマ、マナコさん。園長との話はどうだった?」
この日もインターン担当のシゲさんと巡回していた。
終始、当たり障りの無い笑顔を見せるごく普通の人だ。
私の名前さえ間違えなければ。
「商品に触るなって言われちゃいました」
「なるほど」
私はそのときのことを思い返した。
separator
nextpage
園長は椅子に腰掛けて反対の窓の方を向いていた。
「どうして触ることもダメなんですか?」
「おまえらの汚い手で触ると商品に傷がつく」
「え?」
園長はそのままの姿勢でもう一度、
「おまえらの汚い手で触ると商品に傷がつく」
同じことを言った。
何も返せずにいると、園長の椅子がスッとこちらに回った。
「とか何とか言う人がいるんですよ。上には。だから悪いけど、許してね」
「はあ」
園長はファイティングポーズを取ると、肘を左右に振ってアイドルかゴリラだかの真似をした。
あまり関わるのはやめた方がよいと思った。
私は奇妙な動物は好きだけど、奇妙な人間は嫌いだ。
separator
nextpage
「そりゃあそうだろうな。あの人にとっては商売道具だから。動物への愛着なんてないよ」
「シゲさんもそうなんですか?」
「僕は子どものときからここで働いててね。特に考えがあるわけじゃないんだ。
言ってしまえばここの動物たちの一員だよ」
そう言って笑うものの、私は面白くも何ともなかった。
お客さんの間をくぐり、シゲさんは岩山の方に寄り道した。
「トラは危ない」
見下ろすと、2頭のトラが元気よく地面を引っ掻いている。
「いいかい、僕たちは檻とか、強化ガラスとかは無いと考えるんだ。いつ襲われるか分からない。
でも死なないように、立ち振舞いには注意と敬意を払う。これが動物たちとの付き合い方の基本さ」
「実際に襲われた人はいるんですか?」
シゲさんの顔が曇った。
何かを考えているようだけど、すぐに笑顔に戻った。
「いるわけないよ」
「そうですか」
それ以上は触れないことにした。
separator
nextpage
そうこうする内に1ヶ月が経ち、
最後にダチョウの健康チェックリストに丸を付け終えて、インターン期間は終了となった。
園長を見たのはたった3回だったが、私が去るのをやたらと嬉しそうにしていた。
適当に挨拶を交わし、スタッフ専用の廊下を歩いていた。
左右にはマジックミラー越しに動物、観客が見えるようになっている。
今日は週末のため人は多かった。
「あれは」
サルのような人型の動物が、観客ではなく、こちらの壁にくっついていた。
そもそも、その檻だけ観客側にもコンクリートの壁があった。つまり外から見えていない。
そしてサルにしては毛がどこにも無いし、全体が白っぽい。
ホルマリン漬けにされた人体標本のようなそれは、
立ったまま片方の耳をぴったりと壁に付け、手をしきり揺らしていた。
「あれはヒトの新種だよ」
「はい?」
「なんちゃってね。毛の無いサルさ」
「ストレスですか?」
「副作用だよ」
「病気か何か」
「さあねえ」
シゲさんは興味が無さそうに会話を切り上げて歩く。
だんだんそれに近づくと、手ではなく、人差し指を宙で振り回すように動かしていることが分かった。
その動きにはどこかで見覚えがあった。
「このサル、なんでこんなに指を振っているんですか?」
「黙って歩いてくれないかな」
なぜか急にシゲさんの機嫌が悪くなった。
注意深くサルを見ていると、不穏な空気が立ち込めた。この動きはまるで。
<ピピッ>
シゲさんは信号音で立ち止まり、無線から何か指示を受けていた。
そして私に向いた。
「なんていったらいいかな。とにかくちょっと、こっちの台に乗ってもらえるかい」
シゲさんがそそくさと、私を廊下の隅の荷台のような位置に誘導した。
「なんですかこれ?」
「そのまま」
その直後、目の前に巨大な金属じみた何かが音を立てて落下した。
檻だ。
「しゃべりすぎって言われちゃったよ」
シゲさんはもう笑っていなかった。
私の乗った檻のカートを引いて逆方向へ運び始める。
格子をやかましく揺らしても無反応だった。
そしてようやく確信した。
あれは人だ。私にSOSを送っていたのだ。
separator
nextpage
ずっくんという名前のミミズクを飼っていた。
旅行に行く前、おばあちゃんに預けたのがまずかった。
小さなネズミをエサに与えないといけなくて、おばあちゃんは最初の返事だけは良かったものの、
帰ってきたときには、ずっくんは死体の入った袋になって返ってきた。
どうしてもあのエサが触れなかったらしく、代わりにキャットフードを与えていたと。
おばあちゃんが大嫌いになった。
そのおばあちゃんも心を病んでしまったようで、1年後に心不全で亡くなった。
separator
nextpage
その天罰が下ったのだろうか。
絶望の中、私は我に返った。
大きなエレベータで地下に連れられ、長い廊下を進み、分厚い扉の前で解放された。
異様な静けさがあった。
「この先の部屋に住んでもらう」
「住むってことは、帰れないってことですか?」
「そうだね」
私は扉を開けた。
nextpage
そこは植物園を思わせる、草木と水辺の見えるドーナツ状の巨大な空間だった。
中の見えない黒いガラス窓が帯のように一周している。
それ以外は何から何まで真っ白だ。
天井が高く、見上げると生き物がいた。
小さいサルがツタを使って移動していた。鳥も飛んでいる。
「施設へようこそ」
どこかのスピーカーから女性の声がした。
「あなたの希望ではないけれど、しばらくここで動物の世話をしてもらうわ」
視界横に大きなものが映り、体が強張った。トラだ。
「大丈夫だよ。ここの動物は何もしない」
シゲさんが言うとおり、トラはこちらに関心が無さそうに通り過ぎていった。
「動物ってこれ全部を?」
「およそ30種類いるわ。だけど、担当するのは1匹でいい」
奥からまた何かが現れた。
オランウータンのように太った毛むくじゃらで、足が短く、手が長い動物だった。
「どう見てもオランウータンね」
「そうだね。チンって名前だ。
動物たちにはそれぞれに専用のおやつを食べさせることになっている。チンには必ずこれだけを与えるように。1日1つまみだ」
「はあ」
<ふりかけにもどうぞ!北海道鱈昆布!>と書かれた袋を渡された。
私が封を開けると、チンは目を丸くし、唇をすぼめ、ニオイを懸命に嗅いでいた。
中身を掌に乗せて差し出すと、小銭を受け取るかのようにキレイに取られた塊は、たっぷり凝視されてから、大きな口に入れられた。
口の中で餅をこねるような動きを見せた後、すぐにこちらを見てきた。まだほしいのだろうか。
「ダメだよ」
シゲさんが見張っていたので、封を閉めて鞄に戻した。
チンは人間の私にも分かるくらいに不満そうな顔をした。
そしてゆっくり私の靴を脱がせると、ゆっくり私の頭の上に置いた。
「あんた、あんたねえ」
猛烈な悔しさが込み上げた。
チンはやかましく手を叩いてどこかへ行ってしまった。
nextpage
カピバラ、ダチョウ、テナガザル、九官鳥、アリクイ、ウサギ、トラ、そしてオランウータン。
とりあえず見かけた動物たちを記憶した。
名前のよく分からないのもいくつかいた。
皆揃って一言も鳴かず、ビー玉のような目をしていた。
私はその目が嫌だった。
nextpage
シゲさんに案内された部屋は、狭いけど日当たりのいいワンルームだった。
トイレもシャワーもベッドも無くて、通路側の壁が檻になっていることを除けば。
「あの」
そろそろ私は自分の身に起きていることが分からなくなり、シゲさんに尋ねた。
「私はどうしてここにいるんですか?どうやったって警察にバレますよ」
「来ないよ。まだ夏休みだよね?君がどこで何をしているかなんて、誰も気にしてない」
よく知っているな、と思ったけど、雑談で私が全部話していたことだ。
一人暮らしのことも、たいして友達がいないことも。
「強引に逃げようとしたら」
「捕まって動物に食べられると思う。相手を選べるならまだいい。トラを選ぶんだ。チンパンジーだけはダメだ」
私はトラに人が食べられる映像を見たことがあるので、一気に腰が引けた。
「トイレはそこのマット、シャワーは水場で。エサはそこのボタンを押せばいつでも出てくるよ」
ふざけて言っているようにしか聞こえなかったけど、確かにペットの排泄用マットがあった。
「冗談でしょ」
「冗談じゃないよ」
少し足を踏み入れると、床が低反発素材になっていて、足が柔らかく沈んだ。
「1時間後、運動場でキャッチボールをするので、遅れないように集合してください」
唐突にアナウンスが流れた。
「こうやって度々、訓練をさせられるんだ。アナウンスには絶対に逆らわないようにね」
「シゲさん、あなたは敵ですか?味方ですか?」
「どっちでもないよ。僕もただの動物さ」
シゲさんはとうとう、私から去っていった。
nextpage
しばらく広場のベンチで座っていた。
ウサギが寄ってきたので撫でてあげた。
ここの動物は人なつっこいのか、膝の上でじっとしている。
安心はできないけど疲れた。
少しまどろんできた頃、再び集合のアナウンスが鳴った。
そもそも時計が無かったので、何か言われないと寝てしまうところだった。
道案内はそこらじゅうに吊り下げられていたので場所はすぐに分かった。
なぜか人間の言葉(英語)で書かれていたけど、疑問はすぐに解決した。
そこには私と同じように、捕まった人たちが動物1匹とペアになっていたのだ。
nextpage
運動場というのは、体育館のようなただの広いスペースで、
卒業式のようにペアが整列し、端にはやたらと大きな背の低い水槽があった。
あの中にピラニアか何かがいて拷問を受けるのではないかと想像してしまったが、
何より人が揃いも揃って全裸だったので何もかも穏やかではなかった。
nextpage
「あの」
私は近くでうさぎを連れている男性に話しかけた。
「じじ、じじじ、じ」
「ここからどうやったら出られるんですか」
「じじじ、じ、じじ」
「ちゃんと話してください」
「ぶ、ぶぶぶぶ、ぶ」
それは壊れたゼンマイ人形みたいに音を鳴らしているだけだった。
他の人達も同様だった。
「誰かいないの。頭がまともな人は」
鼻を鳴らすような音が聞こえて振り返ると、先程のオランウータンがいた。
それは<ブフォ>と怪しげな声を出した。
「ペアと一緒にキャッチボールをしましょう」
アナウンスが流れた。
水の入った広い容器には、掌サイズの豆腐が無数に入っていた。
「それをつぶしたり落としたりしないように、キャッチボールしてください。
優しさと強さをコントロールするのです」
水に手を入れ、冷えた豆腐をすくった。
私は少しの間、他の人の様子を見ていた。
全部が全部、力なく豆腐を落とし、べちゃりと床を白に染めていた。
動物はそもそも、四足歩行だと掴むことすらできないようだった。
何の意義も無い茶番だった。
でもこれを無視してトラに食べられるよりマシだと思った。
私もチンに向かって投げてみると、野球選手も驚きのしなやかさで豆腐を掌に収めた。
そして反対にものすごいスピードで投げつけてきて、私の顔で爆発した。
どこかで聞いたが、霊長類は投擲の精度が非常に高いらしい。
背中の方でも豆腐がぶつかってきた。
これは別のペアのものだろう。無視して続けた。
しかし、また数分後に同じところを当てられた。
一匹のチンパンジーがこちらを見ていた。あいつだ。
「いいかげんに」
私は自分の持っていた豆腐をそいつに投げ、見事に顔面に命中させた。
すると壊れた人形のように表情が停止していた。
バァンと飛び箱の練習を思わせる音が響いたときには、もうそのチンパンジーが目の前にいた。
<やっぱり動物は動物だ>フルスイングの腕が私の首をS字に折り曲げるんだと悟った。
しかし、それと同時にチンが間に入り、その殺意ある攻撃を胸で受け止めた。
重苦しい音がした。
「ゾゾ、チン、マナコ、やめなさい」
同列扱いされているのが癪だけど、非が無いわけではないので一応謝った。
あのチンパンジーはゾゾというらしい。
二匹もスピーカーに向かっておずおずと頭を下げた。なんだか自分たちが練習中のサーカス団みたいで哀しくなった。
「今日はおしまいです。落ちた豆腐はマナコ、あなたが片付けなさいね」
「こんなに散らかったのを自分一人で?」
「あなたどこかで言ってなかった?掃除がしたいって」
何も言い返せなかった。動物と人間たちが帰っていく。
シゲさんに与えられたモップを使い、これとは明らかに無関係な動物の糞までも清掃対象になっていた。
部屋に戻った私は床に崩れるように眠りについた。
separator
nextpage
死んだずっくんがなかなか目を開けてくれないから、ビー玉を中に詰めた。
キラキラと光り、生き返ったような気がして嬉しかった。
だけどお母さんにひどく怒られて、おばあちゃんの家の炊飯器の中に隠した。
家が取り壊されることを知ったから、こっそり取りに行くつもりだったのに、
蓋を開けたら中身はキレイに無くなっていた。
そのとき私は、ずっくんは蘇ってお空に飛んでいったのだと歓喜していた。
separator
nextpage
私は目を覚まし、お腹がすいていることを思い出した。
部屋に設置されているボタンを押すと、1秒足らずでカゴにエサが落ちてきた。
袋入りの酢昆布だった。もう一度押すと同じものが出てきたので鼻で笑った。
恐ろしいことに、食べ物がそれしか与えられないのは私も例外ではなかったのだ。
「これでどうやって生きていけっていうの」
酸っぱさが胃に滲みた。
nextpage
本物か怪しい日光を参考にすると、今は早朝だ。
私はいよいよ我慢できなくなり、誰も通らないタイミングを見てマットの上で排泄した。
拭くものも何も無くて、私は背を丸めて床で静かに目を閉じた。
自分がみじめで泣いてしまった。行ったこともない刑務所の方が絶対にマシだと思った。
立て続けに、喉の乾きも限界になった。
nextpage
私は広場の水場に加わった。その道中、観賞用に流れている水を飲もうとしてみたが、
はっきりと分かるくらいのアルコールの匂いがしたので諦めた。
アリクイと、チーターがぺちゃぺちゃしている間にかがみこみ、同じように水をすすった。
おそらく水そのものは綺麗だった。スーパーでよく買うミネラルウォーターの味がした。
一度飲んでしまうと、おなかいっぱいになるまで飲み続けた。
水のおいしさを痛感した。
nextpage
広場にいる動物に話しかけたりもしたが、当然ながら何の情報も得られなかった。
他の檻を回ってみると、キャラメルで口をベタベタにしている人や、排泄中の人がいたのでもう見ないことにした。
出口の扉にはシゲさんが立っているだけで鍵もかかっていないのに、誰も出ようとしない。
「ここの人たちはどうしちゃったんですか?」
「どうもしていないよ」
「なんで話せないんですか?」
「人間性を失っているんじゃないかな」
「シゲさんはずっとここに立ってるんですか?」
「いや、君が寝ているときに眠ってる。君以外は脱出なんて考えないから」
私が勢いをつけて出口に突っ込もうとした直後、その足はピタリと止まった。
何か大きな鼻息が後ろで聞こえた。
3メートルはあろうかというクマが、背後のプランターから顔を出していた。
「とりあえず部屋に戻って、アナウンスを待つんだ。君はメルに目を付けられてる」
「メルって人は動物を操れるの?」
「異常なまでに手懐けているとは聞く」
nextpage
その日のアナウンスではお互いにけづくろいをした。
私の頭はおそらく動物から見ても汚れていたのだろう。
チンは不満げな目つきをしていた。
それから3日が過ぎた頃、私は水場で動物と同じように水浴びをした。
石鹸もタオルも無いので、恐る恐る上半身を脱ぎ、
服をタオル代わりにして体をこすった。
びっくりするほどの垢が取れた。
髪も乾かせなかったので、ひたすら窓からの光に当たっていた。
おそらく太陽光ではないけど、暖かかった。
nextpage
更に1週間が過ぎた。
アナウンスのたびに、シーソーに乗ったり、人間を威嚇する練習をしたり、
とにかく訳の分からないことばかりしていた。
「分からない」
体が酢昆布で仕上がっていた私は栄養失調になっていると思いきや、
肌の艶が以前と変わらず、痩せてもいない。
あの酢昆布に隠された栄養素があるとは思えない。
何かがあるんだろうけど、疑ったところで無意味だった。
とにかくボタンを押せばいくつでも出てくるので、食べたいときに食べることにした。
nextpage
また1週間が過ぎた。
排泄後の股の汚れが気にならなくなった。
この頃からなぜか体毛が生えてきた。
手入れをしていなければ人間はこうなるのかと驚いた。
剃るものも無いので諦めた。
そういえば剃る物、あれはなんていう名前だったか。
「分からない」
nextpage
また更に1週間が過ぎると、
体毛が服から爆発するように飛び出ていたので裸になった。
服が煩わしい。
肌が隠れて見えないくらいに、私は黒い猿のようになっていた。
もはや濡れたり乾いたりすら気にすることもなくなった。
nextpage
1ヶ月になり、もはやここに来る以前の頃を忘れかけていた。
気分は悪く無かった。そもそも私は、どうしてここを出ようとしていたか。
「分からない分からない」
夜と言えば夜と言える時間。フラフラと暗い広場に出た。
裸で柱に縛り付けられたサルがいると思ったらシゲさんだった。ハッキリとは分からないけど、ちょっとばかりの擦り傷や噛み傷が見えた。
「そんなところで何してるんですか」
「たぶん今から死ぬところだ」
「そうなんですか、どうしてまた」
「逃げようとした」
「こんにちは」
ニットにスカートを履き、白衣を纏った女性が死角に立っていた。
にこりと笑って私に歩み寄る。
「指導者のメルよ」
「メル?」
「あなたには特別な訓練があるわ。今からこれを殺して」
「は」
まともな人間に出会えたと期待した自分が悔しかった。
そして思い出した。ここがまともではないことを。
separator
nextpage
高校を卒業するあたりで母から聞いた話だった。
おばあちゃんはしっかりエサを与えていたらしい。
それをずっくんは食べなかった。
本当の死因は何でもなく、ただ飼育が難しかっただけだ。
爪を切ることも拒絶されたようで、おばあちゃんは手に大量の傷を作っていた。
それを隠して、すべて自分のせいにして墓まで持っていったのだ。
separator
nextpage
私は泣いていた。
「できません。人が死ぬのは、とても悲しいもの」
「できるわ。あなたには行動力が付いているはずよ」
「そういうことじゃないんです」
「殺したら出してあげるわ」
「人は人を殺したりしません。普通は」
「何言ってるの。あなたたちを人とは言わないわ、ヒト科とは言えてもね。
ちなみにこのヒト、あなたを逃がそうとしていたそうよ」
心臓が高鳴るのを感じた。
「どうしてそんなことをしたんですか」
「君はいちいち物事に因果関係を求めるのか?僕はただの動物だ。ちょっと人助けが好きなだけの」
私が鼻を垂らすと、シゲさんは笑った。
「マナコ、やっぱり君は人間のままでいい。こいつらの言いなりになるな。あれは人間を」
メルは人差し指をシゲさんの唇に当てた後、幼稚園の先生のような優しい顔で私を諭した。
「さあ、はやく」
「できません」
すると音も立てずにトラがやってきて、シゲさんの頭を咥えて静かに割った。
たったそれだけで、シゲさんは絶命した。
シゲさんの顔がずれて、頭に数カ所の亀裂ができ、血がわんさかと噴いていた。死んでいないとおかしいくらいだ。
そしてずれた拍子に頭からカツラが落ちた。
その姿は私が最初に見た白い人にそっくりだった。
「どうなってるのよ」
「どうも何も、あなたたちと同じ被検体よ。代わりを用意しなきゃ」
トラがシゲさんをどこかに引きずっていく。
「そういえばあなたもそろそろ死んでもらうわ」
私は後ずさった。
「なんで?」
「ここまで育てたけど、毛が生えるだけで進行しないもの」
メルは手を叩いた。
「さあみなさん、ここに迷子がいますよ。助けてあげてください」
ぞろぞろと動物たちが集まってきて、私を広場の中央に追い立てた。
「いや」
そこには黒いタイヤを寄せ集めたような生き物が、それはそれは穏やかな顔で、私の腕を握った。
ゴリラだった。電流を流されたような衝撃の後、腕が潰れる勢いで締め付けられているのが分かった。
視界が変な色に変わり始めたときにそれは離れた。
チンがゴリラを殴り飛ばしていた。私の腕には黒と紫の汚いタトゥーが出来た。
<オオ!?>
ゴリラはわめき、その場で跳ねる。
そしてゾゾが私の後ろに回り込み、彫刻刀のような歯で噛みつこうとしたところで、またチンに吹き飛ばされた。
私はめでたく失禁した。<パンチひとつであんなに飛んでいいわけがない>
他の動物たちがお祭りのように騒ぐ。
チンの鳴き声が<チチホギャブ!>と連呼しているように聞こえたので、
私も目をつむって<ウオラギエ!>などと必死に叫んでいると戦いは終わった。
チンがそこいらのチンピラを叩き伏せていた。
私のおしっこをコウモリがすくいなめていたので思わず蹴り飛ばした。
nextpage
「もう嫌。ウンザリよ」
どこからか顔をマスクで覆ったメルが現れた。
「アレックス。人間の味方だけはダメ」
アレックスとは、このチンの別名だろうか。
なぜ味方をしてはいけないのか。
メルはこちらを見た。
「ここにいるのはみんな人間よ」
こことはどこか?
「動物も含めてね」
チンが、ゾゾが、トラもゴリラもウサギも人間?
チンはまっすぐにメルを見ていた。
「元の名前をアレックスと言うの。息子の名前よ」
私はその言葉の意味が分からないまま、激しい嫌悪感を抱いた。
「飼育コストを抑えたいというものだから、ちょうど神経生物学の研究に使えると思って契約を交わした。徐々に動物から人間へ替えていったの。彼らは動物よりも言うことを聞き、観客にサービスもできる。園長はそれで満足していたけど」
「自分の子どもをなんで」
私の言葉を無視してメルは続けた。
「やっぱりオリジナルの完全コピーは無理ね。触ったら分かるわ。不自然な毛並み。不自然な顔つき。不自然な声。そして不自然な力」
メルは独り言のようにそこまで話しきった。
園長が動物を触らせない理由に行き当たった。
「知りたいことはこれくらいかしら?」
「なんでそれを私に話したの」
「事前学習よ」
ぐらりと視界が床にズームインして、真っ暗になった。
separator
nextpage
騒々しい。
目を開けると大勢の人がいた。
大人と子どもだ。和気あいあいとしている。
あれこそが人間というものだ。
私は自分の手を見た。
ああ、なんでよりによって猿なの。
誰もが私を見て写真を取っている。
裸で広い檻の中を走り回ってみると、それはどこか開放的で。
separator
nextpage
台風の後の排水溝の臭いがして目を覚ました。
チンの強烈な口臭だった。ぺたり、ぺたりと私の頬を触っていた。
「どうなったの」
<ンッマッモッ>
「ぜんぜん分からない」
見渡すと、近くにゾゾも座っていた。
どうやら戦意は無さそうだ。足の指の間にある汚れを取っている。
他の動物たちもフラフラとしていた。
<ンッマッモッモリッ>
「えっと」
スピーカーから声がした。
「人間はもうダメよ。知性と呼べる唯一の長所は何十年も前から出涸らし状態。
動物の体を借りて新しい生態系でやり直すの。誰も動物の思考回路なんて必要としてないもの」
するとゾゾがぎゃあぎゃあと喚いた。
「なぜ人間と仲良くしてはいけないのかですって。
あたりまえよ、あなたたちは動物なんだから、いずれ野生に解き放ってあげるわ。
そして生態系のバランスを整えるの。絶滅を阻止してあげて。あなたたち自身で繁殖しながらね」
メルは皮肉混じりに笑った。
「まあ無理かしら。一度科学に手を入れられた生き物が、独りで生きていけるはずないもの」
ゾゾは明らかな敵意を彼女に向けていた。
どうやら彼らをマインドコントロールするシステムがあるようだ。
私はスピーカーに近づいた。
「メル。今まで生きてきた中で何度も言われただろうけど、やっていいことと悪いことがあるのよ」
「本当に悪いこと?さっきあなたに夢を見せてあげたじゃない。まんざらでも無かったでしょう」
「ちがう」
「本当に悪いことかって聞いてるの!」
メルが突然怒鳴った。
言葉が詰まってしまった。
「それは、自分が自分でなくなっただけ。何の辻褄も合ってない。私はここから出るわ」
「無理よ。後ろを見て」
振り返るといつの間にか、彼らが軍隊のように整列していた。
その姿は人間でもない、動物でもないものだった。
地球に存在しない全く別の生き物に感じた。
「こわい」
「そうね。怖いわ。でもモンスターを従えて旅をするアニメなんて世に溢れてるでしょ」
隊列の中にチンもいた。
「あんたまで」
しかし違う。チンだけが、そこで鱈昆布をねだっている。
私は歩いていき、ポケットからそれを取り出し、チンに与えた。
「どういうことアレックス。あなたの好物は茎ワカメのはず」
「いいえ鱈昆布よ。私がずっと与えてきた。やっぱり食べ物に何か仕込んでいたのね」
「あいつ。あいつか。あの何の取り柄もない人間のクズが。クズが」
シゲさんは最初から助けてくれていたんだ。
「人間って認めてるじゃない」
チンは相変わらず汚い食べ方をした後に、走り幅跳びして壁をよじ登り、黒いガラスをおもいきり殴り割った。
けたたましい音と共に黒色が透明になり、悲鳴が聞こえ、中で人間たちが暴れていた。
破壊音が何度が聞こえたあと、動物たちが急に頭やら手足やらを痙攣させた。
そして正面の自動扉が開いた。
「チン!」
私が叫ぶとチンは戻ってきた。
「出るわよ」
扉を抜けて、私たちは走った。
separator
nextpage
メルが最初に見た夢は、日が差す海で、温かい海水が膝まで使っているシーンだった。
「ああきもちいい」
眩しくて遠くを見れない。
振り返ると、小さな子どもがおもちゃで砂を掘っていた。
そこから人の眼球や耳や指が出てきた。
子どもの顔がサルに変わった。
nextpage
ズル
暗くて湿っぽいコンクリートの上にメルはいた。
何かに体を引きずられていた。ひどい吐き気がした。
立ち上がろうとしたとき、ようやく自分の太腿から下が無くなっていたことに気づいた。
「ハラ?」
メルは何かの冗談だと思って笑った。
「ナンハノ」
足の代わりに血の跡が引かれている。
妙に口の中がゴワついて話しにくいと思ったら、歯がすべて抜かれていた。
「ヒャナシ」
そう言いかけたとき、タンスか何かに頭をひどくぶつけたような痛みが起きた。
それはメルを引きずっていたゾゾの拳だった。
大きな檻の中には、ゾゾと、その取り巻きがいた。
メルの仲間が乱暴に振り回し、齧っていた。
脳が萎縮するくらいの恐怖が走った。
普段、観客が見下ろしている岩山。絶対に入ってはならない空間に自分一人がいる。
メルが慌てて片手をゾゾに伸ばすと、断裂音と一緒に腕ごとねじり取られた。
「ヒ?ヒ?ヒャメヘアアアア」
自身の裂けるチーズを見てしまったメルは絶叫した。
ゾゾは少し驚いたように手を離し、周辺を仲間と走り回った。
山の上からトラが降りてくるのが分かった。穏やかな顔ではない。
メルは残った腕で這いながら、出口に向かおうとする。
その必死さを笑うように彼らは手を叩いた。
出血によって体が痙攣を起こし、視界がぼやけ、口から血と胃液が交互に噴き出した。
<絶対に皆殺しにしてやる。この狂人ども>
そこまで考えたあたりで、最後の腕が象の足に踏み抜かれたように潰された。
そこにはゾウではなくゴリラが立っていた。
次いで先ほどのトラがメルの骨盤を板チョコのように噛み砕き、呼吸ができなくなった。
「グカッ」
一斉に猿たちの笑いが起きる。
<ああ。こいつらが本当の動物だったら、もう少し優しくしてくれたかしら>
ゾゾの指が器用に眼球をくり抜く寸前、
死んだ後も弄ばれる自分の姿を想像して舌を噛み切ろうとした。
そこでメルは歯がひとつも無かったことを思い出した。
separator
nextpage
これみよがしに脛を斬りつけてくる枝葉に嫌気が刺した。
私は栄養が足りない老婆のように重い足取りで、森の中を歩いていた。
道案内はチンがやってくれたので、私はただ棒のように固くなった足を振るだけで良かった。
良かったのだけれど、<そんなに元気ならおぶってくれてもいいじゃない>と思うほどにチンは元気だった。
訳の分からない虫をひょいひょいと掴んでは潰し、ときどき木に登って道を探した。
毒のありそうな蛇やカエルは次々と放り投げていた。
その光景を繰り返していると、やがて開けたところに出た。
「やった」
私は自分に頷きながら、よくがんばったと褒め称えた。
道を辿れば街に着くだろう。
nextpage
動物園を振り返ったが、特に映画のような爆発は起きなかった。
メルの言うとおり、おそらくゾゾたちはあそこから出てくるだろうけど、すぐに死ぬだろう。
脱出する前、檻で園長が数匹の大型動物にいたぶられているのを見た。
どうしてシゲさんは私を助けてくれたのだろう。
あの中で起きたことは、きっと思い出には残らないというのに。
私のインターンはこれで正式に終わった。
とにかくしばらくの間、動物園に行く気にはならなそうだ。
nextpage
車が道路を走り抜けた。
そのヘッドライトがやたらと眩しく感じた。
運転席にいる男がちらっと見えたとき、私は違和感を感じて自分の体を見た。
「ああ」
裸で毛だらけで臭くて汚い体。
それを何とも思っていない自分の壊れた知性。
車という機械にすくんだ足。
こんな私を人間として見てくれる人はいるのだろうか。
人間の住む世界で暮らしていけるのだろうか。
あっちの食べ物よりそこにある木の実の方がずっとおいしそうだ。
nextpage
なんて思うわけがない。
「さすがに懲り懲りよ。全身を永久脱毛して、熱いシャワーを浴びて、
お寿司とピザとラーメンを食べて、安っぽいベッドにダイブしに行くわよ」
<ンッ>
私の視線に気づいたチンが手を差し出したので、
残りわずかな鱈昆布を取り出した。
「あなたのことアレックスって呼んでいい?」
<ンッ>
「チンって名前は忘れなよ。アレックスでいいよね」
<ンッ>
「いやもう無いってば」
<フボォ>
「知らないわよ。あんた人生で鱈昆布しか食べないの?」
チンは首を横に振ったので私は呆然とした。
「言葉が分かるなら最初からそうしてよ!」
nextpage
それから私たちは、彼がアレックスとして生き、アレックスとして死ぬまで、日当たりのよいワンルームで穏やかに過ごした。

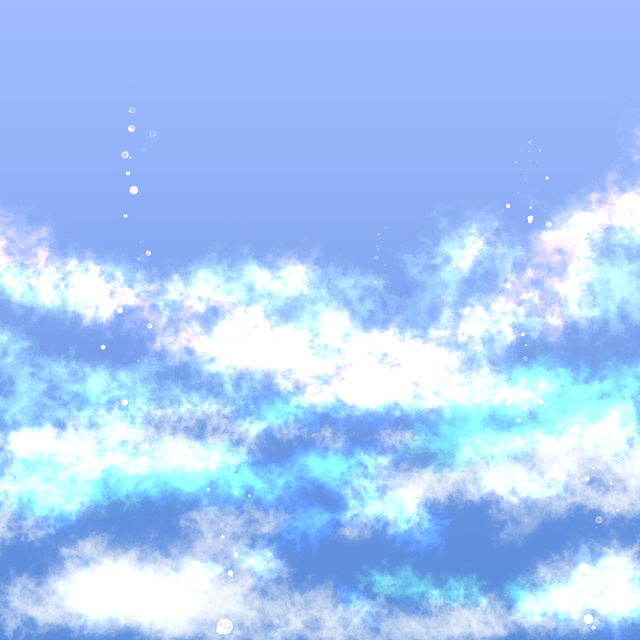
作者ホロクナ
漂うB級感ですね。
ミミズクが好きです。でもオランウータンの方がもっと好きです。