とある友人に聞いた話。
separator
nextpage
彼は大学入学を機に念願の一人暮らしを始めたのだが、張り切っていたのは最初の数ヶ月だけで、すぐに自堕落な生活を送るようになった。
昼過ぎに起きて夕方までダラダラと過ごし、それからアルバイトに出かける。深夜まで働き、その後バイト仲間と少し遊んでから、明け方に帰宅し就寝。そしてまた昼過ぎに起きる━━。学生の本分であるはずの勉学が、入る余地のない生活だったという。
当然、一回生にして留年が決定した。
実家にもすでに留年通知が届いている頃だ。さてなんと言い訳しようか。いっそのこと退学し、働いてもいいかもしれない。
親不幸にもそんなことを考えながら、いつものように明け方に帰宅したある日のことだ。
いつもなら素通りなはずのアパートの集合ポストに、ふと目が止まった。自分の部屋番号のポストから、なにやら白い紙がはみ出ている。抜き出してみると、それは一通の封書だった。
差出人の名前はなかったが、友人はその筆跡に見覚えがあった。その達筆な筆文字は、彼の亡くなった祖父のものによく似ていたのだ。
まさか、じいちゃんからじゃないよな。
冗談交じりにそう思いながら、部屋に帰って封を開けてみた。丁寧に三つ折りされた便箋を開くと、
「お前は、なんばしよっとかぁ!!!」
聞き覚えのある怒声が響き渡り、友人は腰を抜かした。
それは確かに、亡くなったはずの祖父の声、叱り方だった。
怒声は一度きりで、その後はなにも起こらなかった。恐る恐る便箋を見ると、なにも書かれていなかったという。
彼はその後、両親に頭を下げて学業を続けさせてもらった。心を入れ替えて励み、学部を首席で卒業したそうだ。
separator
nextpage
「今でも、気が緩みそうになるとあの手紙を開くんだ。祖父はちゃんと叱ってくれるよ。ただ最近、力が弱くなったのかなぁ。勢いも声も小さくなってね。開くと音が鳴るクリスマスカード、あるだろ? あれが古くなった感じで、笑えるよ」
笑える、と言いながら、友人はどこか寂しそうだった。
私は、大人になっても叱ってくれる存在があることを、少し羨ましく思ったのだった。
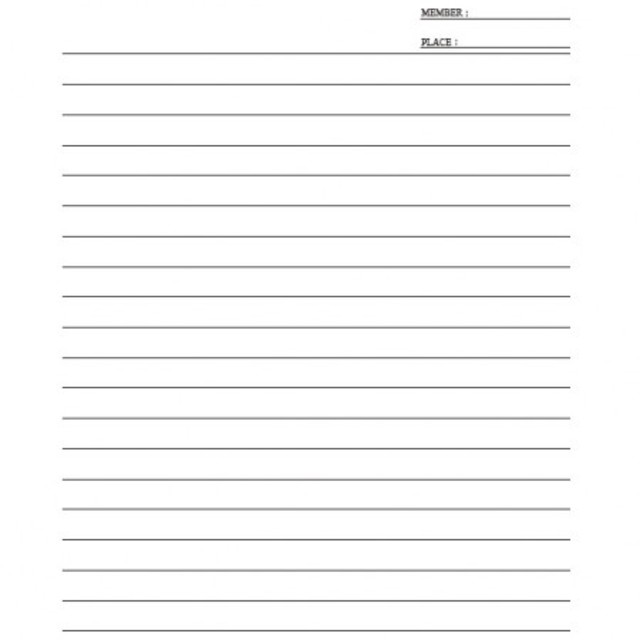





作者実葛
以前他サイトに投稿していた作品を、加筆修正したものです。
画像を投稿してくださった方、ありがとうございます。