ーカンカンカンー
遠くの方から消防車のサイレンがこちらに近づいてきた。
俺は今日1日中、近日大学内で行われる試験に向け、部屋に籠りきりで勉強をしていた。
なんだか外がやたらと騒がしい。
俺は気になって閉め切っていたカーテンと窓を開けた。
外にずいぶんと人集りが出来ている。それに、どこか焦げた匂いがする。
どうやら近所で火災があったようだ。
こんな状態では、気になって勉強どころではない。
俺はそう思い様子を確認しようと外に出た。
そして、野次馬に紛れて俺はサイレンの音がする方へ駆け寄った。
すると、驚く事に火災の原因は俺が借りているアパートから3件隣の戸建て住宅からのものであった。
近づけば近づく程、より一層轟々とさせるサイレン音。
俺は人混みを掻き分け、その火災現場の前に到着した。
メラメラと加減を知らず焼き尽くそうとする炎は、実際目の当たりにすると口を噤むんでしまうほどの凄まじい光景であった。
家はこれから全焼に向け、様々な箇所を臙脂色の熱が蝕んでいく。
「ここっていつもの.....」
「ええ.....あの子の.....」
周りからボソッと、そんな会話が漏れてきた。
俺は最近この住宅街のアパートに一人暮らしをする為に引っ越してきた。
そんな俺でもこの人達が言っている意味を理解することができた。
separator
これは俺が引っ越して間もない頃。
某ファミリーレストランのアルバイトからの帰り道、時刻は22時30分くらいだったと思う。
「あ”~!!」
その家からどこか幼い子供と思しき叫び声が聞こえてきた。
俺は驚きのあまり一瞬身体が震えた。
そして、その家に目をやった。
どこにでもある普通の戸建ての家だ。そして、2階の部屋の窓に電気が付いていた。
こんな時間になにを騒いでるんだ。
そう思ったが、まぁゲームかなにかでもしているんだろう。
その日俺はその程度にしか考えていなかった。
俺は毎日その家の前を通る。そして今日もアルバイトがあった為、昨日とほぼ同じ時間にその家の前を通った。
すると今度は、「だからお前はー!!」
今度は野太い男性の声だった。
俺はまた咄嗟に声がする方へ目をやった。
2階の電気が付いた部屋の窓からその声の主と思しき者が見えた。
少し遠くて、しかも俺は視力があまり良い方ではない。その男性の顔をはっきり確認する事はできなかった。
しかし、声を張り上げたその男性が次の瞬間、ゆっくりとこちらに身体を向け始めた事はハッキリとわかった。
やばい!目が合ってしまう!
咄嗟にそう思い、俺はその窓から目を背け、足早に帰路へ向かった。
どこかあの家に違和感を覚えて胸がザワつき、その日はあまり熟睡できなかった。
次の日、俺はそんな状態で大学に向かった。
今日は一限からの講義なので朝が早く、やはり少々寝不足気味だった。
「まぁ、今日は午前で終わるしアルバイトもないし帰ってゆっくり寝よう。」
俺はそう思い、またあの家の前を通過する時だった。
ーガチャー
その家の扉が開く音がした。
パッと俺はその音のする方へ目をやった。
そこには小学校低学年ぐらいの子供が顔を俯かせてヌラヌラと出てきた。
その表情は薄暗く、この世の果てを目の当たりにしたかのような雰囲気を醸し出していた。
俺はその子を見ていたが、その子は俺に気付く事なく俺の前の通過していった。
そこで俺はあることに気が付いた。
ランドセルを背負ってない.....。
普通なら学校に行く時間だというのに、その子はランドセルはおろか、その他の荷物を何も持たず、ただどこかに向かって歩いて消えていった。
俺はその様子をボヤっと見ていたが、ここで俺は時間がない事に気が付いた。
その時は深く考えず俺は大学に急いで向かった。
ギリギリ間に合い講義を受ける事が出来たが、講義中俺はどこか上の空だった。
先程の子供が妙に気になってきた。
あの子は学校に向かって歩いて行ったんだろうか。しかし、手ぶらというのはどこかおかしい.....。教科書やノートは学校に置いているのだろうか。
それにあの表情.....。あの夜、あれは騒いでいたのではなくもしかして.....。
昨日の夜、あの野太い男性の声は.....。
様々な憶測が脳裏に過る。
しかし、全ては憶測に過ぎない。
「考えすぎか.....。」
俺は一旦考える事をやめ、講義に集中した。
separator
大学帰りのいつも通る川沿いの道、あの子はいた。
川をボーっと見つめるその子は、どこか虚ろげな表情を浮かばせていた。
本日2度目の遭遇となる。
この時間にこの場所に居るということは、やはり学校には行ってないようだ。
あの子は俺に気付かず、ただ落ちている石をカチャカチャと擦らせ始めた。
声を掛けようか.....。
俺は不意にそう思い、逡巡としながらあの子を見つめていた。
すると、あの子は徐に立ち上がりその場を離れようとしていた。
「あっ、なぁ!」
俺は思わず声が出た。
クルっとその子は俺の方を見た。
それがその子と初めて目を合わせた瞬間だった。
「.......」
その子は無表情で口を開け、なにかを言葉を発してるように見えるが、音声が聞こえてこない。
少し距離があるから俺の耳に入ってこないだけで、もしかしたらなにかを言っているのかもしれない。
その時なぜその子に話しかけてしまったのか、自分でもよくわからなかった。勢い任せに言葉を発してしまい、その後どんな会話をするか一切考えていなかった為、どこか気まずい雰囲気を漂わせていた。
俺は無言でその子に近づいていく。
一歩、一歩とその子に歩み寄り、その距離は1メートル付近まで到達した。
季節は9月でまだまだ暑い時期だというのに真っ白無地のロングTシャツを着ている。まぁ、別に不自然ではないが、この子の場合どこか妙な受け取り方をしてしまう。
髪は肩まであるが、伸ばしているというより、ずいぶん切ってないだけのように思えた。そういう髪質なだけかもしれないが、見た目はガシガシに傷んでいるように見える。今朝初めて会った時は顔があまりよく見えなかったから女の子かな。と思ったがよく見ると男の子だった。
「.......」
この距離でも口を開けているが言葉が聞こえてこない。
「こんな所でなにしてるの?」
俺は唐突にそう質問してみた。
「.......」
やはり返事は返って来ない。いや、本人は返しているつもりかもしれない。
吃音症....?
パっと脳裏に過った。最近大学の講義でこの症状について触れたばかりなので、この瞬間、もしかしたらそうではないかという疑惑が生まれ始めた。
吃音症には難発型といって言葉を発したくても一向に声が出ないことがあるらしい。原因として、遺伝的要因、発達的要因、環境要因などがあって、俺の勝手な偏見では環境要因だとなぜか推定してしまっている。いや、そもそも吃音症だと断定できるわけではない。最近学んだことだからか、勝手にそう解釈してしまっているだけか......。
それより、もしこの光景を第三者が見たら、なにかしらの事件だと勘違いされそうだな.....。
このまま何もなかったかのように立ち去るべきか.....。俺は冷静にそう考えた。
しかし、どうしても気になってしまう。この子から発せられたかわからないが、あの謎の奇声や、この子の父親だと思われる怒声。この2つの情報とこの子の独特な雰囲気、虚ろな表情、どうしても自分の中で疑ってしまう。
この子が虐待を受けている可能性に.....。
俺はまじまじとその顔を見た。どうやら痣のような跡はない。俺は少し安堵はしたがそれだけでは疑念は解けない。その覆い隠された前腕が気になってしまう。
強引にその手首まで覆われた白い袖を捲り上げるか?それとも「腕を見せてくれ。」と直接言葉で頼んでみるか?
どちらもしっくりこない。俺は自分の中でどこか、もどかしい思いが募っていた。
すると微かに、「ぁ.....。」
小さい、極々小さい声ではあるが、それは確かにこの子から発せられた音だった。
「え?」
俺は手を広げ、耳の後ろであてがう仕草をしてそう聞き返した。
「.......」
また沈黙の時間が訪れ始めた。
なかなか会話までは発展できない。どうやらこの子は自分のペースがあるのかもしれない。今、もしかすれば俺が聞き返すそぶりをしなければ、そのまま何か話してくれたのかもしれない......。それなのに俺は変にこの子のペースを妨げ、また萎縮させてしまった。
なにも起らず、なんの会話も進まず、ただ子供と大人が顔を合わせ、佇んでいるだけの時間はどこか新鮮で、それでいて、なんだか奇妙な空間とも言える。
俺はこの子を直視しているが、この子はキョロキョロと視線を俺に向けたり、別の所に向けたりでかなり動揺させてしまっている。この子の立場で考えれば、かなりのプレッシャーになっていると自分でも理解できている。でも、俺は目を逸らすことが出来ない。なぜか目を逸らすとこの子は一瞬でどこかに消えてしまう......。そんな気がしてならないから......。
しかし、さっきから俺はなにをしているのか.....なにがしたいのか.....このままでは埒(らち)が明かない。
「あっ」
俺は思わず声が出た。
先程から俺は自分のなかで「その子」、「この子」と呼んでいるがそういえばこの子の名前すら知らない。俺がこの子にした最初の質問は「こんな所でなにしてるの?」だった。
今思うとその質問は、答えの幅が広く、どこか内容をこの子任せにしてしまっていた。いきなり見知らぬ大人が話しかけてくるだけでも子供にとっては不審に感じてしまう。答え方によっては怒られてしまう質問と捉えられてしまう。そう感じるのが普通ではないか。俺はかなり自分本位、自分の都合だけで物事を発展させようとし過ぎているだけじゃないのか。
なので、俺は先程より声をワントーン上げ、出来る限りの優しい言葉遣いで「名前はなんて言うの?」と訊いた。
これも、この子からすれば不審と捉えてしまうかもしれないが、今回の質問は答えが1つしかない。先程のような自分の頭で言葉を整理して、それを自分で、自分の言葉を考えて、答えなければいけないような内容ではなく、シンプルに自分の名前を言えばいいだけなのだから答えやすいはず......。俺は自分で勝手にそう言い聞かせ、質問の返答を待った。
すると、「......ツカ....サ......。」
そうボソッと呟いた。
「ツカサ.....?ツカサ君って言うの?」
ツカサは小さくこくりと頷き、また目線を俺から逸らし、周囲をチラチラ見始めた。
正午に差し掛かるにつれ日差しが強くなり、肌をじりじりと熱している。しかし、それとは裏腹に、耳を澄ませば川の潺が心地よく、どこか涼し気な、優雅なメロディーが耳管を通り抜け、心に染みわたって来る。
「ツカサ君はここでなにしてるの?学校は?」
今ならいけると身勝手な雰囲気を嗅ぎ取り、両手を膝に当て、少し前屈みの姿勢で俺は立て続けに2つの質問を投げかけた。
「......学校は..ぃ....ってな...い......。」
ツカサはかぶりを振りながらそう言った。1つ目の質問は答えてくれなかったが、2つ目の質問は所々途切れてはいるが、なんとか答えてくれた。
「そっか......その事をお父さんとお母さんは知ってるの?」
そう言った瞬間だった。
先程までトロりと落ちていた瞼が突然吊り上がった。
一瞬、ギョロっとした双眸が俺に視線を合わせたかと思うと、クルっと俺に背中を向け、川沿いの道を駆けずり始め、そのまま見えない所まで消えていった。
「やってしまったか......。」
俺はそう思い、頭を掻いた。
ツカサにとって今の発言は恐らく禁句だったのであろう。なにがあったかわからないけど、家庭環境に問題があることは明白だった。
ふと、「俺はツカサを心配しているのか.....?」
そう考えてみたが、それは少し違う気がした。
ツカサにとって、それはとても複雑な想いではあるが、俺にとっては所詮他人事。自分でそう思い、なんと酷い男なのだ......と感じる事もあるが、本心はそうなんだろうな.....と冷静に感じる事もできた。
ただの興味本位。あの家から漏れる不可解な声から、俺がツカサに近づいた理由、それは本心では本当にただの興味本位。
結局俺はあの家に住む子供は『ツカサ』と言う名前である事しかわからなかった。
あの子供の悲鳴とも取れる声と野太い父親の罵声とも取れる声の原因や経緯は全て謎のままである。
「.......」
それにしても、人に名前を名乗らせておいて、自分の名前は一切言わないとは....つくづく自分は酷い男だな。そう思いながら俺もツカサとは逆方向の川沿いを歩き、帰路へ向かった。
separator
3度目だった。
今日またツカサに会った。向こうからすれば2度目の遭遇かもしれないが、俺にとっては3度目の遭遇となった。
またも、この川沿いの道。あれから俺はアルバイトの帰りに必ず通るあの家を自然と意識していたが、あの悲鳴らしき声や怒声らしき声も聞こえてこなかった。ただの早とちりだったのかもしれないな。と思っていたが、今日もツカサはどこか遠くを眺め、虚ろな横顔を覗かせていた。
「なにを見てるの?」
俺はまた自然と口を動かせていた。
夕焼けに照らされたツカサの横顔からは、どこか底深い想いを感じ取れ、放っておくことが出来なかった。しかし、これもまた、ただの興味本位に過ぎないのかもしれない。
「.......!」
いきなり声を掛けられて少し驚いたのか、一瞬瞳孔を開かせながら俺を凝視したが、すぐに元の虚ろな瞳に戻り、また遠くを見始めた。そして、その見つめる方向を指でそっと指し示した。
その方向を俺も共に眺めた。
「夕陽......?」
ツカサはただ真っ赤に染まる夕陽を神妙な面持ちで眺めていた。俺は夕陽とツカサを交互に一定のリズムで確認するが、俄然意味はわからない。
「夕陽がどうかしたの?」
また逃げ出されないように慎重に、出来る限り朗らか口調で俺は訊いた。
「....どう...すれば....ああなれるかなって......」
「?」
俺は首を傾げた。
「どういうこと?」
また朗らかな口調でそう尋ねてみた。
「.....」
また沈黙の時間が場を支配する。
すると、ツカサは徐に立ち始めた。
「もう....いくね.....」
そう言い残し踵を返した。
もうじき夕焼け空が沈み、辺りは暗くなろうとしていた。俺はツカサの背中をぼんやり眺める。暗がりへ向かって去っていくツカサの後ろ姿は、どこか遠くへ、俺の知らない暗い虚無の世界へ向かっているような、そんな印象を受けた。
そして、その日以来、俺はこの川沿いでツカサと会うことはなかった。
相変わらず俺はあの家の前を通るが、あの家からは何も聞こえてこない。もう人なんか既に住んでないのかと思わせるぐらいに静寂としていた。
近くの住人も、ハッキリと言葉には出さないが、あの家を通る度に、どこか訝しむような面持ちで眺め、通り過ぎてゆく。あの家は一体どうなっているのか.....近隣の人間もツカサの事はちょくちょく目撃するそうなのだが、両親は一切見た事がないらしい。近くのファストフード店で近隣同士の会話から、そんな話を耳にした事がある。
separator
そして、今に至る。
俺の目の前であの家が轟々と溶けてゆく....
木材が崩れ落ちる音はどこか虚しく淡々としていた。消防隊が駆けつてホースで消化を試みているが、一向に消え去る事なく燃え続けている。まるで意思があるかのように踊り狂い、炎の激しさが増す一方だった。
その後は一瞬だった。結局家は全焼し、全て灰となった。周りの騒がしい声は段々と静まり返り、なんとも言えない空気になってしまった。しかし、まだ火は完全に消えた訳ではない。
「危険ですので速やかにここから離れて下さい。」
消防隊の1人が俺含め、周りの人間にそう指示を出した。
俺も仕方なくその場を離れる事にした。
少し離れた所で周りも俺と同じようにあの家のあった場所を眺めていた。「家の中に人は居たのかしら.....」と周りがひそひそと声を漏らしていた。
「え....?」
俺は思わず声が出てしまった。周りに聞こえないぐらい小さな声だが....。
見えていたのは俺だけだったのか....?あの轟々と燃え盛る炎の中、2階の窓からツカサが顔が視えた。目が悪い俺でもハッキリと。しかし、周りは誰も気づいてない様子だった。
そして、これは憶測ではあるが、恐らく出火させたのはツカサだ.....。その理由まではわからないが、俺は何となくそう思った。
なにがツカサをそうさせたのか。俺が何気なく送っている平凡な日常もツカサにとっては贅沢なものだったのかもしれない。ツカサの日常はどんなものだったのか。苦しかったのか?それとも単につまらなかっただけか?もう問いかける事はできないが、俺は心の中でツカサに問い掛けた。
もちろん答えは返って来ない。だが、少なくてもツカサは満足しているはず。なぜなら、あの時のツカサはいつもの虚ろな表情ではなかった。自分の身体は悉く燃え盛っているのに、どこか満足な様子のツカサは、まるで付き物が取れたようにとびきりの笑顔だった.....。



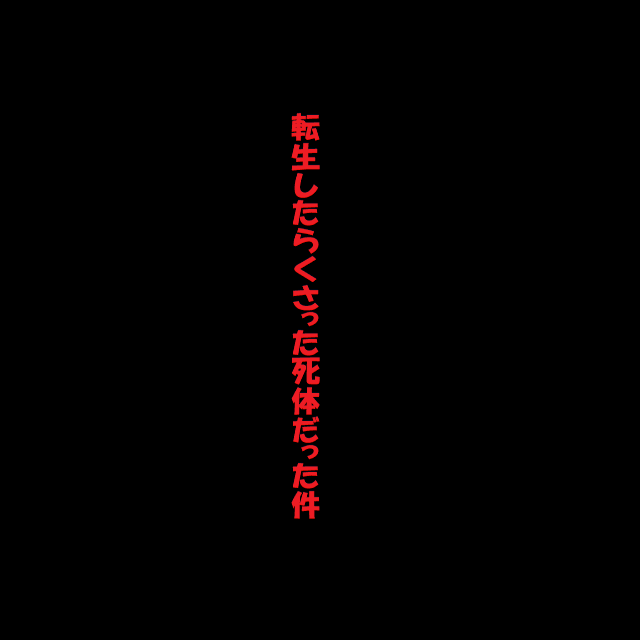
作者ゲル
今回は短編にしようと思ってたけど、いつの間にか.....。