wallpaper:5406
アルカディアベイ南西のとある一区間にあるアパート。その一室で目を覚ました。
目覚めは最高だった。だけど─。
目覚まし時計が1時15分を指差したまま止まっていた。夜間に故障したのか。
まったく目覚まし時計としての職務はおろか、時計としての職務も放棄していた。まあ、今の僕が説教できたことではないのだが─。
目覚まし時計が声帯を持っていればこう反論しただろう。仕事を無くしたお前を起こす必要なんてない、ってね。
目覚めてからさっそく自虐的になった僕だったが、窓から差し込むやわらかな陽光のおかげでいくらか気が和らいだ。しかしさっきから、なんだか落ち着かなかった。
おそらくだが、それは時刻のせいだと思う。こんな状況にならなければ気づかないことだったが、僕たちは社会的な動物として時刻を知らないという状況を居心地が悪いと感じるようだ。
そんなような実に役に立たない発見をしたところで、僕は洗面台へと向かうべく、ベットから立ち上がって、寝室の扉へと歩みを進めた。だが、寝室の扉を開けてすぐのことだ。
僕は異変に気がついた。そこにいるはずのない者がいたんだ。
窓辺で頬杖をつきながら、物憂げに窓の外を見つめる女性がそこにいた。
僕はなんと声をかければ良いのかがわからずにしばらくの間その場に棒立ちしていたのが、なにか気配を感じたのか、ふいに女性がこちらに顔を向けた。息を飲んだ。
長いまつ毛に装飾された琥珀のような瞳に見惚れたわけではない、彼女の身体には窓からの光芒が差し込んでいたのだ。彼女は半透明で、それはまさに幽霊と呼ぶべき存在だった。
「こんにちわ」つんと冷たい水面に滴が落とされたように彼女はそう挨拶した。
「どうも」僕はとっさにそう返したが、はたしてそれが正しい反応だったのかと自問自答した。本来であれば、叫んだりとかしたほうが良かったのではないか。
だって、普通に挨拶を返してしまったらその状況を受け入れることになる。もしも彼女が脅かすつもりでそういったのであれば、僕は極めて間違った反応を示したのではなかろうか。
そんな勝手な自問自答をしていると、彼女はふたたび声を発した。「驚かないのね」彼女はそう言った。
つまり、先ほどの挨拶はやはり驚かせようとしていったのであろうか。まあ、ともかく─。「驚いたよ、正直」
僕はそんな平凡な返答をしながら、彼女の近くまで足を運んだ。おどろおどろしい見た目でないからなのか、不思議と恐怖は感じなかった。
むしろ、好奇心の方があった。近づけば近づくほど、それは不思議さを増すばかりだった。
半透明な彼女の身体を通して奥の本棚を見ることができる。服を着ているのに透けているというのはなんだかおかしなものだ。
「そんなに見つめないで」僕が穴が開くぐらい視線を送っていたので、彼女はややバツが悪そうに苦言をていした。
「ああ、ごめん」僕はすぐに失礼を詫びたが、すぐに彼女から目を離すことはできなかった。
なんといっても今までにないことだったから、幽霊を見るなんていうのは。僕は子供の頃の好奇心を取り戻したようになんだか楽しくなった。
「君はなんていうの?」「クリスティーン」
彼女は窓の外を眺めながらそう答えてくれた。
「僕はジャック」「そう」
興味がないようだったが、僕は質問を続けた。
「普段は何をしてるの」「待ってる」
「何を」「花が散るのを」
窓の向こうを見つめる彼女の視線を追うと、そこにはチャペルがあった。そして、その手前の花壇には爽やかなマリンブルーに咲き誇る花がある。
「あの花が散るのを待ってるの」僕はそう尋ねたが彼女は返答してくれなかった。
それ以上彼女は答えたくなかったのか。僕は質問を変えた。
「いつからここに」「ずっと」
その言葉を耳にした僕はこの部屋での生活を思い出して、とたんに羞恥心がこみ上げてきた。そして、僕の羞恥心を感じ取ったかのように、彼女は窓からこちらへと視線を動かしてこういった。
「ずっといたよ」彼女は不敵な笑みを浮かべた。
「じゃあ─」僕がそう言い掛けて、彼女が声を被せてきた。
「あなたが8時に出かけて、10時に帰ってくることも。帰ってきてから2錠の眠剤を飲んで眠ろうとするけど、なかなか寝付けないことも。部屋の中でぶつぶつ独り言を呟くことも。たまに、鏡と向き合って自分を励ましていることも」
「ちょっと待って待って」僕は彼女を制止しようとしたが、彼女は止まらなかった。
「仕事が上手くいっているとき、別れた彼女とよりを戻そうとしていたことも。でも、上手くいかなくて落ち込んでいたことも。おまけに勤め先の会社が経営難に陥ったせいで、仕事を首になったことも。そして─」
「ちょっとっ」僕はさっきよりも大きな声を彼女に被せた。
「もう、わかったから。悪かったよ」僕がそう言うと、彼女はにかっと意地悪な笑みを見せて、ふたたび窓の向こうに顔を向けた。
「見られてたなんて最悪だ。死にたいよ」「皮肉ね」
これが僕と彼女の不思議な同居生活の始まりだった。
「で、君はこの部屋で首を吊ったってこと?」「ええ」
初めての出会いからしばらくたったある大雨の晩、僕は彼女が幽霊になる経緯を聞かせてもらった。彼女には失礼だがその経緯は案外ふつうのことだった。
人生に嫌気がさして自死した、らしい。あまりにも平凡といっては角が立つが、もっと劇的な経緯があると思っていた僕は少しだけ拍子抜けしてしまった。
だって、幽霊として部屋に化けて出るんだから、何か現世に未練があるのかと勝手な想像をしてしまうではないか。そうなのだ。
ここまで聞いて僕は、ある疑問を彼女にぶつけずにはいられなかった。
「クリスティーン、君は何か未練があったりする?」
彼女はあいかわらず窓辺に居座っていて、雨が降りしきる室外を漠然と見ていた。ときおり吹き付ける突風が窓枠をがたがたと不気味に揺らす。
わざわざ僕の方へ顔を向けることはないが、彼女はちゃんと返答はしてくれた。
「いいえ、そんなものはないわ」「じゃあ、どうして君はまだこの部屋にいるの?」
彼女はすぐに答えてはくれなかったが、しばらくして口を開いた。
「埋葬されなかったものはずっと漂いつづけるの」「どういうこと?」
「ジャックはこの部屋の借りる時に何か聞いた」「いや─」
僕はこのアパートの管理人との会話を思い出してみたが、何か印象に残ることは言ってなかった気がする。
「何も聞いてない」「じゃあ、おかしいと思わない」
僕ははっとさせられた。
「あなたの前には私が住んでたの。私は死んだ。なのに事件にもなっていないし、あなたも知らなかった」
「まさか」彼女の死は隠蔽されたと言うのか?
「でも、どうして?」「さあ」
理解可能な範囲を考慮するとすれば、管理人はアパートの価値を下げたくなかったのだろうか。アパートの一室で自死したものがいれば、こんな小さい街ではすぐに噂になるだろう。
借り手がいなくなることぐらいは容易に想像がつく。管理人はそのことを恐れたのだろうか。
「そんなのってっ」怒りが沸沸と湧き上がった僕は思わず声を張り上げた。
彼女は視線だけを僕に寄越してこう言った。「でも、勝手に死ぬほうもおかしいわ」
それはぽつりと雨が屋根を叩くように部屋の中で響いた。僕は、何も言い返してあげることができなかった。
そして、彼女は語った。自死した当日、管理人には手紙で伝えていたという。
彼女なりの配慮だったというのだが、今にして思えば迷惑をかけますと知らせるのが配慮だと思っていた自分がどうかしていたと、彼女は思い出して苦笑していた。
彼女が幽霊として意識を取り戻した時には、管理人が彼女の骨だけを壁の中に隠していたのだという。どうやら管理人は彼女の遺体を解体したようで、骨と肉を引き剥がして処分していたようだった。
彼女曰く、肉はこまかく刻んでトイレから下水道へ流したのではないかと言う。骨は流すことができないから、壁をくり抜いてそこに隠すことにしたんだと思う、と彼女は平然と語った。
それからしばらくして警察が彼女の部屋を訪れたが、まさか壁の中に骨があるなんてことには気づかずに、最終的には失踪したということになったらしい。それからしばらくして、管理人がふたたび部屋を訪れた。
管理人は壁をくり抜いて、骨の入った袋を取り出すと、どこかへ持っていったという。おそらく、燃やしにいったんじゃないか、と彼女は言った。
確証はないが、いずれにせよ、自分がこの世にいた証拠はもう何も残っていないだろうって。そんなふうに彼女は語り終えた。
彼女はあいかわらず窓の外を見つめたまま。彼女は幽霊なのに窓ガラスには映っていて、雨粒がつるつると伝い落ちているのに重なって、彼女の頬に涙が伝っているようだった。
「じゃあ、ずっとここにいるってこと」彼女は沈黙したままだったが、まさにそれが答えだった。
彼女はこれからずっとこの部屋に囚われるのだ。ずっと。ずっと。ずっと。
「こんなの生き地獄じゃないか」僕がそう呟くと彼女はこちらへ振り向いた。僕と視線をぴったりと重ねて、そして、笑って見せた。
「もう、死んでるのよ」僕はそのユーモアを笑うことはできなかった。彼女の笑みは強がりにしかおもえず、ただひたすらに胸が痛んだ。
「僕にできることはあるかな」それは勝手に、僕の口から吐いて出た。
彼女はふっと柔らかく微笑むと、「なにもないわ」彼女は窓の外へ視線を戻した。
その晩はそれ以上、言葉を交わさなかった。ただ、初めて触れることができた気がした。
もちろん、ちょくせつ触れることはできないけれど、彼女の心に触れることができた気がしたんだ。
それからも僕と彼女の生活は続いた。
だけど─。
三人目の同居人が訪れて、事態は一変した。
それは晴天の真昼だった。
僕たちが部屋にいて、とつぜん玄関扉が開かれたかと思うと、二人の人物が入ってきた。
一人は管理人だった。もう一人は知らない女性。僕はいきなり訪れた管理人の前まで行くと、何の用かと尋ねた。
クリスティーンは自分の死が隠蔽されたことを自業自得だと考えているようだが、僕は管理人が隠蔽したことに対して怒りがあった。彼女をこの部屋に閉じ込めたのはこの管理人なのだ。だからその口調が荒々しくなっていたと思う。
だが、予想外のことが起こった。
目の前にいるのに、管理人はまるで僕が見えていないようだったのだ。それどころか─。
「どうです?いい部屋でしょ。前の住民が家具もそのままに出て行かれましたから、わざわざ揃える必要もありませんよ」
管理人は、部屋を眺める女性に対してそう説明した。僕は言葉を失った。
管理人に触れようとしても、透き通っていて触れることができなかった。いや、僕自身が透き通っていたんだ。
唖然としつつも僕は窓辺にいるクリスティーンを見た。彼女も僕の方を見ていて、憂うような視線を送っていた。
そう。僕はもう、生きてはいなかったんだ。
その後、管理人と女性が部屋を出ていくまで、僕はずっと床にうずくまったままだった。悲しかったわけではない。ただ現状を受け入れられなかったのだ。
「こんなことって」今までなんで気づかなかったのか?食事をしたり、買い物へ行ったり、まったく違和感なく日常を過ごしていたつもりだったのに。
それは──、勘違いだったのか。いったいつから。そんなとき、彼女は僕に声を掛けた。
「へいき?」僕は彼女にこう返した。
「ああ、多分」「思い出した?」
「知ってたんだね」「ええ」
「どうして教えてくれなかったの?」「最初は言うつもりだった。だけど、機会を逃して、それからは言い出せなかった」
「そっか」彼女が言わなかったことに腹は立たなかった。逆の立場だったら僕だってそうしたと思うから。
「教えてほしい、僕に何があったのか」「ええ」
彼女は言葉を続けた。
「酔っていたのよ、冷静じゃなかった。あなたは首を吊ったのよ」僕は呆然と床を見つめた。しばらくの間、そうしていた。
「あなたの意思じゃないわ。状況が悪かったのよ。私は見てたからわかってる。仕事も見つからなくて、家賃も払えてなかった。そんなときに偶然お隣さんからお酒を貰ったのよ」
彼女は僕が落ち込んでいると思ったのか、精一杯はげまそうとしてくれていた。自分の意思で命を絶ったわけではない。彼女はそのことをしきりに僕へ言い聞かせた。
だけど、僕は気落ちなどしていなかった。ただ彼女から事情を聞いて頭に思い浮かんだ言葉があったんだ。床から顔を上げた僕は彼女を見据えて、その思い浮かんだ言葉を口にした。
「馬鹿だな」彼女は僕の言葉にやや戸惑ったようだった。その後で僕は笑いながらこうも言い足した。
「酔っ払って首を吊るなんて、馬鹿だな、僕は。そう思わない?」
彼女は僕が自らの死について思いつめていないことを知ると、「ええ、ほんとね」と笑ってそう言ってくれた。
実際、酔っ払って死ぬなんて大馬鹿だ。普通なら幽霊になって悲しんだり驚いたりするんだろうけど、これは笑うしかなかった。
「よしっ」僕は立ち上がって状況を整理するように身体を確かめてみた。半透明の身体は自分自身で触れることができた。そして、家具にも触れることはできたが、それらを持ち上げることはできなかった。
僕は部屋を見渡して、部屋の壁で目が止まった。
「まさか」「さあね、やってみたら」
彼女が挑戦してみろといったように笑みを浮かべたので、僕は思い切って部屋の壁に突っ込んだ。すぐに結果はわかった。
どんっと盛大に音を立ててぶつかったんだ。幽霊のなので痛くはなかったが、ぶつかった衝撃で地面に倒れ込んだ。
幽霊だけど壁は通り抜けられなかった。僕は笑ったし、それを見ていた彼女も笑った。
そうやって雰囲気がまたいつも通りの和やかさを取り戻した後、僕は「その後」を彼女から聞くことになった。
もちろん、おおよそは想像はついていた。彼女と同じように幽霊になっているということは、彼女と同じような境遇を辿ったのだ。
彼女曰く「私と同じだ」と言った。僕が首を吊った翌日、管理人が家賃の取り立てに訪ねたらしい。そして、首を吊った僕を見つけた。
その後は例の如くことが行われたという。
「そっか」
案外とすんなり僕は事態を受け入れられた。もちろん、それは彼女がいたおかげなんだろうけど。
「じゃあ、僕もこれからはずっとここにいるってこと?」そう僕が尋ねたが彼女は首を振った。
「えっ、だって同じなんでしょ」「起こったことは同じ、でもその後は違う。管理人には誤算があったの」
この部屋には私とあなた、二人が失踪してる。だから今回の警察官たちは管理人を疑うようになったの。
もちろんあなたの骨が壁に隠されているのは見つかってないけど、管理人が疑われているから自由に行動できなかったの。
つまり、あなたの骨を処分しに行けてないのよ。
「じゃあ─」「そう、まだこの部屋の中にある」
彼女は寝室を指差した。僕は急いで寝室へ向かうと、壁紙をくまなく確認した。だけど、僕はその境目を判別することができなかった。
すると、遅れて入ってきた彼女はある一点を指差した。指差された場所をよくよく見ると、そこには不自然なつなぎ目が出来ていた。
「こんなのわからない」「ええ、だから警察も気づかなかった。このアパートを自ら修繕している管理人だからこそ出来たことなのかもね」
僕はベットの端に座り込んで、天井を見上げながら溜息をついた。
「僕もこの部屋からは出れない」「いや?」
「君といることが嫌ってわけじゃないよ」「ええ、そうでしょうね」
「ずいぶん自信があるんだな」「違うの?」
「──別に違わないけど」彼女はふっと笑った。
「正直ね」「それだけが取り柄だよ。でも現世じゃ正直者は損をするよ」
「現世ではね」「えっ」
「正直者にとっておきの情報を教えてあげるわ。今日はだれが来ましたか?」「それは──、管理人と、あっ」
「あなたは床を見つめて呆然としていたようだけど、あの女性はこの部屋に住むことに決めたのよ」「じゃあ」
「まだ、やりようはあるでしょ」
僕は彼女を抱きしめたかったが、触れることができないので空気を抱きしめてしまった。
僕らはそれから作戦を立てた。
そして、3人目の同居人が部屋に引っ越してくるのを今かい今かと待ったんだ。
その晩、ついに決行することになった。三人目の同居人が引っ越してきて一ヶ月たった日の晩だった。
その引っ越してきた女性はだいぶこの部屋に慣れていた。僕と彼女がすぐに決行しなかったのにはわけがあった。それは管理人を呼ばれたくなかったのだ。
引っ越してきてすぐ何かがあれば、その女性は管理人へ連絡するだろうと僕たちは考えた。だから、一ヶ月という日にちを開けなければいけなかった。
一ヶ月という期間は長いようで短かった。彼女との生活は退屈なものではなかったんだ。
でも、その一ヶ月のせいで僕には迷いが生じていた。僕はこのまま彼女を残して向こうに行っていいのだろうか。本当に僕がしようとしていることは正しいことなのだろうか。
彼女は僕が向こうに行くことに対しては何も言ってこなかった。本当にこの選択は正しのだろうか。僕だってできることなら一緒にいたい。でも─。
チャンスがあるんだったら─。どうしても、希望があるのならそれに手を伸ばさずにはいられない。僕は答えをだすことができずに、その晩を迎えることになったんだ。
時刻は22時ちょうどだった。3人目の同居人、その女性はリビングルームのソファーで本を読んでいた。その女性はこの時間になるといつも本を読み終わって寝室へ向かう。
そうしたら、僕たちを計画を実行に移す。僕たちは幽霊だ。その女性からは見えないし、触れることもできない。もちろん、文字を書いて伝えることだって出来ない。
だけど、音を出すことはできた。だからといって、脅かすわけにもいかない。追い出すならその方法でいいけど、目的はそうじゃない。僕の骨を見つけてもらわなきゃいけないんだ。
難しいことは考えなくてよかった。僕たちが考えたのは非常に単純な方法だ。やがて、その女性は本を閉じて寝室へと向かった。
女性は寝室の電気を付けて、カーテンを閉めようと窓際に向かった。そして、僕たちは計画を実行した。
まずはクリスティーンが壁を引っ掻いた。細かく小さく。壁を伝っていくように彼女は引っ掻いていった。
次は僕の出番だった。口を窄めて、めいっぱい息を吸い込んだ。すると、チューという音が寝室に響いた。
その刹那、その女性は窓から壁へと振り向いた。もう一度、僕たちはその行為を繰り返した。
女性はぞっとしたように寝室から飛び出していった。そしてその晩は寝室へ戻ってくることはなかった。
僕とクリスティーンはお互いに顔を見合わせてにんまりとした。ねずみ作戦だ。
翌日になればその女性は壁の奥に住み着くねずみを駆除するために業者を呼ぶだろう。そうしたら僕はきっと──。
なんだかんだ夜が明けて朝がやってきた。9時ごろだった。
案の定、その女性は業者を連れてきた。業者は寝室の壁を剥がして中を捜索した。
そして見つけたんだ、黒いビニール袋に入った人骨を。こうして僕の骨は無事みつけられた。
彼女は自分のことのように喜んでくれた。僕も嬉しかったが、同時に心苦しくなった。
僕の骨はやがて埋葬されるだろう。そうなれば、僕はもうここにはいられない。
彼女を置き去りにしていくことになる。そんなことを分かっていたが、いまさら僕にできることなんてなかった。
僕の骨が見つかってから1日経って、彼女は僕にこう言った。
「気にしないでね」あいかわらず、彼女は窓辺で頬杖をついていた。
「ごめん」彼女は何も言わなかった。
彼女の横顔には光芒が差し込んでいて、その物憂いげな表情だった。出会った時と同じだった。
もうすぐ行かなければいけない。僕にはそんな予感がしていた。自分の骨がもうすぐ埋葬されることがなんとなくわかったんだ。
「やっぱり行くのは止めるよ」「そんなことできないわ」
「でも──」「できないわ」
沈黙がやってきた。その瞬間、僕は呼ばれた気がした。その部屋の玄関からその声は聞こえた。
「もう、行かなきゃいけないみたい」「そう」
「本当にありがとう」「いいの。気にしないで」
彼女は窓の外を見たままで、僕の方を見てはくれなかった。僕は玄関まで歩いて、ドアノブに手を掛けて、最後に後ろを振り返った。
最後ぐらい見てくれると思った。けど、最後も彼女は窓の外を見ていた。
「本当にありがとうっ。君のことは忘れないっ」大きく叫んだ僕の声は反響していった。
そうしたら彼女は振り返ってくれた。でも、差し込む光芒が半透明な彼女の後ろから差し込んで、眩い光が表情を眩ませてしまった。
彼女は手を振った。どんな顔でそうしてるのか。
眩い光に向かって僕も手を振り返した。
そして、その部屋を飛び出した。
やがて季節は何度も移り変わった。アルカディアベイ南西の1区画にあるアパートの一室での出来事だ。
青年はそこへ引っ越してきた。友人に手伝ってもらうことで、引っ越し代を数十ドルも節約することができた。
だけど、そのせいで大きな失態を犯してしまった。寝室にベットを運んでいて、そのベットの角を壁にぶつけてしまったのだ。
壁紙には大きな穴が開いた。「おいっ」
青年はベットの片側を持っていた友人を非難した。「どんすんだよ、これ」
青年は大きな穴を見下ろして溜息をついた。と、青年の視線の先に何かが見えた。
近づいて、手を突っ込んで、それを拾い上げた。「石?」
それは白い石のようなものだった。「それってまさか」
青年の友人が声を上げた。かつて、この部屋には人骨が隠されていた過去があった。
友人はその話を知っていたから、その白い石がなんのかすぐに勘ぐることができた。
「警察に届けよう」
彼らはその白い石を警察へと届けに走った。
その部屋の窓からはチャペルが見える。
その手前の花壇には爽やかなマリンブルーに咲き誇る花がある。
マリンブルーの花弁たちは風に揺られさわさわと囁き出した。
花たちは噂していた。
その日、いつもこちらを見る人物がいなくなったのだ。
チャペルの鐘が人知れず鳴った。
誰も鳴らしていないのに鳴り響いた。
なぜかその日、その花壇に咲き誇る花たちの花びらが春風に舞い散った。
誰かを祝福するように、すべて、舞い散った。

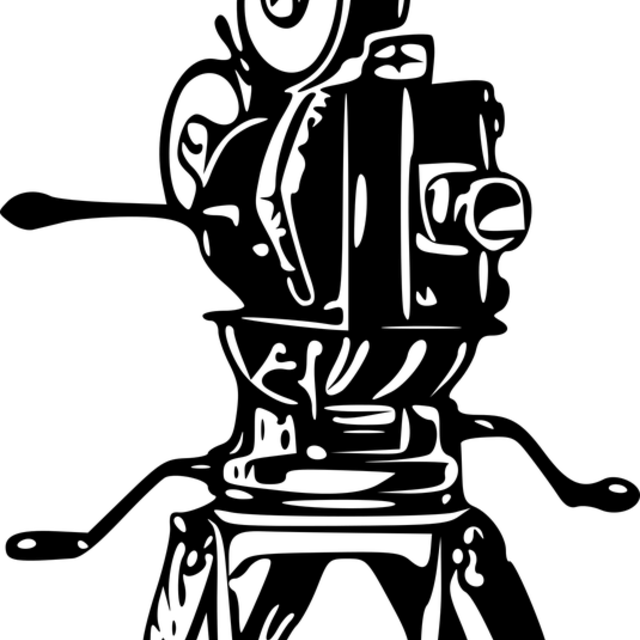
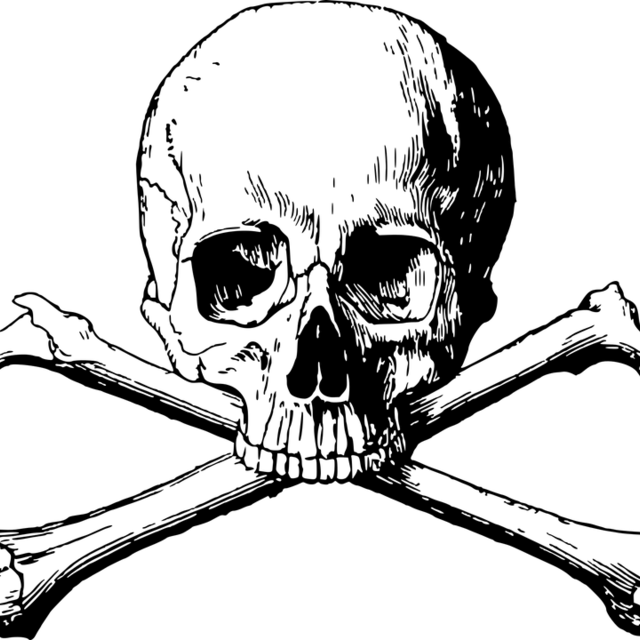
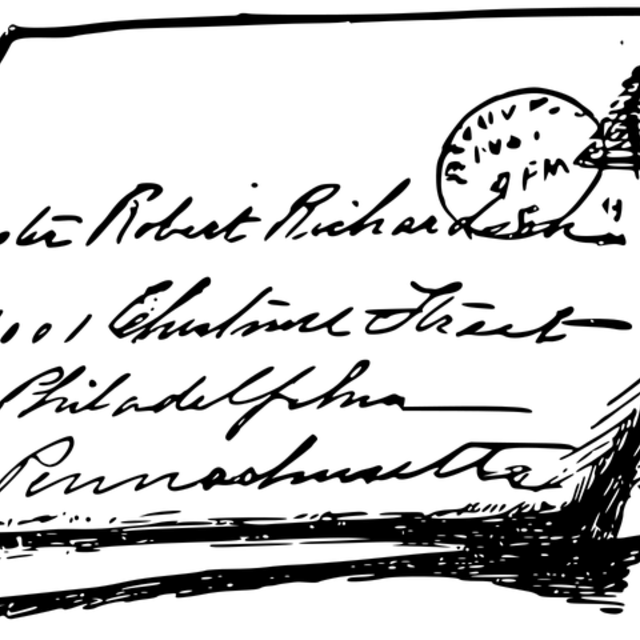
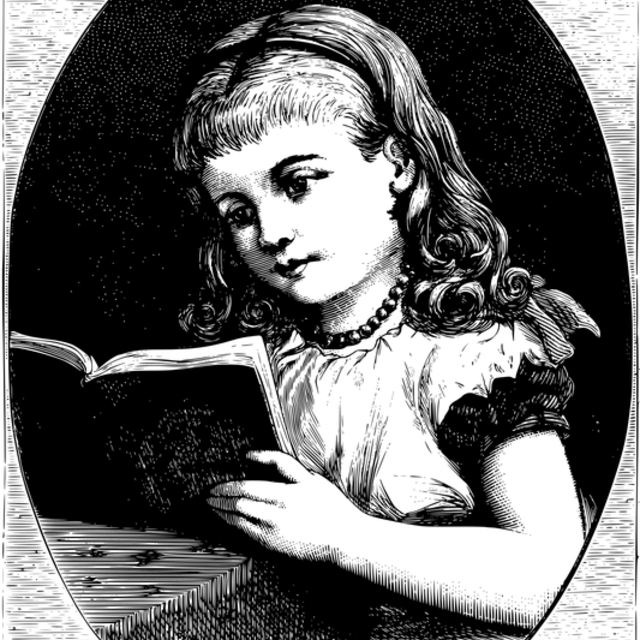
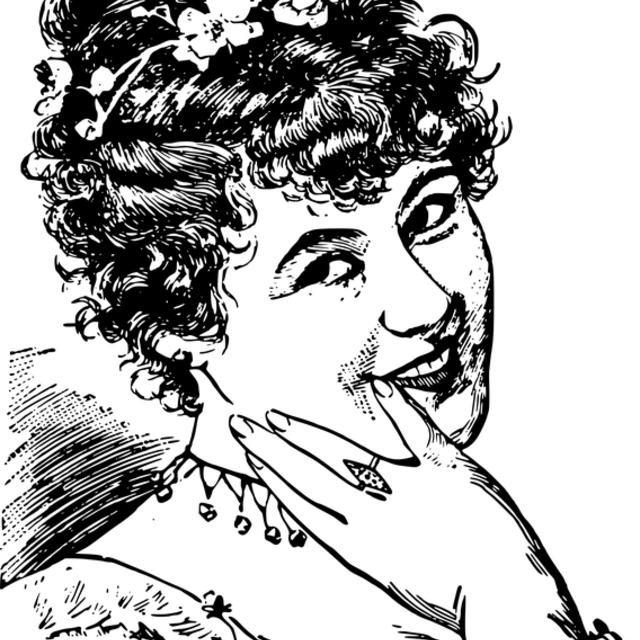
作者Yu