部屋の壁には、幾つもの絵画が飾られている。花や海、街の景色、人物画、今日もわたしは、それらをぼんやりと眺めていた。
ガチャ、と玄関の扉が開く音が聞こえる。父が帰って来たのだ。
「やぁ、今帰ったよ。アル」
「あら、お父様。おかえりなさい」
「良い娘にしてたかい?」
わたしは笑顔で頷き、父を出迎えた。父もまた、朗らかな表情でわたしを強く抱きしめ、小さく囁いた。
「アル、今日も本当に良い娘だ。私は幸せだよ」
父の身体から微かに漂う香水の香り。これは薔薇という植物から作り出された匂いだと、以前父に教わった。しかし、わたしは、その植物を見た事がなかったので、これは父の香りだと思っている。
「あぁそうだ、今日はアルにこれを渡したくてね」
そう言って、父は黒いカバンの中に手を入れた。ゴソゴソと何かを探すようにして、ちょっと待っておくれ、と言った。
わたしは首を傾げ、父の動きを見ていた。
「ほら、これを開けてごらん」
カバンから何か大きな物が入ってるであろう紫色の包み紙を取り出し、わたしに差し出した。
「お父様、これは?」
「開けてみたらわかるよ」
わたしはその包みを手に取り、上部を結んでいた赤色のリボンを外した。その瞬間、包みがサッと音を鳴らし、花が咲くように開かれてゆく。
「まぁ!お父様、素敵なぬいぐるみですこと!」
わたしは飛び跳ねるような声を上げて、包まれていたクマのぬいぐるみを抱き掲げた。
「はは、喜んでくれてなによりだよ」
リビングの天井にぶら下がっている黄金色のシャンデリアがわたし達をまったりと照らす。その光によって、ぬいぐるみはより一層輝いて視えた。
「でも、お父様、どうして?」
「なに言ってるんだい、今日はアルの8回目の誕生日だよ。私はそのお祝いがしたくてね。仕事を早く切り上げて帰ってきたんだよ」
微笑みながらそう言う父を見てわたしは、はっ、とする。
「そうだわ!わたしったら、そんな大事な日の事を忘れるなんて…」
わたしは頬を赤くさせ、恥じらうようにして父から眼を背けた。
「いや、いいんだよ、アル。私がちゃんと覚えているから、アルはそんな事、心配しなくて大丈夫」
「お父様ったら…」
頬はまだ赤くなったままだが、わたしは父の方を見ながら微笑んだ。
「あら、このぬいぐるみ、お腹になにか書いてあるわ」
そこには恐らくこのぬいぐるみの名前であろう『Eddy』という文字が記されていた。
「あぁ、気付いたかい。それがその子の名前だよ。それと、ほら、エディのお腹を押してごらん」
わたしは父の言われるがまま、エディのお腹をそっと押してみた。
シャカシャカと、まるで、わたしを祝福するかのように、エディの両手足は軽快に踊り始めた。
「わぁ、凄い!凄い!」
わたしは、真紅の絨毯の上で飛び跳ね、エディの脇を持ち上げる。父はそんなわたしを見て、小さく微笑み、陶酔的な表情を浮かばせている。
「さぁ、アル。そろそろ食事の時間だよ。エディも一緒に行こうか」
そう言って踵を返す父の後を追うようにして、わたしはエディを抱えたまま、食卓へ脚を運んだ。
テーブルを3脚の椅子が取り囲む、父とわたし、そして、エディ。いつもは父と2人だった食卓、今日に至っては、なんだか賑やかに思えた。
「ねぇ、お父様、今日のお仕事はいかがでしたの?」
わたしは、お皿に乗ったチキンを右手のフォークで抑え、左手のナイフで切り込みながら父に訊いた。
「うーん、少しやっかいな事になってね」
「やっかい?」
「あ、いや、アルが気にする事じゃないよ」
父は一瞬、濁った表情を見せたが、被りを振って、また朗らかな表情に戻る。
父の職業は正直わからない。少し前に、市街地の方へ脚を運んでいる、とだけ聞いた事がある。それ以外は、何故かわたしに話そうとしない。
わたしと父が住むこの家は『上層区』と呼ばれ、少数の富豪にしか住む事を許されないらしい。でも、言葉の意味はわからない。
今まで、わたしはこの家から出た事がないのだから。
「わたし、外の世界が見てみたいですわ…」
和やかな雰囲気の中、わたしは父に眼を向けず、エディに対してボソっと呟いた。
「……」
少しの間が空いた。
「アル。いつも言うが、外は危険がいっぱいなんだ。私はアルが心配で仕方がないんだよ。だから…どうかわかっておくれ」
父はこの話になると、いつも表情が濁る。そして、結局わたしは、外の世界を見る事が出来ない。
「さぁアル。食事も終えたから、もうベッドへ行こうか」
「はい」
わたしは肩を窄めながら、エディを連れて自室へ向う。途中、ピタッと脚を止めた
「お父様はまだおやすみになられないのですか?」
「私はまだやる事があるから、今日は先に寝てなさい、ほら、今日はエディが一緒だから寂しくないだろう」
「わかりました。おやすみなさい、お父様」
「あぁ、おやすみ、アル」
ーー
ベッドに入ると、エディの顔をまじまじと眺めた。茶の毛並みに真っ黒な瞳。わたしは寂しさを紛らわす為にまた、エディのお腹を押してみた。
先程同様に軽快なダンスを披露するエディに、ふふっ、と声を漏らし、少し頬が緩んだ。
オレンジ色の間接照明がぼんやりと辺りを照らし、壁時計の針が音を鳴らす。わたしは、ゆっくりと瞼を閉じた。
ふと、前に父が読み聞かせてくれたグリム童話『塔の上のラプンツェル』を思い出した。物語に登場するラプンツェルという少女は、悪い魔女のせいで塔に閉じ込められてしまう。なんだか、その部分だけ自分と重なり、感情移入してしまう。
しかし、ラプンツェルはまだマシだと思った。だって、塔の中から外の景色を眺める事が出来るのだから。音も聞こえるし、匂いも感じる事が出来る。でもわたしは、物語の中でしか外の世界を堪能することが出来ない。
そう考えたが、咄嗟に被りを振った。
それは、それだけ父がわたしの事を想ってる証拠、外の世界は危険が多い、そう言われ育ってきた。わたしは父に愛されてる。そして、わたしも父を愛している。それだけでも、わたしは幸せを感じなければならない。
わたしは決して囚われてる訳ではないんだ。
ーー
朝、シャカシャカという音で目が覚めた。どうやらわたしは、エディのお腹を無意識に押していたんだろう。
目を擦り、視界にはいつもの光景が広がった。幾つもの絵画が飾られた壁、深紅の絨毯、そして、これは昨日父から貰った物だが、ぬいぐるみのエディ。
わたしはエディに、おはよう、と言ってエディを連れ、自室を出た。
廊下にも、自室とは違う絵画が飾られていた。茶色の額縁に収まったその絵は、どこかの街の風景だった。これが父が言う市街地なのだろうか?わたしは外の世界を絵でしか見た事がない。だから自然と、そんな妄想が過ぎってしまう。
リビングの扉を開けると、父の声が優しく包み込むように耳を通した。
「おはよう、アル」
「おはようございます、お父様」
「今、朝食の準備をしてるから食卓で待ってなさい」
わたしはエディを抱き上げ、台所にいる父が見える位置に構える。
「あぁ、そうだね。エディも一緒に」
わたしは、ニッ、と頬を緩ませ、エディを椅子に座らせて一緒に朝食を待った。
「やぁ、おまたせ、アル、エディ」
食卓には3つのシリアルが並んだ。いつも2つだった筈だが、今日からエディの分が増えたらしい。
「まぁ、お父様、エディも食事を出来るのかしら」
わたしは別皿に入ったヨーグルトとブルーベリーを掻き混ぜながら、父に戯けた口調で訊いた。
「はは、駄目だよアル、エディはもう家族同然なんだ。私達と同じ物を食べる事を、彼も望んでる筈だ。ほら、エディにもコレを」
そう言って父はエディの分のシリアルをわたしに渡した。
「え、お父様、本当に?」
「もちろんだ。私がアルに嘘をついた事はあるかい?」
わたしは小さく被りを振った。そして、エディの分のシリアルにブルーベリーヨーグルトをかけ、父の顔を見た。
「いい娘だ、アル。エディに食べさせてあげなさい」
わたしは父がたまに見せるこの顔が内心苦手だった。表面上は朗らかな表情、口調なのだが、瞳は、一切の笑みを浮かべていない。自然と身体に力が入ってしまう。
「さぁ、アル、はやく」
父の口調が、少し急かすかのようにして、声のトーンが下がり始めた。
「はい、お父様…」
わたしはスプーンにシリアルを注ぐと、エディの口先まで持っていく。スプーンがぷるぷると震えている。なんだか不穏な雰囲気が場を支配させた。わたしはこの時いつも、父の顔色を伺ってしまう。
ゆっくりとスプーンを振動させながら動かす。しかし、途中でエディの口に当たり、ヨーグルトが口元から首先辺りまで垂れ流れ、シリアルが床に溢れ落ちてしまった。
わたしはその瞬間、意識が遠くなりそうになる。そして、父に顔をそっと向けた。
「アルは偉い娘だ。エディも喜んでいるよ」
その言葉を聞いて、わたしは胸を撫で下ろした。父の瞳と口調がいつもの朗らかさに戻っていたから。先程の身震いも、いつの間にか治っていた。
ーー
「お父様、いってらっしゃい」
「あぁ、いってくるよ。今日も良い娘にしてるんだよ」
わたしは小さく頷き、父に鞄を渡した。
でも、それはいつもリビングで行う事、わたしは玄関で父を見送った事は一度もない。
父が扉を閉める音がリビングに響き渡り、虚しさだけが室内に残る。また、数時間、わたしは1人でこの空間を彷徨わなければならない。
シャンデリアの光がどれだけ室内を照らそうが、わたしは決して明るくは感じなかった。この家には幾つもの部屋が存在するが、どの部屋も窓という物が存在していない。
外光が一切ない空間は、いくら部屋を暖かくした所で、どこか冷たく、静寂とした世界で満ちていた。
過去に何度か玄関の扉に手を触れてみたが、施錠されており、開く事が出来なかった。
エディを抱き、わたしは一つの絵画を見つめた。その絵画は黄緑の草原が生い茂る中、ぽつん、と一輪の赤い花が中央に凛々しく描かれていた。
「ねぇ、エディ、外の世界ってどんなもの?暖かい?それとも寒い?エディは外から来たから知ってるんじゃない?ねぇ、わたしに教えて」
わたしの好奇心は溢れる寸前だった。答えなんて返ってくる筈がないが、気付けば、エディにそう囁いていた。
心無しか、エディはわたしに少し微笑み掛けてくれたように視えた。
ーー
大きな振り子時計が、ゴーン、という重圧的な音を轟かせる。これは、19時を知らせる合図だった。その音とほぼ同時に玄関が開く音が聞こえてくる。
「やぁ、今帰ったよ。アル」
「おかえりなさい、お父様」
わたしはいつものように笑顔で父を出迎え、いつのもように、父の胸に飛び込もうとした。
だが、今日はなんだか様子が違って視え、妙な違和感を覚えた。いつもなら朗らかな口調でわたしを抱きしめてくれる筈、優しい雰囲気でわたしを包み込んでくれる筈、しかし、父の表情はどこか濁って視えた。まるで、あの話をしてる時のように…
「お父様…?」
わたしは不安を抱き、父に顔をゆっくりと覗き込んだ。すると、暫く間を空けて父は口を動かした。
「アル。私に何か隠してる事はないかい?」
びくり、と身体が反応したが、わたしは後ろめたい事など何も無いと言わんばかりに、咄嗟に被りを振った。
「本当かい?」
「はい」
父はまた暫く間を空け、肩を落としながら囁くように声を出した。
「……アル、私に隠し事が通用すると思うかい?」
父の表情は徐々に険しく、どこか暗い雰囲気を漂わせていた。
「お父様、わたし本当に身に覚えがありません…」
「そうかい…では、今日エディと何を話した?」
わたしはそれを聞いて、はっ、となる。それは、父には決して芳しくない会話内容だったから、今日、わたしはエディに対して、外の世界への憧れを口にしていた。それが何故、父に伝わっているのかはわからないが、わたしは肩を窄ませた。
「お父様、ごめんなさい…わたしやっぱり…」
「アル、どうやらお仕置きが必要だね」
その言葉を聞いて、わたしは身構えた。
「え…またあの部屋に…厭だ…」
咄嗟に言葉が出た。というのも以前に父から、『お仕置き』と言われ、この複数ある部屋で唯一わたしが立ち入った事がない場所に連れられた事がある。言うならこれは2回目のお仕置となる。
そこは何もない真っ白い部屋。窓はもちろん、家具の1つもない、あるのは天井に吊るされた小さな裸電球のみ。わたしが入ると父は扉を閉じ込め、外側から鍵を掛ける。
わたしはまた、数分間そこに居なければならない。
わたしは先程同様に、厭だ…、と言い抵抗したが、こうなってしまった父は決して意見を変えようとはしなかった。
「暫くの間、頭を冷やすんだ」
父は怒りとも悲しみとも似つかない表情を浮かばせながらそう言い、わたしはまたあの部屋に閉じ込められた。
ガタン、と重圧的な音と共に裸電球がゆらゆらと揺れる。床も、壁も、扉の色も、全て白で統一された異様な部屋。時計も存在しないこの空間は、まるで別の世界に居るような感覚に陥る。
ーー
もうどれぐらい時間が経っただろうか…前回もそうだったが、わたしはこの時間に色々の事を考えた。何も無い空間でそうせざるおえなかったとでも言うべきか…何故わたしはここに居なくてはいけないのか?
前回も最初にそう考えたが、わたしはすぐに被りを振った。
それはわたしがいけない…わたしが父の意見に反く発言をエディにしたから…前回も、何故外へ出てはいけないのか父にしつこく尋ねたせいで、わたしはこの部屋に連れて来られた。
そう、全部わたしがいけない。父の言う事は正しい。本当にわたしの事を想って、わたしの保身を考えて、そう結論しただけの事…それなのに身勝手なわたしは…
ぐるぐると同じ思考が頭の中を駆け巡る。わたしは異端の娘…ひねくれた考えの持ち主…そんな感情が全身を行き来する。動かない裸電球に視点を集中させながらわたしは、この永遠とも思える時間を過ごした。
ーー
ギィー、と錆びれた音が聞こえる。わたしはそっと扉の方に眼を向けた。
「お父様…」
わたしは泣きそうな声を上げながら父に寄り添い、抱きついた。
「アル、よく頑張ったね。本当に賢い娘だ」
またいつのも朗らかな声色に戻り、父はわたしを強く抱きしめた。
「お父様…わたし…わたし…」
「いいんだよ、アル。何も言わなくて…ほら、エディが待ってる。食卓へ行こう」
「はい…」
わたしは鼻を啜り、父と共に食卓へ移動した。
テーブルには既に食事の準備が出来ていて、囲うように椅子が3脚並べられていた。
エディは待ちくたびれたと言わんばかりに自分の席に座っていた。
父はわたしの方を見て顎を上に向かせながら、わたしに合図する。わたしはそそくさとエディの方へ駆け寄り、上半身を前屈させる。
「エディ、待たせてしまってごめんなさい…」
「うん。エディもきっと許してくれてるよ。さぁ、食事にしようか」
わたしと父も自分の席に着き、3人で食事をした。とても和ましい雰囲気、先程1人で居た空間とは天と地程の差を感じる。わたしはなんと哀れで、間違った感情を抱いていたんだろう。どこか、父の示す道を心の奥で疑ってしまっていた。しかし、今、父の朗らか表情を見ていると、それはわたしの心が乱れてしまってるだけなんだと強く感じる。
愚かな心を赦してくれた父に、わたしは改めて感謝した。
ーー
いつのように、わたしはエディと共に父を見送り、いつものように様々な絵画を見流し、家の中を彷徨っていた。いつもと同じ行動、時々、エディのお腹を押し、一緒に戯けるような動きをしていた。
今日も平凡で何も無い時間をエディと共に過ごす予定だった。
しかし、廊下を彷徨っていると、わたしは妙な違和感を抱いた。
その違和感に、わたしは眼を向ける。
それは、いつも父が出入りしているであろう玄関の扉だった。
家の中を彷徨っているわたしには、この場所を通るのはいつもの事なので、すぐに気付いた。
扉の施錠がされてない。
咄嗟に、抱いていたエディを床に落としてしまった。同時に、わたしの胸は沸騰するようにざわめいた。
口を小さく開かせて、ゆっくりと扉に近づいた。
近くで見ても、やはりそうだった。いつも頑丈に施されてるものが今日はない。
恐らく、この扉を押せば、外へ出られる。しかし、今、わたしの心は強い葛藤に強いられていた。
「……」
昨日あれ程、心に誓った筈、もう外への憧れは捨てる。もう父を幻滅させたくない。散々心に誓った筈なのに、わたしの好奇心は大きく揺さぶられた。
自然と瞳から涙が溢れ落ち、囁いた。
「お父様…ごめんなさい…」
わたしは扉に手をかざし、ゆっくりと扉を向こう側へと押し込んだ。
ーー
扉を開けると見慣れない光景が一瞬、視界に広がった。
しかし、わたしは咄嗟に瞼を閉じてしまう。何故か眼がじんじんと痛む。
今まで感じた事のない強い眩しさが襲い掛かってきたのだ。わたしはその場でしゃがみ込み、両手で眼を抑えつけた。涙が溢れて止まらない。
暫くして、涙が治まってきた。わたしは再び眼をゆっくりと開いた。
先程、一瞬だけ広がった世界が視界に広がった。
見渡す限り、複数の緑に囲われている場所。床も緑色で、なにやらフサフサしている。そして、所々に茶色くて太長い棒のような物からも緑色がフサフサと生えわたり、聳え立っていた。
いや、よく見ると、緑色だけかと思っていた床からは、所々カラフルな色が混ざっていた。
しかし、そのどれもは家にある絵画のお陰で既視感はあった。
わたしは見慣れない景色に動揺していたが、ここで、一度冷静に物事を考えてみた。外の世界は初めて見るが、少しの知識なら備わっている筈。
数々の絵画や絵本、わたしはその少ない情報を元に今見えている物を思い出そうとした。
緑色の物、これは恐らく草…?
茶色い物、これは恐らく木…?
カラフルな物、これは恐らく花…?
わたしは、そう連想させていきながら、ゆらゆらと歩き始めた。
しかし、途中で足の裏に細い痛みが走り、咄嗟に足を上げ、確認した。
なにやら、足の裏に細々とした鼠色の物が複数付着していた。わたしはそれを摘み上げ、まじまじと見つめた。
恐らくこれが石という物なのだろうか…?
知識は曖昧でわたしは何一つ確信を持つ事は出来なかった。しかし、初めて見るこの光景はとても新鮮で、美しく視え、わたしの心は踊っていた。
眼には見えないが、肌を撫でるような心地の良い物が常に通り過ぎている感覚がする。これが風だろうか…?先程、眩しくてすぐに眼を瞑ってしまったが、その強い光を放っているのは太陽だろうか…?
わたしは今、外に出て、自分の眼で見て、自分の耳で音を聞いて、自分の鼻で匂いを感じている。
もっと色んな事が知りたい。
わたしは強くそう思った。もうこの時点で。父の言葉など完全に忘れていた。わたしは深い喜びに満ち溢れていた。やっと外の世界を知る事が出来た。その感情で頭がいっぱいになり、思わず走った。
どこまでも、どこまでも続く緑色の景色、それを充分に堪能しながら、わたしは家に背を向けて走り続けた。
ーー
どこまで走ったかはわからないが、わたしは心臓の鼓動は激しく高まっていた。ずっと家の中に引きこもっていたせいで体力が既に限界だった。
少しの間、木の陰で休憩を取り、また歩き出した。先程みたく元気に駆け巡る事はもう出来ないが、ふらふらとしながら目的もなく、辺りを彷徨っていた。
「ちょっと!あんた、なにしてんの!」
突然、背後から怒鳴り声のようなものが響き渡った。
わたしは、ひっ!、と声を上げながら咄嗟に振り返った。
そこには、大柄な人が驚いた表情でわたしを見つめていた。
「あんた、そんな格好で…ちょっと待ってな!今警察呼んであげるから!」
そういうと目の前の人はどこからか、小さい物体を取り出すと、それに向かって話し始めた。
何を話してるかはわからないが、それは、本当に誰かと会話している様子だった。わたしはそれを不審に思ったが、ただ眺める事しか出来なかった。
暫くして、わたしの目の前に、また2人、知らない人が現れた。そして、最初に出会った人と共に白と黒の色が印象的な物にわたしは押し込まれ、動き始めた。
突然の出来事で声が発せられない。
「もう大丈夫だよ」
隣でわたしの手を握りしめて、そう囁きかけられた。その声は先程の怒鳴り声のようなものではなく、朗らかな声色だった。まるで父を彷彿とさせるような雰囲気に、わたしはここで初めて囁くように言葉を発した。
「…お父様に、知らせなくては…」
「え?お父様?」
「ええ、このままでは、お父様に心配を掛ける事になりますわ…」
隣の人は、何故か眼を円くさせていた。
「まぁ、詳しい話は向こうで」
わたしの前方から、また別の人が、今度はやや冷たい声でそう言葉を発した。
一気に場を静寂とさせた。外に眼を向けると、景色が凄い速度で変化していく。わたしは知らない光景がいっぱいで新鮮さを感じていた。しかし、この空間は、なんだか苦手に思えてならなかった。
そして、わたしは黒と白の物から次はどこかの建物へと連れていかれた。
ーー
それからどのぐらいの日が経っただろうか…わたしは自分の置かれてる状況を徐々に理解した。
いや、もう『わたし』と言うのもおかしいと知った。僕は男という性別らしい。あの日、パトカーを呼んでくれた女性、由良さんによって知らされた。
僕は今、病院のベットにいる。精神に異常があると診断されたらしい。あれから、由良さんは定期的にこの場所に脚を運び、様々な事を教えてくれる。今思えば、僕の喋り方や仕草は、羞恥以外の何者でもなかった。
容姿も異常だった。由良さんが初めて僕を見た時、僕は一切の衣類を纏ってなかったから。僕はあの家で、まるでそれが普通のように暮らしていた。しかし、父と名乗る男は、常に黒いスーツを身に纏っていた。今思うと、その時点で異常な事だった。でも、あの時の僕はそれがわからなかった。いや、わからないように育てられたと言う方が正しいのだろうか…
そして、これは警察から聞いた事だが、僕は8年前、行方不明になった人物だった。当時2歳だったから今の年齢は10歳らしい。
『真田 康介』
それが僕の名前。僕はずっと『アル』として育てられた。だから違和感がするが、それが真実。本当の世界だった。
ーー
また数日が経ち、今日は、面会がある、と医者に言われていたので、僕は病室で待っていた。
暫くして、ガチャ、と扉が開く音が聞こえ、僕は眼をやる。
2人の男女が驚いた面持ちでこちらを凝視する。
「康介…?」
最初に言葉を発したのは男性の方だった。
「本当に、康介…?」
続いて女性の方も鼻を啜るような声で言葉を発した。
「あなた達は?」
僕のその言葉が引き金となったのか、2人は突然その場で崩れ始め、泣き出した。
「本当に…夢みたいだ…康介…もっと顔をみせてくれ」
男性はゆっくりと僕に近づき、まじまじと僕の顔を眺め始めた。そして、それに着いて来るかのように、女性も僕へと近づいた。
「あ…あの…」
僕は戸惑いながら視線を2人から逸らした。
「ああ…すまない。つい感情的になってしまった。康介…お前は俺達の子なんだ」
「……そうですか…」
本当は驚くべき場面の筈なのだが、僕は至って冷静にそう答えた。
あの家を出てから、色々な事が起こり過ぎていて頭が追いつかない。ずっと夢の中に居るような気分だった。
また、ガチャ、と扉が開く音が聞こえた。
「あら?無事に再会できたのね」
僕の両親に眼を合わせて、由良さんは安心するような表情を浮かべていた。
「はい。この度は、我が息子を救い出してくれてありがとうございます」
2人は深くお辞儀をしながら由良さんに感謝を伝えた。
「康介くんも良かったわね」
「うん。由良さん、ありがとう」
僕も由良さんには色々な事を教えてもらった。その感謝を伝え、僕達は病院を後にした。
「康介…家へ帰ろう」
父にそう促され、僕は小さく頷いた。
ーー
この一連の出来事は『誘拐事件』という事で世間に公表された。テレビや雑誌なんかでは憐れみの声が多かったが、被害者の僕はなんだか複雑な気持ちだった。
何故、僕は誘拐されたのか?あの男の目的はなんだったのか?それら全てが謎で満ち溢れていた。そして、1番不思議なのは、その犯人が未だに発見されてないこと
僕と由良さんは、警察から何度も事情聴取を受け、あの場所に何度も訪れた。
しかし、あの森の中に家らしきものなんて存在してなかった。
僕が過ごしたあの8年間は一体なんだったのか…そして生まれて来てからの2年間の記憶が一切ないのも、少し奇妙な事だった。
僕は2歳の時に両親と3人で森林浴に出かけ、その後、僕は行方不明になったらしい。
僕は、本来なら学校という場所に通っている年齢らしい。両親からそう教わったが、いきなりそんな所に行ける訳もなく、僕は家に籠り、両親と共に、今までの失われた時間を取り戻すように、様々な会話をした。でも、あの8年間の出来事は、あまり記憶がない、という事にしている。
言葉で上手く表現できないが、何故か僕は話たくなかった。話してしまうと何かが壊れてしまう気がしてならないから。
「相当辛かったんだね」
そう母に慰めを受ける日々を送っていたが、僕は不思議とそう思わなかった。むしろ、あの8年間は僕にとって…
ーー
「康ちゃん、ちょっといい?」
朝、母が手招きしながら僕を呼ぶ。いつの間にか『康ちゃん』と気軽に名前を呼ばれるようになっていた。そして、その事に対して、僕は違和感がなくなっていた。それだけ、僕もこの世界に慣れてきている証拠なのだろうか?
「どうしたの?」
「これ、康ちゃん宛てで何か荷物が届いてるみたいなの」
見ると、なにやら大きなダンボールがテーブルの上に置かれていた。
「わかった。部屋で開けてみるよ。ありがとう」
僕はそう言ってダンボールを持ち上げる。しかし、見た目ほどの重さは感じられなかった。
そのまま自室へ戻り、ダンボールの上のガムテープを剥がし、フタを開けた。
その瞬間、僕の感情は大きく揺さぶられてしまった。
その中身は、紫の包みが入っていて、上部には赤いリボンが結ばれていた。とても見覚えをある光景、その包みの中身を見るまでもなく、僕は何が入っているか、一瞬で想像がつく。
「エディ…」
咄嗟にそう囁いてしまった。
そして、よく見ると、ダンボールの中には包み以外に一通の手紙らしき白い封筒が入っていた。
僕はその封筒を手に取り、中身を確認した。
ーーーーーーーーーーーーーー
アルへ
私は君を本当の子供のように想っていた。
あぁ、でももう行ってしまうのだね。私の元から去ってしまうのだね。寂しいが、それもまた運命というものだと、私は理解しなくてはならない。
さようなら、親愛なる我が娘よ。
ーーーーーーーーーーーーーー
僕はその文字を読んで、何故か瞳から涙が溢れ落ちた。
世間から見れば、僕は誘拐から解放され、幸せな生活を送っているように思うだろう。しかし、僕自身は何故か毎日を抜け殻のように過ごしていた。何が幸せで、何が辛いのか、どうすればいいのかよくわからなくなっていた。
でも、今確信した。
僕はいつの間にか、あの家で過ごした日々を、どこか恋しく感じてしまっているのだろう。もちろん、あの家には、おかしな点が沢山ある。まず、あの家が見つからない事、あの男は一体何者だったのか、仕事と言って外へ出た後に扉の内側に施錠されているのも今考えると奇妙な話だった。
しかし、それらを踏まえても、僕はあの時間が幸せだった。父、エディ、そして、僕…3人で過ごしたあの日々は何にも変え難い幸福で満ちていた。
僕は、崩れるようにその場に項垂れ、声が自然と溢れ出た。
「ねぇ…お父様…どうして…?どうして僕を…わたしを見捨ててしまったの…?どうしてわたしに再びこの感情を与えてしまったの…?」
わたしはあの不思議な時間の中で、何度も外の世界に憧れを抱いていた。しかし、それが現実となった今、皮肉な事にわたしは一切の幸福を感じられない。
現在のわたしは、あの家に居た時より、自由な生活を送っているだろう。でも…わたしの理想とする世界は現実には存在しなかった。
わたしが本当に求めている物は、自由でもなく、現実でもなかった。『アル』というわたしが存在して、『父』と呼べる者が存在するあの世界が、わたしにとって、唯一の居場所なのだと、今更気付かされた。
わたしは包みの赤いリボンを外し、エディを抱きしめた。
「お父様…どうか…出来る事なら…こんなわたしを…こんな愚かなわたしを…もう一度赦して下さい…」
エディを抱きしめながら、わたしは心の底から強く、とても強く念じるように呟いたが、その言葉は室内を虚しく木霊させるだけだった。
あの家に囚われていたわたしは意を決して外の世界へ出向いた。
しかし、そこに待っていた世界は理想とはかけ離れていた。
結局わたしは今、現実の世界に囚われてしまっただけなのかもしれない……



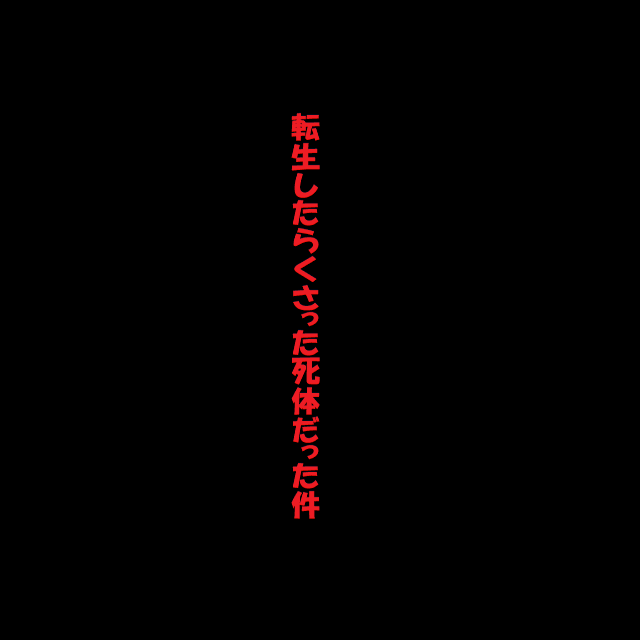
作者ゲル