以前投稿した『いらない心』の別視点の作品になります。もし「まだ読んでないよぉ〜」って方は https://kowabana.jp/stories/34896 ←こちらから読んで頂けると幸です。
-------------------------------------------------------------
私がこの土地に訪れたのは40年前、まだ気流は穏やかで、流れる疎水は澄み切っていた。
やがて息子(天堂照彦)は婚約者の(里子)と共に、この土地を離れ、私達夫婦は細々と暮らしていた。
しかし、8年前、夫を亡くした。
夫は13年前、自身の会社を、とある理由でたたんだ。それは精神的なものが深く関与していた。
それもあってだが、私は夫の容体が悪い事は知っていた。私に気を遣ってくれている事も知っていた。徐々に痩せ細ってゆく夫を見ると、そろそろ時期が近い事も覚悟しているつもりだった。
それでも、いざ時期が来た頃、私の覚悟は瓦礫のように崩れていった。人間というのは、なんて脆い生き物なのか、嫌でも思い知らされた。
それからの生活は孤独だった。1日中、ずっと縁側から田圃を眺めている日も少なくない。意味のない人生に思えて仕方がなかった。
1人でいる時間が、長ければ長い程、つい余計な事を考えてしまう。それは自分を卑下する時間、窮屈で途方もなく、それでいてとても儚い時間だった。
しかし、そんな人生の中でも唯一の幸せがある。
「久しぶりだね!おばあちゃん!」
照彦が連れて来た孫の健介が無邪気な顔で私に挨拶する。
「久しいねぇ〜健介や。また大きくなったんじゃないかい?」
「うん!もうお姉ちゃんより背が高いんだ!」
「そうかい、そうかい。そのまま健やかに育っておくれ」
私がそう微笑み掛けると健介が「うん!」と言い庭を走り回る。その姿はずっと昔、照彦が健介ぐらいの頃を偲ぶようで、微笑ましかった。
隣に目をやると、春香が私と共に縁側に座っている。春香はここから見える広い空を眺めていた。
「春香や、何を見てるんだい?」
綺麗で黒い横髪が風でフワフワとなびき、澄んだ瞳孔がとても大人びて見えた。
「私達が住んでる街はどこを見ても建物ばかりだから、ここに座って見える光景がとても珍しくて、とても落ち着く。毎日こんな景色が見れるといいなぁ〜」
春香は柔かい溜息を交えながらそう呟いた。
「都会は窮屈かい?」
「ううん、色んな人がいるから、それはそれで退屈はしてないよ。それでも、こんな感じの田舎もちょっと憧れる…かな」
春香は照れくさい物言いだが、私から見れば、とても尊い一面に見えた。そして春香の言葉一つ一つがとても美ししい音色のように感じた。私は心の奥底でこの子達姉弟をずっとここに置いておきたいと、わがままな感情が湧き上がる。
無邪気で活発な健介と、冷静で淑やかな春香。先が短い私の余生は、この空間が一番幸せだと、心中で叫んでいる。
ーー
陽が暮れた頃、照彦はせっせと帰り支度を整え始めた。
「もう帰るのかい?」
「ああ、明日も早いからね。母さんも身体に気を付けて」
「次はいつ来るんだい?」
咄嗟に言葉が出てしまった。内側に秘めた『淋しさ』という感情がうっかり飛び出た。
「そうだね…また連絡するよ」
照彦も恐らく察しがついているだろう。私の心情を一番理解してくれている。そのせいか、会話はどこかぎこちなく、私に向ける表情は引きずっていた。
「悪いね…」
そう言って照彦から目を逸らし、贅沢な感情を抑え込んだ。恐らく照彦達が帰ってから、また自分を卑下するだろう。
「出来るだけ早く来れるようにするよ。あっ、父さんに挨拶だけしてくるね」
夫の仏壇、遺影の前で、照彦、健介、春香は線香に火を灯し合掌する。
「父さん、こっちは幸せにやってるよ。父さんは俺達の暮らしを満足に見えてるかい?」
照彦の穏やかな囁き声に健介はまだ理解が乏しいようだった。
「おじいちゃんはどこにいるの?」
無邪気さ故に健介は顔を傾けてそう言った。
「おじいちゃんは遠くから俺達を見守ってるんだよ」
「でも、おじいちゃんはそこに居るよ」
遺影を指差しながら健介は更に質問を繰り出す。
「健ちゃん…」
春香は健介の肩に手を置き、宥めるように囁き、小さく被りを振る。
「そろそろ帰ろう」
照彦がそう言って部屋を出る。
「じゃあ母さん、身体に気を付けて」
白色の乗用車に乗り込み、ドアガラスを開けて照彦が私にそう言った。
「アンタらも元気でね」
車を走らせると、後部座席から健介が大きく手を振っている。私も微笑みかけながら小さく手を振った。
ーー
『玉の緒よ 絶えなば絶えね ながらへば 忍ぶることの よわりもぞする』
書架に収納された百人一首の本より、式子内親王が詠んだ歌である。現代語訳にすると
『私の命よ、絶えてしまうならば絶えてしまえ。生き長らえていたら、胸の内に秘める力が弱まって、秘めていられなくなってしまうから』
正式な歌の内容は恋心を用して造られた物であるが、現代語訳の文字だけで想像すると、私の現状と重なる。私が照彦、健介、春香に抱く想い。先程、うっかり出てしまった感情を思い返し、後悔する。
今は照彦にだけ悟られているが、いつかはあの子達にも…そう考えると、いっそ私の命など尽きてしまっても構わない。苦しくて切ない、それでいてとても激しい感情でもあった。
8年前から徐々に蝕まれ続ける心は、今にも崩壊しそうである。1人で居る時間は苦痛以外の何者でもない。誰の為に生きている訳でもない、誰かに必要とされている訳でもない、先程の幸福な感情との落差が激しい分、私の中に潜む自己否定の感情がより存在感を増すばかり。
私の存在意義など、もうどこにも…
そう思い始めた時、ふとあの噂が過ぎる。
祈願屋…それは必要な人間の前に姿を見せる不可解な店。私は今の環境に1部を除いてだが、決して幸福ではない。
必要と言われれば必要かも知れない…だが、私には望む願いは…
"ずっとあの幸福を側に置いておきたい"
それが本心かもしれないが、それは自分勝手な主張にすぎない。仮にその願いが叶ったとしたら、あの幸福は形が変貌してしまうかもしれない。
現状の少しの幸福を保って生きるか、未知の光景を望むか、その2つが私にとって考えれる唯一の選択肢だった。
前者を取れば、あの子達はいずれはここへ訪れなくなるだろう。私の事など、気にならない人生を歩み始めるだろう。そして私は1人、この土地で生命を終える事になるだろう。
後者を取ればどうだろうか…少なくても現状を変える事は出来るかもしれない。しかし、どう変化するかまでは、わからない。
逡巡とした感情が脳内を行き来する。
若者には未来がある。人々はそう信じて各々の人生を歩んでゆく。しかしそれは、裏を返せば老人には未来など無いと言われているようで、息が詰まる。
私にも、あの子達程ではないが、人生の先がある。その残された未来、このままでは短いようで途方もない、淋しい余生となってしまうだろう。
縁側に腰を落とし、暗い夜の田圃を眺め、そんな事ばかりを過ぎらせる。まるで、深い地の果てで永遠に彷徨い続けてるような孤独で荒んだ感情だった。
ーー プルルルルルッ
突然の電話音に少し驚いた。私は重い腰を上げ、受話器を取る。
「もしもし御母さん」
その声は照彦の嫁、里子のものだった。
「ああ…里子さんかえ?どうしたんだい?」
「いえ、今日、照彦さんと子供達がそちらへお邪魔させて頂いたようで、私も同行出来なくて申し訳ありません」
受話器越しでも伝わる。私の為に頭を下げ、心から申し訳ないと思ってくれている。
「いいんだよ里子さん。そんなに気を遣わないでおくれ」
「ありがとうございます。子供達は、なにかご迷惑をおかけしませんでしたか?」
「迷惑なんてとんでもない。むしろ癒されたよ。里子さんも近い内に是非…」
「はい。またお伺いさせて頂きます」
電話を切って受話器を戻す。
里子とは、最初に会った頃から印象がブレなかった。とても真面目で誠実な人間だと思った。今の春香を少し大人にした感じで、華麗で落ち着きがある。
私は先程、またどん底に陥っていたが、里子のお陰で少し救われた気分になった。しかし、同時にあの家族の一部になりたい。とわがままな感情が浮き上がってくる。
「私もアンタらと一緒に住んでも良いか?」
その一言が言えたら、どれ程楽か…しかし、そんな事は口が裂けても言えない。これ以上、あの家庭に迷惑をかけるなど、考えられないから。
また縁側に腰を落とし、虫や野鳥の声を聴き、遠い夜空を見上げる。
ーー
「御母さん、どうだった?」
里子が心配そうに眉をひそめ、言った。
「いつも通りだったよ。子供達とも、よく喋ってた。でも本心は多分あの頃のままだと思う…」
「そう…本当にこのままでいいのかしら…ねぇ、やっぱり御母さんに言おうよ!一緒に暮らそうって」
「里子…」
8年前、父を亡くしてから、じりじりと母から覇気が失われ続けていた。
俺視点から見てもわかる。母の衰弱し続ける神経は恐らく俺達との同居を望んでいる。しかし、仮に母が俺達と一緒に生活するとなっても、母は本当に幸せなのだろうか。それに、里子だって…母には母の世界がある。里子にだって里子の世界がある。それは決して交わってはいけない。俺はそう思っている。
しかし、そう思っているのは俺だけかもしれない。俺の早とちりなのかもしれない。曖昧な想いを逡巡とさせながら俺は里子に訊いた。
「里子はそれでいいのか?」
「うん。だってアナタの母親だもの」
真っ直ぐとした眼差し、言葉で里子は俺を見据えて言う。里子は俺の母を大切に想ってくれている。それは、里子自身、両親をどちも亡くしてるが故の感情なんだろう。
しかし、俺は母より家族を大事に思っている。母さんには悪いが、本心を言えば、里子、春香、健介の幸せを優先している。もちろん、母にも幸せになって欲しい。
母との同居により、我が家はこれまで通りの家庭を築いていけるのだろうか。父が亡くなる前の母は、活気に溢れる人間だった。そして、決して人に頼み事をしない人だった。
「何事も、自分の事は自分の頭で考えて行動におこしなさい。なんでもかんでも人頼りでは立派な大人になれない。神様なんて何処にも存在しないんだよ!」
俺が小さい頃、よくそう言われ育った。そのお陰で今の俺は存在する。他人に自分の判断を委ねる事は決してせず、強く生きてこれた。
しかし、今回の事象に関して言えば、俺1人の判断では到底決定出来ない。今の俺は、家族を思いやる義務が俺には課せられている。
俺は里子を見据えて言った。
「明日、母さんをここに呼んで話し合おう」
「うん」
里子は固唾を呑んで、俺の言葉を承諾する。
ーー
午前11時、また突然の電話音に驚き、飲んでいた麦茶が喉につかえた。
「もしもし母さん?」
それは、照彦の声だった。
「ああ、照彦かい…どうしたんだい?」
なんだか、切り出し難い雰囲気を感じ、2秒程、時が止まる。
「突然で申し訳ないけど、今日の夜、家に来れるかい?話したい事があって」
「今日かい?」
照彦の声は、昨日のぎこちないものではなく、まるで、私に何かを打ち明けるように真剣で、しっかりとした口調だった。
「電話越しでは話せない内容なのかい?」
「うん。悪いけど家に来て欲しい」
「わかった」
私はそう言って電話を切った。照彦が住む都会は、ここからだと、2時間は掛かる。わざわざ私をそこに呼ぶという事で、おおよその察しはついている。
私をあの家に住まわそうとしてくれているのだろう。
照彦は、何度か子供達や、里子を家に連れて来ては、私の現状を確認していた。恐らく私が弱り果てている事は随分前から察しているだろう。
一度、私を施設に入れる事を提案してくれていたが、私は断固として断っていた。それはまた、私の身勝手な感情なのだが、私は、夫と共に築き上げてきた大切な場所を離れたくなかった。それは、夫に対する裏切り行為だとすら思い、心が赦さなかった。私は、申し訳ない、と照彦に言い、その提案は光彦から二度と口にする事はなくなった。
しかし、今回の件も同じような事、私は結局この土地を離れる事に変わりはない。私の思考で言えば、それは夫への裏切りになってしまう。でも、私は逡巡としていた。いや、本心はハッキリとしている。あの家庭と共に余生を過ごしたい。
でも結果としてこの土地を離れる事に変わりはない。しかし、それは夫への裏切りとはまた違う形に思えなくはない。
私が思い悩んでいるのはそこではなく、やはり、あの家族に私なんかが居座るとなる事が迷惑に思えて仕方がない事。恐らく照彦は里子と共に長い時間を掛けて考慮してくれた判断だろう。それでもやはり、私の余生は私自身で決める。私はせっかくの申し出だが、断ろうと考えた。
ーー 夜。
私は身支度を整えて、家を出る。そして最寄りの駅へ向かった。駅は田舎という事もあって人は少なかった。私は窓側の席に腰を落とし、外の景色を見ていた。電車など何年ぶりだろうか。
外の景色に懐かしさを覚えた。都会に近づくにつれ、見える光景は複数の建物が並び始める。昔は畑だった場所も今は都会に呑まれていた。
目的の駅に到着すると、私は照彦の携帯に電話を掛けた。
しかし、何度掛けても電話に出る事がなかった。少し不安に感じたが、忙しいのだろうと思った。そもそも時間を指定していた訳ではない、まだ仕事を終えてないのかもしれない。
私はあの家に向かう。この道を通るのも、また懐かしかった。昔はなかった筈の建物が幾つも聳え立つ。しかし、ハッキリと憶えている。あの家はここから5分程歩いた先にある。13年前に訪れた記憶がそう示していた。雰囲気は変わっているが、記憶が正しい道のりを示してくれる。
しかし、なんだろうか…あの家に向かう程、人混みが増し始める。そして、駅からちょうど5分程歩いた先に、あの家が見えた。いや、あの家だった土地が見えた…
ーー
私は瞳孔を見開いた。私の眼に映る景色が私の思っていた光景ではなかったからだ。
轟々と燃え盛るあの家が、私の視界を覆い尽くした。何人居るのかわからない程の人溜まりがあの家の前で騒いでいる。
「ちょっと!どいておくれ!!」
私は人混みを掻き分け、あの家に近づく。しかし、どうやら手遅れのようだった。全焼するあの家をただ見つめる事しか出来なかった。
炎は勢いを増すばかりで、これ以上近づく事が出来ない。私の瞳に写る景色は心と共に焼き尽くされ、頭の中がぐちゃくぢゃに壊されてゆく。
もう終わり、私の至福、あの高揚感は二度と味わえないと悟った時…燃え盛る家の中から誰かが出て来た。
「おい!誰か出て来たぞ!」
人混みの中、私と同じタイミングで気が付き、1人の男が家を指さす。
遠目からなので少し見づらいが、私にはすぐにわかった。春香だ。春香がフラフラになりながら外へ出て来た。恐らく黒煙により意識が朦朧としているのだろう。すぐにその場に倒れ込み、暫く動けそうもなかった。
そして、10秒程経った後、春香は猛り狂ったように絶叫した。
「あぁ…私の…あああああああああああああああああああああああああああぁ…!!」
「お父さん!お母さん!健ちゃん!あああああああああああああああああああああぁ……」
その時、私も混乱してしまい、あろう事かその場を離れようと決意した。しかし、春香が誰かに肩を揺られている時、私とチラッと目が合ったような気がした。
それでも私はその場を後にしてしまった。
ーー
結局、あの火事は原因が不明だと公表された。照彦は下肢が瓦礫の下敷きになり焼死。同じく、里子は健介に覆い被さり焼死した。春香がそう告げた。健介は全身に酷い火傷を覆ったが、辛うじて息があるようだ。今は病院で治療されている。そして、唯一軽傷で済んだ春香は私が引き取る事になった。
何故あの時、私は逃げてしまったのだろう。ずっとその考えが脳に過ぎる。恐らく怖気付いてしまったか、私にはあの場で春香に掛けてあげる言葉が思い浮かばない。それは今考えてもそうだ。あの場で私になにが出来ただろうか…そう言い訳がましく考える自分が嫌になる。この歳になっても、やはり自分が愛しいのか…自分の中の醜い心がモヤモヤと蠢く。
病室で春香と共に健介を見る。
「ねぇ、おばあちゃん?」
春香が私に囁き始める。私は「ん?」と声を鳴らし出来るだけ微笑むような表情を作り、春香を見る。
「なんで私だけなんだろうね」
淡々と放つその言葉に覇気を感じられない。透き通るような白い肌に涼しげな仕草、黒く、長い髪から覗くその瞳は…春香はあの日以来、表情がなくなってしまった。
なんて答えればいいのか迷う。あの頃の恍惚的な世界はもう存在しない。目の前には、深く、白濁とした傷を負った少女が健介を見ている。私は被りを振って春香に声を掛けた。
「大丈夫、きっと健介も大丈夫だよ」
喉につっかえた物を無理やり捻じ込んでも、こんな薄い言葉しか出て来ない。春香が何を望んでいるのか、私には到底わからない。春香にどんな人生を歩ませればいいのか検討もつかない。昔から私が照彦に言っている言葉、神様は存在しない、その表現が悲しいかな…1番しっくりきてしまう。
ーー
我が家での会話も殆どない。春香が家事を手伝い、物寂しい食卓を囲う。
「春香や、もう学校には慣れたかい?」
「うん。ぼちぼちかな」
「そうかい」
毎日同じような会話が空を舞う。あれから数ヶ月、私はずっと健介に寄り添い、春香は学校が終わると病院に来て、健介に声を掛け続ける。
しかし、少しずつだが、春香に変化がみられる。日を増す事に健介に対する春香の口調は上がってきている。まるで本当に会話が成り立っているかのような振る舞いに対して、春香の眼は空虚を物語っている。
「ねぇ健ちゃん!この土地でやっと友達が出来たんだ!千代って言う子なんだけど。とても明るくていい子なんだ!今度健ちゃんに紹介するね!」
私は病室の窓から外を眺め、春香と健介の会話を聴こえてないふりをする。私はその空間に関与してはいけない。いや、関与する勇気を持てないと言っていいだろう…
暫くして私は春香に言う。
「春香、そろそろ帰ろうか」
「うん」
健介に向ける溌溂とした声色とは違い、私には氷のような冷たい声色に変わる。やはり、春香はあの日、あの時…
ーー
ある日、春香は一輪の花を持って病室に訪れた。春香は軽快な口調で健介に花の話をする。青紫で可憐な色、春香は花言葉である『明るい未来』、『通じ合う心』を口にする。しかし、その言葉とは裏腹に春香の口調は少し震えていた。対となるその想いに、私はそっと春香の背をさする。
その瞬間、春香の表情が無となる。
「ごめんなさい、おばあちゃん。私先に帰るね…」
そう言って踵を返し、病室を出ようとする。
「そうかい…気を付けてね」
「うん」
私にとって、この間は複雑で苦痛な時間だった。春香はどうだろうか…私は何か言おうと思い、春香に声を掛けた。
しかし、私の口から出た言葉は決して春香には届かない。相変わらず薄い言葉の数々が空を舞うばかりだった。
ーー その日の夜。
私は、いつものように、春香と食事を共にする。無言、無表情で食事をする春香は、現在の心境を口にする事は一切ない。だから、せめて私だけでも朗らかな表情を意識するように心がけている。それを見て春香が私をどう思うのかはわからないが…
沈黙が支配する食卓、私は春香に質問をする。先程、春香が病室に持ってきた青紫の花について。
春香は「友達に貰った」と言い、ムスカリの話をした。
私は花の事はあまり詳しくないので、その話を深掘りする事は出来ないが、それよりも春香の口から『友達』という言葉を聞けた事に喜びを覚え、口角を緩ませた。
しかし、安心した私は、うっかりといらない言葉を口にしてしまった。
春香は箸を止め、顔を顰める。
「部屋に戻るね」
そう言って春香は食卓を後にした。
私はまた深い後悔をした。私の浅はかな思考は春香を苦しめるばかりかもしれない。そして、やはり春香は気付いているかもしれない。あの日の事…あの日、私と目が合った事は春香の記憶にしっかりと残っている。そう考えると春香の心は今、どういう心境なのか…
春香から見て、私に思う事は、なぜ私があの場を去ったのか、それとも、そもそもあの家に火をつけたのは私だと思っているのか…もし後者の方だとしたら、春香は私に…
私はまた、書架に目をやり、百人一首の本を手にとった。
『人もをし 人も恨めし あぢきなく 世を思ふゆゑに 物思ふ身は』
作者は後鳥羽院。世の中に思う不の葛藤や、人に対する情緒が揺れ動いてる感情が込められ、それに対する己の無力さを強く感じてしまう歌である。
春香をそれに当て嵌め、私に思う事…それは…それは、復讐という感情に変化してしまってるのではないだろうか…私が春香の幸福を奪った。私が春香の未来、運命を奪った。それでも春香は生きている。それは健介がまだ生命を絶っていないからなのか、それとも私に対する復讐心が故か…
友達が出来た事で、人生が少しは豊かになってくれていたら幸いだが、恐らくそう簡単にはいかないだろう。
ならば、私が出来る事はなんだろうか…
ーー
「おばあちゃん」
突然の春香の声に驚いた。凍りつくような冷えた声色、それに加えて、なんだか悍ましさを覚える。私が振り返ると春香の表情は、どこか澱んでいた。そして春香は沈んだ双眸を私に向けて訊く。
「おばあちゃん、あの話って本当なの?」
その時、私の中の何かが鈍い音を鳴らした。実際、その話は春香にした覚えがない筈…しかし、里子や照彦には物の弾みで少し話した事がある。恐らく、春香はそれに聞き耳を立てていたんだろう。
私はしらを切り、春香の質問にぼんやりと答えた。春香はその場所に興味があると答えた。口調だけ取れば、その程度で収まるかもしれないが、春香の心情、雰囲気を取れば…恐らく行ってしまうだろう。もしあの噂が本当で、春香が必要とするならば、必然的に…
その場合、私はどうすれば…いや、私自身はどうなってしまうのだろうか…春香が今、何を思っているのかわからない…しかし何故か、あそこへ行ってしまえば、もう二度と春香に会えない気がしてならなかった。
そもそも、里子や照彦にさえ、あの噂には抽象的な部分しか話してない。なのに、春香からは何故か具体的な要素まで抑えてるような感じがした。いや、そもそも私でさえ、誰から伝わった話なのか、実は検討がつかない…私は嫌な予感がした…もしかすると…あの噂って…
私は春香が部屋に戻ると同時に家を飛び出し、あの場所へ向かう。実はずっと私には視えていた。それは、私があの場所をずっと必要としていた証拠でもあった。でも今は、以前とは違う理由が私の中で騒いでいた。
ーー
錆びれた古屋、恐らく特定の人間にしか視えない存在、今までずっと視えてないフリをしていてはっきりと視た事がないが、いざ目の当たりにすると、不気味で恐怖心さえ芽生えてしまう。
看板に目をやると、そこには黒い看板に赤い文字で、『祈願屋』と記されていた。
私が恐る恐る中に入ると、薄暗い店内が映る。ここは本当に現実の世界なのか…と思える程に全身の感覚が薄く広がる。そして、目の前には、男が顔に包帯を巻いてカウンター越しに立っていた。
一応、人の形をしているが、私には自分とは違う生物に視えた。
「いらっしゃい。ずっと視えてないように振る舞っていたね」
目の前の男は私に薄気味悪くそう言った。
「あんたがここの店主かい?」
「ああ…その様子だと、ここがどんな場所なのか理解しているようだね」
「……」
私は言葉を噤んだ。何から言っていいのか、暫く逡巡として、私は訊く。
「この場所は、この場所を本当に必要としてる人間にしか視えない。それはわかっていた。でも、この場所の具体的な内容も、この場所を必要としてる人間にしかわからない。ここは、そういう所だね?」
すると、男はカウンターまで手を上げ、軽快に拍手する。
「察しがいいね。その通りだよ」
だとすると、やはり春香は…そう考えると、春香はいずれここに訪れる事になるだろう。春香が何を願うのか、私には検討がつかない…私自身、どうなる事かわかならない。
あの日、春香は私を見た。それが事実なら、恐らく私は春香に…私は男の前で下を向きながら考える。
しかし、男はカウンターに手を置き、バタッと音を立てた。
「さぁ、願いはなんだい?」
「……」
また、口を噤む。ここで私が願う正解はなんだろうか…このままだと、私はどうなってしまうだろうか…ここに来て、私は微かに自分の保身も考えてしまう。そんな自分の感情に軽蔑を覚えるが、それも本来、人間という動物の在り方だとも考えれる。
この特殊な状況は、そんな新たな考えを教えてくれているようにも思える。しかし、そんな私の心の戸惑いに多くの時間を割いている場合ではないのが現状。
男は私の言葉を待っている。急かす事もせず、何分でも、何時間でも、何日でも待ってくれそうな様子に感じ、どこか私の現状を知っているようにもとれた。
店内は静かでいつも聞こえる虫や鳥の声も一切聞こえない。これが本当の静寂だと思った。何周も思考を回転させた挙句、私が導いた願いは…
「私の孫…春香がいずれここに来ると思う。その時、春香がなにを言っても春香自身が幸せになる方向にしておくれ。それが私の願い…お願いします」
私は深々と頭を下げ、男に願いを言った。
「ああ…わかった。貴方自身はどうなっても知らないよ。それでも構わないかい?」
「構わない」
「わかった」
ーー
店を出て、背後を振り返る。しかし、これまでずっと視えていた古屋は、そこにはもうなかった。きっと用を終えた人間にも視えなくなるんだろう。
まるで、今までの事が全て夢だったかのような爽快な気分になる。私を苦しめる物は全て失われたような感じに思えた。
その後私は、いつものように健介が居る病院へ足を運んだ。
病院に着くと、主治医が私の元へ駆けつけた。
「健介君の容体ですが…先程、意識が戻りました!」
私はその言葉で先程より、一層世界が明るく視えた。
「そうかい…」
「しかし、まだ会話出来る程ではありません。それでも、確実に回復の見込みがあります!」
「ありがとう…」
それは健介の生命力が功を成したのか、それとも…
ーー
あの日、あの火事には私にも原因があると思っている。火事を起こした人間には、心当たりがないわけでもない。13年前、夫が経営していた会社をたたんだ理由は精神的なもの、でもそれは、自業自得でもあった。
夫は常日頃から部下達に対しての扱いが悪かった。上に立つ人間はそうならなくてはいけない事は私にもわかってはいたが、それでも人の人生を左右する者、部下達はそんな夫に怒りを覚え、業績を悪化させた。当然、会社が円滑に回る訳がなく、倒産した。
部下達の遺族は、経営者である夫に全責任を咎めた。夫はそこから精神的に衰弱していった。私もそんな夫を心の底から支える事が出来てなかったのかもしれない。
夫はせめてもの償いと言い、あの土地にあの家を建てた。それでも、かつての部下の遺族は夫をまだ許してなかったのだろう…あろう事か、このタイミングで…その事は悔やんでも悔やみきれない…
私は家に着くと、縁側に腰を落とす。今頃、春香は病院で健介の事を聞いているだろう。そして、私は決意した。今日、春香が帰ったら、全てを話そう。今までの事、一切、包み隠さずに。
ーー
戸が開く音が聞こえる。恐らく春香が帰って来たんだろう。
「おかえり、春香」
私はそう言うが、なぜか春香からの反応が伺えない。
「ねぇ、おばあちゃん?」
どこか、春香の声に違和感を覚えた。いつもより、声のトーンが随分と下がっている。
「なんだい?」
私がそう言うと、また少しの間が空いた。敢えて春香を見ないようにしているが、春香は私へ距離を詰めて来ている。
「ムスカリって別の花言葉があるの」
春香の声が、どこか不気味に満ちていた。
「別の言葉?」
私は相変わらず背を向けながら春香に問う。
「うん。『絶望』とも言われているの」
その濁った声色で私は確信した。あの店に行ったと…どうやら最期の時間のようだ。私はゆっくりと春香の方を向く。
「ねぇ、おばあちゃん?」
春香は包丁を振りかざしながら私に質問をする。
その質問内容は、いつその質問をされるのかずっとヒヤヒヤとしていた内容だった。
しかし今は、安堵している。なぜなら春香は微笑んでいるつもりかもしれないけど、その瞳からは、涙が溢れていたから。あの日以来、ずっと押さえ込んでいた感情がやっと表情で示してくれたから。ようやく、本当の春香に出逢えた気がした。
春香はあの店主に何を言って、何を言われたかは、わからないけど、少なくても私の願いは叶えてくれているように見えた。
私は質問に答えず、開いた瞳をそっと閉じ、自分の最期を悟った。どんな形でもいい、この子が幸せでいてくれたら、残念ながら私にはその幸せを側で見る権利はないようだが…
だから未来の事は、そうだね…神様にでもお願いしようかな…
私達のすれちがう心、それは決して交わる事を赦されないのだから…



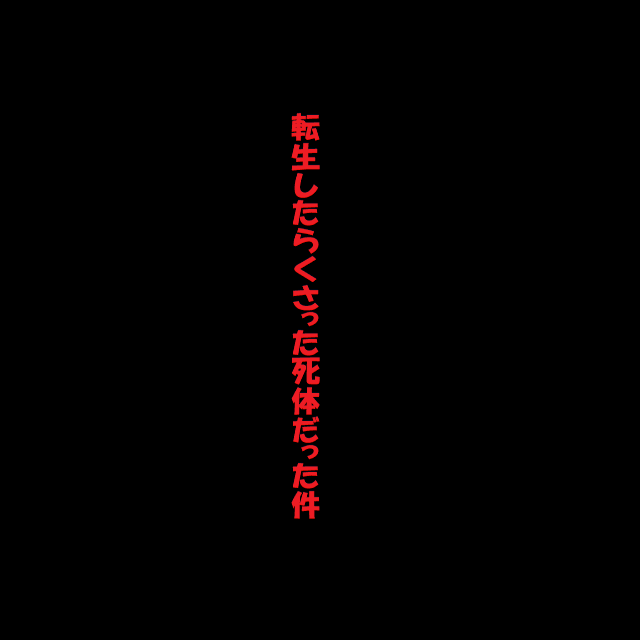
作者ゲル
祈願屋シリーズ6作目になります。
冒頭でも述べた通り、今作は以前投稿した『いらない心』https://kowabana.jp/stories/34896 の別視点になります。シリーズの中のシリーズみたいな感じになりましたね。かなり長編ですが…どちらも読んで頂いた方、誠にありがとうございます。
https://kowabana.jp/tags/祈願屋シリーズ
あと、アイコン変えました。笑