金曜日の夜は業務を終えてもすぐには帰宅しない。
してもいいのだが、私には行きつけのバーがある。週末の楽しみなんてそのぐらいだ。一週間分の仕事終わり、自分への些細なご褒美の時間。
その店はとても珍しく、営業時間が午前の零時から三時までという短い時間。さらに言えば、一週間を通して一日しか開いてない。今から向かう場所はそんな変速的な動きをする店、私はそこを妙に評価して行きつけとしている。しかも、事前にネットで予約を入れとかないと入店出来ない。なので私は毎週、月曜日にその店の予約を入れる。日が変わる土曜日の零時から三時までしかやってない店なので、予約は電話では難しい。だからネットでの予約制を導入したのだろう。
人気な店かと問われれば、決してそうではない。なんせ、私は毎週ここへ通えているし、呑んでいる時もほとんど誰も来ない。行きつけと言うより穴場と言った方がなんだかしっくりくる。
会社から自宅へ向かう電車とは反対側だが、それでも私は自分へのご褒美を優先する。それぐらいしないと、人生に張りが出ない。働く時は働く、休む時は休む、そう自分に言い聞かせ、今宵も会社から二駅離れた場所へと向かう。
改札を抜けると終電のアナウンスが鳴り響く。そのアナウンスは、どこか私に、お疲れ様、と労ってくれてるようにも捉えられる。もう通い始めて一年近く経過するが、それでもこの特別感は何にも変え難い幸福に満ち溢れていた。
そこから徒歩十分程、喧騒とした街は眠りの時間に入っていて、静かなものだった。私の幸せはいつもそんな小さな出来事から連想されていく。
Réunion__。
店の名前はそう言う。裏通りの更に裏通りの小さな雑居ビルの三階にその店はある。看板にはお洒落な飾り付けが施されており、青いLEDランプで店名が書かれている。
『open』と書かれた看板を確認入店する。このバーのマスターである男性は私の方へ歩み寄る。
「お待ちしておりました。工藤様、いつもご利用ありがとうございます。お好きな席へお座り下さい」
そう言って毎回、丁寧にエスコートしてくれる。
「ありがとう、三影さん。今日も素敵なベストね。そのネクタイもとても似合ってる」
「ありがとうございます」
ここは個人経営の店なので、バーテンダーは三影しかいない。私は決まりのように毎週同じような会話をする。黒いベストに水玉模様のネクタイが印象的な初老の男性、名前は胸元にあるプレートで知った。
お好きな席、と言われても私はいつも座る場所は決まっている。窓際席で夜景が堪能できる場所、まぁ、三階だから少し低い位置からではあるが、それでも充分に夜を堪能できる。
少し見上げる形となってしまうが、今宵は満月が見える。先程、ここから遠い場所、あの月に目掛けて花火が上がっていた。私は会社からもその様子が窺えた。それでもやはり、ここから見える夜空の方が居心地が良い。
「三影さん、いつものお願い」
私は手を挙げて三影にオーダーする。
「かしこまりました」と三影。
この店はバーカウンターもあるが普通のレストランみたいな家族席もある。ここはほとんど誰も来ない。私はいつも贅沢な掃き出し窓が設置された席に座ってる。そして、私は敢えてその窓を開ける。つまり、外を見ている時、私からは三影が見えない状態だ。今も外を眺めながら注文を通した。まるで常連客……まぁ常連か、毎週来ているのだから。
注文した品が来るまで私はずっと夜を眺めている。一週間で一番落ち着く時間、誰もいないという空間が恍惚に思えて仕方がない。一応スマホの通知も切っている。
「お待たせ致しました」
三影が足音ひとつ立てずに私に言う。最初の頃は驚いていたが、慣れてしまえばそうでもない。音を立てない理由を聞いた事がある、お客様の大切なひとりの時間を少しでも楽しんで頂きたいからでございます、と言っていた。そう、私はその『ひとりの時間』の為に仕事をしていると言っても過言ではない。だから私はこの店に毎週通っている。
「ありがとう」
「では、ごゆっくり……」
三影は品をテーブルに置くと、また音を立てずにカウンターに戻る。入店時に一杯とその後は一時間おきにひとつ、カクテルを注文する。合計いつも三杯呑む。通い始めて半年ぐらいから同じ物ばかりになったけれど。
ーー
大体二時間ほど経った辺り、私がオーダーする為に手を挙げると同時に、カラン、と店の入口の鈴が鳴った。珍しい事もあるものだと思い、ふと入店客に視線を向ける。
「え、楓?」
咄嗟に声を出してしまった。突然私の目の前に現れた中学時代の同級生『西宮楓』の姿があったから。
「あっ、もしかして林檎?」
「ああ、うん……そうそう林檎だよ」
私の名前は『工藤林檎(りんご)』今、楓に示した動作からわかる通り私はこの名前を好んでない。でも、下の名前を呼ばれるのは凄く久しぶりな気がする。
「よかったら相席するかい?」
楓を私の向かいの席へ促す。
「え、いいの?」
「うん。ちょうどひとりで呑むのも飽きてきた頃だったし」
楓は嬉しそうに私の向かいに駆け足ぎみで歩み寄り席につく。
「楓はここ、初めて?」
「うん。前から気にはなってたんだけど、なかなか踏み込めなくてさ。林檎はよく来るの?」
「毎週来てる。通い始めてもうすぐ一年近ぐらいになるかな」
「へぇ、常連ってやつ?」
「まぁ、自分で言うのもあれだけど、かなりの常連客だね。楓も何か頼むかい?」
「林檎が呑んでるやつと一緒のやつにしようかな? 何呑んでたの?」
「ブルー・カイピリーニャって言ってなんかブラジルのカクテルらしい。詳しい事はよくわからんけど、この青色と味が好きでいつも同じの呑んでる感じ」
「じゃ、それにしようかな」
「了解。私もちょうどグラス空いた所だったからおかわり頼むわ」
私は再び三影を呼び「これと同じやつ二つお願い」と言った。
「かしこまりました」
三影は小さくお辞儀をしてまた静かに戻っていく。
「あの人、渋いね。林檎はああいう人が好みなの?」
「バカ! 違くて! あくまで私はこの店が好きなだけだし!」
飄々と聞いてくる楓に思わず声が昂ってしまった。
「ふぅん。そういえば、よく一目で私だってわかったね」
「だって楓、見た目変わってないから、そりゃ気付くよ。でも驚いた。まさかこんな所で会うなんて」
「林檎は変わったね。見た目も口調もあの頃とは雰囲気が違う気がする」
「まぁ、だって中学ぶりだから、もう十年以上経つかな? でも私だって変わったのは外見だけ! 中身はあの頃とあまり違いはないよ」
「そうかな? 私から見たらやっぱりちょっと大人びて感じるよ?」
「む。それは褒め言葉として、しかと受け取っておこう!」
「あっ、今の表情なんかは昔の面影あるかも」
「そ! だから大人びて見えるのはこのスーツだけだって!」
「お化粧も上手だと思うよ?」
「まぁ、それも私の努力の結晶である」
ーー
そんな会話をしている最中、注文した品が置かれた。
「全然気配しなくて驚いちゃった。あの人何者?」
「まぁ最初はそうなるわな。私もそうだった。でも、それがこの店の醍醐味なんですわ」
「すっかり常連さんだね。林檎」
「……」
「そっか、やっぱりまだ好きになれないんだね? 名前」
少しの表情の変化で楓は悟すように私の顔を覗き込む。
「ううん。昔に比べたらその名前で呼ばられる事もほぼないから少しはマシになったかな……いや、嫌いには変わりないか」
「そう? 私はずっと好きだけどね。その名前、個性があっていいじゃない」
「だって『りんご』だよ。漢字も果物の字のままだし! 少しは捻れって今でも思う!」
「愛着があっていいじゃない」
「まぁ、昔に比べたら他人からどう思われるかなんて気にしなくはなったけどね。愛着か……楓にそう言われるとそんな気もしなくもないね……よし! そう思おう。それより、ほら」
私は自身のグラスを持ち上げ、楓にも同じ動作をさせるように促した。
「あ、そうだね。じゃあ改めて……」
「かんぱーい!」
グラスの、カチーン、という音、私達の声が店内に鳴り響く。他に客は誰もいないので、私達の貸切状態なのがまた贅沢に感じる。
「そういえば毎週通ってるって言ってたけど、ここから家は近いの? もう電車ないけど」
「ん? ああ……近くはないけど、いつもタクシーで帰ってる。ほら、大人の贅沢ってやつ?」
「そっか、それなら安心だね。仕事は上手くいってるの?」
「う〜ん。ぼちぼちかな。出来てるのか出来てないのか、ただの事務員で単純作業ばっかだから。もう慣れた、って言った方がいいかな。でも金曜日は週末だからやる事が多いし、夜も深くなるんだよ。だからせめてものご褒美としてこのバーに通うようになったんだ」
「仕事は楽しい?」
「ううん、全然。会社の人とあんまり喋らんしね。やっぱ私は孤独が落ち着くわ」
「相変わらずだね。中学の頃も同じ事言ってた気がする。林檎は一匹狼がよく似合うよ」
「え、何言ってんの? 中学の時は楓がいてくれたから孤独じゃなかったじゃん。同じ図書委員だったし、私はひとりじゃなかったよ」
「でも、ひとりが好きなのは変わらないんだね」
「それは今も昔もそう。でも、楓は違うよ。楓の事は本当に友達だと思ってる。生涯唯一かもしれないね。学校の中でも、喋る人はいたけど、なんか表面だけというか、馴れ合いみたいになってて、みんな何考えているのかわからなかった。社会に出てもそう……結局今まで本当の意味でわかり合えたのは楓だけかもしれない」
「みんな林檎が美人すぎて嫉妬してた記憶があるね。社会人の林檎もとっても美人だよ。浮いた話とかないの?」
「ないない! 私は生涯孤独。そう決めてるから。会社でもよく「工藤さんモテそうだけど彼氏とかいるの?」なんてセクハラまがいの質問されるけど、私は「間に合ってます」っていつも流してる」
「生涯孤独……か、林檎は寂しくないの?」
「うう……正直、これから先ずっとひとり、って考えたら全然平気って言えないかもね……でも、ずっと誰かと居たいか? 、って問われればそれもなんとなく違う気がして自分が見えなくなる。それが本心かな」
「そっか、林檎はやっぱ林檎だね。あの頃と変わってない。ちゃんと自分の思った事を口にできる。正直羨ましいよ。それでも林檎は林檎なりの葛藤があるんだね。私は林檎がどの道を選ぼうが応援するけどね」
「楓は昔から私の意見を肯定してくれてたね。楓のそういう所、嬉しいんだよなぁ〜。うん。やっぱり私は楓と巡り会えて良かったよ」
「ありがとう。林檎からそう言われると、ちょっと照れるけど……そういえば、この店、リユニオン? って読むのかな? どういう意味なんだろう」
「うん。リユニオンで合ってる。マスターに前聞いた事ある。フランス語で『再会』って意味らしい。そういう意味では正しい言葉かもしれないね。私は楓と再び出会った。看板に嘘偽りないね」
「おっ、それはまたお洒落ですな。私も林檎とまたこうやってお話するの嬉しい。図書委員だった頃を思いだすなぁ〜」
「まぁ楓とは読む本の好みが違ってたから、そこに関して語り合えないのがちょっと残念だけどね」
「今でも本読んだりするの?」
「たま〜にだね。社会人になってから色々忙しくてさ。まぁ、時間がない訳でもないんだけどね。なかなか読む気力が湧かんのだわ。楓は確か恋愛物の小説が好きだったよね?」
「うん。あの頃って恋愛に対して憧れがあったじゃん? それは私だけじゃなくて周りも同じだったと思う。でも、周りの恋愛話なんてぶっちゃけただの惚気にしか聞こえなかった。だから小説の世界に浸って満足してた」
店内にはうっすらと赤い照明が灯っている。それに反射して青いカクテルが入ったグラスは紫色に見える。私はぼんやりとそれを眺めた。私の悪い癖が出る。多分、楓もその事に勘づいてくれていて、静かに言葉を続ける。
「ごめんね。やっぱり今でも辛いんだね」
私は小さくかぶりを振る。
「ううん。そんな事ないよ……いや、それは嘘か、うん。私は今でも人を愛せない。楓が知ってるように昔から。恋愛感情が全くないってわけじゃないけど、それでも私はひとりが好き。それは裏を返せば自分が好きって事になるのかなぁって思ってた時期もあったけど、それも当て嵌まらなかった。いっその事、アナタはそういう病気です、って誰かに宣言して欲しいって何度か思った事もあるよ」
三杯目のカクテルも、もう半分近く呑み干しているので、少し酔いが回りながらぐったりとテーブルに腕をつけ、その腕に顔を乗せながら言う。
「ただ生きてるだけって辛いよね。特に林檎は周囲の事、結構気にしてるタイプだしね」
「でも周囲から見た私は、誰にも興味ありませ〜ん、って思われてるよ。実際私もそう振る舞ってる事多いし。そう思われたいと私自身も思ってる。でもそれが辛いって感じるのはなんか違う気がする。私から見たら、私病んでます〜、って口や雰囲気を出す人間は少しズルいなって感じる。わかってて優しい言葉をかけてもらえるのって一見環境に恵まれると思うけど、優しい言葉の本心は誰にもわからない。そう思っていても、いざ自分がそんな言葉をかけてもらったら素直に嬉しがると思う。結構単純だからね。でも、それすら出来ない私は、出来る人間に嫉妬してるだけかもしれないね」
「林檎はちゃんと自分の意見を表現できる分、その奥の事まで考えてしまってるのかもしれないね。でも生きていく内は人間関係は避けて通れないよ」
「奥か……深い事言うね。私も昔に比べたら人間関係は上手くなったかもしれない。でもその中で建前がほとんど……たまにその建前が自分でも胡散臭くなってバカに思えてくる事もある。それでも人間関係はその建前の元、成立するもんでもあるよね」
「大人になったって事だね」
「大人になればなる程、会話の内容もありきたりなものになるから、子供の頃に抱いていた印象と異なるなぁ、って大人になるほどわかる。大人は退屈だよ。会話が上手くなったと言うより愛想が上手くなったと言った方がいいかも」
「それがこの世界で人間関係をやっていく中で大事な事なんじゃない?」
「うん……でもくだらないって思う事の方が多い気がする」
「林檎の壁は分厚いですな」
「うん。こっちから近づこうとする程、距離が遠さがっていってる気がする。人によっては大した事ない事でも人より自分では傷ついたりしてる。逆も同じで、私が大した事ない事で人を傷つけてしまってるかも、って思うと余計喋るのがしんどくなる」
「林檎にとっての傷はやっぱ恋愛?」
「そうだね。歳を追う事にその傷はだんだん広まってるよ。私は『生涯孤独』という道を選んだ。言ってはいないけどね。でもそういう雰囲気を出してはいる。だから私は年齢と共に周囲から憐れんで見られる事が多い。私の思い過ぎかもしれないけどね……でも私から見た周囲の幸せのゴールって結局は人と築き上げる事が正解だよ、って言われているようでなんか嫌だ。他人の幸せを他人が決めるのって違う気がする」
「しがらみだね?」
「だね……なんかバカみたい……そりゃ結婚してる人から見た私は愚かに見えるだろうし、自分を肯定するだろって思う。『幸せ』って人それぞれだぞ! って言いたくなる。私をアナタ達と同じ幸せの枠に嵌めないで欲しい」
「いっそ、男女とかいう定義をなくしてみたら林檎も幸せになるのかな?」
「う〜ん。仮に私にその権利を与えられて、発動する事ができたとしても、私は使わないかなぁ〜。そうするとみんなと同じになっちゃう。誰かの幸せを奪う事になってしまう。私にそんな権利ないよ」
「世の中にまた新しい幸せの形が出来るかもよ?」
「だったらちょっと考えるかも」
楓は私が何を言おうが、肯定してくれる。私はその優しさについ、甘えてしまい本音をぽろぽろと言ってしまう。昔から抱いていた感情、久しぶりに自分を出した事で私の心は満たされている。でも……
「あっ、もう閉店の時間みたい」
楓が壁時計に視線を向け、言った。
「そっか、楽しい時間はあっという間だね」
「うん……私も久しぶりに林檎とお話できて楽しかったよ。じゃあ、私先に行くね」
「じゃ、今回は再会記念という事で私がここ払うね」
「うん。ありがとう。またね」
楓はそう言って店内を去る。本当は積もる話がいっぱいある。でも、それは私には出来ない。
私は自分の残っていたグラスを呑み干し、レジに行く。しかし、表示された額はカクテル三杯分しかなかった。
「三影さん、金額間違ってるよ?」
「いえ、確かに召し上がられた品は三杯だけです」
「やっぱ気付いてたのね。まぁ、あんなに大きな声で話してたらわかるか……うん。今日、あの子の命日なんだ」
「親しみがあったのですね」
「うん……でも三影さんに私の変な芝居を見せてしまってごめんね」
「芝居、だったのですか?」
「うん。ただの芝居だよ。今日もいい夜だったわ。また来週ね」
「本日もご来店ありがとうございました。おやすみなさい」
私はいつもと同じ金額を払い店を出る。外の光景もいつもと変わらない。毎週同じ深夜の景色。振り返ると『close』と看板が架けられていた。
__またね。
先程の楓の声が脳内に過ぎる。それは、また来年も会ってくれるという解釈でいいのだろうか。
店の鈴が鳴った時は驚いた。だって、あの頃と変わらない、中学生の制服を着た楓が本当にいるのだから。でも久しぶりな感覚もなく、普通に溶け込めた。それは私の中であの子がずっと心に残っていて、もしかしたらこの場所でなら、と望んでいたからか……。
相変わらず真面目な性格だったので、お酒には手を出さなかった。いや、物理的に出来なかったのかもしれない。それもまた、もし会えたら聞いてみたい。
私はずっとひとりだが、未来がある。でも、楓は過去から未来へ進む事は叶わない。私はこれからの未来、楓と築き上げた過去を背負いながら、どれ程の時間が残されているかわからない未来を生き抜いてかなければならない。私はその肯定を考えなくてもいい楓を少し羨ましいと思った。しかし、それは私のわがままな感情だろう。楓は私を置いて、ずっとあの頃にいる。それでも会ってくれたという事実が私の心に温もりを感じさせてくれる。
私の身の上話ばかりしてしまって……そんな自分の性格につくづく嫌気がさす。楓に再会するまで、もうこのまま、若い自分のまま死んでしまってもいいと思っていた。その旨を楓に伝えたら、それも肯定してくれるのだろうか……。
また明日からいつもの日常に戻る。結局私は、過去の、綺麗な記憶のまま、現在、未来の事から逃げてしまっているのだろう。
まぁでも、再会は果たせた。私が望んでいた想いは叶った。一旦はそう考えて明日を迎え、前を向く努力をしよう。そして……
ありがとう……生涯孤独同時の親友へ__。



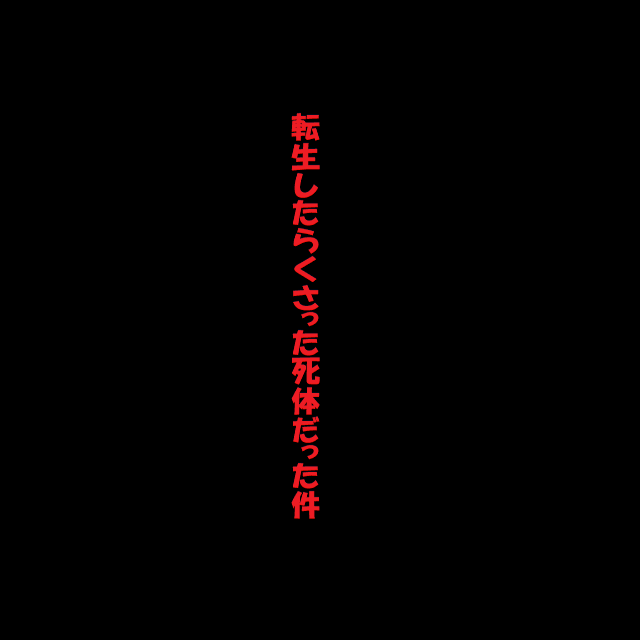
作者ゲル
今日でGW最終日の方が多いのではないでしょうか。
また明日から学校や仕事、頑張って下さい😊