誠さんを覚えているだろうか。
大学生の頃、ゲーム同好会の部長を務めていた青年である。
彼は以前、涼子さんという新入部員、もといその名を騙る何者かによる「鬼探し」という壮絶な<遊び>を体験した。
誠さんが卒業後も同好会は引き継がれ、次の部長になった圭介さんの話になる。
「すみませんね、最近は不摂生で」
私が会ったときは少し酒臭く、目線が虚ろいでいた。
「あのゲームは逃げても大丈夫ですよ。実際は何も起きませんから」
圭介さんは一つずつ思い出すように語り始める。
separator
圭介さんのクラスには京香さんという女学生がいる。
「ゲーム同好会、入る?」
そう言って彼女を口説いているのは圭介さんだ。
「そこって…ゲームで遊ぶだけでしょ」
「失敬な。学生の貴重な時間をゲームやスロットばかりに使うのはもったいないだろう。逆に研究するんだよ」
「そうやって大義名分を作るわけね」
「そうとも言える」
「なにそれ、ちょっと面白いかも」
そう言って華やかに笑うので、圭介さんも気分がよい。
「実は私も研究したい遊びがあるのよ。後で見てもらえるかしら」
「おいおいなんだそれ。ワクワクするじゃないか」
「講義が終わったら行ってみるわね。4階だっけ」
「うん。待ってるよ」
圭介さんは部員を増やそうとしていた。
なにせ人数が少ない上、全員がまともに出席するのも稀な状態だ。いつ廃部を宣言されても不思議ではない。
京香さんとは歴史の講義で席が隣になり、何度か会話もあった。そこで思いきって声をかけた訳だ。
「京香さんの遊びって何だろう」
夕方になり、部室内をふらふら歩き回っていると、約束通り京香さんがやってきた。
彼女は沢山の講義を受けているが、少しも疲れている様子を見せない。
「文系も理系もいろいろ受けて大変だね」
「そうかしら、知識と経験はいくらあっても損は無いわ。ここ座っていい?」
小さなソファとテーブルを挟んで、二人は向き合う。
「じゃあ紹介するわね。鬼探しっていう遊び」
圭介さんは一瞬の間を置いて「いいよ」と返事した。
するとテーブルに紫色の風呂敷が置かれた。
「この中には何枚かの紙が入ってるわ」
「へえ」
風呂敷が解かれた。確かに、はがきサイズの紙束がある。
「この紙それぞれに、クイズと二択の答えが書かれてるの」
京香さんは紙束を両手で持ち、机でトントンと揃えた。何枚あるかは分からない。
「そして2つの束に分ける」
京香さんは束を左右に置き、一方の束の上に手を乗せ、ジェスチャーを始める。
「1枚ずつ紙をめくっていって、そこに書かれている問いの答えを二択から選ぶの。左を選べば左の束から一枚めくる。右を選べば右の束から、ね」
「なんかそういうの子供の頃に流行ったなあ」
「そっか。じゃあ今から始めていい?」
「いや待て」
圭介さんは手を挙げ、静止した。
京香さんはぴたりと止まった。
「何?」
「今日は遅いからやめておくよ。ゆっくりできる時がいいだろ」
「あらそう。じゃあまた今度ね」
「素直だね。助かるよ」
京香さんは風呂敷を元通りにして鞄に詰める。
そしてスマホをいじると、用事ができたと言って去っていった。興醒めという言葉が非常によく当てはまる表情だ。パンプスの<カツカツ>という足音が廊下に消えていく。
「そんな急に用事ができるのか…」
圭介さんはつぶやきながら、前の部長だった誠さんとのやりとりを思い出す。
<鬼探しという言葉を聞いたら、絶対に続きをするな>
nextpage
「なんですかそれ?鬼ごっこじゃなくて?」
「ちがうよ。おまえはそういうの好きそうだからな。遊びに聞こえるけどやっちゃダメだ、絶対」
「どうしてです?」
「言えない。話すと俺も何かされそうで怖い。もうこの時点で何か起きるかもしれないんだ。でもおまえには言っておきたかった」
「はあ」
「くれぐれもこの件で俺に連絡しないでくれ」
誠さんの真剣な物言いは、圭介さんの心の隅に記憶を刻んだ。
そのようにして、圭介さんは京香さんを怪しんだ。
鬼探しというワードで意味のありそうな文献を探すも、大した情報は見つからない。
しかも大学は意外と狭く、図書館に長居したからか京香さんと遭遇してしまった。
「何を探してるの?」
「いや、まあ、その」
「あら、私に緊張してるのかしら」
彼女はパッと笑顔になった。
いちいち自然な女性の素振りを見せる京香さんに、圭介さんはしどろもどろする。
「鬼探しの話って、昔話とかにあるのかなって」
ふいにそんな言葉が出た。別に自分が探っていても不自然ではないのだ。
京香さんはいたって普通の反応をした。
「うーん。私の実家に伝わるしきたりだから、無いんじゃないかな」
「君の実家ってどこ?」
「東北だったり、四国だったり。家系を辿るとバラバラに住んでいて、この遊びの出自は分からないのよ」
「なるほど」
「圭介さんの周りにこういう遊びは無いの?」
「あると言えばあるけど…鬼ごっことか」
「それはしきたりじゃないでしょ」
京香さんが失笑する。
二人は場所を移すことにした。
nextpage
「やっぱりここが落ち着くなあ」
部室にやってきた。いつ来ても誰もいないので、もう自分の第2の家のようだった。
「そういえば他の部員はいないの?」
痛いところを突かれる。
「それがさ。俺が部長になってから、なぜかみんなサボり始めて」
「あんまりパッとしないもんね。ゲーム同好会って」
「君までそう言うなよ」
「紅茶はあるかしら?」
「ごめん、今は切らしてて」
「そっか」
「何かゲームでもする?」
「私はあんまり詳しくないから」
「そ、そっか」
なんとなく気まずい空気になった。そもそも京香さんがゲーム好きとは一言も言っていない。
いわゆる家に友達を招いたはいいが、特にすることがないという空気だ。
圭介さんは思い立った。
「よし、鬼探しをやろう。この遊びを広めれば人気が出るかもしれないぞ」
「本当に!」
京香さんが喜ぶ。圭介さんにとっては口からでまかせで、このときはただ京香さんに嫌われたくないことを優先した。
すると彼女は鞄から風呂敷を取り出し、紙の束を出す。
「え?それ…いつも持ち歩いてるの?」
「うん。大事なものだから。じゃあここに手を乗せて」
圭介さんは言われたとおり、紙束に手を乗せた。
直後に京香さんは立ち上がり、カーテンを閉めてゆく。
「何してるの?」
「あなたが逃げれば鬼探し、あなたが探せば鬼泣かし」
圭介さんの言葉に返事をせず、そのようなことを口ずさむ。
「何だって?」
圭介さんは鼻で笑う。
戻ってきた京香さんは笑みを浮かべていたが、目は笑っていなかった。
「始めるね」
時刻は午後二時を廻ったところだ。
nextpage
「紙は私が開くから、答えは言葉か指をさして教えてね」
最初の一枚目が開かれる。
nextpage
【鬼はどちらか】
左には水浸しのトカゲのような生物と、右には虎のような生物が描かれている。
「へえ」
紙自体は荒んでいるが美しい墨絵だ。誰が描いたのだろうか。
しかし虎が鬼となって追いかけてくる様子を想像すると恐ろしい。かといってトカゲもどうだろうか。
「これは何を根拠に答えたらいいのかな?」
「あまり詮索しなくていいわ」
「じゃあ左で」
次に左の紙がめくられる。
nextpage
【どちらが結実か】
左には枯れた木。右には桃のような実が付いた若々しい木が描かれている。
しかしよく見ると、桃と思われた実は人の顔、それも赤子の顔だった。
「うっ」
どういう意味だろうか。
圭介さんはアイコンタクトで京香さんに尋ねるが、じっと紙を見下ろしているばかりだ。
「どっちも嫌な感じがするんだけど」
「あなたは導く存在よ。何も心配しないで」
「釈然としないよ。でも実って言われたらこっちだろうな」
圭介さんは右を選ぶ。
すんなりと次の紙が開く。
nextpage
【針を持つか鋏を持つか】
隅で描かれた針も鋏は少々おっかないものである。
「ちょっとホラー入ってない?」
なぜだか分からないが、この絵を見ると実際にそれを受ける痛みを想像してしまうのだ。
「恐怖という感情はあまり重要じゃないわ。何を選んだかの道筋が大事だから」
「これって自分が持つってこと?」
「そうよ」
意外とすんなり答えてくれたので、圭介さんは悩みつつも「針」と答える。
「なんとなく痛くなさそうだし」
「そうかしら」
京香さんが静かに呟いたが、圭介さんは聞かなかったフリをした。
nextpage
【鬼はどこにいるか】
その紙が開かれたとき、何が描かれているか一目で分かり、圭介さんはぞっとした。
部室の外の廊下だった。左右どちらも同じだが、右側には廊下の奥に黒く塗りつぶされた何かが立っている。
「なんだ…こいつは」
その黒いものを見れば見るほど寒気が増していく。
「えっと。絵、上手いね」
圭介さんは冗談めかしたが、反応が無い。
「悪いけどもうやめていいかな?」
「ダメですよ。それは危険です」
<何が危険なんだよ>と突っ込みたかった。
「だよね。でもちょっと怖くない?これ」
「ふっ」
京香さんから嘲笑に近い声が漏れて、圭介さんは舌打ちしそうになった。
もはや彼女への美しいイメージは崩れている。
黒いモノがいない方の、左の絵を選んだ。
<ガタン>
「うわ!」
部室のドアが揺れた。
「何だ。何だよ!」
「あなたが選んだとおりになったわ」
二人ともドアを眺めている。おそらくは、施錠されたドアを誰かが開けようとしたのだ。
圭介さんは次々と違和感を感じた。そもそもなぜ施錠されているのだろうか。
「もういい!俺が悪かった。さっきのは何だ?説明してくれ」
非常に重苦しい空気だったため、圭介さんは窓を開けようと立ち上がる。
「開けていいんですか?」
「なんで?窓を開けるだけだよ」
サアっと光が差すのだが、何かが遮っている。
「う!うわあ!」
窓の外に、赤子の首がぶらさがる木で埋め尽くされていた。
本物だ。すべての顔が目を瞑っており、少なくとも死んでいる生首だ。
<ガラガラガラ>
今度は後ろ。ある気配が背中をすらりと撫でる。
それは風ではなく何かの気だった。鼻で気づかないニオイと言うべきか、それが一つの信号を圭介さんの脳に叩きつける。
絶対に振り向くな、と何度も何度も。
「ぐっ」
圭介さんは手を握っては開き、唾を飲み、今更になって後悔した。地上から叫び声が上がっている。おそらくこの樹の実に気づいたのだろう。
部長の言葉は本当だった。
「早く座ってよ」
「嫌だ」
「早く座れ」
「へ?」
その唐突の怒気によって圭介さんは硬直した。
「まったく」
京香さんの足音、そして眼前に紙が掲げられた。
nextpage
【最初に選んだのはどちらか】
左には赤い羽織に黒い目をした女性と、黒い鎧に赤い目をした侍の絵があった。
生首からの木漏れ日が紙を透かして気持ち悪く煌めいている。
「最初って…」
一枚目はこんな絵ではない。
<ああそうか>と一人呟く。
自分の選んだものが答えになる。少しだけでも理解できたことに圭介さんは希望を抱いた。
「おまえの…いかれた遊びに付き合ってられるか!」
圭介さんは窓に足をかけ、情けない悲鳴を上げながら飛んだ。
「ぎゃあ!」
枝に当たりながら落下する。体がバラバラになるのではないかと思うほどの衝撃の連続。
最後に突き抜けるような痛みが四肢に及び、思考が吹き飛ぶ。
圭介さんは是が非でも息を整えようとした。
「せいぜい4階だ。芝生の上だから大丈夫、芝生芝生」と何度も頭で呟く。
ようやく記憶が戻ってくると、自分が飛んだ窓を見上げた。
「あいつ」
京香さんがしっかりとこちらを見据えていた。その目は細く、不愉快そうだ。
「俺が何したっていうんだ」
圭介さんは走った。まずいことに肺に何かが当たっているらしく、足を地に付けるたび痛みが走る。
周りの学生は圭介さんのことよりも、至るところから生える木に夢中になっている。
空がだんだんと見えなくなってきた。
「ど、どこだ!ここは!」
走っているうちにも木が伸びてくるので、もはや自分のいる場所が分からない。
建物の壁もすっかり見えなくなり、圭介さんは勘だけで校門を目指した。
「痛い」
脂汗が滲み出てくる。他の学生もちらほら逃げ惑っているが、大抵はぼーっとしているか、カメラに収めているだけだ。
すっかり息を荒げ、辿り着いたのは中庭だった。そこにはいくつか折れた枝葉が落ちている。
絶句した。ここは圭介さんが飛び降りたところだ。
あたりを見回すが、木の根がすっかり地面を突き破っていて、どこへも行けそうにない。
「逃げちゃだめよ。すべてあなたが決めないと」
目前に京香さんが歩いてきた。
<ヒタヒタ>
背後からはモップが歩いているような音がした。人間の出す音ではない。
圭介さんはいよいよ振り向くこうとしたが、ブツッという音と共に胸に激痛が走る。
体の制御がきかず、その場に倒れ込んだ。
「穴が開いたのね」
「あ」
あまりの激痛に言葉が発せなくなる。
<ヒタ>
不気味な足音が止むと、粘着性のある何かが圭介さんの足を掴んだ。
「ひっ」
圭介さんの体がずるずると背後に引っ張られてゆく。
木やらコンクリートやらの感触は、柔らかくて温かいものに変わった。
途端にまとわりつく粘り気。だがどうしたことか、圭介さんはこれを少しだけ心地よく感じた。まるで溶けていくような感覚だ。
「逃げたらダメよ。どうしてそんなことをしたの」
視界の奥の方にまだ京香さんが写っている。彼女は肩に落ちてくる木の葉を払い落としている。
「ああ」
少なくとも肺の痛みからは解放されそうだと思えた。
京香さんがまだ何か言っているが、その声がくぐもってゆく。
外の世界の一切合切の恐怖から守られている安堵の中、圭介さんは目を閉じた。
nextpage
「うう」
声が聞こえ始めた。それが自分の唸り声だと気づく。
「起きたのね」
側に京香さんがいる。
圭介さんは部室にいた。ソファの上で仰向けになっており、起き上がってみると、胸の痛みも綺麗に無くなっている。外に生えていた不気味な木も消え去っていた。
「なんなんだ…」
とりあえず京香さんから距離を取り、説明を求めた。彼女は肘を付いて楽しそうに微笑んでいる。
「死ぬとでも思った?」
「人を何だと思ってる!悪ふざけにもほどが」
圭介さんも何をどう怒って良いものか分からず、とにかく真実を知りたかった。
「とりあえずあれは幻だったんだな?」
安堵しようとした瞬間、京香さんは目を大きくし、手を顎から離した。
「いいえ、あなたはもういないわよ?」
すんなりとそう言い切った。
「今からあなたは圭介さんだけど、元の圭介さんはいない。あなた以外は誰も気づかない。今のあなたは鬼の世界から取り寄せただけ。元の圭介さんはというと…」
そこまで耳を傾けていたが、急に胸と腹に痛みが走る。
「向こうではらわたを食われているわ。少しずつ契りを交わしながら」
声が出せず、ソファから転げ落ちる。
「その痛みは定期的にやってくる。そして疾患を抱える。確かこの世界で言う癌とかいう名前の」
「おまえは何の目的で」
「治療法は細胞ごと焼き払うんだってね。人間の力は恐ろしい。でも私の力はもっと強力だから間に合わない。最後まで元の圭介さんを喰らい続ける」
「やめてくれ」
「ところで目的だったな」
京香さんの口調が低く無機質に変わった。
「それはおまえたちの生きる目的と同じだ。丑三つ時ではない。おまえの知らない理のもと、ここは鬼が棲みやすい。私の名は仕来り」
separator
圭介さんは同好会をやめ、大学を辞めた。
おおよそ半年に一度は眠れないほどの体の痛みに悩まされているそうだ。
「彼女にはそれから一度も会えませんでした。僕は病院を転々としましたが、原因不明と言って聞いてくれないんです。でも確実に蝕まれているのが分かります」
圭介さんはつらそうな素振りを見せたと思うと、突然表情を一転させた。
「そこで考えたんですよ!」
そうしてポケットからタバコを、鞄から酒瓶を取り出した。今度は目を輝かせている。
「これですこれ。毎日こうしてね。病気になっちゃえばいいいんです。それなら文句は無いでしょう?」
「すみませんがここは禁煙なので」
「ああ、そうですか、そうですか。じゃあ後にしますね」
そこまでに至るほどの苦しみだと推測できる。彼の浮き沈みが激しい、コントロールできていない態度を見ると哀しくなってしまった。
そもそもこの話自体が真実でなければ、圭介さんはどこに向かっているのだろうか。
分かっているのは、実際には何も起きていない。目の前にいる人物は確かに人間であり、圭介さんということだけである。

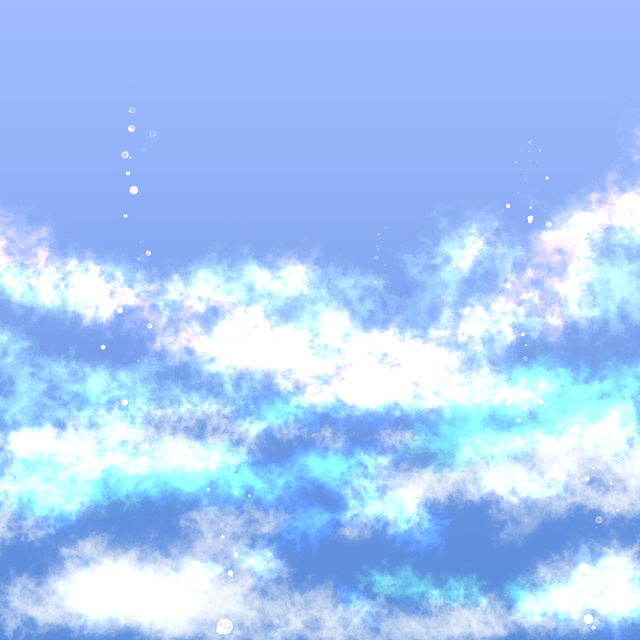
作者ホロクナ
今もなお怖いをいただけたので生存報告です。