wallpaper:234
Mの体験した話だ。
千葉県・銚子市に生まれたMは大学で海洋学を学び、卒業後は大学院の修士課程に進学した。
修士一年の夏。Mは教授の勧めを受け、深海調査船による小笠原諸島沖の調査プロジェクトに参加した。
「参加が決まった時は嬉しかったですよ。貴重な経験ですから」
前日の夜は興奮からか、一睡も出来なかったという。
「小さな頃から海が好きでした。両親は居酒屋を経営して、ストレスを貯め込んでいて。家の中には居場所が無くて……。砂浜で貝殻を拾ったり、波間に向けて石を投げたり。そんなことばかりしていましたね」
船はモーター音を響かせ、沖を進み目的の地点に止まった。
ハイビジョン・カメラや海底堆積物を採取するチューブ、通信装置を積み込んだ無人探査艇が深海に潜航していく。
「魚群が近くを通ると、船がぐわんと持ち上がる感じがするんです」
USTREAMのように、無人探査艇が船のモニターに映像を送る。
「光の加減によるものでしょうが、青、赤や黄のクラゲがゆらゆら液晶に映ったり......」
船から僅かに漏れたであろう油が、船の後方で白く尾を引く。
白い床がジリジリと太陽を反射すると、左手の薬指に指輪を嵌めた助手の女性がだるそうに手摺りに寄り掛かった。
「日射病でしょうね。胃下垂ですごく痩せた人でしたし、暑かったですから」
助手の女性は青山学院大学を卒業後、一般企業の事務職に就くも突如、海洋学に開眼し、Mの通う大学の大学院に入学し、博士課程に進学。三十路に突入してからも、研究室に残っているという少々特殊な経歴の持ち主だった。
周囲の人間の中には、助手の女性に対し「学歴ロンダリングだ」「教授に媚を売っている」「海洋学の研究者では無く、ただの物好きだ」などと陰口を叩く者も居た。
白い翼をばさばさと動かし、カモメの群れが船上に飛来した。
ぐわ、ぐわ、ぐわ。
カモメの両目には目ヤニがたまり、異様に発達した胸筋を反らして鳴く度に涎が下に垂れる。カモメの群れはくちばしを突き出して滑空し、助手の女性を襲った。
執拗にカモメは、側頭部や後頭部にくちばしをぶつけた。かちかちかち、と奥歯を打ち鳴らすような音もした。くちばしの先には糞尿のかすのようなものが付いていた。日焼け止めのクリームの芳香と“獣臭”、潮の匂いが甲板の上で複雑に混じり合う。
悲鳴を上げ、助手の女性は蹲った。覗くこめかみから、血がだらりと流れていた。
三発の銃声がした。空砲に怯み、カモメはぐわ、ぐわと逃げた。
白い煙の残る拳銃を手に、教授はMに、助手の女性をモニタールームのソファで休ませるように指示をした。
「何と言うか……。偉そうに聞こえたら申し訳ありませんが、感心しました。教授は取るべき行動をベストのタイミングで、しっかり取ったように思えたので」
助手の女性はモニタールームのソファに座り、ポカリスウェットを飲むと数回しゃっくりをし、全て吐き出した。
唾と混じった液体はぶくぶくと泡立ち、湯気を発し、腐った藻のような黒い染みを残した。染みの上、何処からともなく現われた白い蛆が這う。
「何、これ……」
助手の女性はわなわなと身体を震わせ、海の底の様子が映し出されているモニターを指差した。
植物がゆらめき、深海生物が蠢く。
時折、砂が舞う。
カーペットのように、星条旗が海底数十メートルに渡り、広がっていた。
そして助手の女性の“遺体”がモニターの中央に漂っていた。海底を背景に、肌は蝋のように白く、胸の辺りから煙草の煙のようにゆらゆらと血が流れ出していた。
「目を離すことが出来ませんでした。美しい光景に見えて。どんな絵画や映画よりも――」
*
間もなくして、助手の女性は大学院を辞めたという。「思い直したらどうか」という教授の説得にも、助手の女性は耳を貸さなかったそうだ。
Mは博士課程への進学を希望している。




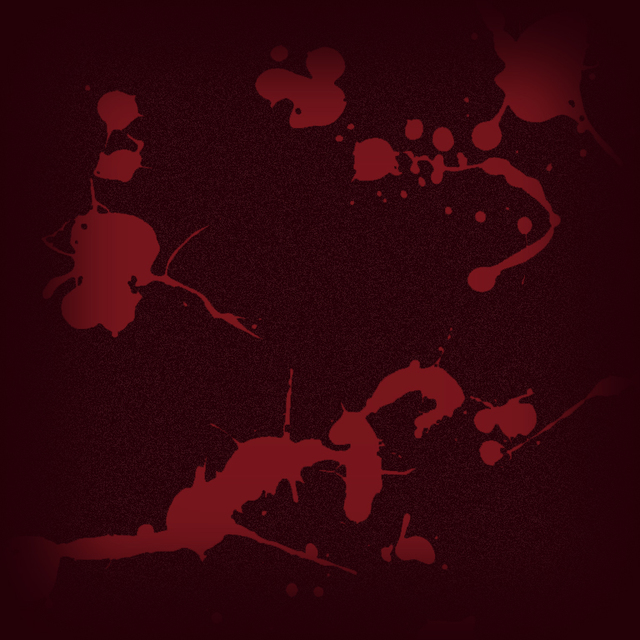

作者退会会員