wallpaper:137
IT企業に勤めるタカシの話だ。
タカシの勤めるIT企業は90年代末にサーバー管理を主な事業として創業されたが、インターネット広告市場の拡大を受け、広告プラニングと運用にも力を注ぐようになった。
「完全に手探りでしたね」
とタカシは語る。
「サーバー管理と広告では同じITでも仕事の内容が全然違いますからね。広告の世界では後発の企業ですから、どうすれば他の会社に優位性を発揮出来るか試行錯誤が続いていました」
タカシは毎日昼食もまともに摂らずに働いていた。タカシは新婚だったが、帰りは遅かった。
バングラデシュの首都・ダッカに“クリック工場”を建設したのも、会社の“試行錯誤”の一環だったという。
「バングラデシュは日本よりも人件費が安いから現地で大量に人を雇うことが出来るんです。兎に角沢山、facebookやtwitterのアカウントを取得して『いいね!』を押すんです」
何故、建設先が他の国や地域では無くバングラデシュなのか。
「“社会貢献”の一環ということになっていましたが、詳しくは分からないですね」
抱えるクライアントには新人女性アイドルを抱える芸能事務所が多いという。
「『江南スタイル』がYoutubeを通じて世界的なヒットになったでしょう。以来、それまでネット戦略に力を入れて来なかった芸能事務所もYoutubeのビュー数や『いいね!』の数に敏感になったんです」
ある日、タカシはバングラデシュに向かった。
「日本とバングラデシュは離れていますから。上がって来る報告に目を通すだけでは無く、視察に行くことも大切なんです」
タカシがバングラデシュに行くのはその時が初めてだった。仕事とは言え、行ったことの無い国に行けるということでタカシは視察を楽しみにしていたという。
日本からバングラデシュへの直行便は無く、タカシはバンコクで乗り継ぎをした。
飛行機の待ち時間等も含めて、およそ十時間でバングラデシュに着いたという。
空港には現地法人の責任者が迎えに来ており日本語の挨拶を受けた後、タカシは宿泊先のホテルに案内された。
ホテルは想像していたよりも遥かに綺麗だったが、その夜は何故か一睡も出来なかったという。
翌朝、タカシはホテルの一階のカフェテリアで朝食を食べた。
スクランブルエッグをスプーンで口に運んでいると五歳ぐらいの現地の子供たちが七、八人ほどタカシの周りに集まって来た。
(日本人が珍しいのかな)
とタカシは思ったという。また(この子達はホテルの支配人の子供なのかな)とも考えた。発展途上国では大所帯の家庭は珍しくないからだ。
「君たち、何処から来たの?」
タカシは簡単な英語でゆっくりと発音し、子供たちに訊いた。子供たちは問いに答えなかったという。
子供たちの内、一人の男の子は手に鉄の棒を握っていた。
「危ないよ」
タカシは男の子に鉄の棒を床に置くように促した。男の子は“あはは”といった調子で笑った。
一歩ホテルの外に出ると、冷たい汗が出た。
「日本に比べて、バングラデシュは太陽が地表のより近くにあるような気がしますーー」
タカシはそのように振り返る。
工場にはWindowsのPCが縦に数十台、横に数十列並べらていた。階段を上った階には食堂があり、微かにコンソメ・スープの匂いがした。
「バングラデシュ人は皆、同じ顔に見えました。よくアメリカ人やイギリス人は『日本人は皆、同じ顔をしている』と言いますけど、それと同じ感じでーー」
タカシはこのようにも語った。
「彼らが何を考えて仕事をしているのか全く分からなかったんです。バングラデシュ人は皆、真面目で背筋をぴんと伸ばして作業をしていました。それは良いんですけど......ぴんとし過ぎているんです。作業の合間に水ぐらいは飲んだり、隣の席の仲の良い人と話をしたり......そういうコミュニケーションが存在していなかったんです」
昼食の時間になるとクリック工場にはベルが鳴り響いた。作業員は一斉に立ち上がると綺麗に整列し、食堂に向かい階段を上がっていったそうだ。
現地法人の責任者は
「日本のビジネスマンは昼食の時間、どのように過ごすのですか?」
とタカシに尋ねた。
*
視察を終えたタカシは、日本に帰国した。
成田空港を降り、電車を乗り継ぎ世田谷区の自宅に着く頃には、時刻は0時を過ぎていた。
ドアに手を掛けると、鍵が掛かっていた。
(まあ、時間が時間だし仕方ないか)
タカシは鞄から鍵を取り出し、鍵穴に鍵を差そうとした。
鍵が合わなかった。
(あれ)
タカシは鞄の中を再度見て、手にしているのが間違いなく自分の家の鍵であることを確かめると鍵穴に差した。
鍵はやはり合わなかった。
(おかしい)
庭の方に回り、家の様子を覗いた。カーテンの隙間から明かりが漏れている。
ぴんぽん、ぴんぽん。
ドアの前に戻り、インターホンを鳴らした。妻が起きているなら、家の中から鍵を開けてくれるはずだった。
反応が無い。
タカシは新聞受けを開け、中から合い鍵を取り出した。万が一のため常備している合い鍵で、そちらの鍵は鍵穴に合った。
玄関を上がり、廊下を歩く。リビングに複数の人間の気配を感じる。
(誰だ)
明かりの方向に恐る恐る近づいていく。
ドアを開けた。
常温の中、放置された魚の刺身のような匂いがした。影がまず目に入った。
子供のものだ。七、八人分の影がある。
(バングラデシュ人だ)
目がとても大きい。
くしゃくしゃとした髪の毛がキュートだった。
季節外れの薄汚れたadidasのジャージを着て、暑そうに袖をめくっていた。
手持ち無沙汰なのか、子供たちはしきりに指を唇に当てた。
黒真珠のようなバングラデシュ人の子供たちの肌を見て“綺麗だ”とタカシは思ったという。
「何故かは分かりませんが、その時は妙に落ち着いていました」
机の脇で妻がうつ伏せの格好で倒れていた。その周りをバングラデシュ人の子供たちが取り囲むような位置関係だった。
妻は目尻から血を流していた。口の端には涎が乾いた跡があった。覗く舌が膨れていた。H&MのグレーのTシャツは汗でぐっしょりとしていた。肩の辺りや右腕に大きな痣があった。
(もっと色々な話をすれば良かった。もっと良い結婚生活の形があったかもしれない)
タカシは妻の脇に屈み、妻の前髪を横に流した。開いたままの妻の目は、黒目が収縮し切っていた。
(結局、子供を作ることは出来なかった)
俯くタカシの顔を、バングラデシュ人の子供たちはじっと見つめた。
タカシは携帯電話を取り出し、警察と病院に電話を掛けた。タカシは腕を突き出して、バングラデシュ人の子供たちに“動くな”と意思を伝えた。
「家の中で妻が倒れています。それから見慣れない子供たちが何人もーー」
先に家に着いたのは、警察だった。
ドアがノックされ、タカシは「こっちです!」と叫んだ。後ずさりし、一瞬後ろを振り向いて廊下のドアを開けた。
拳銃のホルダーに手を掛けた警察官が一斉に部屋の中に入って来た。
その内の一人が困惑したように言った。
「奥さんはどちらですかーー?」
(え?)
バングラデシュ人の子供たちの姿は無かった。妻の姿も消えていた。
部屋には、刺身のような匂いだけが残されている。
(皆、何処に消えたんだ)
タカシは戸惑った。何故か寂しい気持ちにもなった。
「そんなはずはありません。今日僕はバングラデシュから帰って来て、家の鍵が開かなくて。合い鍵で入ったらバングラデシュ人の子供たちが居て、真ん中で妻がーー」
「少しお休みになった方が良いでしょう。出張でお疲れでしょうから。明らかな事件性が無いと、警察は市民の方々の力にはなれないんですよーー」
どれだけ言葉を重ねても、妻もバングラデシュ人の子供たちもその場に居ないことは確かだった。警察官は皆、家から引き上げていった。
間もなくして到着した救急隊員には「泥酔しており、でたらめな内容の電話をしてしまった」と言った。
救急隊員は「こうしたことをしてもらっては、困ります。他の家庭に今すぐ助けを求めている人が居るかもしれないんですよ?」と憮然とした表情で言った。
タカシは家の中で朝を迎える気にはなれなかった。
家の近くのマクドナルドで萎びたフライドポテトを食べ、タカシは夜を明かした。
頭痛がした。
身体中から疲労が噴き出してくるかのようだった。
朝。
午後からの出社に備えて、タカシは家に帰った。
太陽が悪性のものであるかのように照り付けていた。掛けたはずの鍵が開いていた。玄関に妻のヒールがあった。
「あら、お帰りなさい」
妻の声がした。
「どうしてーー」
他の言葉が見つからなかった。
妻は
「お母さん、体調を崩したみたいで。昨日から夕食を作ったり、部屋の掃除をしたりして、今日の朝の電車で帰って来たの」
すらすらと語った。妻の声は靄がかって聞こえた。
「そうかーー」
妻の服装はタカシがバングラデシュに発つ前、最後に見たそれと全く同じものだった。
妻はタカシに「コーヒー、飲む?」と尋ねた。タカシは頷いた。妻の身体には所々、痣が残っていた。
痣、痛くない?
痛いに決まってるじゃない。
タカシの問いに、妻は答えた。
*
「冬にはもう一度、バングラデシュに渡る予定です。その時にはまた妻を一人にしてしまうのですがーー」
と、タカシは語る。
タカシの仕事は順調だ。給料が増えた。夫婦仲も前に比べ、多少は良くなったという。
「この間は一緒にフランス料理を食べに行ったんですよ」
タカシの妻は不妊治療を続けている。結果はまだ出ていない。




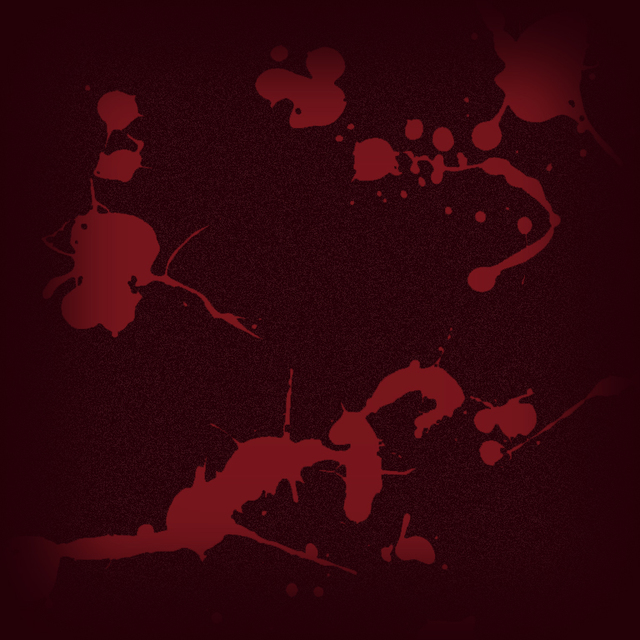

作者退会会員