music:1
最近、実家に帰ったからか、余計なことを思い出す。
M県S市に居た頃は思い出す暇も無かったけど、ここは良くも悪くも娯楽がないからか、頭が暇だ。
昔見た怖い事を思い出しては考えるようになった。
今日は、そんなすっかり忘れてた小噺。
music:4
1『お風呂、怖い』
小さい頃の話なんだけど。
私が今仕事をしている酒屋の近くに、昔はラドン温泉と言う所があったのですよ。
そこが、私には怖くて怖くて仕方ない場所だった。
当時は3、4才位。
視える物がなんなのか分からないけど、とにかく気味が悪い事だけが分かってる。
ただ、親に言うには語呂が無さ過ぎて、ただ『怖いー怖いー!口、怖いーぎゃあー!』としか言えなかった。
今では親や祖母に、あの時、宵はお風呂が大きな口に見えて怖がっててさーなんて言われるけど、実際は違う。
でっかい頭があったんだよね。
ヘドロに塗れて薄汚れたデカイ女の顔が、目の上位ほど顔を出して、ギョロギョロした目を髪の隙間から光らせてこっち見てる。
たまにグァパーっと大きな口をあけて湯を飲み込むのか何なのか、歯並びの悪い黄ばんだ歯列を私に見せるんだよ。
そこにも、ヘドロが歯茎に絡まってて気持ち悪い。
『なんで入れるの、嫌だよ、怖いよ、やめて!』と、ギャン泣きする私を無理やりにでも湯船に入れようとする祖母が鬼に見えた。
『なんで、家の風呂はいいのにねぇ』と、首を傾げる祖母の方が、私には理解出来ない。
けど、ある日を境にソイツは居なくなり、私も大浴場に入ることが出来たけど、その後すぐにそこは潰れた。
あれ、なんだったんだろうなあ。
今だに、あの近辺は土地が悪いので、生物学上の父が家を買う!と言った途端に『悪いけど、私は住まないから』と言い張った因縁の場所だ。
music:4
nextpage
2 『55柱になれなかった人たち』
確か14才位だったかと。
記憶があやふやな殺伐とした時期の事だったと思う。
奴らがいてもいなくても人生が生きにくい事は確かだと達観していた私は、偏屈な少女だった。
専ら、図書館で漫画のプロットやら新撰組やら薩摩長州やら美術書、オカルトなどを調べてるのが好きだった。
よく一人で居るので、おじさん達が諭吉をちらつかせて交渉されるのなんか、日常会話だった時代だ。
(i市図書館は死角だらけの構造だしね)
そんな殺伐とした心を癒しに、図書館帰りに日向ぼっこがしたくなると私はわざわざH山神社の公園まで行くのが常。
でも、その手前辺りにツナギを来たボロボロの人たちが居る場合がある。
忘れもしない4月28日(この日がいろんな意味で私には因縁深い日だ)とても天気が良い日だった。
自転車を押して坂を登る途中、目の前からボロボロの例の人達がゾロゾロ歩いてくる。
当時、戦争なんて言葉は教科書の中の話で、なんの興味も無かった私は彼等が兵士で戦死者とは分からなかった。
兵士って迷彩服を着てるもんだし、無地の軍服があるとは露とも思ってない馬鹿者だった。
俯いていて足やら手やらなくても歩いてくるもんだから、人じゃないのは直ぐに分かる。
でも、ある一定の場所まで歩くと彼等はスタート地点まで戻らされ、また隊列を組んで歩く…
なんでこんな事をしてるんだろう、この場所に縛られる地縛霊とか?と考えつつ、見えないフリして私も歩き続ける。
そのうちの一人が私とすれ違った瞬間に顔を上げた。
『○○は何処ですか?』
『……。』
無視無視、そこ分からないし。
i市に英霊を祀る様な神社、今でこそ分かるけど当時の私が知るよしもない。
その人は、隊列を抜けて暫くついてきたが、私は何もしなかった。
スタート地点まで歩くと、彼はまた隊列に戻り、また歩き出す。
今思えば、あの地点から英霊を祀る神社まで数メートルで行ける距離を、彼等は何度も歩き続けていたんだと思うと悲しい話だなと思う。
それにその神社には、55人の英霊が祀られてるらしいと今になって分かった。
彼等はそれになれたんだろうか?
今通っても、あの隊列は見かけない。
後日、この話を別所でしたところ、拝み屋の相方から連絡があった。
『あの隊列さんね、大丈夫だよ、ちゃんと55柱になれたから』
彼らはやっと戦争を終える事ができたと分かって、ほんの少し嬉しかった。
music:4
nextpage
3 『ねぇ、みえんの?』
良く、そんな事でいじめられた。
小学生って、何で言わなきゃいいことを言ってしまうんだろう。
霊感って皆にあるわけじゃないし、言うとウソつきになるのは分かってた筈なのに、強情な私は何かの拍子でそれを言ってしまったらしい。
あれから、特別っぽく振る舞いたい痛いコって事でいじめられたりしたが。
夏場やこっくりさんには強制参加と言う、変な扱いをされる様になったキッカケがある。
『ねぇ、あれ視えるの?』
一人の女の同級生がそう聞いて、アパートの5階辺りを指差す。
『うん、女の人がいるけど…』
『ウソつき!何もいないよーだ!バーカ!宵って気持ちわるーい!特別とか霊感少女ぶってさ!アホー』
shake
その時だった、彼女の後ろでイキナリ『ンダーーーン!』とか『パーン!』と軽い音が響いた。
まるで、トタンに石を叩きつけたみたいな音。
彼女は小さな悲鳴を上げたが、驚くのは私の方だ。
顔面蒼白で引きつって、ガタガタ震えが止まらない。
『何?何の音?』
『何も落ちてないじゃん!』
なんかやったのか?と女子が私を見る。緊張しまくる私が
『お、落ちたよ…女の人…帰る!』
後ずさりして、私は逃げた。
だって、全身血塗れでまた階段を上がって行くその女の血や臓物の匂いが、夕餉の匂いと共にしてきそうで怖い。
だが、それよりも怖いのが。
彼女達がキョロキョロしている間に、女の人が立ち上がり口から血泡を吐きながら『いごう、あんべ、あんべや』
(こちらの方言で、一緒に行こうと言う意味)って言った事だった。
彼女達を残して帰宅した翌日から、私は蔑まれるのと同時に一目置かれ始め、肝試しには必ず連れてかれる様になった。
因みに、何の関係もないかもだが。
同時そんな意地悪をした彼女は、今はこの街には絶対に帰れない。
帰りたくても絶対に。
何があろうとも。
もし帰って来たら『人殺し!』と彼女が今度は蔑まれる番だからだ。
終わり
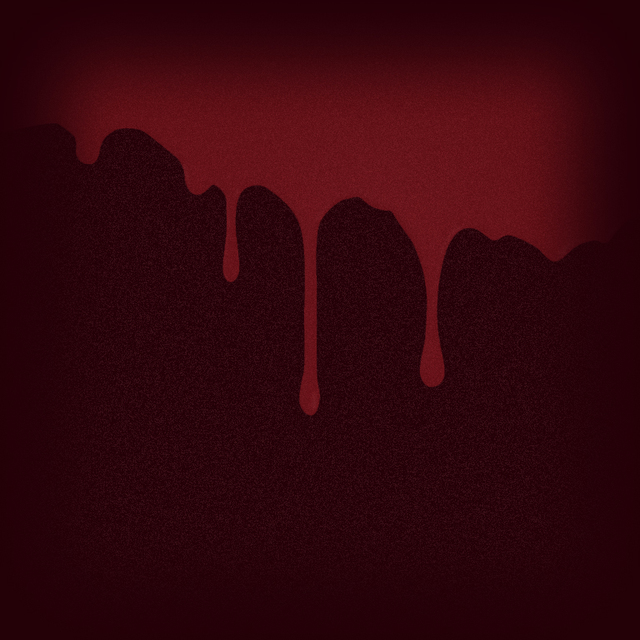

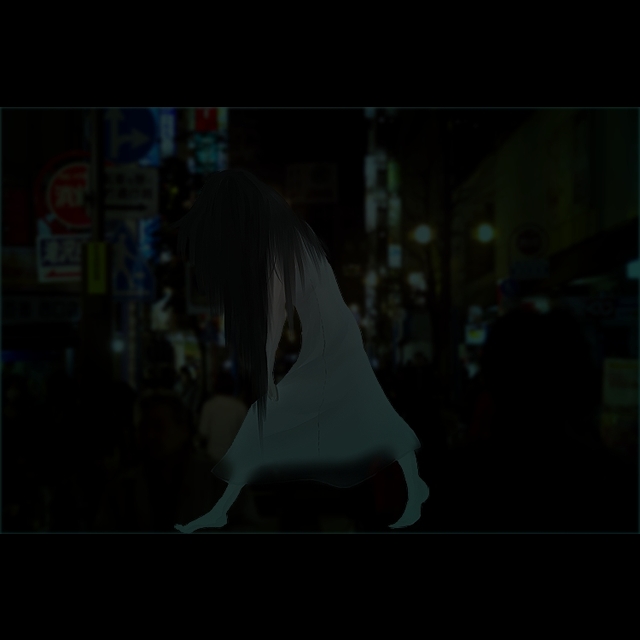
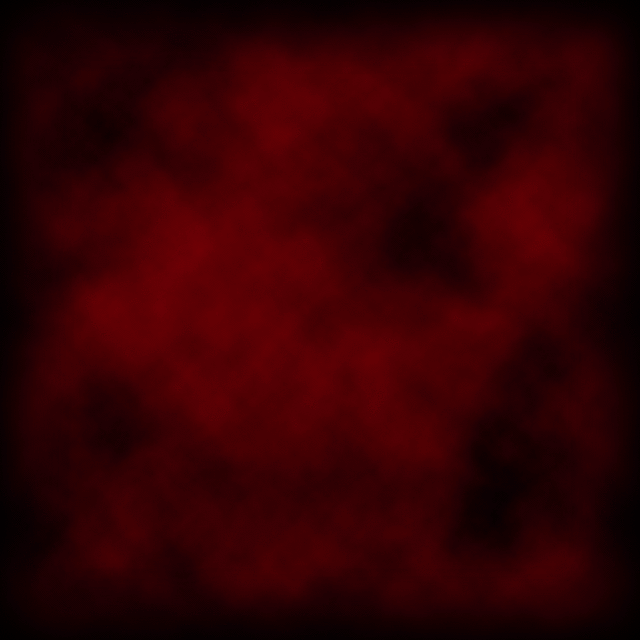
作者宵子
小さい頃の実体験です。
最後の話にある事は、実際に彼女が手を下した事ではない事件だけども、この話は諸事情があって言えません。聞けは皆も『あーあの事件か!』と分かる方もいると思うので。