wallpaper:203
知り合いもいない、誰も俺を必要としない、この里山にきて一週間が過ぎた。少しずつ、自分ってのを取り戻している感じは悪くなかった。
一週間前、近永 修尉チカナガ シュウイと云う陶芸師に連れられて、枯れ木だらけで灰色の景色に囲まれて初めて口が利けた。
「よろしくお願いします」
「おう。名前、何だっけな」
「石田 凛イシダ リンです」
「中にいるのが家内の優花ユウカだ。好き嫌いがあるなら言ってこい」
「あ」
好き嫌い以前の問題だ。今までろくに食べなかった俺はちゃんと摂れるだろうか。正直に優花に話すと笑われた。
「じゃあ、ご飯炊くとこから教えなきゃね」
修尉も優花もそのままの俺を受け入れ、学校のように弾くことはなかった。青い作務衣を渡され、着替えたらすぐに薪割りをさせられた。とにかく割れない薪に悪戦苦闘。夕闇に紛れるまで戦った。
「凛、風呂に入れ。よく解すんだぞ、明日、筋肉痛で動けないとか言わせんからな」
「はい」
青い色が変わるくらい汗をかいた。無心、がこんなに心地いいとは。頭のてっぺんから足先までさっぱりしてから大きめの湯船に浸かった。
顎が浸かるくらい沈むと肌から熱が伝わっていき、筋肉がキシキシいい始めたのが分かる。
nextpage
ほんの一瞬、意識が飛んだ。移動もあったし、初めての薪割りが全身に疲れを溜めていた。頬を撫でられて意識か現実に還ってくる。肉体と精神がピッタリ重なった瞬間だった。
「ひっ」
湯船に張るのは透明だったお湯ではなく、髪の毛だった。
真っ黒で、闇夜のような。
動けない身体に髪の毛が絡み付き、膝と膝の間がぷっくりと膨らみ始めた。頭だ。
誰の。
nextpage
「凛、背中、流してくれ。開けるぞ」
「うわっ」
修尉の声が闇夜を消した。髪の毛に引き摺り込まれたが、助かった。気管に入ったお湯に噎せる。
「寝てたか、溺れるぞ」
笑われた初夜から一週間が経った。毎夜、あの髪の毛と戦っている。昼間は薪割りと戦っているから、本当に腹が減る。優花が作る食事を問題なく平らげる俺を、修尉はまた笑っている。
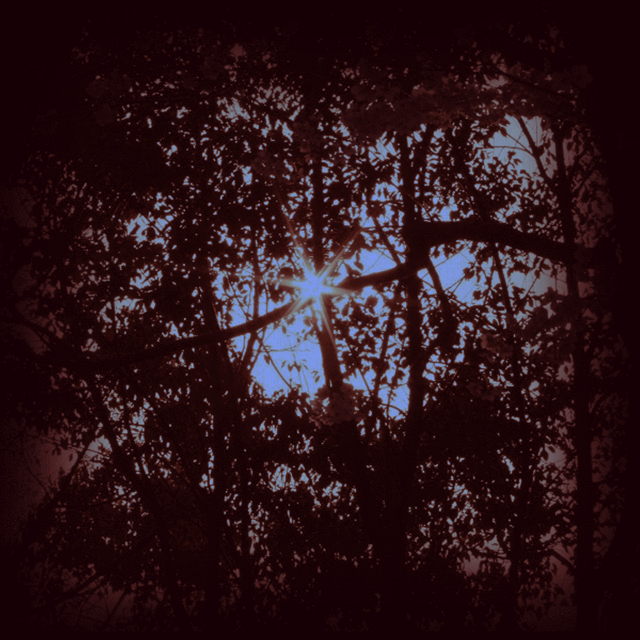





作者退会会員