暑かった夏はあっという間に過ぎ、街は徐々に秋色へと染まりつつある。
見慣れていた街路樹の葉は、いつの間にか黄色く落葉していた。
先ほど交差点ですれ違った若い女性が、タートルネックのセーターを着ていたのには驚いた。
就職活動に躍起になっていると、季節感も麻痺してくるらしい。
今日も3社面接に扱ぎつけたが、正直自信はなかった。
「貴方の強みはなんですか?」
「これまで取り組んできた事はありますか?」
―――何もしてこなかった僕に、介護事業系会社の面接官からの質問に回答する術はなかったのだ。
唯一褒められたのは、
「靴、ピカピカで綺麗ですね」
と言われた事だけだ。靴なんかより、僕自身の評価をして欲しい。
部活や趣味等、何もない。
これまで特にやりたい事も夢もなく、クラゲのように漂う生活をしてきたのだから。
もちろん、一時期は希望に燃えていた事はある。バンドを組んだり、海外での生活を夢見てバイトをしたり、とにかく色々だ。しかし全て中途半端に投げ出し、何一つ達成できたという成功体験はない。
就職活動というのはある意味いい機会である。これまで自分と向き合ってこなかった僕にとって、半ば強制的に自己分析を行わざるを得ないからだ。
そして出た結論が、「自分には何もない」という事だった。
そんな自分に嫌気を感じながら、今日も惨めに帰路に着く―――
最近はもっぱらこの繰り返しである。
スマートフォンが振動し、メールを開くと先日2次面接をした外資系企業からであった。
“松本優太様
平素よりお世話になっております。先日は弊社の2次面接にお付き合い頂き誠にありがとうございます。大変残念ではありますが、今回は松本様の選考を見送らせて頂く運びとなりました。またご縁がありましたら何卒宜しくお願い致します。なお末筆ではございますが、松本様の就職活動とご健康を心よりご祈念申し上げます。”
お決まりの“お祈りメール”にもすっかり慣れてしまったが、2次面接まで進んでいただけあり、さすがにショックは大きい。更に肩を落としながら、僕は自宅のドア静かにを開けた。
今日の夕食はカレーらしく、いい香りが玄関まで漂っている。靴を脱いだのと同時に、母がリビングから顔を覗かせた。
「あら、優太お帰り。ご飯食べるでしょ?手洗ってきちゃいなさい」
忙しくそう告げると、キッチンへと戻っていった。
洗面所で手を洗い終えリビングへ行くと、父が仏頂面で新聞を広げている。僕はこの父が苦手である。無口な上頑固で、非常に厳格な人物である事も手伝い、僕が高校生の頃あたりから会話らしい会話は皆無であった。
そして、出されたカレーをスプーンでカチャカチャとしていると、ゴロッと大きなビーフの塊が現れた。それを口に頬張ると、あまりの熱さにびっくりしてしまったが、ビーフは口内ですぐに解けて舌いっぱいに旨味が広がった。おもむろにご飯をかきこみ、冷たい緑茶を喉に流し込む。
ふう、と一息つくのと同時に父が口を開いた。
「今日は、どうだったんだ。」
「何が?」
「何が、じゃない。面接に行ったんだろう。手応えはあったのか聞いているんだ。」
「まぁ、別に普通だったけど。」
「普通って何だ。受け答えがスムーズにできたとかできなかったとか、色々あるだろう。」
ムッとした僕は、テレビをつけてカレーを二口、三口とかきこむ。その様子を見た父は、大袈裟に溜息を吐き言葉を続けた。
「優太、お前の人生なんだぞ。もっとしっかりしたらどうなんだ。」
「わかってるよ、だから就活だってしてるじゃん。俺だって色々とーーー」
「わかってないからこうやって言うんだ。どうせ、面接じゃ大した受け答えができなかったんだろう。お前の様子を見れば分かるぞ。いいか、しっかりと対策を練った上で臨まんと印象っていうものがーーー」
「もう、勘弁してくれよ!なんだよ帰ってきて早々説教なんてさ、その前に“お帰り”とか、“疲れただろ”とか、言うことあるだろ。こっちだって一生懸命やってるんだよ!」
「甘ったれるな!社会はもっと厳しいんだぞ。大体なんだ、そのしわくちゃなスーツは。だらしのないお前の事だから、ハンガーにかけずに丸めて置きっ放しなんだろう。俺が面接官だったらそんな奴雇わんぞ。そういう所から心構えをだなーーー」
僕は思わず、持っていたスプーンを床に叩きつけると父にありとあらゆる罵詈雑言をぶつけた。
「死んじまえ」「お前なんかいなくなれ」「お前に何がわかるんだ、馬鹿野郎」
そんな言葉ですら、今の僕にとっては罪悪感を持たなかったのだ。
優太、と母に激しく右腕を引っ張られた時に、父に掴みかかっていた事に気付いた。
僕はハッとし、手を離すと父が床に倒れ込む。
いつの間に、父はこんなに軽くなってしまったのだろうか。あんなにがっちりとしていた体格は今や見る影もなく、痩せ細った体は弱々しさすら感じる。
激しく咳き込む父を、母は肩を支えながらゆっくりと立ち上がらせると、今まで見た事のないような表情で僕を睨みつけた。
「優太!あんた、やっちゃいけない事をしたよ!謝りなさい、お父さんに謝りなさい!」
僕は堪らず玄関に走り、無造作に履き捨てられた革靴を履くと、家を飛び出した。そして、自転車をとにかく漕いだ。目的地なんて無かったが、とにかく遠くへ行こうとした。スマートフォンが激しく振動し続ける。恐らく母であったが、僕は構わずにペダルを漕ぎ続けた。
separator
それから2日間、僕は友人の家に身を寄せていた。
友人からは「いい歳して、家出かよ」なんて笑われたが、確かにその通りだと、今の状況に僕自身も馬鹿らしくなり、帰宅する決意をした3日目の夜の事だった。
あまりの寝苦しさに目が覚めた僕は、明らかな異変を感じていた。体が硬直して動かないのだ。だが不思議と目は冴えて、感覚が研ぎ澄まされている気がする。
ーーーこれが所謂、金縛りという現象なんだろう、そう直感的に考えていた次の瞬間、玄関の方からゴソゴソと、奇妙な物音が聞こえる。小さなワンルームなので、玄関は部屋と直結である。
音の正体を確かめる為、首だけ起き上がらせ目を凝らすと、白いモヤのようなものが玄関を覆っていた。“それ”が段々と人のような姿へ形成されていく事に気づくのに、時間はかからなかった。
“それ”は、しばらく玄関へ留まっていたが、僕の方へ向き直り、ゆっくり、ゆっくりと近付いてくる。友人は寝息をたて熟睡しており、起きる気配もない。僕はというと、情けなさそうに口をパクパクとさせるだけであった。
一歩、また一歩と、ゆっくりと確実に僕の方へと迫ってくる。
ーーーもうだめだ。
次の日、友人の呼ぶ声で僕は目を覚ました。
「優太、おい、優太。電話、すげぇ鳴ってるぞ。起きろって。」
僕はむくりと起き上がり、辺りをキョロキョロと見渡す。
ーーー夢だったのか。
ホッと胸を撫で下ろすと、いつまでも鳴り響くスマートフォンを確認する。
母からの着信だった。
ずっと無視をしていたが、今度こそ電話を取って、“もう帰ろうと思う、ごめん”と言おう、そう考えながら液晶をスライドさせ、スマートフォンを耳に当てると、母から思いもよらぬ言葉が出た。
「あんた、何してるの!何で、何で電話も何も出ないの。あんたねぇ、あのねぇ、お父さん、お父さんが、死んじゃったよ。優太、もう、母さんどうしたらいいのか、わからないよ。」
涙声でつっかえながら話す母の言葉の意味を理解すると、僕は頭の中が真っ白になるのと同時に、何かが音を立てて崩れ落ちるのを確かに感じた。
separator
父が急逝したのは、昨日深夜らしい。死因はすい臓がんで、既に末期状態であった事を母は静かに僕に告げた。いつ危篤状態になっても、おかしくない病状だったようだ。
僕は、何も知らなかった。
父が、僕の疲れを気遣って好物のビーフの塊でカレーを作ってくれていた事。
いつも僕と言い合いをした後、僕から嫌われていないか、いつも心配していた事。
頑張っている僕に心配をかけまいと、ガンの事は絶対に言わまいと決めていた事。
それを悟られないよう、入院せず自宅で療養していた事。
僕の革靴を、夜中ピカピカになるまで磨いてくれていた事。
そして、誰よりも僕の事を心配してくれていた事。
僕は、何も知らなかった。
というより、知ろうとすらしなかったのかもしれない。自分の事だけで精一杯で、1番近くにいる家族の事を気にかける事もなく、ただただ文句ばかり言って日々を過ごしていたのだ。
だが父は、自分が短い命だと知りながらも、息子である僕にありったけの愛情で尽くしてくれていた。
葬儀の後、母はこんな事を言っていた。
「あの人ねぇ、本当に不器用な人でね、人一倍優しいんだけど、それを表現したりするのが苦手なの。でもね、最近珍しく酔った日があって、何を言うかと思ったら、“俺は絶対にガンなんかに負けないぞ。優太があんなに頑張ってるんだ、俺も負けてたまるか、皆で乗り越えるんだ”ってね。それで、“俺にはこんな事しかしてやれないから”って、あんたの好きなカレー作ったり、靴磨いたり、コソコソとねぇ。素直に言えば良かったのに。」
そんな事を、どこか嬉しそうに話す母の横顔がとても綺麗に見えた。
separator
ーーーそれから3年後の今、僕は介護福祉士として、特養介護施設で勤務している。忙しい毎日だが、とても充実した毎日を送っている。
ここに内定が決まった理由は、父のおかげなんじゃないかと思っている。父が磨いてくれた革靴がきっかけで、ここへ就職できたのではないかと、僕は勝手に考えているのだ。
そして、父が死んだあの日、父はあの白いモヤとなって最期の挨拶に訪れたのと、靴を磨きに来てくれたのだと、確信している。
あの時、父へ謝罪もできず、仲直りもできずに死に別れた事は、今では後悔していない。そんな事をしたら、僕らは僕ららしくないからだ。
ーーーだが、僕が父の事をもっと知っていれば、と考えると今も胸がチクリと痛むのだ。
だから、少しでも誰かの何かの助けになるように、一生懸命この仕事をして、しっかりと生きていく事が父に対する供養になるのだと、そう信じている。


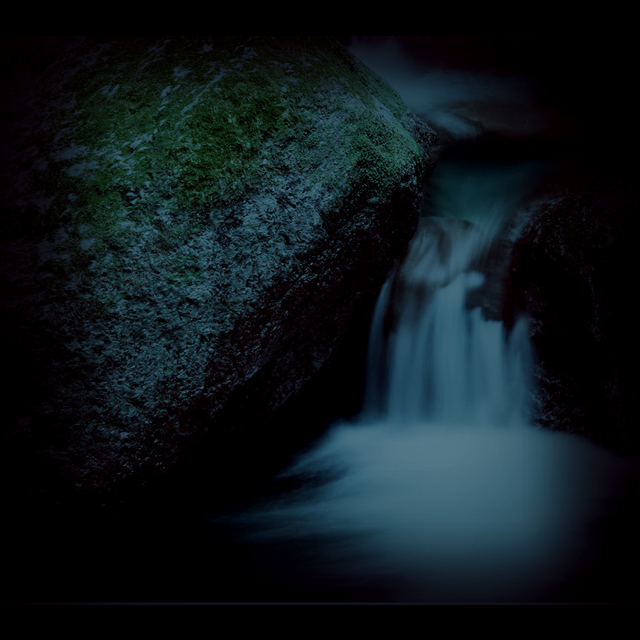
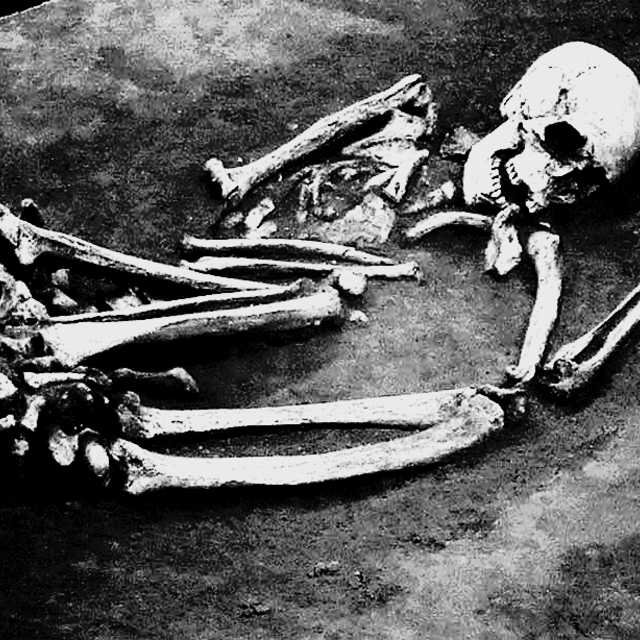


作者タカミヤ