世間が夏休みになって、家族で過ごす時間が増えた。
娘のなつみは泳いでいる魚が好きで、マンションの広場にある池をよく眺めていた。
ただそこには魚はおらず、どちらかというと貯水池のような、底の見えない無機質な水だった。
<何かいる!>と嬉しそうに言うものの、実際に見たことはない。
ともかく私は、巷で流行っているおもちゃを、なつみに渡した。
「なあにこれ」
「これはピンポンって、音を鳴らす道具よ」
「おさかなの形だ!」
「好きでしょ、おさかな。
何か悪いことが起きたら鳴らしてね」
なつみはさっそくボタンを押した。
<ピンポン>
少しだけ緊張させるような音程のアラームが鳴った。
「分かった?」
「悪いことってなに?おなかが痛くなったときに鳴らすの?」
「ううん。ケガをしたときとか、しそうになったとき」
「うーん」
6歳に持たせるにはまだ早かっただろうか。
いや、早いに越したことはない。
私はなつみの手を引いて部屋に戻った。
nextpage
次の日。
「もう1こひろったよ!」
「あら、どこで拾ったの?」
「池の前」
「マンションの前の?」
私はそれを受け取った。
そのアラームは数種類売られていて、それは鳥の形だった。
電源は入っていないようだ。
きっと他の部屋に済む人の物だろう。マンションの落とし物ボックスに入れることにした。
separator
nextpage
2日後、電話が鳴った。
「奥さん、ちょっとお聞きしたいんですがね」
大家からだった。
「あれはどこで拾ったんです?」
「はい?池の前って書きましたが」
「ちがいます、きっと池の中です」
言っていることがイマイチ分からない。
「あの」
「あの池には。あれが、あれは」
ため息のようなものの後に電話は切れた。
少し嫌な予感がしたと同時にそれは鳴った。
<ピンポン>
私は息を呑んだ。
なつみは3つのアラームを持って遊んでいた。
nextpage
夫の帰りを待って相談した。
いつもどおり仕事に疲れているようだが、
真剣に話を聞いてくれた。
「後でなつみを呼ぼうか」
nextpage
なつみは少し眠たそうだった。
「どうしたの?」
「ここにすわって」
「うん」
「あのおもちゃを、また拾ったのかい?」
「拾ってないよ。隣に置いてあったの」
「誰かが持ってきた?」
「ううん。これだけ置いてあるの」
「他に変わったことはないかな?」
「ときどき、なつみを呼ぶ声がする」
夫は天井を見上げ、うなだれた。
私は大家に電話をかけた。
「はい」
「あれは何なの」
「今から行きます。人を紹介するので。
ごめんなさい、あとは何とかしてください、ごめんなさい」
それはこっちのセリフだ。そう言おうとして電話が切れた。
10分ほど経って、インターホンが鳴った。
白いワンピースで黒いセミロングの分かりやすい女性が立っていた。
separator
nextpage
「霊能師をやっています。八乙女と申します」
上から下まで白黒の姿の女だった。雰囲気だけはそれらしい。
彼女をリビングに招き入れ、すぐに本題に入った。
「これが勝手に増えていくんです」
「なんですかこれは?」
「最近流行ってる、護身用の警報装置みたいなものです」
「へえ」
八乙女と名乗る女は、首を斜めにしつつ、まじまじとそのおもちゃを眺めていた。
しかしその行為から出てきた言葉は、期待とは真逆だった。
「どうしようもありませんね」
一番聞きたくないセリフだ。
まさか開始早々、そう言われるとは思っていなかった。
私は一気にその女への信頼を失った。
「霊能者なんでしょ?退治するフリくらいしなさいよ!」
女の口から<ふっ>と笑いがこぼれた。
「じゃあ、簡単に退治できますよって言ったら信用します?」
私は何も言い返せなかった。左からも右からも押しやられる気分だ。
「これに手を出したら殺されます。お金をもらっても無理です」
怒りが沸いてくる。
「どうしろって、言うのよ」
「なつみちゃんの言うことを聞いてあげるのが一番です」
「なつみは、自分を呼んでるって言うのよ?どういうことなの?」
「このままだと、おそらくあの池に呑まれます」
私は恐る恐る聞いた。
「死ぬってこと?」
「死ぬかもしれませんし、死なないかもしれません。
まあ、引き寄せられているのは確かです」
「私たちは占いを聞きにきたわけじゃないの」
「では大金を払えますか?」
「いくらでも払うわよ!」
「人の命にいくら払えますか?」
「はあ?」
分かった。
この人はただ暇つぶしに話がしたくてここに来ただけなんだ。
昔からそういう類の友人がいた。
普段から人にかまってもらえないからって、こういうところに来て茶化して帰っていくだけの人種だ。
「もういい。他を当たるわ」
「いえいえ、また来ますよ。結末が気になるので。
それに今言ったように、私の見た限りこれを手に負える者はいませんから」
私はそこにあった湯呑を投げつけてやりたくなるのをこらえた。
一瞬にしてここまで人を嫌いになるのは珍しかった。
separator
nextpage
そして言われたとおりになった。
別の人を探しても予定が合わないだとか、手に負えないだとか、
むしゃくしゃするような理由ですべて断られた。
あの女が手引きしているのではないか。
どうでもいいことばかり考えて、対策が見つからない。
夫が帰ってきた。どこかに寄ってきたようだ。
「だめだ。やつら、これっぽっちも話を聞かずにバカにしてくる。
自分で笑えてきたよ。実際バカげた話だ」
nextpage
私はその場にじっとしていられず、マンションの外に出た。
コンビニでどうでもいいものを買って戻ってくると、
自然と池の前に足が向いた。
nextpage
夜に見ると、より深い怖さがあった。
底の見えない淀みが、昔海で溺れた経験を思い起こさせる。
これなら何かいてもおかしくない。背筋に緊張が走った。
そもそも、この池は何だ。
何のためにあるのか?
分からない。分からない。
私は一人呻きながら、その場を去った。
separator
nextpage
何もできないまま翌日になり、
昼下がりにまたあの「八乙女」がやってきた。
「調子はどうですか?」
「最悪よ。あなたが来たから」
「入れていただけますか?少しだけ話が」
私はドアを勢いよく閉めた。
しかし彼女はそこで喋り始める。
「昔は井戸だったようです。ただ、井戸として使っていればの話ですが」
一呼吸置いて、続けた。
「病気などで死んだ子どもをあの中に埋葬したようですね」
「は?」
「マンションなんて言葉が存在しない頃の話ですよ。続きを聞きたいなら開けてください」
私はドアを開けた。
「このおもちゃが、そんな昔からあるわけ」
八乙女は<ふっ>と笑った。
「物が重要ではないんです。気ですよ。結局のところ」
separator
nextpage
夫と二人で、女と向かい合った。
「そういうところに、そういうものが集まるということですか?」
夫がおずおずと聞いた。
「そのとおりです。例えば刀ですね。
不気味なものを感じたことはありますよね。
あれは当然。人を斬ったものですから。
怒りと悲しみがすべてではありません。
喜びもありましょう。
斬ることが好きなモノからも興味を引くわけです。
そういうものは総じて禍々しいです」
じっとりした目で、霊能者は夫を見ていた。
私はその妙な空気に怖気づかないようにした。
「どうすればいいんですか?」
「手っ取り早く解決するには、身代わりになればいいんですよ。あなたが」
「私が?」
「だってもう時間がないですもの、呪いを移す方法なら私が」
「何を言うんだ!」
突然立ち上がった夫の顔は強張っていた。
「やけに震えていますね」
「どうしたの」
女の言う通り、確かに夫は、怯えたように膝から震えていた。
視線が合っていない。何か私とは違うものを怖がっているようだった。
「なぜあれが現代に残っているのか考えても意味はありません。
何か事情があるのは世の常です。
もう話すことはないので失礼いたします」
女は布の擦れる音だけを立てて、静かに去っていった。
私は引き止める力を失っていた。
夫はふらふらと寝室に歩いていく。
「ねえ、どうしたの」
目で追っていると、夫は崩れるように床にしゃがみこんだ。
そしてどこを見ているのか分からないまま呟いた。
「なあ、おまえ、忘れたのか」
「何が?」
「まあそうだよな。覚えておけるはずがない」
夫はタンスの引き出しから何かを出した。
それを見て、自分の頭半分がえぐられたようなひどい頭痛がした。
写真だ。
それは私たちと、お腹にいる、なつみではない女の子。
7年前、なつみの姉になるはずの子は、名前が付く前に死んでしまった。
「俺は帰ってくるときに見かけたよ。池の前で、この子が俺を見ていたんだ」
「見ていたって。ばかなこと」
「いやあれは間違いなく俺たちの子だ。間違いなく」
普段は生真面目な夫が怯えていた。その肩に触れて、落ち着かせようとした。
「俺たちなんだ。俺たちが」
いよいよ終わりが近いような気がした。
separator
nextpage
そうして時間だけが過ぎた。
もしかしたらこのまま何も起きない。
またいつものように、日曜の朝にトーストを焼いて、テレビを付けて、3人で見れるような日がきっと。
その可能性は、じわじわと私たちを追い詰めるように消えていく。
なつみは相変わらずいろんな形のアラームをそばに置いて遊んでいる。
その数が10に増えていた。
捨てても、壊しても、必ずなつみの手元にやってくる。
「霊能師、霊能者、除霊、霊媒、おさかなさん、なつみ、なつみなつみなつみ」
夫も壊れかけだった。ひたすらネットで無意味な文字をタイピングしていた。
nextpage
<ピンポン>
どこからか音が鳴り、私も夫もビクリと肩を震わせた。
なつみはふいに立ち上がり、ベランダの方を見た。
「行かなきゃ」
「だめよ!」
私は怒りを込めて、なつみの前に立った。
それと同時に、広場に何かがいる気配がした。
身震いし、目を逸らさないままなつみに言った。
「見つけてって言ってる」
「あんなのダメに決まってる。理由なんかいらない。あなたはここにいて」
夫がふらふらとなつみに歩み寄った。
「なつみ。ママの言うことを聞くんだ」
「でも」
「でもじゃない!」
夫が叫んだ途端、部屋中のアラームが一斉に鳴った。
耳を塞いだ。もはやその音は人間に聞ける類のものではなく、人の絶叫のような異音だった。
「うるさい!うるさい!」
しかし、なつみは何も聞こえていないかのように、ふらっと玄関に向かっていった。
私は目眩がしてまっすぐに歩けず、気がつくと壁に頭をぶつけていた。
視界が暗くなった。
separator
nextpage
揺さぶられて目を覚ました。
目の前になつみの顔があった
「起きたか?」
夫の声もした。私たちは広場にいた。
「ママ」
なつみは私の手を握っている。
そして池の水面から小さな子どもたちが体を出し、にこにこ笑ってなつみを見ていた。
夫はぼーっと座ってそれらを眺めていた。
その子どもが生きた人でないことがすぐに分かった。何人かが時代に合わない服装をしていた。
それがなつみを引いて行こうとしているのだ。
「やめて!」
私はなつみをかばうように、自分の体で覆った。
夫も近づいてきて、振り絞るような声で言った。
「行くんじゃない。ママをこんなに泣かせていいのか」
なつみは哀しそうな目で私を見ている。
この子は、この状況で、何を想うのだろう。何を考えているのだろう。
「どうして行っちゃうの。お願い行かないで、ねえ。なつみ」
「大丈夫だよ。私が行かなきゃ、ママもパパも、みんな死んじゃうんだって」
「それなら一緒に死のうよ?ね?」
「それはだめ」
「いやよ」
「ごめんなさい」
複数の手が、なつみだけを引っ張り始めた。
無表情の子どもたちは私には目もくれないようだった。
「行かないでって言ってるでしょ!」
離すまいと、なつみの体を押さえ込んだ。
「ごめんなさい。こんなふうになってごめんなさい。
なつみが、パパとママの言う事聞かずに、拾ってきたから。
今度はいい子になるから」
死にものぐるいに掴んでいた自分の手の感覚が、痺れたように消えた。
もうだめだった。
寂しそうに笑ったなつみの手が、私たちから離れる。
そのまま<ざぶん>と、池に呑まれた。
私は這うように水面に向かい、覗き込んだ。
分厚いガラスの向こう側に行ってしまったように、決して手の届かない世界を感じた。
音が無くなり、静まり返った池の中は、しばらく黒々と淀み続け、
やがて透き通り、ようやく私のやつれた顔が映ったとき。
泡がたちのぼってきた。
nextpage
戻ってくる。
nextpage
「なつみ!」
なつみが水面から顔を出し、めいっぱいの空気を必死に吸った。
私は地面に引っ張り上げ、抱きしめ、謝りながら泣いた。
「たくさん遊んできたよ。おさかなさんもいたの」
「沢山って」
「でも飽きちゃったのかな。みんないなくなっちゃった」
「そうか、そうか」
夫は私と同じように涙を流した。
みんなで子供のように泣いた。
まるで出産したときのようでおかしかった。
「最初から言う通りにしろと言ったでしょう」
背後に人がいた。あの霊能師だった。
私はなきじゃくるだけで、言葉が出ない。
「これに懲りたら、落ちているものは拾わないでくださいね。といっても、どうせ人は繰り返すのですが」
最初から最後まで達観している態度にはうんざりしたが、
今はそんなことはどうでも良かった。
すぐにここを引っ越そう、そう決意して私たちはその場を後にした。
separator
nextpage
月が消え、夜が闇一色になるのが分かった。
「いつも裏方でいるのは寂しいものです」
そして、人に使うものではない道具で殴られた感覚も分かった。
袖口が血で滲み、手首に伝う。
nextpage
「死んだってお金はもらいますからね。分かってますか?」
「わかった、もうわかったから、早くしてくれ」
大家の男の顔は死んだ梅の実のように青ざめている。
池の周りに、瞳が怒りに燃えた子どもたちが立ち、その全員がこちらを見ていた。
突き刺すような敵意を私に向けていた。当然だ。私が引き剥がしたのだから。
ここからが本当の戦いだ。

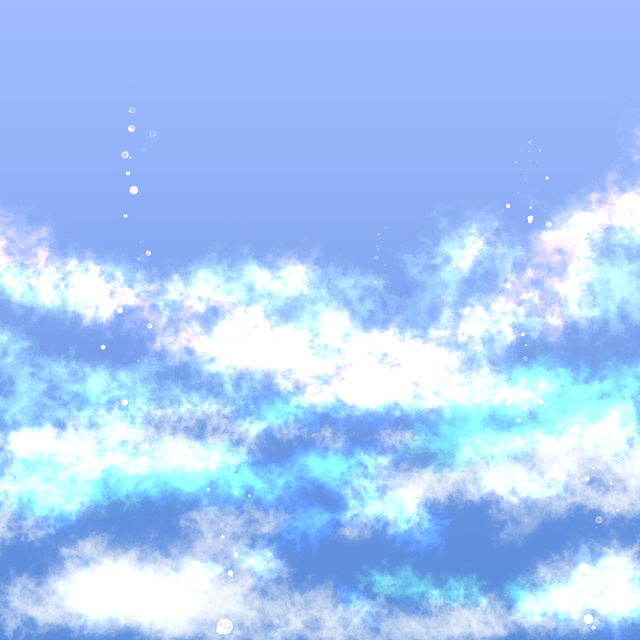
作者ホロクナ
読んでいただけると幸いです。