真夜中のサービスエリアは気持ちが高揚とする。周りに人の姿がなく、ひんやりとした空気、綺麗な夜空、都会の喧騒とした雰囲気とは大きく異なる。
田舎から都会に上京して、真っ先に思った事は、なんて煌びやかな世界なんだろう、だった。しかしそんな気持ちに浸れたのも、ほんの数ヶ月の間だけだった。今はもはや、当時に抱いた特別な感慨など一切湧かない。贅沢な思いもあれば、虚しい思いもある。
僕は特等席であるベンチに腰を下ろし、今宵を満喫する。山を挟んで眺める事が出来る都会のネオンの灯りは、その場に居ればなんて事ない光景に映るが、遠くからだと『夜景』という華やか言葉に変わる。
ひとつ、ふたつ、みっつ、いつも小さな結晶のように夜空を飾る星々を数えてみる。どれだけ数えようが全てを見つける事は決して出来ない事はわかっている、無意味な行為だと知っている。それでもあの星々は、僕から見れば自分を見つけて欲しいと言っているように思う。
「数え星……」
ぽつりと僕は口にした。およそ小さな声ではあるが、そんな言葉が出た。そう、こんな無意味な行いも名前さえ付けてしまえば、それはれっきとした行為になる。僕は、ふふふ、と自分で自分を笑った。
「数え星、ですか」
突如、背後から声がした。僕は驚き、前方へ倒れ込んでしまいそうになる。
「いや失礼、面白い言葉遊びをしているものですから、つい」
僕は飄々と現れた男性に視線を配る。
グレーの背広に水玉模様が描かれている茶色いネクタイを締めた紳士的な印象の男性、見た所、年齢は五十代ほどか。
「びっくりしましたよ。なんせこんな時間、そうそう人が居ないのですから」
「私も驚きましたよ。まさかこんな深い時間に人が居られるとは。夜を眺めるのがお好きなようで」
「ええ、まぁ……」
「それでもこんな暗い場所、ひとりでは怖くないのですか?」
ひとり__。その単語に僕は何故かぴくりと反応を示す。けれど後半の部分を答える。
「怖い? いったい僕は何に怖がる必要があるのでしょう?」
そう言うと男性はおっとりと笑う。
「おやおや、それは逞しい。普通ならば、街灯が殆どなく誰も居ない場所、アナタのような若者は視えない存在に怯えそうなものですが」
文字だけで読み取れば、どこか見下しているように思うが、この男性の声のトーン、喋る速度からして、決して嫌味な言葉遣いには感じなかった。
「はは、確かにそうかもしれませんね。でもですよ? 誰も居ないという言葉は僕には少し違います」
「ほう」
男性は白い顎髭を親指と人差し指に乗せて考察を行う。僕は、どういう意味か考えて下さい、と言わんばかりに男性の考えを待った。
暫くして男性は答えた。
「わかりました。つまりこういう事ですな。アナタには本来視える筈がない存在が視えてしまう」
「正解です」
「それはそれは、珍しい眼を持っていますな。しかし、そうなると余計に恐怖心を抱くのでは? アナタからすれば、ここに人ではない何者かがずっと彷徨っている筈です。それなのに、一切動じない」
「ええ、僕は視える眼を持っています。幼い頃から……逆に言えば視えない人達の方が僕にとって不思議なぐらいです。慣れ、という言葉がしっくりくるかもしれませんが、実際の所、視えない者からの危害などありません」
「なるほど、アナタは……あ、いえ、アナタと言い続けるのも、そろそろ気が引ける、お名前を頂戴いただけませんか? 私は三影と申します」
「白石と申します」
三影はにっこりと微笑み僕に握手を求める。僕がそれに答え、握手を交わす。
「隣り、よろしいかな?」
「はい」
僕はベンチの隅に移動してスペースを作る。三影はそこに腰掛ける。
「白石さんは今まで視た者の中で恐怖を感じた経験はないのですか?」
「ありません。というよりあちら側の者達は僕らには触れる事さえ出来ません」
「ほう……しかし姿は、はっきりと視えるのでしょう?」
「ええ。しかし皆が想像している姿ではありませんよ。むしろ普通、至って普通の人間と変わりません」
三影に視えていない存在を僕は指で示していく。
「あの者、それにあの者も、あと、三影さんの真後ろに居るその者も、我々と見た目に違いがありません」
真後ろ、と言う言葉に動揺したのか、三影は咄嗟に振り返る。そして胸を撫で下ろす。
「はぁ、まったく老人を驚かせないで頂きたい。その仕草はまるで私の後ろに悪霊が潜んでいるように感じましたよ」
「悪霊など存在しませんよ、三影さん。よくある怪談話とか、恐怖映像、それに霊媒師などはでたらめです。そもそも誇張しすぎなのです。ありもしない事を。それではあちら側の人達が報われません」
すると、三影は不思議な面持ち、故に好奇心ともとれる表情で僕に問いかける。
「となると、白石さんの理論では、この世に怪異現象などないと?」
「ええ。先程も言った通り、あちら側の者達は僕らに触れる事が出来ません」
「なるほど、では物はどうでしょうか? 直接的ではなく、間接的にこちら側に干渉出来るのではないでしょうか?」
「……まぁ、そうですね。出来るかもしれません。現にポルターガイスト現象など、事例がありますし、一概にないとは言えませんね……それでもですよ三影さん、よく考えて下さい。あちら側の者が我々に危害を及ぼしたとしましょう。それに何のメリットが? あちら側の者はこちら側の者に発言する事さえ出来ません。それをいい事に、年々とありもしない逸話が世に広まってます。それはあまりにも不甲斐ないと思いませんか?」
遠い街灯を見ながら気付けば声が荒がってる。僕はいったい何に怒りを? 何に不満を抱いているのだろうか。ふと、そんな感情が過ったが、すぐに通り過ぎた。湧き上がり続ける別の感情がそれを超えてこない。
「白石さん、一度落ち着いて下さい。お身体に障ります」
「……はい、失礼しました……僕は視えてしまう者、それ故、好き勝手にあちら側の者の話を捏造される事をとても悲しく思います。何も知らないくせに……って感じます。でも、そんな事、周りには言えない。そもそも視える事自体、信じてもらえないような気がして」
「それでひとりに?」
三影の問いかけに僕の心臓の鼓動がぽつんと鳴った。再び、説明出来ない歯痒い感情が湧いた。
「はい。ひとりになったきっかけをあちら側の者のせいにしたくありませんが、実質的にそうなってしまいますよね……僕は人が嫌いです……言葉というものは人が人に向けて放つもの、時に、それは鋭い刃となって人の心を傷つけてしまいます」
「確かにそうかもしれませんが、そんな人ばかりではない事も事実です。白石さんはあちら側の者に悪霊もいなければ善霊もいないと考えていると思いますが、それは人も同じ事、極端に良い人もいなければ極端に悪い人もそう巡り会えません。そして、人という生き物は良い人の仮面を被っている者が大半です。なので善悪の判断が難しいと言えますね。あちら側の者はそういった判断を出来ますか?」
「先程も言った通り、あちら側の者の言葉はこちら側には聞こえません。なのでわからない……が答えです」
三影が徐に立ち上がり、夜空の星々を仰ぐ。
「もしかしたらですよ。白石さんが聞こえないだけで、あちら側の者達は何かを伝えようとしているのではないでしょうか。もしかすると白石さんのように姿が視える者を必要としているのでは? そう考えた事はありますか?」
「いえ、それは考えた事すらなかったです……確かに僕はあの者達を凝視した事すらありません。人も同じです。ちゃんと目を見て言葉を交わす事が苦手なのです」
「なら、一度試してみてはいかがでしょうか? 白石さんにしかわからない事、あちら側の心意が受けられるかもしれません」
三影は真剣な面持ち、それでいて円かな口調でそう言う。しかし、僕は躊躇っていた。
「僕はひとりが好きです。なので今まで人との関わりを避けてきました。多分これからも……でも、ずっとひとり、というのも心が苦しいです。未来の事、およそどうなるかは検討もつきませんが、今はひとりで居る事を苦に感じません」
今、純粋に思った事を言葉にしてみた。けれど自分で言っていて、自分でも何を言いたいのかわからない。心が乱れている。
ひとり__。その言葉が強く乗しかかって離れない。重い……とてつもなく重い感情、核のように感じる。三影はどう思うだろうか、どこか、今の僕の言動を明確な言葉で表して欲しい。そう願いつつ三影に視線を配る。
しかし、僕の願いとは裏腹な面持ちだった。複雑な表情で僕を見る。
「白石さん……自分に正直でいいんです。何も複雑に考える必要はありません。残念ながら人は嘘をつく生き物です。それは他人に対しても、そして自分に対してもです。善意ある嘘、悪意ある嘘、他人に対してはそれらが当て嵌まります。しかし、しかしですよ。一番心を苦しめるのは自分に対する嘘なのです。人の心を動かすのは難しいです。自分の心もそうです。とても難しい。見栄や嫉妬、そういった感情は人間関係を行う際に、避けて通れない道なのです。それは白石さんもよくご存知の筈です」
三影の瞳孔が真っ直ぐ僕を捉える。そして朗らかに囁く。
「焦らなくても大丈夫です。きっと白石さんは正しい方を選ぶと思いますので」
僕は三影の異様な程の説得力に首を傾げた。
「三影さん、アナタはいったい、どちら側の者なのでしょうか?」
すると、三影は小さくかぶりを振る。
「白石さん、それは自身に問いかけてあげて下さい」
「え?」と僕が言葉を返すと三影はすっと立ち上がる。自然と三影の背後にいる者と目が合う。
ゆっくりと……恐らく僕にわかる程の速度でとてもゆっくりと口元が蠢いているように視える。
「ヤット、キヅイタネ……」
そう口ずさんでいた……。
ああ……そうか、そういえばそうだった。もう何十年前の事だろうか、僕は自身が既に死んでいる事さえも忘れていたのだ。この者達は死者だと思っていたが、僕を招いている別者なのかもしれない。ずっとそう言っていたのだろうか、僕にとってそれは最善の道なのか、無機質な表情で何度も同じ事を口ずさんでいる。不思議と恐怖心はない。でも、やはりこの者からは優しさも悪さも感じられない。僕はくるりと三影に向き直る。
「なるほど、三影さんはずっと気付いていたのですね」
「白石さんは先程、死者に対して大きな反応を示し、不甲斐ない、とまで言っていました。それはどこか自身を哀れんでいるように映りました。まるで、自身を肯定して欲しい、と嘆いているように……」
「そうですか……僕は長い間、自分を見失っていたようですね」
三影は僕の苦笑いに、優しく微笑みかけ「そのようですね」と言う。
決して悪い気分ではない。今宵も僕が望んでいた最高の景色を堪能出来た。三影は本当の僕を見つけだしてくれた。
段々と身体が形を保てなくなってゆく、最期、天を仰ぎ、三影に問いかける。
「三影さん、僕はいったいどの星になるのでしょうね」
「さぁ、でも、今宵の星々のように色鮮やかな者になると思いますよ」
「その時は、僕を数えてくれますか?」
「数え星ですね。ええ、約束します」
「ありがとう……」



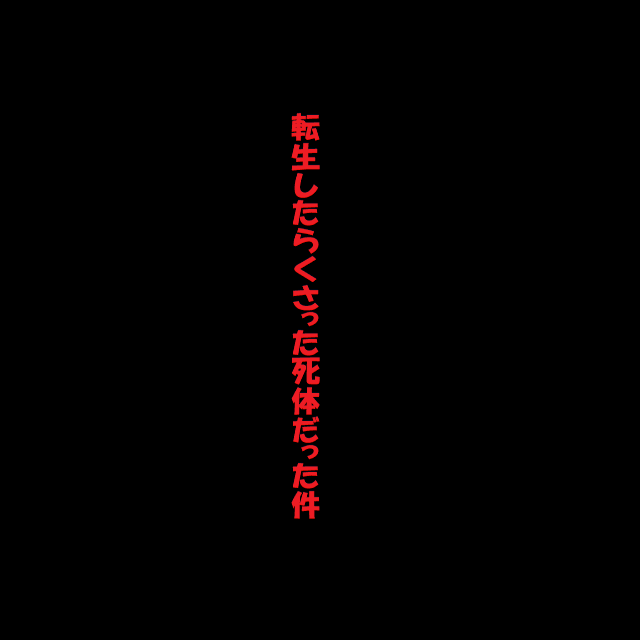
作者ゲル