温泉に浸かりながら、新入りに聞かせてやることにした。
「今となっては古い思い出だが、おまえも村になじんだようだから話しておく」
この話は東海地方の山奥にある、自分の旅館の玄関から追い出されたところから始まる。
separator
nextpage
「よくもこんなことができたな」
「社会にいいことをしたんだろ。
俺の仕事を用意してくれたんだよ。おつかれさん」
「帰る場所なんかない」
「このへんで吊るのはやめてくれよな」
起業仲間がピエロのように笑いながら、交通費か手切れ金のつもりか万札を数枚、俺の頭に落とした。
nextpage
脱サラをして夢を掴んだはずの俺は、いつのまにか利権を騙し取られていた。
契約に詳しい者への代行をケチってしまったために、微細かつ重要な項目を見落としていたのだ。
nextpage
社会にいいことをした。
そう考えることでしか自分を慰められないことに絶望した。
あらゆることに背を向けてここまで来た俺に、頼れる味方は一人もいなかった。
nextpage
適当に近くの林道に入り、藪の中で乱暴に停車した。
ガソリンが半分以上残っていた。
起業するまでに何回満タンにして走り回っただろう。
原油価格高騰にどれだけ苛まれたことだろう。
<もうそんな必要も無い>とエンジンを切る。
nextpage
なんとなく、歩いているうちに疲れて死ぬだろうと考えた。
それまで試そうとしたことも無いので、正しい死に方が分からなかった。
森の奥を闇雲に歩くこと数分、前方に開けた場所が見えた。
屋根瓦もあるのでどこかの村だと直感した。
そして人がいた。二人が向き合い、何かを見下げている。
変に絡まれるのも面倒だったので、引き返そうとした。
nextpage
そのとき二人が同時に俺を見た。
そしてまっすぐこちらに歩いてくるのだ。
体がぎょっとしてしまい、動けない。
「待ってくれ、俺は別に怪しくは」
否、俺のほうがどう見ても怪しい。
手を前にしてぶんぶんと振ることしかできなかった。
nextpage
一人はマスクとサングラスの若そうな男。
もう一人は頭巾を被った小汚いじいさんだった。
そのじいさんが、皺に隠れてほとんど見えない瞳で俺を睨む。
「なんやあ、おまえ」
「通りすがりです」
「こんなとこ通りすがる奴がいるもんかい」
「自殺しようとしていました」
そこで空気が黙ってしまった。
サングラス男がフンッと息を漏らす。
nextpage
「こいつ、どうすんの」
「トミオさんに聞く」
サングラス男が後ろの車に気づき、歩を進める。
俺はじいさんに向いた。
「すみません。俺は本当に何でもないんで」
そのとき、後頭部を大砲の玉で抉られたかのような衝撃を受けた。
nextpage
俺は自分のうめき声で何事かと目を覚ました。
「立てるか?」
視界に天井とじいさんの顔があった。
俺は古びた部屋に寝そべっていた。
「ひどい二日酔いの気分です」
「すまんが、おまえさんは俺等の領地を踏んじまったんだ。
で、どこの領地にも入った途端に規則ちゅうもんが充てられる。
おまえさんの場合、この村への侵入は良くない。本当に良くない」
ここから先はぶつぶつと何を言っているのか分からなかった。
「そのへんのブラック会社よりもブラックですよ」
じいさんは俺の言葉を無視して部屋の扉を開けた。
「はようしろ、ジサツオトコ」と顎を動かす。
nextpage
「こんばんは」
外に出ると、また初対面の中年男が立っていた。
その他、視界にやたらと畑が映る。
田んぼは一つも無い。
10人に満たない者たちが、何らかの野菜を収穫しているようだった。
nextpage
中年男は、こめかみから顎までびっしりと固そうな髭をたくわえているが、どこか清潔感があった。
都会の人間だろうか。
「こんばんは」
俺はこの期に及んで無惨に殺されるのが怖かったので、丁寧に接した。
「別に殺したりはしないよ」
「あ、いや」
「顔にそう書いてある」
「すみません。死にたくてふらふら歩いていたのは事実ですが」
「張り付けにされて燃やされたりとか、生贄にされるのは嫌かい?」
「正直、きついです」
男は失笑した。
「僕はトミオさんと呼ばれている。
どこの村にも、外界に対する不安があるから君をすぐには帰せない。
それは分かってくれ。
安全な人間と分かれば帰せる」
不安だからすぐに帰すものだと思ったが、逆の考えもあるようだ。
「どのみち車で寝るので大丈夫です」
「良かった。
明日から村の仕事を手伝ってもらうよ。
ごはんなら、外におにぎりの配給があるから、
自由に食べていい」
nextpage
トミオさんはどこかへ歩いていき、
先程のばあさんが代わりに俺を誘導した。
村は小屋からすべて見渡せるくらいの広さしかないようだ。
ただ背の高い森に囲まれているので、隣に別の村があっても分からないだろう。
ばあさんはあるところで立ち止まった。
「好きなだけ持っていけ」
木の長机に、おにぎりが無造作に積まれていた。
俺は3個を手に取った。
「全部同じ味ですか?」
「小松菜、平茸、わらび、あとは知らん」
ばあさんは去った。
nextpage
車に戻り、冷えたおにぎりをかじる。
特に逃げ出そうとは思わなかったが、
あたりが妙に臭ったのでエンジンをかけてみると、
ガソリンがすべて抜かれていた。
nextpage
食べたことの無いラインナップだが、
おにぎりはおいしかった。
そして今の自分を小さく笑った。
nextpage
充電がほどなく切れるスマホの待ち受けを眺め、
来るはずの無い連絡がふいに来る瞬間を目に浮かべていた。
別れた恋人。
元同僚。
同窓会のときに、一言話しただけの同級生。
その誰でもいいからスマホを鳴らしてほしい。
そして少しでいいからこんな自分を慰めてほしかった。
おもいきりの無い涙が出た。
おにぎりは全部、平茸だった。
nextpage
翌朝。
「ジサツオトコ!もっと腰入れんかい」
「すみません」
俺は朝から叱咤されていた。
悲しいあだ名を付けられ、畑の収穫を手伝っている。
野菜畑だが、見る限りすべてが大根だった。
それをひたすら「もぎとる」作業をしている。
もぎとるというのは、何の知識の無い自分でも違和感を持つわけだが、
大根は一本で独立しておらず、地中で水道管のような形で繋がっているのだ。
俺が小さい頃に学んだ知識では絶対にこんな生え方ではない。
これをばあさんに聞いても<はあ?>と聞き返され、ついでに馬鹿扱いされた。
ちぎれる瞬間に「ブチブチッ」と気持ち良い音が鳴る。
nextpage
「この大根はどこで食べられるんですか?」
「食べられんよ、街には卸してない」
「え?じゃあ村の食料ですか?」
「食料ちゅうより、命そのものだ」
「へえ」
「しっかし今日も暑いわなあ」
「ええ」
「後でラムネ飲むか?」
「え?」
「トミオさんが時々持ってきてくれるんだわ」
ここの人たちは皆、人を殴って気絶させることを除いては、妖怪や精霊でもない普通の人だった。
例えばトイレは山の墓地にあるような汲取式のものがあって、
そうした人間らしい物を発見すると<彼らは人間だ>と僅かながら安心感を抱く。
nextpage
「トミオさんってどういう人なんですか?」
怪しくないですか?と聞こうとして考え直した。
「トミオさんが一人でこの村を蘇らせたんだ。
神様みたいな存在だ。
暮らし方を知らんわしらが、
こうして何代も生きてこれたんだから」
昼に差し掛かった頃、森の中から誰かが現れるのが見えた。
nextpage
「あああああ、オト様じゃ」
「あああ」
「ああああ…」
「ああああああ!」
nextpage
皆が一様に変な声を出して不安になったので俺も真似をしてみると、ばあさんに頭を殴られた。
「わめくなボケ!」
「すみません」
「よそもんがオト様を称えるんじゃないよ」
nextpage
どうやらそのオト、と呼ばれている女性は相当に偉い人らしい。
表情は分からないが、白く滑るように綺麗な顔と細い腕が見える。
なびく長髪は肌より更に白かった。
サングラス男の後を極端にゆっくりと歩き、麻布が肩から地面を引きずるほどまで体を覆っている。
その隠された部分もきっと美しいに違いないと確信した。
そしてまったくもってこの村の景色にそぐわない。
nextpage
「おまえよお」
後ろからこれまた初対面のじいさんに声をかけられた。
今のところ、トミオさんとサングラス男以外は皆同じ見た目で区別が付かない。
「見るのはいいが、オト様とは絶対に会話をするな。
したらその場で殺すぞ」
あまりにストレートに言われ、俺は咄嗟に頷いた。
「まあ会話する機会なんて無いがな」
オトは皆に奇声で崇められながら、森のどこかに消えていった。
やっぱり普通じゃない。俺は考えを改めた。
nextpage
夜の帰り道、通りがかった畑で妙な行為を目にした。
誰かが地面に向かって鎌を振り下ろしている。
「これでええ。これでええぞ」
俺には何が何だか分からないので尋ねた。
nextpage
「何がいいんですか?」
「傷を付けりゃあ、ええ汁を出す。うまあくなるんだ」
じいさんはそう言って嬉しそうに皺を延ばす。
野菜へのまじないだろうか。
未だかつて聞いたことがないが、俺は取り敢えず納得した。
nextpage
眠りに付いている真夜中に至ったとき、村の方から音が聞こえた。
何となく覗きに行くと、地面を刺しているシルエットが見えた。
「まだやっているのか」
そこで何かが恐ろしくなった。
nextpage
翌朝、畑に行くと、
そこはまるで雨が降ったかのように湿っていた。
そして蜂蜜とはまた違った、きつく甘い香りが全身を包み込んだ。
「ジサツオトコ!」
ばあさんがやってきて、いつもの作業に入った。
「何が起きたんですか」
「おいしそうなニオイだろ」
「はい」
ばあさんは昨日より嬉しそうだった。俺も作業を始める。
もぎとった大根は見るからに瑞々しくなっていた。
食べてくれと言わんばかりの存在感だ。
「今食べたらおまえは帰れんなるぞ」
俺の考えが顔に出ていたのか、ばあさんがぼそっと言う。
「なぜです?もしかして覚醒剤が混じってるとか?」
冗談ぽく言うと、ばあさんはしげしげと笑った。
「そんな易しいもんじゃあない」
「やさしい?」
それ以上の返事は無く、代わりにこう言われた。
「じきに分かる」
nextpage
夜になり、手伝いが終わっておにぎりをもらった。
「臭いから風呂に入ってこい。
親切心じゃない。臭くて迷惑だからだ」
居合わせた初対面のじいさんに森の方を指差された。
みんな似たような姿形のじいさんばあさんなので、
もう何度も会っている人かもしれないが。
「ありがとうございます」
おそらく着替えなのであろう、折りたたまれた衣類を受け取った。
nextpage
そこには木に挟まれた露天の温泉があった。
服を脱ぎながらふいに、
<ここに旅館を建てられないか>と考えをよぎらせ、振り払う。
もう終わったことを蒸し返してもしょうがない。
それはさておき、その場に自分しかいないのが不思議だ。
他の住民は家に風呂があるのだろうか。
足を浸け、温度を確かめながら肩まで体を落とした。
都会と異なる、満点の星空を眺めながら俺は確実に癒やされていた。
そういえば自分の旅館でさえ一度も温泉に入っていなかった。
なんとなくだが、こちらの湯の方が居心地が良さそうな気がした。
nextpage
まどろんでいると、森の深い方から声がした。
誰かが向かってくる。とうとう俺を殺しに来たのだろうか。
頭をかがめて、できる限り隠れようとした。
nextpage
「相変わらず電波が悪くて」
どうやらただ通り過ぎるだけのようだ。
その人物はサングラス男だった。
俺に気づかず、通話で何者かと話している。
nextpage
「ある程度の世代まで持つよう改良してあります。
連作のリスクもありません。
芽は定期的に切り落としてください。
削りすぎると芽が出るのも早くなるのでご注意を。
食事は初めの45日までは1食、
それからは3日間隔で、
300日を過ぎたら水だけで。
くれぐれも根切りを怠らないでください。
吸い付くされます」
nextpage
細胞がきゅっと締められた感覚の後、耳鳴りを起こした。
一体何の話をしている。
発せられている言葉のすべてが理解できるようで、できなかった。
男が遠のき、その後は聞き取れなかった。
nextpage
「ジサツオトコ!」
俺は肩を震わせ、声の方を向いた。
例の、初対面かどうか分からないばあさんが鎌を持って仁王立ちしていた。
月夜に背中から照らされたその姿は、安いホラー映画か宇宙映画を思わせた。
「なんですか」
「さっさと上がって、ついて来いや」
ばあさんはタオルを俺の顔に投げつけた。
nextpage
道中、畑が気になって仕方なかったが、
連れてこられた家の開いた窓から漂う何とも表現し難い、濃厚な香りが鼻をくすぐる。
入ると、誰かが囲炉裏の、一番身分の低い位置に座っていた。
「いらっしゃい。ばあちゃんも良かったら」
トミオさんだった。
彼は鍋からほのかに湯気を出す吸い物らしきものを混ぜていた。
nextpage
足元が暖かくなったところで、トミオさんが徐ろに口を開く。
「真実について、あまり踏み込んじゃいけないよ」
「真実って?」
「大根だよ」
「真実以前に、最初から何も分かっていません」
「味噌汁は好きかい?」
「あの」
<食べてごらん>と、汲まれたものを俺は手に取り、凝視した。
大根が入っている。
ばあさんにちらりと目をやったが、じっとしていた。
顔全体が梅干しみたいに皺だらけでどこを見ているのかも分からない。
「大根は食べるなと言われてますが…」
「いいから」
一口、すすったところで俺の理性はどこかへ消えた。
全身が痺れるような辛さから、それを解きほぐす甘みに蹂躙された。
それは食べ物とは言い難い、もっと超越的なものだった。
一気に飲み尽くし、息が荒くなる。
「どうだい」
「朝が来た気分です」
そんな意味の分からない感想を述べると、トミオさんは微笑んだ。
「自殺を辞めさせる人の心理は、それがどれほどみっともないことかと自身が後悔した部分にある。
つまり苦難をとうに乗り越えた人間がものを言ってくるわけだ。
そんな人間に諭されるほど単純な状態には既にない。
だからせいぜい、僕はお願いをする。死なないでくれと。
生きてくれとは言わない。生き方が分からない者が死ぬんだから」
「なんでそんな話を」
「君は死にたがっていなかったかい?」
「あれ」
そういえば俺の感情はどこへ行ったのだろうか。
冷静に考えてみると、具体的な終わり方など考えずに助けを求めていたのだろう。
それがたまたまこの村に見つかり、命を繋いでいる。
「ふがいないですが、今は特に考えていません」
「今そう考えているならそれでいい。
ちなみに僕の両親は二人共、大学を卒業したあたりの僕を見て自殺したよ。
育て方を間違えた、と」
「何をしたんですか」
「それは言えない」
「もう一杯いただいてもいいですか」
「それもだめだ」
<なぜだ>俺は怒鳴った。
すると全く存在感を出していなかったおばあさんが立ち上がり、
暴れようとする俺の頭を木柄で小突いた。
顎を揺らしただけなのだが、急に吐き気を最寄して床に突っ伏した。
「やっぱり初めてはきついようだ」
頭上でトミオさんがそんなことを言っていた。
「ちなみに君の仲間が経営している旅館だが。
もうすぐ事故を起こしてとんでもない賠償責任を負わされるよ。
後で一緒に大笑いしよう」
俺は耳を疑った。
「なんで知ってるんですか」
「人間には分かりっこないさ。
すべては大地の下で起きている」
nextpage
車のエンジン音で目を覚まし、俺はふらふらと外に出た。
俺は例によって再び小屋で寝かされていた。
しかし、なぜ自分は突然激昂したのか。
nextpage
軽トラックの運転席からサングラス男が出てきた。
そしてじいさんと話し始める。以前も見た光景だ。
足元には俺も手伝ったであろう、大量の大根が積み上げられていた。
周囲の畑はすべて掘り返されている。
俺は近くに立つ人に尋ねた。
nextpage
「大根は外には出さないんじゃ?」
「残骸だ。あんなものは大根とは言わん」
「どういうことですか。どう見ても大根ですが」
すると<ああ>と視線を流す。
「あれが普段あんたらの食ってたやつだよ。
俺等からすりゃあ、年を食って出てくる老廃物だな」
nextpage
俺は何気なく、掘り返された畑の穴に目をやった。
何かいる。
<ところで>と、彼が真顔で俺を見た。
nextpage
「トミオさんから聞いてるが、大根を食いたいのか?」
「え」
俺は目線を土に戻した。
鼓動が早くなり、大きく頷く。
nextpage
「それでええ」
視線の先で、白い足が蠢いたようだった。

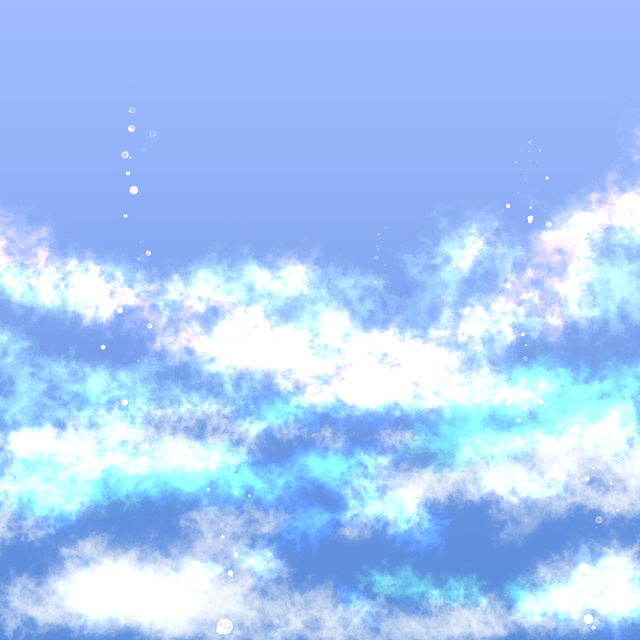
作者ホロクナ