真一さん含むその家族に起こった話。
「あれからパタリと見なくなったので、生きてるうちに誰かに話しておこうかなと」
separator
「またか」
真一さんは瓶から取り出した薬を含み、ミネラルウォーターで押し流した。今朝の特別ひどい暑さのせいか、仕事中まで動悸が起こるようになった。
「これじゃあ来週も病院を予約しないと」
買ったばかりのスマホを開くが、指の反応が悪い。
「くそ、返品しとけば良かった」
「仕事中に触るなよ」
上司に注意され、真一さんは黙ってポケットにしまう。
「事情も分かってないくせに」
入社3年目。大学卒業後に新しい生活を迎えるはずだったが、何年経とうと実家暮らしだった。真一さんは生まれつき心臓が弱く、数種類の薬を飲み、定期的にかかりつけの医者から診察を受けている。
いつまで経っても完治の目処は立たず、時折こうして動悸を起こすのが理由で、一人暮らしは母に猛反対されてしまったのだ。
「何かあるとダメだから」
まだフレッシュマンだった頃、愚痴るたびにそう言われるので諦めることにした。追及してはいけない問題なのだろう。
「ただいま」
「おかえり」
帰宅してご飯やら風呂やらを済ませるだけで、大した会話も無く終わる。真一さんの父親は、ちょうど物心が付いた頃に出張先の交通事故で亡くなっている。そのためか、テレビで見るような明るい家庭の空気が生まれないことに対して、心から幸せを感じられなくなっていた。
nextpage
土曜日。部屋で本を読んでいた。
「いて!」
心臓が揺れるように高鳴った。それと同時にインターホンが鳴る。
「誰だよ。タイミング悪いなあ」
モニタに向かうと、映っていたのは黒いキャスケットにロングコート姿の女性の上半身だった。
馬鹿みたいに季節外れな服装だった。俯いていて表情は見えないが、知り合いじゃないことは一目で分かる。居留守しようとしたが、また鳴らしてきたので通話ボタンを押す。
「はい?」わざと不機嫌な声を出した。
「…」
相手は俯いたまま考えている。
「かえしたい」
かすれた小さな声だった。
「何ですか?」
「…」
「ちょっと」
「かえしてあげるからね」
いったいどうしたんだこの人は。
真一さんは唖然とした。そして「かえす」がどちらの漢字で使っているのか分からず困惑し、ともかく返品の方だと踏んだ。
「何を返すんですか?」
「…」
「答えてくださいよ」
「あなたのものよ」
「うわ!」
女が顔を上げた。驚いたのは、それが満面の笑みだったからだ。
しかもそのまま微動だにしない。これでは通りすがりの変人と断定するしかなかった。
「もういい。帰ってくださいよ」
「…」
「必ずかえすから」
女は縫い付けた糸のような細い目で笑っている。埒が明かないと踏んだので通話を切り放っておくと、満足したのか去っていった。
「返事は遅いけど物分りはいいな」
nextpage
しかし、次の日曜日もその女は現れた。
今度は最初から笑顔を見せて。ちょうど母が出かけたタイミングでやってくる。真一さんは大きく息を吐き、強気に出た。
「またおまえか」
「…」
「で、また考えるのか」
「かえしたい」
「だから何を?」
そして間。
「これはあなたのもの」
仮面のように固定された表情で、この調子だ。
怒りを抑えて今度は息を吸った。
「俺は一休さんが嫌いなんだ。いや一休さんそのものは好きだ。けどトンチンカンチンなことは嫌いなんだ。あと返事はさっさとしろ。おまえから来たくせに何を考え込んでる?」
そこまで一気に言って様子を見る。
「痛くない?」
真一さんは声を荒げた。
「気味が悪いなまったく!いい加減にしないと警察を呼ぶぞ」
「…」
この、必ず入ってくる間は何なのか。
「また来よう」
真一さんの怒りは収まらない。いっそ外に出て問い詰めてやろうか。いや、狂人だったら振り向きざまに刺されるかもしれない。
切るボタンを連打してベッドに向かい、寝転がって悪態を付く。
せっかく落ち着いていたのに、どいつもこいつも心臓に悪い。ただでさえ腐った人生を、これ以上邪魔されてなるものか。
nextpage
月曜日の夜。帰宅すると母は風呂に入っていた。寝室に鞄を置いたところでインターホンが鳴った。嫌な予感がしたので無視していると、いったんは静まり返ったその矢先。
<こん、こん>
「なんだよ。嘘だろ」
老人のように力無い音で、ドアをノックしてきた。
<こん、こん>
「…」
<こん、こん>
あの女だ。一定の間隔と早さ。まるで時計のような無機質な所作にひたすら嫌悪感が増した。
この存在は自分にとって非常に良くない。
「うるせえ!」
真一さんは廊下に出て、ドアに鞄を投げつけた。参考書だらけの鞄はけたたましい音を出し、静かになった。
「俺にどうしろと言うんだよ」
母が慌てて出てきた。
「どうしたの!」
「なんでもない。イライラしただけ」
「そう」
母はそれ以上の言葉を発しなかった。
nextpage
翌日。二人で朝食を済ませたところで、真一さんはふと口にしてみた。
「俺って、なんで病気になったんだ?」
「それはあんたの心臓が元々…」
「遺伝ってこと?他に心臓病になった身内は聞いたことないけど」
少しの間、無言が続く。
「おかず、片付けるから」
元々、真一さんの口数は少ない。食べている間もスマホばかりを見るせいだが、このときだけはそんな気分になれなかった。
じっとしていると、母が座り直した。いよいよ自身の眼差しにも真剣さと言うのか、そんなまともらしい感情が伝わったようで、諦めたように口を割る。
「父さんがそうだったのよ」
初耳だった。
「ずっと薬飲んでたから、これって遺伝しちゃうのかなあって。案の定あんたを生んだ後にお医者さんに言われた」
「そういうことか」
「それで、小さい頃に命に関わるほどの発作が起きた。ほんとは助からなかったんだけど、奇跡的にドナーが見つかってね」
「ドナーだって?」
「隠しててごめんね。あんたが忘れたのをいいことに」
「じゃあ俺の心臓って」
「他所様からいただいた大事なもの」
母は徐ろに立ち上がって皿を食洗機に移す。
「大事にするんだよ。何があろうとあんたが一番だから…母さんと父さんにとってはあんただけが…」
そう独り言のように言いながら、パートに行く準備を終えて玄関に立つ。話がそれで終わろうとしている。
何かが腑に落ちなかった。肝心な何かが。真一さんは頭の整理が付かず混乱し、ただ視界を動く背中を追っていた。
ガラスのドアへと伸びる廊下に黒い影がゆらめく。
「絶対に…」
母はノブに手をかけて言った。
「絶対に生かしてもらえるよう手を尽くした。後悔はしてない。だから言われたの。そんな業を背負ってしまえばどこかで報いを受けるって。嗚呼。父さんはどうして先に死んでしまったんだろうね。あんたに迫る影を追い払おうとして。しつこいしつこい影を。だから母さんも必死で…」
<開けちゃダメだ>そう言おうとしたが、喉が詰まった。
開いたドアの向こうに女が立っていた。
「う」
真一さんは拳を握りしめた。しかしどういうわけか、母は女の横を素通りして行ってしまう。廊下に差した陽光を影が悪戯に遮り、真一さんを呑み込む。
代わりに入ってきてしまった。
nextpage
一瞬にして生ゴミの塊のような異臭が立ち込めていた。もう画面越しではない。異様な笑みを浮かべてそこに立っている。笑っていても生きた様子が無く、肌がひび割れた土のようにがさついており、そしてなぜかコートの中に頭陀袋のようなものをぶら下げている。
女が歩むと袋のあちこちから砂埃が落ち、フローリングを跳ねた。引きつりながら笑う目は自分の視線と全く合っていない。
そこで玄関のドアが完全に閉まった。やけに大きく響いたその音は何かの終わりを告げたようによそよそしかった。
「やめてくれ」
声を絞り出し、張り付いた足を上げて後ろにやる。体が石のように重い。
女は笑顔で言う。「やめてくれって…」
すると違う所から声がした。「…やめない」
「今日はやめないからね」
女は袋を両手で繰り返し撫で下ろしている。まるでそこに赤ん坊でもいるかのように、優しく。
なんてことだ。ここにきてようやく、真一さんは目の前で起きている根底の恐ろしさの正体を知った。女は今まで自分との会話で間を置いていたのではない。頭陀袋に入った「小さな何か」と会話していたのだ。
「許してくれ。俺のせいじゃない」
「俺のせいじゃないって……ゆるさない」
「なんでこんな目に遭うんだよ」
「なんでこんな目に遭うのって……引きずり出してやる」
腰が抜けてしまった。真一さんは言葉にならないことを叫ぶ。鞄を投げつけたが力はまともに入っておらず、女の足元を滑っただけだった。
「ちくしょう!俺に罪は無いんだよ。これは理にかなってるぞ。おまえが人間か化け物か知らないけどな。こんなことは」
「煩い」
その一言で心臓が血の気をすべて集めたかのように熱くなった。やがて視界が暗くなり、自分の頭が床に叩きつけられる音が聞こえた。
「ママが取り返すからね」
nextpage
母が自分を呼ぶ声がする。目を開けて起き上がるが、またぐらりと崩れ落ちた。
「じっとしてなさい」
上半身が血まみれになっており、包丁が傍に転がっていた。外が何やら騒がしい。
「後で、全部話すから」
母は目をぎゅっと閉じて、涙を落としていた。真一さんは口を開こうとしたが、いつの間にか入ってきた救急隊員に運び出される。
nextpage
母によると、家を出た後にどうしても真一さんが心配になって戻ったところ、仰向けになり包丁で自身の胸を刺している姿を発見した。それは操られた人形のような動きで力強さが無く、幸い大事には至らなかったとのこと。
「あれは昔、近所に住んでた人よ」
病室の椅子に腰掛け虚ろな目をする母は、知る限りのすべてを真一さんに語った。
nextpage
にわかに信じられない話だが、母は真一さんに持病があることを知ってから、あちこちにドナーの登録を呼びかけ、裏では同じ年代の子どもが不慮の死を迎えるようにと、呪う方法を手当たり次第に試していたという。それが理由で叶ったのかどうかはともかく、どこかの子どもが事故死して、実際に真一さんの元に届いて生き永らえることができた。
問題は、その子どもの母親が後を追うように自殺したこと、そして真一さんの母の奇行は近隣に知られ、相当に有名になっていたことである。
「子を失った親からすれば、私が殺したと思われて当然よ。実際、誰にもバレずに人を殺める方法があるなら実行してたと思う」
「もしかして父さんが死んだ理由って」
「きっとあんたと同じ。刃物で胸を何度も刺して、一人だから誰も止められずに死んだのよ。あんたも一端の大人になったみたいだし、家を出ていく。母さんにだけ祟が来るように。それで終わらせる」
別れ際に母は言った。
「あんたの人生は、母さんが取り返すから」
separator
「あれから何年も経ちますが一度も連絡を取っていません。そしておかしなことも起きていません。結果として一人暮らしが叶ってしまいましたが、なんていうか、もう何も喜べなくなりました」
そう言って鞄から取り出した薬を飲む。
「一度も欠かしたことはありませんよ。飲み忘れるとアレが来そうで。ああ、それとも自分も死ぬべきですか?」
達観したように笑う真一さんだが、ペットボトルを掴む手はわずかに震えていた。

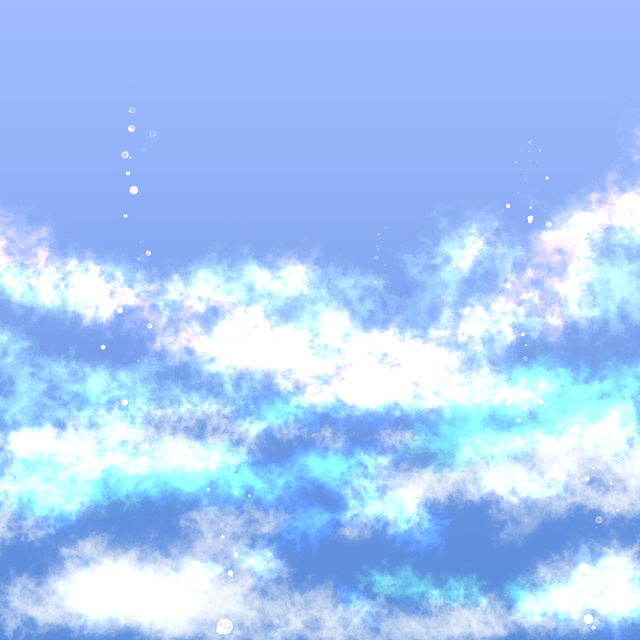
作者ホロクナ