かつて私は、休日となると趣味で始めたカメラを持って、一人撮影に出掛けていた。
行先はいつも気まぐれ。ふと足を止めた場所に、面白い被写体や風景がある事が多かったし、「偶然」というのが、私の写真における、テーマの一つだったからだ。
そして、その日は朝から何となく、「いつもより遠くに行きたい」という気持ちが湧いて、私はおもむろにパソコンの地図アプリを起動すると、目を瞑って画面に指を当てた。
指し示した場所は、東京より北の方面にある、某県の住宅地。それもどうやら再開発された場所で、新興住宅地が立ち並んでいるようだった。
普段なら、こういった新築の建売は、味気無いものとしてスルーしていたのだが…何故かその日に限っては、たまにはこういうのもいいかも知れないと思って、足を運ぶ事にした。
電車に揺られること二時間半。中々に年季のあるローカル線の駅を降り、人通りの殆ど無い歩道を三十分程進む。
すると、途中でアスファルトの色が真新しく変わり…それから間もなく、視線を上げた先に、緩やかな上り坂と真っ白な屋根が姿を現した。
「…すごい…」
整然と並ぶその姿に、思わず声が出た。
左右に五棟、合わせて十棟ある家の全てが、つま先から頭のてっぺんまで白い塗装で覆われ、それが、黒光りするアスファルトの坂を軸に、きっちり左右対称に配置されていた。
真っ黒なアスファルトの上に建ち並ぶ、真っ白な家…こんな風景は都内でもそうそう見られるものではない。私は、周囲に人がいないことを確認して、早速カメラを構えた。
恐らく、既に住人はいるのだろう。だが…洗濯物や自転車、車など、生活感を感じるものがこちらからは一つも見えない。だから、シャッター越しに見ると無機質感がいっそう増して、まるで工業地帯を撮っているかのような、不思議な錯覚に陥った。
やはり偶然とは面白い。何なら、ここから年毎に、少しずつ町の一部として溶け込む様子を撮るのも面白いかも知れない、と…私は新たな創作のテーマが出来た事に嬉々としながら、夢中で写真を撮った。
だが…坂の下から、風景全体を撮影しようとした時だ。
坂の右側にある、一番上の住居の奥…そこだけ木々が雑然と生い茂っていて、どうにもバランスが悪く感じた。
坂を上って確認すると…それは小さな藪で、手前にはフェンスが一枚建てられていた。
フェンスはかなり錆びて傷んでおり…しかもその中央には、大人一が入れる位の穴が、無理矢理こじ開けたような形で開いていて、その奥には狭い道が続いていた。
一体どこに繋がっているのだろう…と私はいつになく好奇心に駆られ、身をかがめてフェンスを抜けた。
そして、何度か、木の根っこや湿り気の有る赤土に足を取られながらも進んで行くと…十メートルほど行ったあたりで視界が開け、私の目の前に、大きな広場と、横に長い平屋建ての建物が姿を現した。
かすれた文字で「〇〇園」と書かれたそれは幼稚園で…さっきの道は、通学路だったのだと気付く。
そしてこの幼稚園も、住宅と同じく、頭からつま先まで全体が白で塗られていた。
休日とあって、人の気配は無い。が…やはり幼稚園とあって、そこかしこに、色紙の欠片や絵の具のシミといった図画工作の跡があり、先程よりもずっと、生活感が漂っていた。
その様子を眺めながら、すかさずシャッターを切る。横長に続く外廊下。小さな上履きや椅子。
そして、教室の窓に飾られた、何かの絵…
「……?」
それは、青や茶色で書かれた大きな円の下を、赤やピンクのクレヨンでぐちゃぐちゃに塗った絵なのだが…それが、どの教室にも所狭しと、まるで目張りするように飾られていた。
何かしらの「物」である事には間違いないのだが、該当するものが辺りに見当たらない。
私の想像力が鈍いだけ?とも思ったが…その絵が何を意味しているのか、全く見当が付かなかった。
ただ…被写体としてはかなりインパクトがあるから、変に勘繰って、撮り逃すのは惜しい。
とりあえず、深く考える事は一旦止めようと自分に言い聞かせ…私はその後も、アングルを変えながら撮影を続け、そして、ある程度撮り終わった所で、今度は背後にある広場の方にカメラを向けた。
しかし…一見、何の変哲もないこの広場も、よく見ると何だか不思議だった。
中心から半径五メートルにかけてのみ、赤土の地面がむき出しで、雑草一つ生えていない。そして、その赤土の中心には、マンホールほどの大きさの石が、地面から二、三センチほど突き出た形で置かれていた。
しかもその石は、地面に出来た窪みを塞ぐような形でそこに埋まっていて…さっきの絵と同じく、一体何の為にあるのか想像が付かなかった。
だが…これも被写体としては個性がある。私は再びカメラを構えると、画角一杯に石を収めてシャッターを切った。
が…その途端、両手に力が入らなくなった。
見ると、手首から先が小刻みに震えていて…あれ?と思った矢先、今度は、身体全体をひどい寒気が襲った。例えるなら、重い風邪を引いた時の、関節の痛みを伴った悪寒によく似た感じで…額からは汗が噴き出し、次第に目の前もくらくらと渦を巻き始める。
あまりに突然の不調に、「本当に風邪引いたのかも知れない」と思って、引き上げるべくその場を離れようとしたのだが…まるで漬物石でも背負わされているかのように、体が重くなっていた。
と同時に…私は、周囲を囲む雑木林のあちこちから、何かが一斉に、こちらを見ている感覚に襲われた。
動物のような、人のような…いや、そのどれでもない、「何か」の、刺すような鋭い視線…それが、少しずつ少しずつ、私のいる方にではなく、「私に向かって」近付いていると知り、どうにか手足を動かすと、元来た藪の道をがむしゃらに駆け下りた。
今思えば、相当ヤバい姿だったと思う。
誰にも見られなかったから良いものの…地元の人間ではない見ず知らずの大人が、顔からダラダラと汗を流し、手足をばたつかせながら、声にならない悲鳴を上げて走って来るなんて…住人からしたら、恐怖以外の何物でも無い。
だが…私に、他の住人を気にする余裕は無かった。
藪の奥から感じた「視線」が、すぐ背後まで迫っていたのだ。
separator
時刻は既に、夕方になっていた。
いつの間にか背後の気配も消え、風邪のような症状も収まっていたが…藪から出た勢いのまま、右も左も分からない町の中を訳も分からず走っていたせいで、気が付けば、自分が一体どこにいるのか、分からなくなっていた。
棒切れになりかけた足を引きずりながら、とにかくどこかで休みたい…と薄暗い路地を彷徨うこと数十分…私は、ようやく薄暗い通りの奥に一軒の喫茶店を見つけ…店に着くなり思い切って扉を開けた。
「いらっしゃい」
店主らしき、初老の男性がけだるい声で言った。薄暗い店内は、古びたエアコンから出ている以外の音は殆ど無く、他に客は居ない。
お世辞にも居心地がいいとは言えず、店に入った事を一瞬後悔したが…暫く経って、注文を運んできた店主が、肩から下げていたカメラを見るなり、明るい声で言った。
「いいカメラだね。お客さん、写真家か何かかい?」
店内の雰囲気と相反した気さくな声に、やっと緊張の糸が緩む。
「ええ、…あの、趣味でして…」
「そうかそうか。いや、俺も昔、写真に凝ってた事があってね…ほら、これとか、俺が撮ったんだ」
そう言って、店主は私の席から斜め上にある額縁を指差した。
それは、今から十数年も前の、この辺りの風景で、田畑の中に日本家屋が点在する、のどかな田舎の光景だった。
だが…その中に一つだけ、不自然な木々の塊が映っているのを目にした途端、ついさっき自分の身に起きた様々な事が、一気に脳内でフラッシュバックした。
「あの…これ…」
「え?」
「この、山みたいなのは…?」
「ああ、これは山じゃなくて…ただの雑木林だよ。まあ、今は家が建ってるけどな」
店主はそう言って私の向かいに座ると…誰に言うともなく、話を始めた。
「あそこはなぁ、元々何にも建ってなくて、長らく余った土地だったんだよ。でも…五年前だったかな。いつの間にか建売の分譲住宅が出来て、人が移ってきたんだ。で、家と同時に幼稚園も新しく建てられたんだが…二年と経たずに、みんな出て行ったんだ」
「え…?みんなって…」
「みんな、全員だよ。だから、あそこにある分譲、今は誰も住んでない。家が残ってるだけ。」
道理で、異様に静かで生活感が無いと思った。
留守にしているでも何でもない。最初から、あの場所には私以外誰もいなかったのだ。
「あ、その…何か、いわくの有る場所なんですか?」
「う~ん…土地についての詳しい事は知らない。でも、アレはさすがになあ…説明しようにも、出来ねぇよなあ。」
「…アレ?とは…」
「ん、ああ…」
集団ヒステリーってやつだよ。
…ある日、みんな普通に登園して、いつも通り過ごしていたのに…突然、園児が騒ぎ始めたんだってさ。
それが、次から次へと伝染して…何がきっかけなのかは分からないが、園児が何かに怯えて泣き叫ぶってのが、立て続けに起きたんだ。
それだけじゃない、更におかしい事が起きた。そこの園児がみんな、示し合わせたように、同じ絵を描くようになったんだ。
何かを見て描いている訳じゃなく、まるで取り憑かれたように、全員が、同じ色のクレヨンとか絵具を使って、同じ姿形のものを描くんだよ。
これは何?って聞いても…頑なに答えようとしない。いや、答えようにも、どう言っていいのか、自分が一体、何を描いているのか、本人も分からない感じだな。
何故知っているかというと…俺の孫もそうだったからさ。
一時期、娘夫婦が通わせていてね。突然変な絵を描いたり、大泣きするもんだから、どうしたらいいんだって困惑してた。
…まあ、それは当然ながら、他の保護者も同じだった。それである時、緊急で保護者会議が開かれたんだ。
だけど、先生達も何が原因か思い当たる節が無いから、保護者と先生のやり取りも次第に膠着していって…空気がピリピリし始めた。
でもな、その時だよ。
保護者の一人が、急に窓の外を指差して叫び出したんだ。
『誰かいる!こっちに来る!』
って…本当に、何の前触れも無く。
そしたら…他の保護者も次から次へと騒ぎ出して、最後には先生達もワンワン泣き出して、もう、幼稚園全体がパニック状態。
俺は、何とかギリギリ平静を保っていたけどな。あれは、恐ろしかったよ。
…で、何を見たかって?それが…俺には何も見えなかったんだ。
だが、娘も孫も、しかと見たらしい。娘が言うにはな…それは、
青黒い色をして、根元からボタボタ血を流した、人の頭部だったそうだよ…
separator
店主の、その暢気な口調が余計に怖さを増して、私は足の震えが止まらなかった。
それでも、私は黙って、店主の話を聞き続ける他無かった。
いや、「聞かなければならない」という、強迫観念のようなものにとらわれて、動けなかった、いう方が正しい。
「……こわい…ですね…」
「ああ、変な事ばかり話してすまんな。だが…本当に変な場所なんだよ。場所全体が妙に薄暗くてなあ…思うに、過去に何かあったんだろうよ。」
そう聞いて、私はある言葉を思い出した。
「忌み地」―――――
…もしかしたら、あの石も、石が埋まっていた穴も、忌々しい過去の産物だったりするんだろうか…?
店主の娘さんとお孫さんが見たという、人の頭…
もしかして、あれって…
「あの、ありがとうございました…もう、帰らないと」
「そうか、まあ、気ぃ付けて」
店主はコーヒー代を受け取ると、それだけ言って、店の奥に姿を消した。
何故、私にあんな話を聞かせてくれたのかは分からない。しかし、「血を流した首が出た」、なんて話をされた後で食欲が湧く訳も無く、私は店を出るなり、逃げるように駅へと向かった。
そして…数か月後。私は、ある一人の友人の元を訪ねていた。
忌み地、という言葉を教えてくれた張本人で、本人は「ただの趣味」だと言うものの…オカルトに関する知識は、私から見ればかなりの量だった。
訪れた訳は、他でもない。あの町に行った時の事について、友人なりの見解を聞きたかったのだ。
「まあ、土地の歴史とか知らないで建てると変な事が起こるって、デフォルトなんだよねー。それに、不動産会社とか仲介屋とかって…案外土地勘無かったりするし、でも、園児だけじゃなくて、親とか先生まで泣き叫ぶって…ヤバいね」
その土地の古地図を辿れば、他にも色々な事が分かる筈、と言われたけれど…私にそこまでの探求力は無かったし、むしろ、調べない方が良いのではないかと感じていた。
…あの場所に着いてからの時間の進み具合もおかしいし、何より、私があの広場で体感した、酷い寒気や気配…そして、店主の話を思い出すだけで、未だに足が震えるのだ。
「ねえ、これって、『忌み地』ってやつなのかな…」
「そうだなあ…元から家の建設に向いていない土地もあるし、後から、そこが『忌むべき場所』になってしまう事もある。まあ、今回の場合って、後者なんじゃないのかなあ」
私は、友人の前にカメラを置いた。
あの時から一度も使っていない。いつもなら、撮ったその日の内に、パソコンにデータを移すのだが…怖くて出来ていなかった。
電源を起動して、恐る恐るパソコンに接続する。…そこには、確かに撮影したはずの住宅も、幼稚園も謎の石も、全く映っていなかった。
「え、あれ…全部真っ黒…?」
変だと思いつつ、不気味なものを見なくて済んだ、と胸を撫で下ろしたのも束の間…次の瞬間―――――友人の、絶叫とも取れる悲鳴が部屋中に響き渡った。
「えっ…大丈夫?!何…どうしたの…?!」
友人は…両手で顔を覆い、全身を震わせながら私に言った。
「……ぃる……いる……!!こっち、見てる………!!」
その言葉の意味を理解するのに、そう時間は掛からなかった。
真っ黒な画面に、カメラを構えた私が反転して映っている…何かに反射しない限り、こんな映り方はしない。
…そこには、人の黒目が、画面いっぱいに映し出されていたのだ。
separator
私はそれ以降、写真について何も話さなくなった。
自分が体験した事を思い出したくない、というのは勿論だが…「本物」を見てしまった事で、一時期写真恐怖症になってしまった友人への贖罪というのが、何よりの理由だからだ。
カメラは今でも続けているけど、誰に見せるでもなく、完全に自己完結で…気まぐれに撮影に向かう事はもう無い。
そもそも、どうして私は、あの場所に向かったのか…それすら分からない。何故なら、
私が訪れたあの町と、パソコン上で指を差した場所とは、方角はおろか地名も何もかも、全てが違っていたのだから。
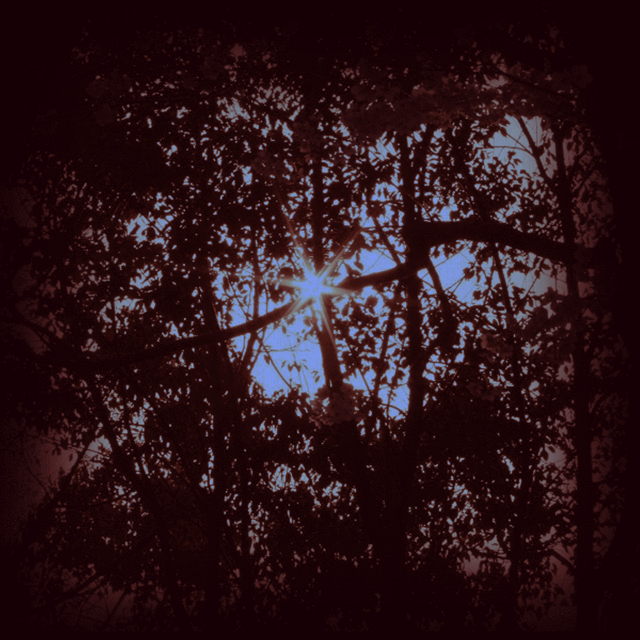




作者rano_2