「この子に今そんな話しても分からないさ。さあ、おにぎりだ。モウソウチクがよく伸びる」
「おいしい!」
「ねえ。いつまでこんな生活をするの」
「もう少しの我慢だよ。きっとうまくやってくれる」
「やってくれるって?そんな人任せで何とかなるのかしら」
nextpage
日差しが瞼を温める。
目を覚ますと家の中にいた。誰かが話している夢を見ていたようだが、起き上がった瞬間に忘れてしまった。
「よう寝るやっちゃな」
「うわ!」
窓の格子にばあさんの顔があった。
「すみません、もう昼ですか?」
俺が神妙な顔で<何ばあさん>か当てようとしていると、おにぎりを部屋に投げつけてきた。それは床でバウンドし、俺の膝に当たって更に転がった。
「それ食え。食ったらトミオさんとこ行け」
「食べ物を投げるのは良くないですよ」
「おまえがちゃんと受け取らんからじゃ!殺すぞ!」
「そんなすぐ殺すって言うのは」
こういう扱いを受けると、俺はまだ犬畜生のように死ぬか生きるかの境目にいるのかと考えてしまう。
拾ったおにぎりから出来立ての温かさを感じた。
「もしかして具はタケノコですか」
ばあさんは目を少しだけ大きく開いた。
「よう分かったの」
「なんでしょう、なんとなく。夢でそんな話を聞いたような。モウチクショウだったか」
言い終わる前にばあさんはいなくなっていた。
nextpage
トミオさんの家に入ると、彼の周りを数人の子どもたちが囲んで座っていた。
「おじさん、ラムネはどこにあるの?」
「さあ、あの箱のどこかにあるかも」
すると子どもたちは騒ぎながらダンボールの山に向かう。
「この村に子どもなんていたんですね」
「いや、預かっているだけだよ。それより君、馬鹿みたいに大根食べたんだってね」
トミオさんが口角で髭を持ち上げて笑う。
「もしかして俺はそのせいで眠りこけてたんですか」
「誰もが通る道だよ。君はこの村に住み続けたいかを聞きたい」
「どっちでもいいと思ってます」
「それならたぶん、住み続けるだろうね。ただ村にも寿命があって」
「おじさん!これは何?」
女の子が何かを指さす。
「それは灯油だから飲めないよ」
灯油という言葉でなぜか俺の心臓が唸った。
「寿命ですか」
「村と共に死なないようにね。ここから出ていきたければ」
「はあ」
「老衰と一緒でね。前触れもなくやってくるんだよ。我々はそのときになって寿命だと察する。一人が察した途端にすべてが終わる」
その言葉は深いようでいて核心を突かない。そのまま俺は仕事に向かい、列に加わった。
nextpage
あれこれと考える間も無く夜になった。布団を敷いている最中、外から荒々しい声がした。耳を澄ましていると、どこか覚えがある不快な話し方だった。
「はなせ」
立ち上がり、格子窓から顔を出して覗いた。
声の主は芯田だった。どういう訳か、俺を旅館から追い出したあの人間がここにいる。更には後ろから両腕を掴まれ拘束されているのだ。
俺は食い入るように顔を押し付けた。
nextpage
「何見とる?」
「ズア!」
突然、下からばあさんの顔が現れたので、ウルトラマンのような声を上げて卒倒しそうになった。
昼間と同じばあさんだ。この人はどうも俺を脅かすことを楽しんでいる。小さな仕返しを込めてウルトラばあさんと名付けることにした。
「あれは何をしているんですか」
「気になるなら見に行ってこいや」
「いいんですか?同じように捕まったりしませんか?」
「おまえさんはもう捕まっとるがな」
「また重い言葉を放ちますね」
捕虜みたいな扱いは受けていないが、誰かと親密になった気もしない。それは村のせいなのか、俺のせいなのか。
nextpage
「新人君か」
トミオさんが腕を組んで立っていた。
その場にはサングラス男と頭巾じいさんもいた。そしてひざまずく芯田と目が合う。上下ジャージ姿で、寝ているところを拉致されたのだろうか。月の光しか無いので数秒かかったが、俺のことを思い出したようだ。
見て分かるほどの鬼気迫る怒りを顕にした。
「てめえの仕業かよ」
「そう思うだろうけど違う」
「何が違うんだ何が」
「一言もあんたの話はしていない」
「覚えてろよ。体中の血が無くなるまで殴り続けて、雑巾のように絞って、干物にしてお歳暮にして家族に食わせてやる」
「お友達のようだね」
この会話のどこがお友達なのか。
「旅館を一緒に開いたはず、の知り合いです」
「なるほど。彼に立ち退きをお願いしているんだが、暴れるものでね」
「どうしてですか?」
「忠告だよ。あの旅館は必ず潰れる」
「だからその理由を言えってんだよ!インチキ占い師が!」
「何回も説明してるんだけど」
芯田が振りほどこうとするが、サングラス男はそれなりに鍛えている彼の体を難なく抑えつけている。見た目以上に腕力があるようだ。
「ちょっと新人君の話を聞こうか。その旅館を守る固い意志があるなら、何とかできる可能性もある」
俺はまたトミオさんの家に呼ばれた。今度はばあさんが三人。無言ばあさん、おにぎりばあさん、ラムネばあさんだ。そろそろ名前を聞くべきだろうが、間違えるのが怖い。
そんな中、自分がビジネスを始めた頃から、最終的に騙されてここまで来たことを正直に話した。
ばあさんの一人が息をつく。
「おめえ、なんでそんな事したかったんだ」
「え?」
「旅館を開いた理由だよ」
「それは」
何か話そうとしたのに、言葉にならなかった。自分はどんな思いで、そもそもどんな目標で経営しようと考えていたのだろう。人生の節々で、何かを変えたい。そう考えて生きてきたはずだ。
「なんだか分からなくなりました」
「目的もねえのに始めたんかい」
「じゃああなたたちは何のためにここにいるんですか?大根だけ育てるためですか?」
つい反論してしまった。
向かいのばあさんが眉をひそめた。
「おめえを責めてるんじゃねえさ。ただこのままじゃあな。わしらと同じになっちまうぞ」
「おじいさんになるってことですか」
「この村になじんで、幸せを感じるようになる。そうなったらもう、その先は無い。ずっと幸せのままで終わる」
「良い意味に聞こえませんね」
幸せという言葉がなぜか不気味な響きを纏っていた。そこで皆黙ってしまったので、俺は話を戻した。
「とりあえず、芯田の性格では正直に話しても聞いてくれないと思います。出会ってしまった時点で詰んでいたんです」
「ツンデータン?」
「人生が詰むってことです」
「どういう意味じゃ!」
「ええと、物事が悪くなる未来が決まったってことですね」
すると、周辺の土地にどんな建物があるかを聞かれた。林道と川があるくらいなのだが。
結果、ラムネばあさんが口を開く。
「ほんだら、詰んでるのは向こうも一緒や」
「何を言ってるんですか」
言葉が伝わってないんだと思った。そして無言ばあさんが立ち上がり、大きな紙を持ってきて床に広げた。そこには黒インクだけの落書きのような地図が書かれていた。
「おまえさんの言う、旅館ってここじゃろ?」
「はい」
「ほな!詰んでるのは向こうやがな」
じいさんばあさんがウンウン頷いている。
「あのう」
無言ばあさんは無言でペンを握り、無言で線を引いた。それはこの村から旅館を通り、更に紙の端まで突っ切る。
「こいつらは絶対に塞いだらあかん道をやっちまってる。オト様の通り道や」
「だからトミオさんが話付けに行ったんやな」
「あいやあ。こげなとこ旅館立てるバカがおるかあ」
芯田ではなく自分がバカにされた気分だった。
nextpage
朝になると村はいつもの空気に戻っていた。芯田は最後まで納得しないまま帰らせたらしい。俺もとりあえずは忘れて仕事を始める。
「そういえば車があったね」
トミオさんが畑の外から声をかけてきた。
「今夜は危ないから、僕の家の隣にでも移動させていいよ」
「移動させないとどうなるんですか」
「車が無人のままどこかに行っちゃうと思う」
それはそれで興味があったが、やはり車は大事だ。
だが俺はこの人たちにガソリンを抜かれている。<ガソリンを返せ>と言わなきゃならない。
「どうかした?」
「いや、ガ。あの」
変な空気になり、黙って車に向かった。あろうことか、乗って確かめると満タンになっていた。
nextpage
久しぶりの運転だ。心なしかハンドルが重く感じる。
住民は特に関心が無いのか、見慣れない車が村に入ってきても各々の作業を続けていた。とりあえず怒鳴られないかが不安だった。
結果的に鎌のばあさんだけが、トランクを柄で叩いてきた。
「はよいけ!」
恐ろしい。そもそもこの人は鎌を何に使っているのだろうか。大根の収穫には必要無いし、それ以外でも使っている姿を見たことがない。
こうして見渡すと畑は十箇所以上ある。素人の俺はもぎとる段階になった畑をローテーションしているわけだ。
人物相関として俺が知るのは、トミオさん、サングラス、頭巾じいさん、鎌ばあさん、ラムネばあさん、ウルトラばあさん、無言ばあさん。おにぎりばあさん。名前をつけられるのはそれくらいだった。
そういえば俺の呼び名も、ジサツオトコからようやく「シンジン」という中国人のような呼称に変わった。それはつまり、時給800円から850円に上がったような気分だ。
nextpage
「慣れたか、シンジン」
夜、ラムネばあさんと外でおにぎりを齧っていた。
「ありのままを言うと、慣れたり慣れなかったりしています」
その言葉どおりだ。慣れたと思ったら想定外のことが起きて認識を改めなければならない。それだけで一日が終わる。
「そんなもんやろ。どこに住んでたって」
「そう言われたらそうですが」
「お」
遠くでカラスが鳴いていた。
「そろそろ帰って寝ろ。オト様が出る」
nextpage
深夜、地響きが一時間ほど繰り返された。人の言葉では表現できないような、重くて大きな音だ。
これで眠れる人がいるものか。何をやっているのか覗きたかったが、ばあさんに窓から監視されているようで動きづらかった。頭から布団を被り、耳を塞ぎ、夜を耐えた。
nextpage
朝になって外へ出ると、村全体が少し埃っぽく、視界が悪くなっていた。鎌ばあさんが旅館まで用があるらしく、その付き添いで俺が同伴することを許可された。
「まるで災害ですね」
nextpage
昨日まで車を停めていたあたりは道ではなくなっていた。木が根っこから引き抜かれたように倒れており、砕かれた岩盤があちこち飛び出している。そんな途方も無い破壊が点々と例の旅館の方へ続いていた。
この先にでひどく悪いことが起きていることは疑いようがない。その予想は的中しており、旅館は天罰を受けたように滅んでいた。しばらくその場で動けずにいると、土塊が動き始め、中から人が出てきた。
nextpage
「やばいやばい病院だ病院。行かないとまじで死ぬ」
手足を骨折したらしく、芋虫のようにのたうっていた。近づくとそれは芯田だった。
「人呼んでやばいも虫」
ばあさんが俺を見てニカッと笑った。俺が全く笑わらないのでばあさんは真顔に戻った。
この光景は惨劇と言える。
芯田が俺の気配に気づき、いろいろと自由に悟ったようだった。
「おまえ、人殺しだからな」
そう呟くと、這ってどこかに向かおうとする。俺の人生を殺した人間が、物理的な死の危機に瀕している。
「俺にはどうすることもできないよ」
この出来事、仮に俺が経営を続けていても起きたのだろうか。そして知らない村から警告を受けて簡単に信じるだろうか?
考えていると、鎌ばあさんが芯田に歩み寄り、何の躊躇もせず刃を背中に振り下ろした。
<トツ>という音と共に、命の琴線が断たれる瞬間を見た。胴が三度脈打ち、頭が数え切れないほど左右に揺れた後、動かなくなった。
芯田は息絶えた。
「ぼーっと見とらんと、死にかけたもんにはトドメくらいさせえ」
鎌ばあさんは土を蹴ってかぶせると、他に人が埋まっていないか一通り調べて、その場を後にした。
俺の足は動かなかった。あれは治療すれば助かったかもしれない。なのに殺した。
俺はなぜ殺されないのか。<死にかけたもん>といえばまさしく村に迷い込んだときの俺自身だ。芯田の方がずっと懸命に、生きようとしていたのに、俺の方は。
nextpage
そのとき背後に動物の気配を感じた。
「あ、すんません」
人だった。男女二人。
「どうした」
「車が大破しちゃってねえ」
軽いノリの男だ。話を聞くと、夜にこのあたりで車中泊していたところ、土砂災害に巻き込まれて車を失ったとのこと。
「それでどうするんだ?」
「近くに泊めてもらえる場所ないかな。あんた、このあたりに住んでるんだろ?」
「まあ。うちの村長に話せば泊めてもらえるかも」
「助かる!」
「でもおすすめしない」
「なんで?」
「そういう態度の人間に容赦が無い」
「俺そんな悪い態度か?」
男は女の方に首を向ける。
女は反応に困りながら<行かない方がいいんじゃない?>と小さな声で伝えるが、男はすぐに俺に向き直る。
「じゃあ勝手に付いてくわ」
説明するのも面倒くさかったので、俺は無言で歩き出した。
nextpage
「すみません。この二人、寝る場所が無いらしくて」
おにぎり配給所のばあさんに声をかけた。
「寝る場所は世界中にあるやろが」
「まあそう言わずに」
男が前に出ていきなりおにぎりを手に取って食べ始めた。女性はおろおろしている。おばあさんは俺たちの後ろに目をやった。
どこからともなくサングラス男が現れ、間抜けな顔でおにぎりを咀嚼する男を雁字搦めにした。
「なんだなんだ、なんだよ!」
「こいつ武器を持ってやがる」
サングラス男が彼の後ろポケットからナイフを取り出した。
「護身用だよ!彼女を守らないと」
「知るか。ここに入った以上はルールがあるんだよ」
そしてゆっくりと俺を見た。
「シンジン、てめえ裏切ったな」
「どうしてこれが裏切りになるんですか」
俺が村を襲撃しようと企てたとでも言うのか。どちらにせよ最悪な空気になった。そうこうするうちにトミオさんがやってくる。
「三人を僕の家に閉じ込めておいて」
nextpage
俺たちは縛られも目隠しもされず、トミオさんの家に詰め込まれた。いつもの囲炉裏と、野菜の名前が印字されたダンボール、そしてラムネと灯油タンクが大量にあった。
「私たち、殺されるんですか?」
女性は怯えていた。外には何者かの気配を感じる。男はしばらくドアを叩きまくっていたが開くことはなく、疲れてしんなりしていた。
「どうだろう。普通にやってれば死なない。普通すぎても死ぬかもしれない」
この人達に何を言って良いのか、悪いのか、俺にはいまいち分からない。
「オト様っていう神様みたいなのが村を守ってる」
「神…ふふ、神だって?はあ…ふふ」
男はまるで信じていないようだ。こういう性格はおそらく長生きできないだろう。
「すみません、私達のせいで」
誰かに謝られたのは久々だ。
「おい。その神様はどこに住んでるんだ?」
「森のどこかに住んでいた。今はどこかに引っ越した」
男は大笑いした。
「あんたまともじゃないなあ」
俺は男を無視して自分の境遇を振り返った。成り行きでここにいるだけだが、一生畑を耕して生きる未来に小さな違和感を覚えた。これで死んだら死刑囚と変わらない。
「あなたはこのままでいいの?」
「え?」
女性が発したかと思ったが、気の所為だった。そのときドアが開いた。男がすぐに飛び出そうとしたが、頭巾じいさんに正面から蹴り飛ばされた。
「話し合いの結果だけど、君たちを殺すことになったよ」
トミオさんは不気味なほどに穏やかだ。この感じは非常に良くない。
「待ってください」
ここまで働いたのに、殺されないといけないことに納得ができなかった。俺は次の行動を考えつつ説得を試みた。
「殺すのはダメだと思います」
「ずっとそうしてきたんだよ」
「ずっととは、今まで何人くらいですか?」
「数え切れないほどだ」
「殺すことに罪悪感は?」
「あるよ。同じ姿形をした生き物なんだから」
「人が一人死ぬだけで不幸の連鎖が起きます」
「戦争絡みのインタビューでもしているのかい?それに君は自分で自分を殺そうとしたが?」
「それはその」
「なんだい」
「じゃあ彼らが自殺するなら大丈夫です」
男女がビクリと肩を震わせる。苦しまぎれに変なことを言ってしまった。
「なら何も与えず閉じ込めておこうか」
「そうなるでしょうね」
俺は灯油タンクの蓋を開けて蹴飛ばした。
「これで終わりだ。家が燃えるぞ」
「確かにそれは灯油だ。危ないね」
トミオさんがじっとしているので、更に俺はタンクを掴み上げ、四方八方に撒き散らす。
「君、ライターは持ってるのかい?」
「持ってません。勝手に引火するんでしょ?」
「ああ…あのね。いくらガソリンでも火種が無いと燃えないよ。しっかりしないと」
「そうなんですか」
「例えばほら。青酸カリを一滴飲むだけで人が死ぬと思っているのかい。もう少し科学的な視点から知識を付けなきゃ」
「付けました」
俺は半泣きの男の胸ポケットからライターを取り出し着火した。炎が川のように縦横へ広がる。
「うわあっ」
男女が悲鳴を上げて出ていった。
代わって、どこからともなく村人がゾンビのように入ってきて、トミオさんの周りに並んでゆく。消火活動をするような雰囲気ではない。
nextpage
すべての村人と思われる人数が集結し、全員が俺を見ていた。それぞれの顔が炎に照らされている。煙も増してきたが、俺はその場を動かなかった。
「トミオさんは死んでもいいんですか?」
「僕を助けたいのかい」
「可能な限り助けたいです」
「優しさが最後に報われるなんて保証はどこにも無いんだよ。散々経験してきただろう。ここはそういう者たちが集う場所なんだ。でも飲み込まれる前に決別を果たしたようだね」
「俺の父親は」
野菜を育てるのが好きだった。大根で味噌汁を作って、家族で囲炉裏を囲うことが好きだった。夏にはラムネを大量に買ってきて子どもたちに配り、冬にはいろんな温泉に連れてくれた。
そしてその優しさを訳の分からないビジネスに利用され、騙され、家ごと燃やされて死んでしまった。俺は父の死後、故郷を捨てて立派になると決めた。有名になってお金持ちになって、過去の一切を忘れようと。
「父さん。助けられなくてごめん」
「大丈夫だ。立派じゃなくてもいいから、まずは生きてみろ」
めきりと音を立てて落ちてきた瓦礫が、俺の頭を打った。
トミオは俺の父だったのだ。
nextpage
「なに寝てんだてめえ」
目の前に芯田が立っていた。
「さっさと金拾えよ。もったいないだろ」
「いてて」
俺は首の後ろを押さえた。頭をぶつけると土でも案外痛い。
やり返さなければ、と思った。立ち上がって倉庫の鍵を開け、中から鎌を取り出した。使った覚えのないもので、こんなもの用意していたか?と疑問を持ったが、ともかくそれを固く握りしめて向き直る。
「てめえ馬鹿か。俺は開店準備に忙しいんだ」
大して驚いてもいないようだ。
「呼べよ。どのみち俺に明日は無い」
俺がじり、と近づくと、空気が変わるのを感じた。
「なにやっとる」
人がやってきた。このあたりの住民だろうか。頭巾をかぶったおばあさんだ。
おばあさんは俺の手から鎌を取り、芯田の後ろに回ってうなじのあたりを<トッ>と刺した。時が止まっていたかのような一瞬の出来事だった。
「は?」
という表情で芯田はうつ伏せに倒れ、痙攣を起こした。
「どうして」
「こいつ人の言う事聞けんじゃろ。人の言う事聞けん奴は人を殺す。だからその前に殺す」
「むちゃくちゃですよ」
芯田の痙攣が止んだ。
「おまえもやる気満々やったが」
「そう言われたらそうですね」
今度はおじいさんが二人やってきて、芯田を持ち上げた。すると息を吹き返したように痙攣を再開する。
「じゃかあしい!」
おじいさんが芯田の頭を平手打ちした。
やがてどこかに運ばれて見えなくなる。俺がその光景をじっと眺めていると、おばあさんが怪訝な顔をした。
「えらく落ち着いてんな」
「落ち着いてはいないんですが、どこかで見たようなデジャヴュが」
「でじゃぶが?」
「いえ何でもありません」
「んで、おめえは旅館まで建てて何がしたいんだ?」
「そりゃあ経営のために」
「そうじゃねえ!ここまできた訳を言わんかい」
ここまで。冷静に辿ってみると、答えは自然に出た。
「新しい自分を迎えることですかね」
「この旅館に?」
「そういうことになるでしょうか」
ばあさんはしばし黙り、近くの一軒家まで歩きながら誰かの名前を叫ぶ。すると中から別のおばあさんが現れ、何かを話し、戻ってきた。
「おまえさんがわしらの言う事を信じるなら、次の家を建てるまで面倒を見てやる」
「もう家を建てるどころじゃないと思うんですが」
「さっきの兄ちゃんのことなら気にせんでええぞ」
ばあさんの目つきに凄みを感じた。
「そんで、この旅館はすぐに壊す。しばらく家を貸すからそこに住んで、わしらの村で働け。ここには住んじゃいかん。死にたいと言うならええが」
「死にたくはないです」
「それでおまえさん、畑仕事はできるか?」
「やったことありませんが、大根を引っこ抜くくらいなら」
「大根?」
俺は両の手のひらを見つめた。
「なぜかそれだけはできるような気がします」
「まずはそれで十分だ」
おばあさんがわずかに笑った。
あとは住民の言う通りにした。仮家に住まわせてもらっている間の一晩だけ、<ずずうん、ずずうん>と、巨大な鉄球でも引きずっているかのような音が響いた。
「外見に行くのは絶対やめときや」
そう言われていたので我慢した。
nextpage
それから一年ほど経った。
夕食後、皿を洗い、タオルと下着を手に取り、地下への階段を降りてゆく。
形は違えど、俺は露天風呂付きの家を完成させた。独り身の俺にとっては十分すぎるほど広く、湯けむりからどこか懐かしい香りがして、そこがまるでもうひとつの家のようだった。
温泉に関する諸々の権利も譲ってもらったので、再び経営を始めてもいいそうだ。ただ今は村そのものに働き手が必要で、若者の移住支援のようなことを担当している。
しばらくはそれをやっていたい。
この村の何もかもに既視感を持つのだが、はっきりと思い出せない。住民たちは皆自己紹介してくれたのだが、俺はなぜかそこに感動した。
肩まで浸かると、吹き抜けから覗く星空と目が合った。それらを薄く並べた透明な湯は、自分の過去の一切を溶かし、温めた。
その最中に振り返る。
「おまえも入れよ」
「いひ」
俺が促すと、デッキブラシを持ち全裸で突っ立っている芯田が反応した。彼はここの清掃係として住んでいる。
後遺症で脳の幾らかに信号が届かなくなったらしく、常に口を大きく開けてぼんやりしている。
デッキブラシを放り出してよろよろ歩き出すのだが、すぐに足元を滑らせ、ビタンと胴を打ち付けた。
「大丈夫か」
「いい~」
俺は彼の手を握ろうとする。触れた瞬間、雷の直撃を受けた猿のような雄叫びを上げて転がる。ずっとこんな調子だ。
「だめか」
俺は反対から回り込み、背中を叩きながら湯に落とした。無限に跳ね回るが、<うるさい>と言うと一瞬で静かになる。
こいつはもう俺以外の役に立たない。それでも生きているだけマシだ。あの世には温泉も無ければ味噌汁も無い。
nextpage
「今おまえは何を見ているんだ」
「いひ~!」
幸せそうに笑っている。俺も久しぶりに笑うことにした。

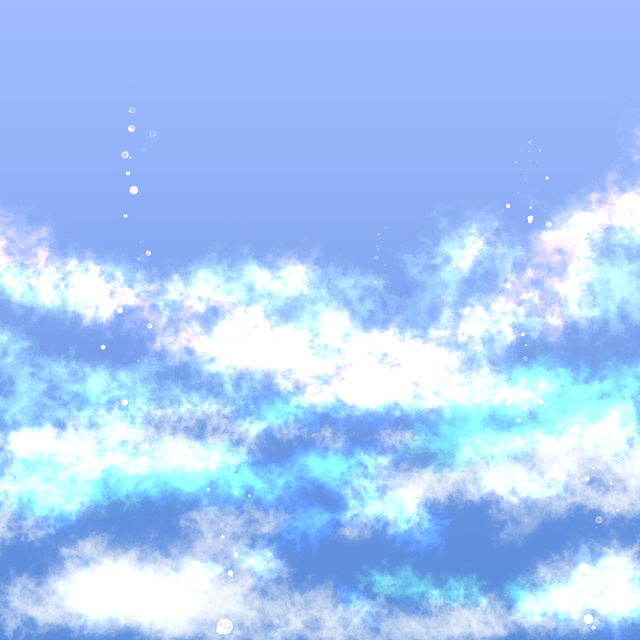
作者ホロクナ
今日も元気に生きています。