中部地方に遊びに行った智子さんの話である。
separator
興味を引く観光業があった。たらい船に乗って沖をぐるっと周る体験ができるらしい。
それに乗って願い事をすれば縁起の良いことが起こる。と言われたが、信じてはいなかった。いなかったが、これはもうすぐ結婚を控えていた私の、女子旅の締めくくりとしては丁度良かった。
旧友と1人ずつ、その人の出身地を旅する。そんなに友達は多くなかったので、今回であっけなく最後の一人になった。
彼女の名前は皇子。初対面で美しい、上品な名前と言われるが、性格はそれなりである。部屋がいつも散らかっていたり、突拍子の無い行動をしたり。
nextpage
「え?終わり?」
私は呆気に取られた。
港にやってきた私達の前に映ったのは、船頭さんたちが引き上げてゆく光景だった。
今は午後3時。まだ閉める時間じゃないはずだ。
「すみません。もう終わるんですか?」
「ええ、まあ、しきたりで」
「しきたり?」
「今日の夜はみんな、ウチで過ごすんです」
「はあ」
慌ただしくしているので、それ以上は追求しなかった。皇子は変わらずニコニコしながら言う。
「ごめんね。せっかく来たのに」
私は手を左右に振った。別に乗れないからどうということはない。
「大丈夫。お酒買ったし、ここで海を見ながら飲もうよ」
「彼も海が好きなんだって?」
婚約者と皇子に面識はない。
「そうみたい、私とはまだ行ったことないけどね」
あまり見ない、紫色の夕焼けだった。少々不気味だったが、海は大層静かで、さらさらした小粒の光を反射している。
「綺麗だね」
そのへんを散歩するうちに夕方になり、頬に当たる風が冷たくなってきた頃だった。
「あ」
と、皇子が指をさした。船頭さんが一人、小さなたらい舟の中で腰掛けている。
笠で顔は見えない。皇子が腰を上げる。
「まだできるんじゃない?行ってみようよ」
「え」
戸惑った。すでにたらいのことはどうでもいい気分になっていたからだ。そのまま皇子は船頭さんに話しかけ、こちらを向いて腕を輪っかにし<大丈夫>の合図を送った。
皇子はこんな風に、相談もなく行動に出る癖があった。
nextpage
「一人しか乗れないみたいだから、私は待ってるね」
皇子が微笑む。船頭さんは海の方を向いて、準備を終えているようだ。
「わかった」
床がぐらついて緊張した。こんなところに人が乗れるのかと感じたが、やめるわけにもいかないので思い切って体を預ける。
乗り込むと小さな揺れを起こしたまま、舵が取られた。
「これけっこう怖いね」
少しずつ陸が離れてゆく。
「智子。気をつけてね」
皇子が笑って手を振る。私は海ではなく彼女を見ていた。彼女が離れていくことに、不安と、わずかな安心を覚えた。その理由を考えようとしたところで、櫓を操る船頭さんの口から何かが聞こえた。
nextpage
<みまかり、さぶし>
今この人は何を言ったのか。
<げに、やをらたゆ、たゆ>
何かがおかしい。喉が締め上げられるように苦しくなる。
ぐらんぐらんと視界が煽られながらも、陸の方を見た。
そんな馬鹿な、と思った。ほんのわずかな時間で、皇子に声が届かないくらいの距離になっていたのだ。
私は首を横に振った。何か合図をしようとしたが、手が強張り、縁を掴んだ手が動かない。
<そらうそぶく、か>
皇子がずっと笑っている。あんな、いつまでも笑って手を振れるものだろうか。
見晴らしは良いのに周りには誰もいない。広大な海の真ん中まで来てしまった。たちまち恐怖がやってきた。
「あの」
ここまで言って、続きが言葉にならない。
水が跳ねる。
木が軋む。
服が擦れる。
それらが絶望という形に代わる。
「返してください」
やっと喉がまともになった。そして手を擦り合わせて頭を垂れた。
「ごめんなさいごめんなさい」
櫓を握る手がぴたりと止まった。
<さらふ、ぞ>
首をこちらに回そうとしている。そこで私の理性が極限に達したのだろう。上半身が逃げるように後ろに倒れ、そのままバランスを崩して海に落ちてしまった。
nextpage
途端に別の苦しみが襲ってきた。全方向からやってくる水。凍てつくように冷たく、油のように重たい。
いくらもがいても気力を奪われ、沈んでゆく。体を飲み込もうとする。
離れなければ。
そう考えながら意識を失ってしまった。
nextpage
目が覚めたのはホテルの一室だった。なぜか衣服が濡れておらず、着の身着のままベッドに転がり込んだようだった。外は完全に真っ黒な夜だった。
隣のベッドには皇子が眠っており、私の物音に気づいて目を覚ました。
「おはよう」
ゆっくりと起き上がる。
「ここまで連れてくるの大変だったよ」
「どうして?」
「二人とも酔っ払ってたもん」
そうだったか?と記憶を辿る。
「それより、無理に乗らなきゃ良かったね」
私は小さな嫌味を込めてそう言った。皇子はきょとんとする。
「何が?」
「たらい舟のことよ」
「何言ってるの?この寒さでそんなの乗るわけないでしょ」
皇子はくすりと笑った。
「皇子こそ何を言ってるのよ」
では自分たちは何のために近場にホテルを手配したのか。
「私たちは旅行で」
皇子は首をかしげて言葉を遮った。
「私たち?彼との時間を邪魔しないでよ」
目を細くし、眠たそうにしている。彼とは私の彼のことを言っているのか?
そんなはずはない。ただの寝言だろう。それ以上聞くのが怖くなり、無理やり眠ることにした。
それから帰路に着いて別れるまで、皇子はなぜかずっと不満そうにしていた。ホテルまで運んでもらったこと以外に心当たりがない私には、ただ謝ってみることしかできなかった。
separator
帰宅して1週間ほど経った頃、皇子さんとは突然連絡が取れなくなってしまい、今に至る。
旅行先について調べたところ、その地域の伝承として、決して夜に外出してはいけない日があるらしかった。
智子さんは無事に結婚したが、あれから二度と海へは行っていない。

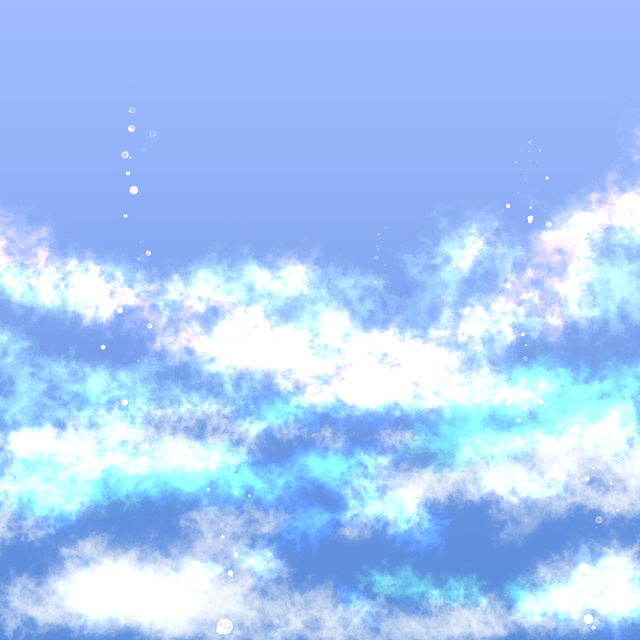
作者ホロクナ