月の裏側がどうなってるのか、ずっと疑問に思っていた。本当に兎が餅を突いてるかもしれないし、本当は何もないかもしれない。ただ、月はずっと正面を向いたまま、私(真崎恭子)を見下ろしている。ずっと、ずっと昔から…
ーー
一八時半、陽も暮れ始めた初夏の匂いが身を包む。帰路に続く田圃道で私は夕焼けに隠された三日月の表情をちらりと覗いた。
三日月は『剣の月』とも言われている。形が剣のように尖って見える事からその通称に由来されているらしい。『弓』、『鎌』、『舟』とも例えられる事もある。
その中で私はなんとなく『舟』が一番しっくりくる。海面に月の灯りがぼんやりと映り、波によってその美しい光景が掻き乱されていく。どこか私の心情と重なるような気がして、想像すると心が和む。
家に着くと、私は玄関を横切り中庭に向かった。そして縁側に腰を落とす。祖父が庭造りに力を注いでいる事もあって縁側から見える光景はなかなかの風情を感じる。
幾つかの石灯籠がずらりと並んだ光景、綺麗に手入れされた生い茂る草花、中でも私が好んでいるのは小さな池に配置された獅子脅しだった。
上部の竹が下部の竹に少しずつ水を垂らし、下部の竹は徐々に水の重さで下降していく。一定の量の水が与えられると、カコッ、と音と共にまた下部の竹が上行する。その音が私の風情感をまた唆る。
「おや恭子、もう帰ってたのかい。おかえり」
祖父が室内から縁側に訪れ、目尻に皺を寄せながら私に話し掛ける。
「ただいま」
「それで、どうやったか?思いつきそうかい?」
「いいえ。今日も何も浮かばなかったわ」
私は被りを振り、自分の膝に眼を落とす。
「そうかいそうかい。まぁそう焦らんでな」
祖父はいつもそうやって私を宥めてくれるが、私の心は、この夕陽のようにまったりと溶け、沈んでいくばかりだった。
「うん。もう少し考えてみる」
祖父の顔をまともに見る事出来ない哀れな思い、ふらっと意識が向こう側へと持っていかれそうになる。
私の拙い夢を応援してくれるのは祖父だけだった。私の書き上げてみたい物語、小説と言う形で私の世界を創造してみたい。今決まっている事といえば、タイトルだけ…
『裏月』
さて、どんな内容にしようか、どんな世界を創ろうか、どんな思いを馳せようか、書き出しはどうしようか…
ーー
暗い空が広がる、上空に浮かぶ『ソレ』は大福のような円みを形成していた。あの物体の裏側に秘めた謎を解き明かしたい。
この始まりはどうだろうか?いや、もっと『月』という単語を表面に出した方が良いかな?
小説の始まりはその小説の全てを決める。そうどこかで聞いた事があるが、考えれば考える程に頭を抱えてしまい、足場が存在しない沼にハマっていくような錯覚に陥る。
「…こ…ょぅこ、恭子」
三度目にしてようやく祖父の声に気がついた。
「ごめんなさい、考え事をしていて全然気づかなかったわ」
「小説の事かい?」
「ええ…」
そう答えると祖父は舟月を見上げた。
「恭子は一度決めた事は必ずやり抜くとお爺ちゃんは知っている。だから、恭子の物語をいくらでも待てる自信がある。それまでは、くたばる訳にはいかないね」
「うん。ありがとう」
祖父から見れば、私は物語に対して急ってるように映るかもしれないが、実はそうでもない。私自身、この物語は淡々と書き上げる訳にはいかないと心に決めていた。じっくりと練って、灰汁が出るまで煮込んで仕上げたいと思っている。
「お爺ちゃん、おやすみなさい」
そう言って、祖父を寝室へと促した。そして再び、縁側から夜空を見上げた。
ーー
舟月の周りに小さな星々がキラキラと輝いている。あの星一つ一つに深い物語が宿っている。
この始まりはどうだろうか?いや、少し陳腐かな…書き出してとしてはどこかもどかしい。
本来、小説というのは自由に言葉を綴れる。少なくても私はそう信じていた。しかし、いざ書き始めてみると、どこか不自由さを感じてならない。まるで見えない何かにずっと縛られているような感覚だった。
時刻は二十一時をまわった頃、私はスリッパを履き、夜道へと赴いた。暗く澱んだ空気はジメジメと肌を這う。消え掛かった街灯がぽつぽつと足元を照らし、辺りは少し怖々としていた。
私はいつも街並みから少し離れた所にある丘へ足を運ぶ。人の気配がまるでなく、物語と向き合うにはうってつけの場所だと思っているから。
丘を登るにはこの長い石段を登り切らなければならない。少し呼吸が乱れるが、その後の開放感を味わえば、どこかクセになる。
散歩コースの終着点、丘の頂上に辿り着くと、まず息を整えた。何度も訪れてはいるが、未だに息切れを免れない。まぁ、お陰で日頃の運動不足の解消にもなった。
丘の上から私の住む街を一望する。暗い空の中に舟月がまったりと一面を照らす。民家からは、ぽつぽつと灯りは消えていき、街は就寝時間のようだ。
ゴォー、と強い夜風が吹き上がり、少し湿った空気が肌を掠めた。雲が一定の間隔で月を遮っている。なんだか小雨でも降り出しそうな気がした。
初夏といっても夜の空気はまだ少しひんやりとしていた。何も考えずに薄着で出て行ってしまった事に後悔を覚えた。
まぁでも、せっかく訪れたという事もあって、私はいつもの茶色い木製のベンチに腰を落とした。
座ると古い木材が、べきっ、と音を鳴らす。いつ寿命が来てもおかしくないので、私はいつもゆっくりと腰掛ける。
ーー
さて、思考の時間が訪れた。物語と向き合う時間だ。実は幾つかの書き出しの候補の中で私は既に、どれにするか定まっていた。後は章ごとに物語を綴っていくだけ、章のタイトルも既に決まっている。
第一章『舟月』
第二章『異端者』
第三章『街の記憶と私』
第四章『虚構』
私はいつも物語のタイトル、章のタイトルから決め、そこから話を構成していく、今回はこの四部作から展開させていく事になった。
まずは第一章『舟月』の書き出しから想像して物語を思考する。
記憶力にはそこそこ自信がある方だと自負しているので、ここで考えた構成を帰宅後書き下ろすのは容易に出来る。私はタイトル通り『舟月』を見上げながら想像を膨らませた。
ーー
ゴーン、と離れにある寺が鐘の音を鳴らす。どうやら午前0時に差し掛かったようだ。気付けば民家の灯りは全て消えていた。
同時に第一章『舟月』が完成した。丁度、こちらの舟月は雲に覆い被さり、ぽつんと濁った水滴が空から降り注いできた。
そろそろ帰ろうと思った私はベンチから腰を浮かせ、立ち上がろうとする。しかし、ここで私はなんだか違和感を覚えた。
人の気配がする…
私は全身が凍ったように動けなくなる。直視している訳ではないが、どこかに居る。それも、恐らく近くに…
「誰かいるの?」
私は中腰の体制で、その何者かに言葉を発した。
しかし、辺りは静寂としたままで、夜風の音が虚しく聞こえるだけ。
気のせいか…と思い私はそのまま立ち上がり丘を降りようとする。考えると私は数時間あそこのベンチで一人、月を見上げていた。今思うと少し恐ろしい気持ちになる。
もし、何者かに背後から襲われたとしても、どこにも逃げ道などない…大声を出しても、きっとその声は誰にも届かないだろう…私は少し早足で石段を降ろうとした。
その時、微かに聞こえてしまった。私が先程まで居たあの場所から…古い木材が軋む音が…
ーー
咄嗟に立ち止まり、私は恐る恐る振り返った。
すると、誰かがベンチに腰掛けている。先程の私と同じように、夜空をぼんやりと見上げているようだ。
私は呆然と立ち尽くしたまま、その者を凝視した。少し遠目で分かりにくいが、恐らく男性である。そして、じりじりと気付かれないように、私は後退りをする。
しかし、途中で茂みを踏んでしまい、ガサッ、と音を立ててしまった。
まずい…気付かれたか?私は男から眼が離せない。とりあえず、男は反応を見せない。どうやら気付いてないようだった。
私は安堵して石段に眼をやり、そのまま下降しようと思った。しかし…
「そんなにコソコソしなくてもずっと気付いてるよ」
私は身体を硬直させ、再び男の方へ眼を向けた。すると、ベンチに腰掛けていた男は私に眼を向けずにそう呟いていた。それは、独り言ではなく明らかに私に向けて放たれた言葉だった。
「あなたは誰…?私に何か用でもあるの…?」
声を震わせながら、私は男に質問を繰り出した。
「用?いやいや、用があるのはむしろ嬢ちゃんの方かもしれないよ」
「どういう事…?」
男は徐に立ち上がり、私の方を向いた。
私は同時に、ひっ、と声を上げてしまう。月灯りに照らされた男の顔は、まるで蝋で造られたかのように白く、ドロドロとしていたからだ。
人間、本当の恐怖に直面するとその場から動けなくなる。どこかで聞いた言葉だが、私はそれを犇々と痛感した。
「ああ…すまないね、驚かせるつもりはなかったんだが、まぁ無理もないね。先程の質問に答えよう。私が何故、嬢ちゃんの前に現れたか」
そう言って男は再び夜空を眺め、言葉を続けた。
「あの月の裏側はどうなってるんだろうね」
その言葉を聞いて、私は驚きを隠せなかった。それは私が心中で抱いている誰にも打ち明けた事のない疑問だったから…まるで心の中を抉り取られてるような瞬間だった。
「どうしてそれを…?」
「おや?嬢ちゃんもそう思っていたのかい?奇遇だね」
「いや、違う!嘘よ!あなたは私の心を読み取ってそう言ったでしょ?」
私は半ば混乱状態だった。男が言ったことも、もしかすれば、偶然かもしれない。これといった根拠など何もないが、気付けば声を上げ、男に感情をぶつけていた。
「ほう…いいね。ようやく恐怖心が消え始めた」
私はハッとした。確かに男が言う通り、私は今癇癪を優位にさせ、恐怖心など何処かに消えてしまっていたから。なんだか男の掌で弄ばれてるような気がする。
ここで私は一度冷静になり、男に尋ねた。
「あなたは何がしたいの?」
「そうだね…簡単に言えば、私は嬢ちゃんの内に秘めた願いを叶えに来た。とでも言っておこうか」
「願い?」
「ああ、私は人々の願いを叶える事を生業としていてね。普段はなかなか店から出ないのだが、嬢ちゃんの秘めた思いが強すぎて呼び寄せられたのかもしれないね」
男の言ってる事がいまいち理解が出来なく、私は首を傾げた。
「人々の願いを叶える職業なんてあるわけないじゃないの。それに呼び寄せられたって…意味がわからないわ」
「嬢ちゃんが理解する必要などないよ。ほら、願いを言ってごらん」
男の声色が妖しく一段上がる。何故か私は男に対して妙な信憑性を感じ始めていた。どういう理由でそう感じたのか、私自身説明出来ないが、どこかこの男に私の全てを見透かされてるような気がしてならない。
私の心は男によってぐちゃぐちゃに掻き乱されていた。しかし、せめて男にその事を悟られないように、極めて冷静を装い私は凛々しく立ち振舞った。
「ふぅん。願いかしら?それは私が改めて言葉を発するまでもないんじゃないの?あなたはもう解ってる筈よ」
「ほう…強気に出たね。それは月の裏側を知りたいって事でいいのかい?」
男はそう言って私の方へ向きを変えた。その瞬間、再び背筋に悪寒が走った。咄嗟に一歩後退りをしてしまう。そして、男は言葉を続ける。
「嬢ちゃんは本当に月の裏側を知りたいのかい?そんな単純な願いなのかい?」
「え?どういうこと…?」
「あの月…そもそも本当に裏側なのかな?」
「……」
その言葉に再び驚き、私は口を噤んだ。それは私が、私自身の内に隠れていた深い思いの象徴だったから。
そして、私は何かを吹っ切らかすように鼻を鳴らした。
「凄いね。あなた本当に何者?」
先程小雨が少し降り始めていたが、いつの間にか雨雲は去り、綺麗な舟月が顔を覗かせていた。
「はは、いいね。やっと思いの内側が現れた。さぁ、今一度嬢ちゃんの内に秘めた願いを言葉で示してごらん」
ーー
"月の裏側がどうなってるのか、ずっと疑問に思っていた。本当に兎が餅を突いてるかもしれないし、本当は何もないかもしれない。ただ、月はずっと正面を向いたまま、私を見下ろしている。"
それは、私の物語『裏月』の序章。
一見単純な疑問、子供の頃なら誰しもが抱く疑問ではないだろうか。しかし、その羅列には違う捉え方も隠されている。
ずっと正面に浮かんでいる煌びやかな月、それは本当に表面なのか?仮に私達、いや、私だけかもしれない、ずっと裏面の世界に身を置いて生きているだけだとしたら?あの月はずっと私に裏面を魅せているだけ。
この主人公は世界そのものに疑問を抱いている。裏側の世界にずっと一人取り残された哀れな少女、街の人々は身動きさえするが、その中身は空かもしれない。魂が宿っていない人の姿をした作り物かもしれない。そう考えると孤独に思えてしまう。
私の物語は動き始めた。長い間、向き合いを拒んでいた真実が浮かび上がっている。
そして、暫く口を閉ざしてから、私は男に言う。
「本当の私を返して欲しい」
男はニヤりと口角を吊り上げ、不気味な犬歯を覗かせた。
「ああ…いってらっしゃい」
ーー
広がる夜空は先程とは変わらない。星々が綺麗に並び、その中央に浮かぶ尖った舟月。丘の上から街を見渡すと街灯一つなく、暗く、荒れ果てた民家がずらりと並ぶ。そもそも最初からこの街に灯りなどなかったのだ。
私は丘を降る。降りた先の道中は足の踏み場所に困難を要した。足元に散りばめられた瓦礫を避けて通り、月灯りを頼りに帰路を歩む。
家に着くと私は玄関を横切り、縁側へと向かう。少し前までは綺麗に手入れされていた中庭、今は面影がない。荒れた草花に濁った汚水、崩れた石灯籠、そして私が好きだった獅子脅しはもうどこにいってしまったのかわからない。
あの時の絶望が再現される。空襲を受け、無惨に散りゆく街並み、私はその時、街外れに居て、戻った時にはもう遅かった。
ずっと信じたくなかった。ずっと自分を偽っていた。あの頃の綺麗な記憶をずっと内に秘めていたかった。それでも、現実はそうさせてはくれない。
私は縁側から自室に向かい『裏月』と記された背表紙を手に取り、ページを捲った。
ページはまだ白く何も記載されていない。私は筆を手に取り序章から四章全てを一気に書き綴った。
家の天井など、あってないようなもの、それでも私は薄い月灯りを頼りに丁重に文字を綴った。その文字は、私の潤った瞳からは確認が出来ない。しかし、私はここで手を止める訳にはいかない。残りはあと僅かなのだから。
さて、これから終章を綴ろう。もう終わりにしよう…この物語を…私自身の最期を…



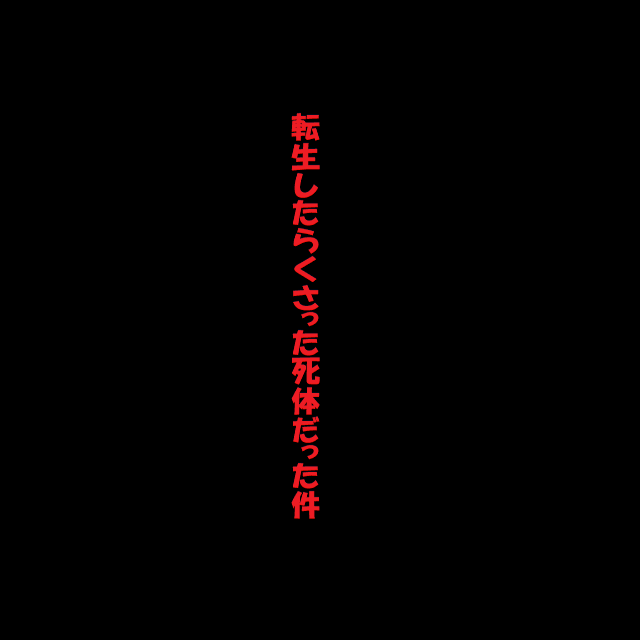
作者ゲル
読んで頂いた方、誠にありがとうございますm(_ _)m
実は最近、密かにシリーズ化を目指しております。全て読んで頂いている方は察しがついてると思いますが、この作品も『祈願屋』シリーズの一つとして書き上げました。楽しんで頂けると凄く嬉しいです😊
また、シリーズと言っても「前作を読んでないからわからないよ」って事がないような構成にしています。なので、どの作品から読んで頂いても、前作を未読でも全然問題ないです。
けれども、是非、関連作も読んで欲しいな、っと意を込めて、一応リンク貼っておきます…😓
https://kowabana.jp/tags/祈願屋シリーズ