慌しい夜が訪れる。
俺(桐島圭吾)は今、監獄生活に終止符を打ったのだ。刑期を大人しく待つ事が出来なかったが故に脱獄という更なる罪を犯し、再び外の世界へ舞い戻った。
看守の眼を盗んで一気に駆け抜けた事もあって、靴を履く暇もなかった。足の裏がじんじんと痛む。
刑務所は深い森の真ん中に位置する為、外に出たからと言ってもまだ安心は出来ない。地面に散りばめられた枝や小石を何度も踏みつけながら俺は必死に走った。
俺には目的がある。だから脱獄を決意した。しかし、現状行く当てがわからない俺は、体力ばかり無駄に消費するばかりだった。
もう何時間ぐらい走っただろうか…闇雲に移動しているだけで、今いる方角すらわからない。俺は少し休憩を取ろうと近くの木に背中を合わせ、そのまま身体を下降させた。
ふぅ…と荒い吐息を漏らし、右ポケットから一枚の写真を取り出した。その写真を眺めていると、俺なんかが生きていて本当にいいのだろうか…、とぼんやり思い、胸が痛んだ。
しかし…やってしまった事を振り返っても仕方がない。例え進むべき道が過ちであろうと、例え進むべき道が何者かに閉ざれようと、俺にはもう選択肢はない。
ふと暗い空を見上げる。月が見えず怪しい雲が疎らに広がっていた。なんだか一雨降りそうな予感がした。
このままでは、ただでさえ傷だらけ足の裏がふやけてズタズタになりかねない。しかし、体力はもう限界に近い…
そう考えた時だった。突如近くの茂みが、ガサッ、と音を鳴らす。
咄嗟にその方向を見ると、不気味な声を上げ、夜鳥が空へ羽ばたいていった。驚いたが、俺はその反動で立ち上がる事が出来た。
溜息を漏らし俺は仕方なく、また当てもない暗闇へと歩み始める。
歩行がゆっくりになると、自然と呼吸の乱れが消えてゆき、気持ちが和らいだ。
だがそれも一瞬の事、俺はまた、自分を卑下してしまう。落ち着いた先に待っているのはいつも深い絶望感しかない。
それを考えてしまうとまた呼吸が乱れ始める。別にこのまま死んでしまっても良いのだが…俺には確かめる事がある。それを全うするまで死ぬわけにはいかない。
ーー
まだ日は登っていない。俺はこの暗闇を只管歩き続けているが、まだ夜を超えていない。感覚的には永遠に歩き続けているのだが、実際には大した時間を経ていない。
意識が朦朧としているが、俺は惰性で歩き続けた。
すると、俺は突然バランスを崩し、その場で、ドサッ、と倒れ込んでしまった。
見ると、そこには太い枝が転がっていた。俺はこれを強く踏み転倒してしまったのだ。暗闇でよく見えないが、恐らく足の皮膚は赤く染まり、捲れてしまっているだろう。
しかし、その痛みのお陰で朦朧とした意識は鮮明になりつつあった。だが、まともに歩行出来ない俺はふらふらだった。
また転倒しそうになり、片足だけでバランスを保とうとする。だが、コントロールが出来ない身体は、次第にどこかの木にぶつかり、その場に座り込んでしまう。
流石にもう限界か…と諦めかけた時、ふと違和感がした。
今、ぶつかったのは木か…?それにしてはなんだか表面が広い気がした。背中をぶつけ、俺は咄嗟にバランスを保とうと両手を広げた。その時、広げきった筈の両手はその木に収まっていた。面積を考えるとそれは木ではない。
俺は後ろを振り向いた。
すると、俺がぶつけたのは外壁だった。木造の広い外壁がそこにはあった。俺は少し離れて外壁を眺めた。すると、そこには大きな古屋が佇んでいた。
幻覚でも見てるような錯覚に陥る。こんな深い森の中に佇むその古屋は不自然でしかなかったから。
同時にぽつりと水滴が鼻先に滴り落ちた。空を見上げると、細い雨が降り注いできた。
俺は古屋を回り込み、入り口付近で足を止めた。目の前の扉からは息を呑む程に不気味な雰囲気が漂っていた。
それに、古屋の中から薄らと灯りが漏れていた。人が居る気配がする。まるでこの古屋は、俺を招き入れようとしてるのではないか…と不思議な気持ちにさせていた。
次第に雨は勢いを増すばかりで、濡れた衣類は身体を重くさせる一方だった。仕方なく俺はこの不気味な古屋に雨宿り目的で立ち入った。
ーー
「ごめんください、どなたかいらっしゃいますか?ここで少し雨宿りさせてもらいたいのですが」
そう言って暫く返事を待ったが、音沙汰がない。誰も居ないのか?と思いながら俺は中を見渡す。
天井からは一つの裸電球がぎぃぎぃと音をさせながら揺れていた。灯りはこれのみのようだ。そして、ここには家具らしき物は殆どなく、幾つもの棚が並んでいるだけだった。
その棚もがらりとしていたが、よく見ると一冊の本が収められていた。俺は薄暗い中、眼を細めてその本を確認する。
背表紙には『裏月』と記されているようだった。他に何もなさそうだったので、俺はその本を手に取ろうとした。
その時だった…
「それには手を触れないで頂きたい」
咄嗟にひっ!と声を上げてしまった。突然奥から発せられた言葉に、俺は心臓を射抜かれる程、驚かされた。
「驚かせてすまないね。でも、それは私のコレクションの一つでね。出来れば触れないでほしい」
暗がりの奥からその声の主がじわじわと輪郭を現す。男の顔は、目元と口元以外に包帯を巻きつけ、俺の前へ姿を見せた。
「度々驚かせてすまないね。私の素顔を見て怖がる人達が沢山いて、こうせざるを得なくなってしまってね。しかし、君のような客人は珍しい…」
「客人…?」
「ああ…君はここを知ってる。そして自分の意思でここを追い求めていたんだろう?」
そう言って妖しく蠢く男の眼は俺の身体を硬直させる。客人、店、そしてこの気味の悪さ…そのキーワードで俺はある噂に辿り着く。
「まさか…」
祈願屋…人伝えで聞いた話だが、恐らくそれがこの店の名前だろう…
ーー
空いた口が塞がらないとはまさにこの事だった。まさか求めていた場所が向こうからやって来るとは…俺はごくりと息を呑んだ。
「何故、俺がここを知ってると?」
「匂いでわかるよ…そう…君が放つ独特な匂いでね…」
口元の空いた包帯の隙間からニヤリと不気味な笑みを浮かばせながら男は言う。
「わからないな…いや…この際どうでもいいか…なぁ、アンタに頼めばどんな願でも叶えてくれる、その噂は本当か?」
「ああ…本当さ…ただし、それ相応の代償は頂くがね」
「構わない。ただ、その前に一つ訊いてもいいか?」
「なんだい?」
「"楽園"という場所は本当に存在するのか?」
『楽園』それも人伝えで聞いた話だが、俺が求めているのはまさにその場所だった。
なんでもそこは、"現世"、"天国"、"地獄"、そのどれもに結びつかない世界、その世界では己の幸福を永遠に堪能出来る場所と噂だった。
しかし、所詮は噂の範疇、実際誰かがその場所に訪れた訳でもないだろう。もし、そこに行ったとしても現世に帰還する人間などいない筈…
夢物語、もちろん俺もそんな場所があるとは殆ど信じてはいない。だが、少しだけ…本当に少しだけだが、もし本当にそんな場所があるとすれば…俺は縋り付くしかなかった。それが俺に課せられた最期の…
「楽園ね…その質問が君の願いかい?もしそうじゃないなら申し訳ない…私は一つの願いしか叶える気はない。だからその質問には答えられないね」
「そうか…」
「仮にその楽園という場所が存在するとしたら、君は何を叶えるつもりなんだい?」
「……」
その問いに俺は押し黙ってしまった。それは俺の罪…生涯拭いきれないであろう過ちの根源だから…もし楽園が本当に存在するならば、俺は命に変えても…それが、俺が出来る唯一の贖罪だった。
「妻を…俺が殺めてしまった妻をそこに送ってやりたい」
「ほう…面白い願いだね。わざわざ自身の手を汚した存在を楽園に送りたいとは…君は奥さんが憎くてそうしたんじゃないのかい?」
「…俺は妻を愛している…それは今でも変わらない…」
「そうかい。しかし、どうにもわからないね…君は奥さんを愛している。それでも君は自分の意思で奥さんを亡き者にした。なんだか矛盾していないかい?」
追い込むように質問を繰り出す男、俺は徐々に喉が詰まるように声を震わせていた。まるでそれが俺にとっての代償と言わんばかりに聞こえてしまう。どうやら、男は俺を逃してはくれないようだ。
「"ありがとう"、妻が俺に向けた最期の言葉だ…」
俺は目線を下に向け、白状するように湿った声でそう言った。
「ほう…殺される瞬間、奥さんは君に感謝したのかい?」
「ああ…妻が言ったんだ。"私を殺してくれ。"と、もう喋るのも動くのもやっとの状態だった…妻は病気だったんだ。余命も宣告されていた。だから妻を…」
「なるほど…動機はわかった。でもわからないね…君は奥さんの最期の願いを叶えた。奥さんも満足してこの世を去ったに違いない筈、それなのに、どうして君の表情はそんなに罪悪感で満ちているんだい?」
「……二度目なんだ…俺は妻に、殺してくれ、と二度言われた。一度目は断ったんだ…でもそれは…それは俺の本心ではなかった…」
「ほう…と言うと?」
「妻は俺の生き甲斐だった。毎日仕事でクタクタの状態の俺に、いつも笑顔で、おかえり、と言ってくれた。それだけで毎日が充実していた。眩しい幸せだった。もうそれ以上なにも望まなくて良い程に…でも、ある日を境に妻は衰弱していった。異変を感じ病院に行った時にはもう遅かった…妻は余命宣告を受けた…」
深い罪を告発するように俺は声を震わせながら話す。その話に男はをまじまじと耳を傾けている。顔は包帯で覆われており表情がよくわからない。しかし、どこか俺の話を楽しんでいるように思えた。
「はは、そうかい。しかし、話が逸れているよ。それで…君の本心とはなんだったんだい?」
「俺は…俺にとって妻は邪魔な存在になりつつあった…結論から言えばそんな感じだ…」
「なるほど…また矛盾が生まれたね。君は今でも奥さんを愛しているんじゃないのかい?」
「ああ…愛しているさ…俺は妻を愛している。いや、正確には"健全な妻を愛している"と言った方が正しいかもしれない…仕事を終えて病院に寄り、そして家に帰る。毎日それの繰り返し…俺は心の奥底で、そのルーティーンに苛立ちを覚えたんだ。今俺の目の前にいる存在はかつての妻ではない。そんな思いが段々と芽生え始めたんだ…病弱して会話すらまともに出来ない…それでも俺は話続ける。他愛もない日常の話しを、一方的に…それを繰り返している内にどこか虚しさを覚えたんだ…これは本当に俺の妻なのか…?そんな感情にすら陥っていった…そしてある日、妻が口を動かした。でもその第一声が"私を殺して"だった…それ以上は言葉にしなかった…」
「それが一回目という訳だね。それで、君はその時どう思ったんだい?」
「言葉を発したという現状に奇跡を感じたよ。なにしろ何ヶ月ぶりだったか…妻の声を聞くのは…でもその内容は絶望だった…恐らく妻の精神はもう限界だったんだろう。それは自分自身に対してなのか、俺に対する罪悪感なのかはわからない…わからないが、それでも俺は妻に言った、頑張れ!まだ希望はある!、と妻の手を握り、何度も、何度もそう言った。その言葉が妻に届いているかはわからないが…」
「そうかい。それで…二度目はどうだったんだい?」
「……一度目からまた数ヶ月経った頃だった。再び妻が言葉を発した。その時、妻の瞳から涙が滲んでいた。そしてこう言った。"もう苦しいよ…もう生きたくない…この病気に殺されるぐらいなら…せめてアナタに…お願い…"結果的にそれが妻の最期の願いになった…正直俺の精神も、もう限界だった…あの頃の妻はもう存在しない。活気に溢れ、幸せだった日常はもう取り戻せない。そう悟ってしまったんだ…そして俺は妻を…もうこれ以上は話させないでくれ…全ては俺の弱い心が原因なんだ…だから…」
「……そうかい。じゃあ最後の質問をするね」
「ああ…」
「なぜ君は奥さんを生き返らせるという選択をしないのかい?」
「……俺は刑務所内の医療スタッフ、青山と名乗る男にこの場所を聞いた。最初俺も、そんな場所が本当に存在するならそう願いたいと話をした。しかし、それでは病弱の状態で生き返るだけで根本の解決にはならない、と青山は言っていたんだ。その後、"楽園"を教えてくれた」
「なるほどね…では、君の願いを叶えよう。覚悟は出来てるね?」
「ああ…」
そう言い終えると、徐々に意識が失われていくのがわかる。視界が暗く澱んでいく。それと同時に、今までの人生が高速で脳内を過ぎり始める。これが走馬灯というやつか…しかし、そんな中で俺は、なんだか気分が晴れていく気がした。それは、長く忘れていた感情だった。俺は指名を果たした。もう充分だろう…もう何にも縛られる必要はない…もうこの世に未練などない…だからもう…
ーー
「終わりましたか?」
「ああ…見たまえ、この満足した表情を」
「ええ、こんな表情をする人物、この店で初めてかもしれませんね」
「そうだね…しかし、どうもわからないね…私は君に特定の人物をここに招待するように命じただけの筈だが…なんだい?楽園とは?そんな場所を私に創らせて君は一体何がしたいんだい?」
「さぁ…どうでしょうね…」
「そうかい…まぁいいさ…それより彼のポケットを探ってくれるかい?もし何か入っていたらそこの棚に収納してくれ」
「はい」
「しかし、どうもねぇ…彼の奥さんはどうして自ら命を断たたず、彼に罪を課せたんだろうね…」
「どうでしょうかね、まぁそもそも自ら命を断つ点で考えれば、単純にそんな行動を取れない程、衰弱していたんじゃないですかね。罪を課せた点は、もう奥さんの思考回路が正常を保てなくなっていた…と言った所ですかね。少なくても彼に恨みなどはなかったと思いますよ」
「ほう。どうしてそう?」
「だってほら、この写真を見て下さい。こんなにも微笑ましい夫婦が簡単にそうなりますかね?」
「ああ…なりそうもないね。ただ、それはこの写真を撮影した時の表情にすぎない、人の感情なんてものは、状況次第でどうとでも変わるよ…どんな人間でもね…」



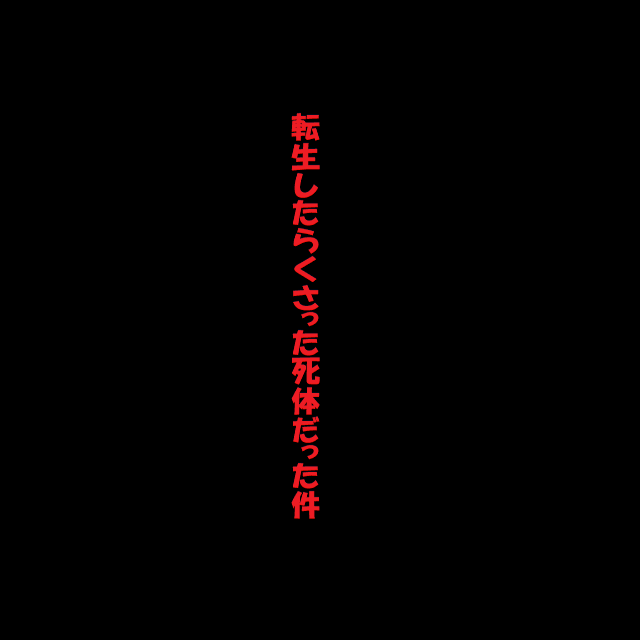
作者ゲル
祈願屋の新作です😊
https://kowabana.jp/tags/祈願屋シリーズ