「最近、変な夢を見るんだよね」
同居する弟が、ソファに寝転び、テレビを見ながら私に言った。
「そこで寝ているからじゃないの?」
「そうなのかなぁ…」
気の抜けた声。暇さえあればソファの上でゴロゴロ…しかも最近は、そのまま就寝する始末。
新築分譲ファミリー向け住宅の第六棟。結婚前からずっと理想に掲げていた、念願のマイホーム…おまけに幼稚園は、玄関から徒歩で約五分という超好立地。
このおかげで、日々の生活にだいぶ余裕が出来た私は、一通りの家事を済ませた後、ゆったりと一人の時間を満喫する…その筈だった。
「ほんと、だらしないね、自分の部屋で寝てよ」
「はは、ごめん…」
いいご身分、とまでは言えない。
私が、あの子を「弟」として受け入れるまで、かなりの労力を要した。そして…同居をお願いしたのも私。
引っ越した矢先に夫が単身赴任となり、娘のリリアを一人で面倒見るという生活が、当時は、どうしても心細くて堪らなかったのだ。
幸い、夫もリリアも、弟を慕ってくれているからいい。そして、このまま過去を知らずに時が過ぎてくれれば…
「りょうたくん、おはよう!」
「おはよ~、早起きだねぇ」
「リリア、良太“おじさん”でしょ?」
「良太君、だよね~」
そう言って、ぐうたらとソファを陣取る良太を尻目に、私は幼稚園へ向かう準備を手際よく進める。
リリアに着替えと食事をさせ、家を出た後は手早く先生に預ける…今日も、私の時間割り通りだ。
清々しい気持ちで木々の繁る通学路を下り、道が開けると、両側に整然と建つ白い外壁は、陽光で照らされて白飛びし、視界を遮った。
「まぶしい…」
見学に来た時も、同じ事を思った。白すぎて、目がおかしくならないか?と。夫は、私の言葉に苦笑していたっけ。
ああ、今頃、家族三人水入らずで暮らしていたはずなのにな…
「…ねえ!いつまでソファを占領するつもり?」
「あ~、ごめん…いや、夜、全然寝れなくてさ…」
「言い訳しないで。何、今朝言ってた、夢の話?」
「そう…何か、めちゃくちゃリアルなんだよ…」
良太はそう言って、夢の内容をブツブツ語り出した。
曰く…その夢は、この家に越してきてから見るようになったという。
どこかの森の中、周囲を木々に囲まれた丸い沼があって、良太はそこに膝まで浸かりながら、スコップのような工具で、ひたすら泥を掻き出しているそうだ。
自分の他にも十人程の男がいて、同じ作業をしているのだが…その殆どがかなり痩せていて顔色も悪く、服や髪の毛はボロボロ。更に…泥は非常に臭く、ヘドロに近いそうだ。
止めたいと思っても、何故か止める事が出来ない。…というより、止めたら「あいつら」に何をされるか分からない、という恐怖で、手を休ませる事が出来ないらしい。
「あいつら」の正体は不明。だがそれは、他の男達も同じ心境らしく…空気は、かなり殺伐としているそうだ。
そうして、息苦しさや全身の痛みに苛まれながら、延々と作業を続けている内に、次第に意識が薄れ…ぼんやりとした視界の中、いつも目が覚めるのだという。
…要約すると、だいたいこんな感じの内容。
そして、今朝見たものには、続きがあったらしい。
いつものように、息も絶え絶えに泥を搔き出していると…目線の先の、沼から上がった所に、女性が立っていたという。
白のノースリーブのワンピースにセミロングの黒髪と、いかにも清楚な姿をした可愛らしい女性だったというが、その顔には表情が無く、一瞬人形のようにも見えたらしい。
良太は作業を続けながらも、その女性をぼんやり眺めていたそうだが…、暫くすると、女性は突如服を脱ぎ始め、全裸になったかと思いきや…男達の目の前で、恥じらいも無く誘う仕草をしたという。
すると次の瞬間―――――良太以外の男達が、それまで疲労困憊だったのが嘘のように、工具を投げ捨てて勢いよく沼から上がると、次から次へと女性に抱き着いていったそうだ。
それは、獣が肉にありつく様子そのものだったというが…女性は嫌がる所か、汚泥や汗にまみれ、貪るように絡みつく男達の塊に埋もれながら、恍惚とした表情をしていたという。
その生々しさに、良太は思わず、その場で嘔吐したが…その光景を見続ける他なかったという。
そして…とうとう女性の顔半分しか見えなくなった時…突然、良太の頭の中で、
「死ね!死ね!」
という、耳をつんざくような大勢の怒号が響き…そこで再び意識が途切れ、目が覚めたらしい―――――
話している間…良太はずっと、声を震わせていた。
「怖いよ…ここ、何かヤバいんじゃないの?」
第三者に、ここまで事細かく語れるほど覚えているという事は、夢の中で見た光景はもっと、おぞましいのだろう。
…だが、ここは私の家だ。悪夢にうなされるのは同情できるが…それを、我が家の所為にされても困る。
「変な事言わないでよ。寝不足なら部屋で寝て!」
「ごめん……わかった」
良太は、うつむき加減で渋々立ち上がると、ダルそうに足を引きずりながら、二階へと向かっていった。
「はぁ……」
良太がうずくまっていた凹みに腰を下ろす。レースカーテンの隙間から陽が差し込み、涼しい風が流れた。
本来なら穏やかに、一人の時間を過ごすはずなのに、朝から悪夢の話なんて…一体どういうつもりだろう。
けど、良太が、夢で見た出来事を話すのは、これが初めてかも知れない。
毎日見ているとはいえ、内容も描写も、かなり詳細だった。
演技ではないという事は分かる。だが、どうしても私には、ゲームだとか漫画とかで見た光景を、夢に見ているとしか思えなかった。
そんな事を考えながらも、私は、一人快適に、うつらうつらと舟を漕いだ。
…が、数時間後。
けたたましくスマホの着信が鳴り、見ると、幼稚園からだった。
separator
教室の前で、若い職員に手を繋がれたリリアは、顔中を涙でいっぱいに濡らしてじっと立っていた。
どうしたの、と私が言うのを遮って職員が言う事には、リリアは、幼稚園の隣にある広場で遊んでいた時、突然泣き叫び、暴れたらしい。
そんな事ある訳ない。リリアは良い子だ。癇癪に至る理由が絶対にある。先生に何度も問い正したが、「思い当たる節は無い」の一点張りだった。
だが…私は気付いていた。リリアの背後にある手洗い場の壁から、小柄な男の子が、私達をじっと隠れ見ているのを。
年の割に小さい体つきと、女の子の様な見た目…安江さんの所の子供だ。
その、スーパーボールのような真ん丸な目で、物珍しそうにリリアの顔を覗く様子に、私は苛立ちを抑えられなかった。
「ちょっと、ねえ!…リリアに何かした?じろじろ見ないでよ!」
私が大声を出すと、彼は壁にすっと姿を隠した。そのすばしっこさに、更に怒りが増す。
「ちょっと待ちなさいよ!」
「…お母さん、落ち着いて!あの子は関係ありませんよ!」
「うるさい!」
「…おかあさん、おかあさんおこらないで…」
足元で、リリアが力なく言ったのが聞こえる。見ると、リリアは申し訳なさそうに私の様子を伺っていた。
「ねえ、何があったの?あの男の子に何かされたんでしょう?ねえ、答えて」
「…ちがう」
「何が違うの?何かあったんでしょ?教えなさい」
「…わかんない、わかんない…ごめんなさい…」
リリアは、そう言って首を横に振った。あの子を庇っているのか、それとも他の理由か…
ふと辺りを見回すと、他の園児や先生が、私の方をチラチラ伺い見ているのに気付いた。
この場でこれ以上、話を長引かせるのは得策ではない。
私は、職員からリリアの手を引き離し、早足で家へと戻った。
リリアは、自分の状況がイマイチ分かっていないようで、制服を着たままリビングの床に座り込んで、ぼんやりと私を眺めていた。私はその顔に向かって、すぐさま問いかける。
「幼稚園で何があったの?何で泣いたの?あの男の子と友達なの?」
リリアは頑なに「ちがう、わからない」と言い続けるだけだった。…一体誰に似たのか…この頑なさが鬱陶しくなる。
何度も何度も否定するリリアの態度に、私のイライラは、頂点に達していた。
「…ねえ、いい加減にしなさいよ?上手に答えられない子は、良い子じゃありません!」
そう言った瞬間、ハッと我に返る。
リリアは驚いた顔をして、その丸くて大きな目から、大粒の涙をボロボロとこぼした。
そして…間を開けずに、今度は爆発したような大きな泣き声が、家の壁という壁に反響した―――――
…また、やってしまった…これで何度目だろう。
――――あなたはね、真面目なのは良いの。でも…固すぎる。窮屈に感じるのよね。正論を人に押し付けるのは駄目よ――――
義母に言われた言葉が、頭の中で繰り返し再生される。
真面目のどこが悪いの。
テレビも漫画も、ネットの中の下らない世界も、昔から好きじゃなかった。
夫は、それを認めた上で私と結婚してくれた。この家だって、私の潔癖さを知った上で、頑張って買ってくれた。
ここなら、一から真新しく始められる。幼稚園だって、家だって、クリーンで、嫌らしい要素は一つも無い…そう信じていたのに。
近所のママ達は、変に若作りして…むかつく、あんな奴ら、あんな奴らの子供、近付けさせたくない。
だから、リリアには一人遊び出来るように、何度も何度も教えてきたのに…何で、こんな事ばかり起きるの。
「…なに、どうしたの…!リリアちゃん?どうした?大丈夫…よしよし、よしよし…」
いつの間に二階から降りてきたのか、良太が、リリアの頭を撫でていた。リリアは、しゃくり上げながらも、少しずつ泣き止んでいた。
何で…
「…私の問いかけに答えないから…」
「…きっと、上手く言えなくてリリアちゃんも困ってるんだよ、怒るのは良くないよ」
夫がいてくれたら。
夫は、読み聞かせもなだめるのも上手い。抑揚や声色をコロコロ変えるから、リリアは夫に絵本を読んでもらうのが大好きだ。
私には、そういう引き出しが一つも無い。全てが、つまらない。でも、恥ずかしい事はしたくない。みっともない事は、罪だ。
だから、良太のことも、最初はみっともなくて仕方が無かった。
でも…最終的に受け入れた。私が貴方の為に、どれだけ精神を削ったか…なのに、都合の良い時だけ、リリアを慰めて味方になろうとして…!
「…ねえ、リリアちゃん、僕と散歩に行こうか。散歩して、アイスクリーム食べよう」
「…うん、行く…」
「食べ物で釣らないでよ、みっともない。リリアにはちゃんと答えて貰わないと—――」
「お姉ちゃん」
良太が、私の前に立ち塞がる。久々に聞いた、鋭い口調。
私の目に映るそれは、かつて「唯」と名乗っていた人間…
「リリアちゃんに聞くのは、もう今日はやめた方がいい。苦しいのは、リリアちゃんなんだよ?」
「な…」
「お姉ちゃんが一生懸命なのは分かるよ。…血が繋がっていなくても、リリアちゃんの母親になろうと頑張ってるのは…良く知ってる。でも、最近やりすぎだと思う。
僕が言える立場じゃないけど…だから、お姉ちゃんは、ここで行彦さんと過ごした方がいいよ」
「待って、どういう意味…」
「僕がいるから、バランスが悪くなるんだと思う。僕は近々家を出るから…」
「は…なんで、貴方は私が居ないと…」
「それは昔の話じゃん…さ、リリアちゃん行こうか」
私の気も知らないで、リリアは嬉しそうに良太の手を掴むと、玄関から出て行った。
暗い。
さっきまで、あんなに眩しかった部屋が、日陰に沈んでいる。何の音も聞こえない。
私は震える手で、夫の電話番号を押した。何十コールして、ようやく夫は電話に出た。
「はい、もしもし~、どうしたの?」
その気の抜けた声に、私は気持ちを抑えられなかった。
「あんたのせいで…!!!」
私は夫に、怒りをぶちまけた。自分が何を言っているか分からないくらいに喚いて、気が付くと私もリリアと同じように泣いていた。
夫は、「え?」と何度も言いながら、それ以上の言葉を言ってはくれない。それが私の怒りを増長させた。
「リリアを、リリアをちゃんとした子にしなきゃいけないのに!!!私達は!!!崇高な血筋の持ち主でしょう!!!汚い!皆汚い!!」
「ちょ、ちょっと…ねえ何を言ってるの?落ち着いて…リリア?血筋って…何かのドラマの話?」
「馬鹿にしてるの?!妹があんな事して!!!穢れてしまったんじゃないの!!!」
「ほんと、落ち着いてって…そ、そうだ今日は、そっちに行くから…ね、落ち着いて…」
「うるさい!死ね!死ね!死ね!死ね!死ね!」
「え…え、何言って―――――」
「死ね!!!!!」
ツー、ツー、ツー、ツー、ツー、ツー、
夫の通話は、一方的に途切れた。
全てを言い終えた後で、私は、我に返ってソファに倒れ込んだ。
自分の口で言った事は覚えている。でも、何故それを言ったのか、意図した覚えがない。
…崇高な血筋?妹?
…死ね、って…
私、大変な事を言ってしまった。後悔ばかりしている。でも、止められない。
だって私の血筋は…
separator
「リリアちゃん、おいしい?」
「うん!」
リリアちゃんはすっかり泣き止んで、目の前のアイスクリームを笑顔で頬張った。
以前、散策していた時に偶然見つけた喫茶店。初老の男性が一人で切り盛りしている、地元の店だ。
古びていて薄暗く、音楽も掛かっていないが…この静かな空間が、僕にはとても居心地が良かった。
「りょうたくんも、はい!」
リリアちゃんは、覚束ない手でアイスをスプーンに乗せると、僕の口元に近付けた。
甘い、美味しい。こんな気分は、久しぶりかも知れない。
姉の要望で、あの家に来てから…僕はずっと、調子が悪い。一歩離れるとマシになるけれど、あの敷地に入ると、途端に具合が悪くなる。
いや、僕だけじゃない。姉も…
バラエティやお笑いに一切興味を示さず、口数の少ない真面目一徹な姉が、昔はスゴイと思っていたけど…ここ最近、潔癖で神経質な性格に、拍車が掛かっている。
行彦さんと結婚して、連れ子のリリアちゃんを快く迎えたと知った時は、本当に心から安心したのに…姉の精神は、思わしくない。その証拠に…いつからだろう、姉は僕の事を、「実は元々女だった」なんて、言い始めた。
確かに、子供の頃は「女の子みたい」と良く言われて、両親に女の子の服を着せられていたし、学生時代、仲間内のノリで、女装コスプレをしていた時期もある。
だけど、僕は生まれた時からずっと、「山沢良太」として生きてきた。
姉は、何を勘違いしているんだろう…精神科の先生に聞いても、ハッキリした答えは出ていないままだ。
「お嬢ちゃん、お口がアイスまみれだよ。ほら」
ふと顔を上げると、店主がリリアちゃんにおしぼりを差し出し、笑っていた。
物静かで、話しかけづらいと思っていたが…リリアちゃんを見つめる表情は、好々爺そのものだ。
「あ、ありがとうございます」
店主は、細い廊下を挟んだ向かいの席にドカッと腰を下ろすと、僕らをじっと見た。
「…ところで、見かけない顔だね。あの分譲地に住んでるのかい?」
「はい、そうです」
「じゃあ、幼稚園も俺の孫と一緒だな。娘夫婦が通わせていてね…サクラ、っていうんだ。仲良くしてくれると嬉しいよ」
「そうだったんですか…リリアちゃん、仲良くだって」
リリアちゃんは、すっかり笑顔に戻って、店主の方を見て元気よく挨拶した。
「こんにちは!やまさわ、ありす、です!」
「ん?アリスちゃんっていうのかい?さっき、リリアって…」
「リリアは…リリアはニックネームというか…家族の中ではそう呼んでて…」
「ふうん…そうなの。で、君は…パンダ君?」
「ぱ、パンダ?」
「目のクマが酷いなぁって、ずっと思ってたんだよ。パンダみたいだって(笑)」
ふと、窓ガラスに映る自分を見る。
いつの間にか、両目の下まぶたが、濃いグレーのアイシャドウを付けたように変色していた。
あの家に来てから、夜、まともに眠れた覚えが無い。
毎晩見る謎の悪夢。そして今日に至っては…あの女性。そして、姉も…
「はは、確かにパンダだ…」
「アリス、パンダ大好きだよ!りょうたくんパンダも大好き!」
「そうかい、そうかい(笑)でも…よりによってあの地域にねえ…」
「え?」
「あ、いやこっちの話」
店主はそう言うと、席を立って僕達の元を離れた。ふと壁の時計が目に入り、いつの間にか夕方になっているのに気付く。流石に姉も、心配しているに違いない。
お代をテーブルに置き、足早に店を出ると、僕とリリアちゃんは家路へと向かった。
微かな外灯に、心細さを感じる。リリアちゃんも、うら寂しい町の空気を感じ取っているのか…じっと黙り込んでいた。
「リリアちゃん、大丈夫だよ、すぐおうち―――」
「わたし、リリアじゃない…アリスだもん…」
「ごめん、そうだね…アリスちゃん、お母さん待っ―――」
「…かえりたくない、おかあさん…こわい、すごくおこってた」
「もう、怒ってないと思うよ。大丈夫大丈夫!…だ…」
その時…目線の奥、古びた街灯が照らす暗がりに、見覚えのある人物が立っているの見た。
黒髪を肩まで伸ばし、裸足で、白いノースリーブのワンピースを纏った…夢と同じ姿の女性が、路地の奥から、ジッと僕とアリスを見つめていた。
そうだ、あの人の名前…皆叫んでいた…泥だらけで…
――――――唯様あぁぁアァア!!!!!
separator
車をガレージに停め、インターホンを鳴らす。が…何の反応も無い。
「おーい…」
時刻は午後七時。普通なら、みんな家に居ても不思議じゃない。なのに、妻もアリスも、良太君の姿さえも見えない。
―――――死ね!!!!!
「うぅっ…」
妻の絶叫が、頭の中で繰り返される。
神経質で、時折口調は強いけど…「死ね」なんて言葉は、今日という今日まで、聞いた事が無かった。
やっぱり、アリスと二人きりにさせたのがいけなかったのか…
良太君がいるとはいえ、真面目な妻は、抱え込んで何でもやろうとしてしまう。単身赴任だって、二つ隣の県なのだから、いつでも様子を見に行けた…その筈なのに。
後悔と不安。それに…心なしか、身体が重い。まるで何か、ドロドロした場所を歩いているような…
「こんばんわ」
びっくりして振り返ると、いつの間にか、良太君とアリスが真後ろに佇んでいた。
だが…様子が変だ。二人共、心此処に在らずといった顔をしている。
「なっ、びっくりしたぁ…あ、あのさ、孝子、どこ行ったか知らない?」
良太君は、無表情のまま、ぼんやりと私の後方を見つめるだけ。アリスは、状況を理解できていないのか、俯いたままだ。
「良太君…ねえ、どうしたんだ一体…孝子は、孝子は一体どうしたんだ?!」
たまらず肩を揺すると、良太君はようやく目線を向けた。しかし…依然無言のまま、口元に微かに笑みを浮かべて、私の肩の向こう、アリスが通う幼稚園の方向を指差した。
「孝子…」
ガチャン
背後で鍵の閉まる音が聞こえ、気が付くと良太君もアリスも居なくなっていた。
一体、どこで何をしていたのか…何が起きているのか何も分からない。…私は、指を差していた方向にとりあえず足を向けた。
不気味な程、整列した家々を通り過ぎる中…時折匂ってくる夕飯の香りや、風呂場の湯気に、胸が締め付けられる。今頃、普通の家族なら、夕飯を囲んで暖かい団らんの中だというのに…
足元は依然重い。それでも、どうにか坂を登り切り、雑木林を抜けた。
目の前は、真っ暗な空間が広がっているだけ…昼間は、園児たちの賑やかな声が聞こえるのだろうが、今は、木々が大きく揺れる音しか聞こえない。
「…孝子、おーい、いるのか?」
そう声に出した時、広場の真ん中の方で、何か人影が動いたのが分かった。
「…孝子なのか?…ちょっと、何をやってるの…」
一歩一歩、重い足を引きずって、影の元へ向かう。たった数メートルの距離なのに、息が上がって、呼吸が苦しい。痛い。体が…足が、腕が、痛い…
「た、たかこ…」
妻は、直立不動で何かを呟いていた。小さくてよく聞こえないが…その声には、負の感情が込められていると、何故か分かった。
顔は、暗がりに溶け込んでよく見えない。が…その手元に、何かの紙を持って、ひらひらさせている。
…そこには、書き殴ったような「●」が描かれているだけだった。
「孝子…帰ろう…ごめんな、アリスを任せっきりにしてしまって…な、帰ろ―――」
「リリアが悪いのよ」
腕を握った途端に、妻が恨みの籠った低い声で言った。りりあ。電話で言っていた、誰かの名前だ。
「…ねえ、その…リリアって誰の事?ドラマか、本の中の名前…とか?」
「わたしたちは、清らかな血筋なの…リリアのせいで、妹のせいでめちゃくちゃになったの…あいつとあの男のせいで汚れてしまった…だから、だから…!!!」
「孝子!しっかりして!!なあ!リリアなんて名前の人、家族にいないよ!?妹って…誰の事?!」
「うるさい!!!お前の…!」
お前達のせいで―――――!!!
…ザクッ、
聞き慣れない音と共に、お腹の辺りを生暖かい感触が広がる。
痛い。今までのものとは違う…鋭い痛み。
体がふらつき、意識が朦朧とするさなか…妻の背後に、もう一つ…別の人物の影が、重なるように漂っているのに気付く。
恨み、苦しみ、嫌悪を抱え、髪を振り乱した女性の姿…そして、私の頭の中を、言葉がよぎった。
「…かおるこ…」
許してくれ………
separator
気付くと、僕はソファに寝転んでいた。
ベランダから差し込んだ陽の光が顔を照らし、眩しさで目が覚める。
どうやって帰ったのか、そこだけ記憶がすっぽり抜けていて、思い出せない。
暫くして、泥だらけのスーツ姿の行彦さんが、疲れ果てた姿で家の玄関を開けた。
家に入って来るなり、しきりに、「孝子に刺された」と言っていたが…刺された形跡も、出血も、全く見当たらなかった。
そして…当の姉は、スマホも荷物も全部置いたまま、靴も履かずに、姿を消した。
「あれは、孝子だった…なのに、なのに…ボクが知っている孝子じゃない」
聞けば、僕が幼稚園の方を指さして、そっちに向かうよう促したらしいが、覚えていない。もしかしたら、僕も何かに操られていたのかも知れないが…確証はない。
それよりも何よりも…僕は、自身の傍らで、穏やかに寝息を立てているアリスちゃんの姿を確認して、心からホッとした。
「…りょうたくん…」
「アリスちゃん、おはよう」
いつも通りの朝。ぐちゃぐちゃに荒れた室内と、パニック状態で風呂場に駆け込んだ男の姿を除けば…
「…もしもし。山沢さんのお宅でしょうか…アリスちゃん、まだ来てないのですが、どうされました?」
「…あ、えっと…その事なのですが…」
実家に連絡を取り、荷物を纏める。アリスちゃんも一緒に帰ると言ったら、両親は喜んで了承してくれた。
血の繋がりは無いとはいえ、思いがけず出来た初孫だ。遠方なのに加え、姉とは折り合いが悪かった為、中々会えずにいたが…
これからは、ずっと一緒。…その筈。
「アリスちゃん、バイバイできる?」
「…うん…」
せっかくお友達が出来たばかりで酷だが、こんな所に、ずっと居させるわけにはいかない。
早く、ここを離れなければ…
「おはようございまーす…あれ、アリスちゃん、お出かけ?」
確か、安江さん…だったっけ。
母親にべったりくっつきながら、男の子は、飴玉みたいなキラキラした目を見開いて、ジッと僕らを見つめていた。
「はい、ちょっと実家に…」
「あら、そうなの。いいなあ…若いお父さんね」
「いや、いや僕は…」
「じゃあ、親子で楽しんで!いってらっしゃい」
男の子の目は、どことなく怯えていた。
まるで、これからお化け屋敷にでも向かうかのように…いや、そうなのかもしれない…
電車に揺られながら…僕は、姉がアリスちゃんから、執拗に何かを聞き出そうとしていた事を思い出した。
「アリスちゃん、幼稚園で何を見たの?」
「う~ん…」
「もしかして、怖い事?」
「おーっきな、まあるいどろだんごが、ふわふわしてたの…」
「どろだんご!?」
「うん、それでね…おいかけて、さわろうとしたらね…いーっ!ってわらったの…」
「え…?」
「いーっ!って、笑って…目が付いててね、こっちを見たの、それで、それでね…」
どろだんごが、たくさんこっちをみてたの…
たくさん…
たくさん……
でもね、
お母さんの背中にも、ついてたんだ…
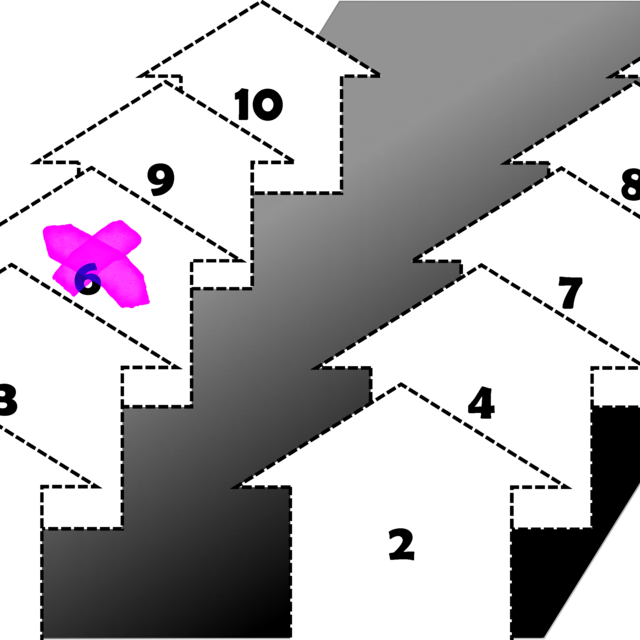




作者rano_2
ご無沙汰しております。また時間が空いてしまいました…
前作、分譲地の怪、オムニバス形式の第二話となっております!
前作含めて全十話、絶賛執筆中なので、是非楽しみにしていてください。
分譲地の怪、シリーズはこちらから。
{本編}
https://kowabana.jp/stories/36304
{オムニバス}
第一話
https://kowabana.jp/stories/36387