「不法侵入ならまだしも、器物破損とは…」
アキラは割られた窓ガラスと、辺りに散乱したガラス片を見て嘆いた。
「なによいまさら。これくらいの小さい罪…、怖気ついたの?」
喟然と嘆息をもらしたアキラは呆れながら言葉を返した。
「犯罪に小さいも大きいもない。それに臆してもいない。手段が手荒だと呆れている」
現在、甘瓜美波、秋永九十九、護摩堂アキラの3人がいるのは旧校舎の通用口、先日美波と九十九が侵入の際にガラスを叩き割ったあの場所である。
あの時は陽が傾き薄暗くはあったが、まだ中の様子が確認できた。しかし今はその一切が窺い知れなかった。
「そういえば、遊輔君と沢さん大丈夫かな」
九十九はここにいない大神遊輔、沢カレンの事を気にかけていた。
「少なくとも、魔夜中に侵入を試みようとしてる我々よりは安全じゃないかな。化け物がアウトドア派でもない限りは」
何故2人が今ここにいないのか。それは先刻、0時を告げる鐘の音が響いた直後、旧校舎の外壁から突如として現れたカレンが原因であった。
彼女は自分に降りかかった悪夢を端的に説明したのち、人に出会えた安堵感からか、緊張の糸がほぐれ、堰を切ったように涙をぼろぼろと流し、遊輔の足にしがみついてそのままわんわん泣き出してしまったのだ。
詳しい事情を訊こうにも泣き止まず、呂律の回らない彼女との会話はままならず、しかしこのまま放置するわけにもいかずに皆が困り果てていると、
「とりあえず落ち着いたら僕が家まで送るよ。それが済んだらすぐ戻ってくるから」
と遊輔が提案するので3人はそれを吞むことにした。出鼻を挫かれたようでアキラは不服そうであったが、3人は遊輔にカレンを任せて、先に魔夜中への侵入を試みる運びになった。
「それより覚悟はできてる?多分、もういちいち眠らなくても魔夜中へは侵入できる、はず。カレンさんが出入りできたなら、私達にだってできるはず。とにかく私が最初に魔夜中へ入るから、あなた達は後からついて来て」
美波はそう言うと、ひとり通用口の扉へ向かって行った。
「あ、甘瓜さん。最初はやっぱり僕が行くよ…」
「今そういう男らしさとかいらない。黙ってついて来て」
美波に気圧された九十九は唯々諾々と従うしかなかった。
―——ヘタレ陰キャの秋永君。
先程のアキラの言葉が身に沁みる。
「しかし、本当にこんな簡単な方法で魔夜中へ侵入出来るのか?」
アキラの問い掛けに美波は振り返り、
「旧校舎の中と外が現世と魔夜中の境目だとしたら、旧校舎へ入ることがイコールで魔夜中へ侵入することになるのよ。多分」
「もしそうだとして、侵入して一体どうするつもりだ?何か算段があるんだろうな」
「ない」
「考えなしに飛び込むのか?君ね、それは無謀だよ。てっきり何か計画があるのかと思っていたが、思いつきで行動をするのは利口とは言えないな」
アキラ合理的で論理的な行動を好む。だからこういう計画性のない人間が解せないのである。
「無謀とか利口とか知らないわよ。私は1日でも早く魔夜中から解放されたいの。嫌なら帰ればいいでしょ、堅物。なに?臆病なの?」
「慎重なだけだ」
二手に分かれてから2人はこんな調子だ。九十九は先程までの和やかムードを懐かしく思い、
———あれ以来、甘瓜さんの笑顔を見てないなあ。
と、心の中で嘆いた。
「もういい。行くわよ」
美波の言葉に2人は息を呑む。そして彼女は勢いよく通用口の扉を開き、中へ飛び込んでいった。校内に侵入した美波を2人は黙って見つめていたが、…反応がない。痺れを切らしてアキラが口を開いた。
「…侵入出来たのか?てっきりSF映画の様な、異次元の向こう側へ行くイメージを持っていたから、扉を潜った瞬間に姿が消えるものだと思っていたが…。」
「どうなのかな…?あ、甘瓜さん?」
九十九が呼び掛けたが反応がない。
「…甘瓜さん!」
再度呼び掛けるも応答はない。
「…まさか、侵入出来たんじゃないのか」
「なら急いで僕達も…!」
九十九は慌てて美波の元へ駆け寄ろうとしたが、同時に彼女が勢いよく振り返って、悄然とした表情でぼそりと、
「なんで…?」
その様子を見るに、どうやら魔夜中への侵入は失敗したらしい。
「となると、旧校舎の内と外が現世と魔夜中の境界線という線はハズレだな。やはり夢を見る以外に侵入する方法はないのか」
「ならどうして沢さんと松井君は魔夜中へ侵入出来たんだろう」
「さあね」
「遊輔君がいる時に話してたけど、ゲームみたいに入り口を開く為のキーアイテムが必要なんじゃないかな?」
「もしそうだとしたら、沢さんか松井君のどちらかがその鍵を持っていた事になるじゃないか。それに魔夜中常連の甘瓜さんなら、顔パスで入れそうなものだがね」
「なら校舎内のどこかの教室が、魔夜中に繋がってるんじゃないかな?」
「じゃあこの広い校舎の教室ひとつひとつを調べて廻るのか?そんな事をしていたら夜が明けてしまうぞ。まったく…。地獄の釜の蓋が開いたんじゃなかったのか」
九十九とアキラがあーだこーだ言い合っていると、美波がぼそりと呟いた。
「…校長室」
「なに?」
「校長室に行きましょう」
「何故?合理的な理由がないのなら同意しかねる」
思えば、アキラのこの上から目線の態度が、2人の間に流れる険悪ムードの原因なのかもしれないと、九十九は思った。しかしそんな上から目線に臆することもなく、彼女は言ってのけた。
「なんとなく」
〇
通用口へ向かう3人を見送った後、遊輔はカレンが落ち着くまで直立不動のままだった。彼女が足にしがみついて離れないので、動くに動けないのだ。
しかし、女性とあまり縁のない彼にとって、こういう状況でもいささか胸が高鳴るもので、なにより弱りきった女性にこうして泣きつかれると、「自分は頼られているんだ」と、男としての優越感みたいなものがふつふつ沸き上がってくるようで、悪い気がしなかった。
しばらくして嗚咽もなくなり、鼻をすする回数も減ってきて、遊輔は彼女に声をかけてみた。
「沢さん、大丈夫?」
彼の問い掛けに彼女は小さく、「…うん」と頷いた。
「そっか。念の為訊くけど、今から一緒に旧校舎に入る気は…」
彼女は大きく首を横に振った。その時、ズボンを引っ張られてずり落ちそうになるのを、遊輔は慌てて手で押さえた。なるべくならすぐにでも3人と合流したかったが、どうやらそれは難しいようだ。
「じゃあ、帰ろうか。家まで送るからさ」
彼女はまた小さく「…うん」と頷くと、ゆっくりと立ち上がり、今度は彼の腕にしがみついた。ぞんざいな振られ方をしたとはいえ、まだ美波に想いを寄せていた彼だったが、その甘味な感触に心が傾きかけてしまいそうになる。
だがそこは、グッと堪えて前を見据え、彼は一歩を踏み出した。そしてカレンは力なくそれに付き従った。
旧校舎の周囲は街灯もなく、夜道を進むには月明かりだけでは心許なかった。晩秋の肌寒さが身に沁みて、風もなく、静寂が遊輔達に纏わりついているような、とても静かな夜だった。
「沢さん、寒くない?」
「…うん」
「歩くペースちょっと速いかな?もう少しゆっくり歩こうか?」
「…ううん」
「そっか。疲れたら言ってね」
スマートフォンの明かりを頼りに、2人は徐々に旧校舎から離れていく。静寂に吞まれないように、遊輔はカレンに話し掛け続けていたが、未だに会話はままならず、彼の問い掛けに一言返事をするだけで、彼女はずっと俯いたまま陰々滅々としていた。
時々彼女がよろけて遊輔に体を預けるたび、甘い香りが彼の鼻をくすぐり、また心が揺らぎそうになる。年頃の男子にとって、それは果実酒の様に魅惑的な香りだった。
———そういえばあの時も、この香りよりも強い香りに誘われて、あの墓地へ…。
その時、不意に後ろに引っ張られて体勢を崩しそうになった。見るとカレンが立ち止まったらしく、遊輔は彼女が疲れて休みたいのだと、そう思った。
「あ、大丈夫?疲れたなら少し休もうか。でも、この辺ベンチとかないし…」
「気水となにしてたの」
遊輔の言葉を遮り、カレンは重く、低い声で彼に言葉を投げ掛けた。
「…えっ」
遊輔の腕を握る彼女の手に、徐々に力が込められていく。ただならぬ雰囲気に遊輔の首筋を汗が伝っていく。
「私さ、あんたと気水が旧校舎に入っていくの見たんだよね。教師と生徒が密会。私さ、気水嫌いなの。目障りだったの。それでさ、あいつ追いつめて学校辞めさせるために、ユウタと一緒にあんた達の密会現場を写真に収めてやろうと思ってた。
それで旧校舎に侵入して、あんた達探してたら、ユウタがいなくなった…。ユウタじゃなくて、キモいバケモノがいた。あいつ私を殺そうとした。ずっと逃げ回って、…せっかくユウタ見つけたのに、ユウタ連れてかれて…。
…ねえ、なんであんた達あそこにたむろしてたの?4人でなにしようとしてたの?なにか知ってるの?…なんか知ってんのかよ」
ぼそぼそと呪いでもかけるような鈍い口調だった。彼女は突然顔を上げると、鬼の形相で憤然と叫んだ。
「私がこんな目にあったのおめぇらのせいかよ!」
爪が喰い込み、肉が引き裂かれそうだった。彼女の目は血走り、髪は乱れ、傷口からまた血が滲んでいた。
「さ、沢さん、落ち着いて!せっかく止まってきたのに、また血が…」
突如豹変した彼女に周章狼狽する遊輔は、情けなく諭すことしか出来なかった。
「僕達は何もしてない!今もこうして君を助けようと…」
「嘘だっ!じゃあなんでッ———」
彼女は急に黙ってしまった。そして何かを探すように、キョロキョロと辺りを見回し始めた。
「さ、沢さん?」
「…ユウタ」
「えっ?」
「ユウタの声がする。呼んでる。いるって…、ここにいるって…」
カレンはそう言うが、しかし遊輔にはその声は聞こえなかった。
「沢さん、何言って———」
彼女は遊輔の言葉に耳を貸さず、踵を返すと旧校舎へ駆け出してしまった。
「ユウタ!ユウタ!」
「沢さん待って!」
慌てて後を追ったが、彼女は信じられない速さで、みるみる遠ざかって暗闇へ消えていく。遊輔は不意に、アキラの言葉を思い出していた。
———何者かによって、そうせざるを得ないように動かされているのかもしれない。
カレンは何かに取り憑かれたように、そして遊輔は何者かに導かれるかのように、再び旧校舎へと引き戻されるのであった。
〇
「スマホ」
一言、美波は九十九に向かって手を差し伸べた。
「えっ?」
「暗いから、明かり。スマホで照らせるんでしょ?」
なるほど。と、九十九は彼女にスマホを差し出した。美波がぺたぺたとあちらこちらに触っていると、反応して画面が光り、彼女の顔が美しく照らされた。
「…弱くない?」
「ああ、いやそれはライトじゃなくて…」
校内は朽ちた木材とカビの嫌な臭いが充満していた。スマートフォンの明かりでぐるりと周囲を照らすと、漂う埃が光を反射して、それが少し幻想的であった。
「校長室、場所は分かっているのか?」
「校長室ってだいたい2階にあるイメージだから、とりあえず2階に行きましょう」
「分かっていないんだな…」
以前訪れた際、校舎の中心に洋館でよく見るような、踊り場で両端に分かれた豪奢な階段を美波と九十九は目にしていた。なのでとりあえずはそこへ向かう事になった。
「では校長室に向かおうか。先導、頼むよ」
「…その前に」
美波は振り返ると、2人の目の前に立ちはだかるように仁王立ちでアキラを見据え、
「あなた、なんで今回の件に関してやたらと詳しいの?大神くんの家のことや、学園の創立に関わることも、それに関する校長と大神家の間にある因縁のことも。自分の家の事ならともかく、独自で調査をしたっていうけど、あなた一体どこまで首を突っ込んでいるの」
「むしろ君達は何も知らずに首を突っ込んでいたのか?」
「知りたいから首を突っ込んでるの」
再び険悪ムードが戻ってきてしまった。2人とも物腰を柔らかく、謙虚な姿勢で話すということを知らないらしい。
「訊くならさっきいくらでもタイミングはあっただろう。何故今更」
「大神くんがいたから…」
「気を遣って?彼の気持ちを蔑ろにしておいて」
「それとこれとは話が別」
気を遣って、というよりも、美波は遊輔に掛けられた呪いのほうを恐れていた。狼へ変貌する条件が本人ですら曖昧な今の状態で、例えば大神家の凄惨な過去を知ったらどうなるだろう。
勘違いとはいえ、美波と九十九の睦事手前の現場を目撃して心が揺らぐような彼が、果たして自分の心の許容範囲を超えるような事実を知ってしまった時、それで理性も自制もきかなくなったら…、と想像して、遊輔の前でアキラに問い詰める事を憚っていた。
だから一時的に、遊輔と別行動を取れたのは美波にとって好都合だった。
「まあまあ、2人ともそんな怖い顔せずに、落ち着いて話し合おうよ。とりあえず校長室に向かいながら、ね?」
九十九が2人の間に割って入ると、美波が渋々といった感じで、「なら歩きながら話しましょう」と、正面に向き直って歩き出した。
———先が思いやられる。
と九十九が嘆息をもらすと隣にいたアキラが、
「彼女、僕が嫌いみたいだから、君があいだにいてくれ」
と、背中を押した。それから美波を先頭に、九十九、アキラの順で校長室を目指した。
「で、なんでやたらと詳しいの?」
アキラは深くため息をついた。どこから話そうかと、顎に指を添えて少し考えた。
「…きっかけは我が家の過去、歴史について興味を持ったのが始まりだった。代々祈祷師を生業にしてきた護摩堂家が、何故その一切を捨てて医療の道に転じたのか。両親や祖父母に訊いても、安定して暮らしていく為にそちらの方が都合が良かったのだと、はぐらかされて過去の仔細を全く話してくれなかった」
美波が教室の方に明かりを向けると、「調理実習室」と書かれた白いプレートが目に入った。廊下の先を照らすと、スマートフォンの明かりでも果てが見えぬほど、校内は暗闇に支配されていた。
「だから自身で調査する事にした。両親や奉公人の目をかいくぐり、邸内にある開かずの蔵に侵入し、そこを隅から隅まで調べた。そこで見つけたのが明治時代、鳳徳学園設立に伴い護摩堂家、並びに大神家に起きた陰惨な事件について。そしてその際、悪魔によって掛けられた醜い呪いについてが記されていた文書だった」
調理実習室を通り過ぎると理科準備室があった。中を照らすと奥に人体模型と骨格標本が鎮座していた。長い間放置されいる割にはだいぶ綺麗だった。
「呪いって、具体的にはどういう事が書かれていたんだい?」
訊ねたのは九十九だった。
「具体的にと言われると、少々難しい。何せ紙の劣化が激しくて、肝心のところでページが破けていたり、字が掠れていたりで、恐らくあの蔵から今回の件に関して得られた情報は5割にも満たないだろうな。もしくはそれ以下か…」
理科準備室を過ぎれば、当然ながら理科室がある。暗幕が閉め切っている為か、中は闇に包まれていた。光を向けると、室内は不気味なほど整然としていて、まだ理科室としての役割を充分に果たせそうであった。
「じゃあ、さっき旧校舎の前で話した事がアキラ君の知っている全てだったのかい?」
「いや、それだけじゃない。蔵の中にあったのは文書だけではなく、4本の掛け軸があったんだ」
「4本の掛け軸?」
「それぞれ狼、蝙蝠、鳳凰、死神が描かれた4本の掛け軸。文書を全て読み解いた上で推察するに、狼は大神家の事を指し、蝙蝠は護摩堂家を指す。だが問題は残りの2つだ。これはつまり、護摩堂家と大神家以外にも呪われた家系があるということだ」
「だからアキラ君は、校長先生と八島さんをマークしていたんだね。どちらかが鳳凰と死神の呪いを掛けられていると…」
「と思っていたのだが、もしあの2人が呪いを掛けられた一族だとしたら、いささかパズルのピースとしてはしっくりこない。どちらかといえば、パズルを納める為の額縁か…。それよりも僕が気になるのは———」
「待って」
ずっと黙っていた美波が口を開いた。
「なんで校長と八島ってやつが怪しいと思ったの?」
美波は再び仁王立ちで、これでもかとライトの明かりをアキラに向けた。アキラは眩しそうに眼を細めながら、
「文書の中にヘンリー・ウィルソン、八島清右衛門の名が記されていた。前後の文章は残念ながら判読出来なかったが、明らかに校長と八島の先祖だろう。今の所、僕は呪いの原因がその2人にあるのではないかと睨んでいる。…もういいかな?眩しいからやめてくれ」
美波はぷいっと向き直り、再び歩きだした。
「そういえば校長先生と八島さんの会話の中で遊輔君と甘瓜さんの名前が出てたんだよね?それってどういう事だろう」
「僕もそれが気になっていたんだ。特に甘瓜さん、君は魔夜中の常連だ。現場経験のある君からも、是非とも詳しい話を…、どうした?」
美波が突然足を止めた。
「甘瓜さん、どうかしたの?」
「…調理実習室」
美波は「調理実習室」と書かれたプレートをじっと見つめていた。
「その教室がどうかしたの?」
「調理実習室って2つもあるものなの?」
2人には質問の意図があまり理解出来ず、互いに目を合わせて首を傾げた。
「聞いた事はないけど、これだけ広かったら2つあってもおかしくなさそうだけど…」
九十九が言い終わる前に、美波は急に走り出してしまった。2人が慌てて後を追いかけると、美波が教室の前で立ち止まって教室の名前が書かれたプレートを見ていた。
「見て」
追いついた2人に美波が言った。言われ通り見上げると、そこには「調理実習室」と書かれたプレートがあった。それを見て2人は美波が言いたい事を理解した。
「理科室は第一、第二って2つあるのは普通だけど、調理実習室が2つあるのは変だと思ったの。そしてこれで3つ目…。あのね、さっきから調理実習室、理科準備室、理科室の繰り返しなの」
美波が廊下の先を照らすと、相変わらず果てのない闇が続いていた。
「いや、待て。もうひとつ不可解な事が起こってる…」
アキラの言葉に2人が振り返る。彼は唖然として後ろを、自分達が通ってきた廊下を見ていた。2人もその光景に慄然として目を見張った。こちらも同様に廊下が延々と続いて、果てが見えぬ程の深い闇に染まっていた。
アキラは慌てて窓から脱出を試みたが、引こうが押そうがびくともしなかった。その時、窓の外を見て驚愕とした。黒一色に染まった夜の空に、深紅に煌めく巨大な月が浮かんでいたのだ。
「魔夜中だ…」
美波が呟いた。
「まさか…っ!一体いつ入ったんだ?なんの前触れもなかった。お前達が何かしたんじゃないのか?」
「僕は何もしてないよ!アキラ君が何か言ったんじゃないの?」
「ぺらぺらペラペラ喋ってるから、扉を開く呪文でも言ったんじゃないの?」
魔夜中へ侵入するつもりが、魔夜中に捕らえられてしまい、全員が周章狼狽していた。
「僕が何を言った?君が訊くから答えただッ…、がっ、アッ…」
アキラはまるで何かに首でも絞められたように、声を発する事が出来なくなってしまった。しかし、美波と九十九は彼がどうしてそうなったのか理解出来た。
突如として空気が3人に重く、重くのしかかった。全身が総毛立つほどの悪寒を、気配を全員が感じとっていた。
———背中…、後ろ…、背後だ…。
———ずるっ
全員がその音を聞いた。何かを引き摺るような、不気味な音。
———ずるっ
恐怖で動く事が出来ないのか、それとも金縛りにでもあっているのか、3人は指ひとつ動かせなかった。それをあざ笑うように額から汗が溢れ、頬を伝い、首筋を通り過ぎるとワイシャツの襟に吸い込まれていった。
———ずるっ
最初に動いたのは九十九だった。ゆっくり、ゆっくりと音のする方を振り返る。
———ずるっ
闇に紛れたそれは、赤い月明かりに照らされて不気味に姿を現した。自分達よりもはるかに巨大で、南瓜のように醜く腫れあがった頭部。手に持った鎌は紅蓮の炎を纏い、悍ましく鈍い輝きを放っていた。間違いない。魔夜中で幾度となく美波を襲ったあの化け物だ。
———ずるっ
九十九は不意に化け物の左手に視線を向けた。何か手に持っている。
「…ヨこ。…こニい…。るよコ…」
それは腹話術の人形のように、カタカタと口を開閉させていた。
「コに…。イるヨ…。こコに…」
まるで誰かに呼び掛けるような、しかし無機質で抑揚のない声。
「いルヨ…。ココにいるヨ…」
九十九はあれをカレンと一緒に魔夜中へ迷い込んだ、松井ユウタだと判断した。恐らくああして彼女をおびき寄せているのだ。
———ずるっ
「コこニ…。イるよ…」
鈍足だが、しかし化け物は着実に距離を縮めていた。
———このままじゃ僕達もああなる!殺される!逃げないと!
そんな事を考えるよりも先に、九十九は美波の手を掴んでいた。そしてアキラに向かって腹の底から叫んだのだ。
「走れ!!」
その言葉に、アキラは金縛りが解けたように体の自由を取り戻し、無我夢中で走り出した。美波も同様に、九十九に手を引かれながら必死に走った。果てのない、延々と続く廊下をひたすらに走り続けた。景色の変わらない魔夜中の廊下を…。
理科室。理科準備室。調理実習室。理科室。理科準備室。調理実習室。理科室。理科準備室。調理実習室。理科室。理科準備室。調理実習室。理科室。理科準備室。調理実習室。理科室。理科準備室。調理実習室。理科室。理科準備室。調理実習室。理科室。理科準備室。調理実習室。
どれだけ走ったのだろう。背後から気配が消えた気がして、アキラが少しスピードを落として後ろを確認した。
「待て、いないぞあの化け物」
その言葉で全員が走るのをやめて後ろを見た。
「はあ…、逃げ切れたのか?」
「はあ…、正直この一本道では、っ…、逃げ切ったというよりも、距離を取ったと言った方が正しいな…。じっとしてたら追いつかれるぞ」
アキラが歩き出し、九十九もそれについて行こうとすると、
「待って…、もう少しっ、…ッ、休ませてッ…」
美波が息絶え絶えに訴えた。
「ここでじっとしていたら追いつかれるぞ。休んでいる暇はない」
「逃げるって…、一体どこまで、逃げるのよッ…」
美波の言う通り、これだけ呼吸が乱れるほど走り続けたにも関わらず、未だに廊下の果てに突き当たる気配もなく、同じ教室が繰り返し続いて、果たしてこのメビウスの輪のような廊下を、一体どこまで行こうと言うのか。
「アキラ君、一旦教室に隠れて息を整えよう。色々と急展開過ぎて、少し状況を整理したいし」
確かに色々と急であった。なんの前触れもなく、知らぬ間に魔夜中へ足を踏み入れ、まるで待ち構えていたかのように鎌の化け物が現れた。
———何者かによって、そうせざるを得ないように導かれているのではないか…。
だとしたら自分達はまさに、飛んで火にいる秋の虫だ。
「仕方ない…」
アキラは渋々その提案を呑み、目の前の理科室の扉に手をかけた。
「もしかしたら教室の窓からなら脱出出来るかもしれない。沢カレンに出来たのなら、我々にだって———」
アキラの意に反し、扉がひとりでに開くと、暗闇から腕が伸びてアキラの手首を掴んだ。
「なッ———」
骨と皮だけの黒に染まった腕は、瞬く間にアキラを理科室の中へ連れ去ってしまった。
「…ア、アキラ君!」
九十九はすぐに反応出来なかった。少し遅れて彼を追いかけようと理科室へ向かったが、それを遮るように無数の蝙蝠が理科室から飛び出し、九十九達に襲い掛かった。
そしてピシャリとひとりでに扉が閉まると、九十九達に纏わりついた蝙蝠はまるで役割を終えたように三々五々に散っていき、魔夜中に2人だけが残された。
「…あ、追いかけないと!」
九十九はアキラが呑み込まれた理科室へ入ろうとしたが、美波がそれを制止した。
「秋永くん待って!」
「待てって、なんで…。アキラ君が…」
その時、九十九は美波が自分の手をぎゅっと握りしめている事に気がついた。か細く、小さな手は恐怖に震えていた。表情には出さないが、彼女は怯えているのだ。
あの日、旧校舎に連れていかれた日の事を思い出す。窓から差し込んだ西日に照らされた、彼女の鳶色の瞳。あの時も彼女の瞳には恐怖による動揺の色が見てとれた。しかし、
「離れないで。ここで別々になったら、私達まで闇に呑まれて、帰ってこれなくなる…」
恐怖に怯える瞳の裏には、敢然とした覚悟の色が滲み出ていた。
「だから、行くなら2人で一緒に…」
美波は九十九の隣に並び、教室の扉を真っ直ぐ見据えた。そして2人で扉に手を掛け、呼吸を合わせて声を上げた。
「せーのっ!」
〇
遠くでガラスの割れる音がした。
恐らくカレンが窓を割って旧校舎に侵入したのだろう。しかしあれだけ嫌がっていたのに、一体どういう風の吹き回しなのか。遊輔は女というのはなんて難しい生き物なのだろうと、愁然とため息をもらした。
旧校舎に戻ってきて、遊輔はまず最初に違和感を覚えた。建物に対して使う言葉ではないが、旧校舎が大人しい、そんな感じがした。まるで眠りについているように静かだった。
普段なら誰も立ち入らない旧校舎だから、静かで当たり前だが今日は違う、校舎内には美波、九十九、アキラ、そして今しがた侵入したカレンの4人がいるはずなのに、校舎から人の気配が一切しない。
不意に乱暴に破壊された窓が目に入った。カレンはここから侵入したらしい。よく見るとガラスに血が付着している。恐らくカレンの血液だろう。ただでさえ怪我が酷いのに、傷の上に傷を作るようなまねをするなんて、何を考えているのか。
遊輔もそこから校舎内に侵入すると、スマートフォンの明かりを頼りにまず医務室を探す事にした。1階を歩き廻っているとそれらしい場所を見つけた。教室の前の掲示板には随分と古い医療関係のポスターや、インフルエンザの予防を呼び掛ける校内新聞が貼られている。
たいしたものはないかもしれないが、カレンの為に何か使えるものがあればと、扉に手を掛けようとしたその時だった。
「せーのっ!」
という掛け声と共に扉が勢いよく開き、医務室があるはずの教室にはこちらと同じ廊下があって、そこに仲良く手を繋いだ美波と九十九がいたのだ。
遊輔は驚きのあまり声を上げて飛び上がった。美波と九十九は遊輔の再会を喜ぶよりも先に、急いでこちらにやって来て勢いのまま扉を閉じた。
「で、出られた?」
「分からないけど、多分」
遊輔は状況が掴めず、ひとり取り残されていた。
「2人ともどうしたの?それよりもなんで、ここ医務室だよね?」
遊輔の問い掛けには九十九が答えた。
「僕ら、今まで魔夜中にいたんだ。それで鎌を持った化け物に追われて、逃げてる最中に、アキラ君が教室の中に引きずり込まれて…、それで」
そこで遊輔はアキラがいないことに気がついた。
「引きずり込まれたって、一体どこに?」
「分からない。引きずり込まれた教室の扉を開いたはずなのに、何故か現世の旧校舎に…」
「待って…、違う」
美波が愕然として一点を見つめていた。2人もそちらを見ると、深紅の月が燦然と空に浮かんでいた。
———ゴーン、ゴーン、ゴーン…
突如として響く鐘の音に、3人は戦々恐々とした。特に美波と九十九は千変万化する魔夜中の脅威を肌に感じていた。
———ずるっ
鐘に紛れて聞き覚えのある音がした。
———ずるっ、ずるっ、ずるっ
音は確実にこちらに向かっている。
———ずるっ、ずるっ、ずるっ
「遊輔君、多分鎌の化け物だ。僕達じゃ勝ち目がない、逃げよう」
九十九が走り出すと、美波もそれについて行った。が、しかし、
「遊輔君?」
遊輔はただ前を見据え、その場から動こうとしなかった。九十九が再度呼び掛けても、それでも彼は振り返らなかった。
「僕があいつをなんとかする…」
何を言い出すんだと、九十九は遊輔の元へ駆け寄った。しかし、遊輔の意思は固かった。
「化け物には化け物だ」
遊輔はそう言ってちらと美波を見た。
———ずるっ
暗闇から姿を現した化け物はゆっくりと、じりじりとこちらへ向かってくる。
「変われ…、変身しろっ…」
遊輔は自分に掛けられた呪いを利用するつもりだった。大神家の一族に掛けられたその呪いで、愛する人を守る為に。
———ずるっ
遊輔は両手を強く握りしめ、自分に言い聞かせる。
「変われ…、変われっ…」
———ずるっ
しかし、遊輔の姿は一向に変わる気配を見せなかった。月は出ている。鐘も鳴っている。愛する人が他の男と仲良くしてる様を見せつけられて、これなら狼に姿を変えられると、そう思った。しかし…。
———ずるっ
遊輔は目を閉じて、心の中で叫んだ。
———変われ!変われ!変われ!
自分が狼になった姿を想像する。そして心の中で叫び続ける。
———変われ!変われ!変われ!
ひたすら心の中で叫び続けた。目の前に愛する人がいるんだ。自分がやらなきゃ誰がやるんだ。変われ、変われ。そう強く強く思いをこめる。
「———君!———輔君!」
———変われ!変われ!変われ!変われ!変われ!
「遊輔君!!」
はっとして目を開くと、眼前で化け物が大きく鎌を振りかぶっていた。遊輔は咄嗟に身を翻し、横に薙ぎ払われた鎌をすんででかわした。鎌は教室の壁を焼き崩し、辺りに焦げた木材や溶けたガラス片が散乱した。
化け物が再び鎌を振り上げる。
———だめだ、殺される
そう思った瞬間、
「大神くん!!」
美波の叫び声がして、遊輔は顔を上げた。しかし美波は名を呼んだはずの遊輔には目もくれず、真っ直ぐ九十九を見つめていた。
「あ、甘瓜さん?」
それは一瞬の事だった。美波が九十九の首に腕を回すと、彼の唇を強引に奪いにいったのだ。
———ドクンッ
その光景を目の当たりにして、遊輔の心臓が大きく脈打ち、全身に勢いよく血が巡っていくのが分かった。鼓動は加速し、身体中が熱を帯びていく。筋肉がでたらめに隆起し、身体がどんどん大きくなると、黒い毛が皮膚を覆っていく。
———ゴーン、ゴーン、ゴーン
鐘の音は鳴り続けている。その音と共鳴するように、狼に姿を変えた遊輔が深紅の月に向かって、悲壮に満ちた遠吠えを上げた。
〇
耳に突き刺さるような、けたたましい烏の啼き声がする。どれくらい気を失っていたのだろうか。とても気怠く、体が重い。ゆっくりと体を起こして辺りを見ると、どうやら墓地にいるらしかった。
———僕は、旧校舎の中にいたはず…。
気を失う前の記憶が判然とせず、思い出そうにも烏の啼き声が鬱陶しくて集中出来ない。
———甘瓜さんと、九十九君と一緒に化け物から逃げて…、それから?
見上げると月は赤く煌めいていた。どうやらまだ魔夜中にいるらしい。
———とにかく2人と合流しないと。
その時、ぴんと空気が張り詰め、一瞬にして音が消えた去った。慌てて耳に手をやると、音が聞こえなくなったわけではなく、どうやら烏の啼き声が一斉にやんだらしい。
それに取って代わるように、女性の啜り泣く声が聞こえた。振り返ると女性がひとり、膝を抱えこんで墓石の前で泣いている。鳳徳学園の制服を着ているようだが、少々デザインが違う気がした。
まさか魔夜中に迷い込んでしまった生徒ではないか。だとしたら、現世と魔夜中を繋ぐ扉が開きかけているという推測が当たっている事になる。
「君、鳳徳学園の生徒だね?僕は生徒会長の護摩堂アキラだ。君の名前は?」
女性は問い掛けに反応するように、泣くのをやめた。そしてゆっくり、ゆっくりと顔を上げた。
アキラは思わず言葉を失った。その日本人離れした仙姿玉質な顔立ちは、一度見たら忘れる事はないだろう。だが、アキラは彼女に見覚えがなかった。
完全に表情が露わになると、原石を散りばめたように美しく輝いた瞳がアキラを見つめた。そして果実のように潤った淡い桃色の唇がゆっくりと開き、
「私の名は………」
続く


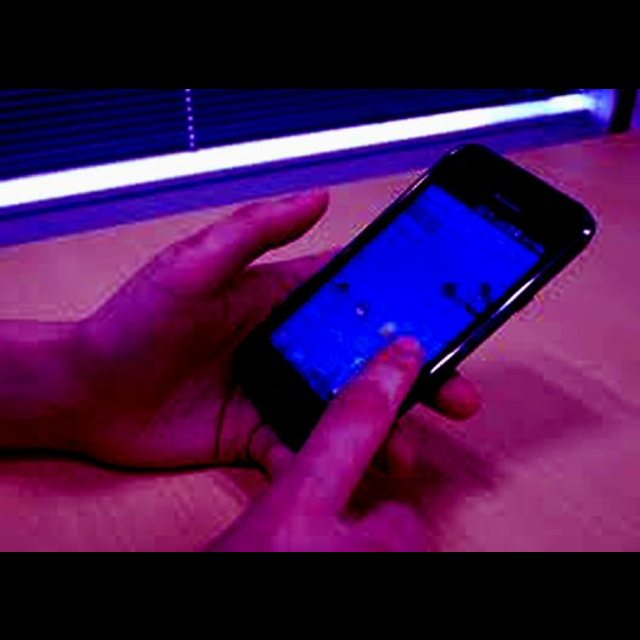



作者一日一日一ヨ羊羽子
本作品は、掲示板にて行われている「第四回リレー怪談 https://kowabana.jp/boards/38 」の第6話です。
第7走者は綿貫一様になります。お楽しみに。
第1話 : ゴルゴム13様
https://kowabana.jp/stories/35392
第2話:五味果頭真様
https://kowabana.jp/stories/35416
第3話:ロビンⓂ︎様
https://kowabana.jp/stories/35444
第4話:rano_2様
https://kowabana.jp/stories/35448
第5話:あんみつ姫様
https://kowabana.jp/stories/35481
第6話:ここ
以下、リレーに関する注意事項です。
注1、
本作の趣旨は、有志11名によるリレー形式でひとつの「怖話」をつくることです。
参加者多数のうえ、全体でかなりの長編になりますので、ところによっては怖さが控えめになる場合もあるかと思いますが、あくまで当初の目的としては「怖話」を目指すものであることをご理解いただけますと幸いです。
注2、
本作はアワードの対象からは辞退申し上げます。
また、リレー小説参加者は投稿作品に対して「怖い」ボタンを押すこと、およびコメントを書き込むことはいたしません。
注3、
企画に対してのお問い合わせやご質問につきましては、企画の窓口であるゴルゴム13・ロビンⓂまでご連絡ください。
本作の掲示板、およびリレー小説参加者個人のページでのお問い合わせやご質問は、ご遠慮下さいますようお願い申し上げます。