ーー 晩。
僕(秋永九十九)と遊輔、アキラ、その三人であの校舎に向かう。
到着すると、僕達三人は今までにない違和感に気付く。
ゴーン!、と旧校舎の鐘の音が地鳴らしのように冷たく激しくなり響いていたから。
まず口を開いたのはアキラだった。
「あれ?おかしい…」
同時に遊輔も同じく違和感を抱く。
やはり、二人共、僕と同じ意見のようだ。
本来この鐘の音は魔夜中にしか鳴らない筈、現実世界では決して聴こえる筈のない音だったから。
僕達は恐る恐る旧校舎の中に脚を運ぶ。すると、目の前の大きな階段の上に真っ赤なドレスの女性が薔薇の背景を模している薄いステンドグラス越しに立ち往生している。外の赤い月に照らされながら。
恐らく見えているのは僕だけではない。二人も僕と同じように息を呑んでいる。
それもその筈、なんせ今目の前にしている女性の姿は魔夜中でしか生存を確認出来ないから。何故、どうして現実の世界で…と僕達は目を凝らしてその女性を凝視した。後ろ姿で判断するに、金色の長い髪は、もしかすると日本人ではないかもしれない。そしてその女性はこちらの存在に気付いていないのか、背景の赤い月をぼーと眺め、立ち往生している。
そして数秒の時が経ち、突然その女性は僕達三人に向けているのか、小さく溜息をついた。そして言葉を発する。
「はぁ…なぜ来たのだろうか…このままそっとしていれば私が母の魂を呼び戻すという人々の希望に沿う末路を送れたというのに…まぁ、それで終わりと言う訳ではないのだけどね。それともこっちの結末の方を好むのかな」
僕達三人はその声に仰天した。姿形は異なるがその声の主は今まで散々耳にした聴き覚えのある声だったから。
僕は息が溢れるような声を上げて尋ねた。
「もしかして、甘瓜さん…?」
何故か赤いドレスを身に纏い、雰囲気がガラッと変わっていた。僕達は言葉が出なかった。口調もいつもの甘瓜ではない。一体なにが…そう考えていると甘瓜は僕の質問に答えた。
「ええ、でもそれは貴方達から見ればの話で、貴方達が考えている"甘瓜美波"とは少し違う」
「どういう事…?」
僕は聞き返す。すると甘瓜は目線を上にする。
「今聞こえているこの鐘の音、もう察しているかもしれないけど、魔夜中にしか鳴らない。それってどういう事だと思う?」
僕やアキラ、遊輔はいっそう混乱した。そして言葉を返したのはアキラだった。
「つまり…今が魔夜中って事?」
「まぁ、そう言ってしまえばそうかもしれない、でも、正確には違う。貴方達は根本的に勘違いをしているよ」
僕達三人はお互いに目線を合わせ、皆、困惑する。僕は小さく囁くように言葉を投げた。
「甘瓜さん…君は一体…?」
その言葉を受け、甘瓜は右腕を天に挙げた。すると、今まで聴こえていた鐘の音がピタリと止まり、場は静寂となる。
「遊輔くん、今、見えていると思うけど、何故貴方はあの赤い月を見て狼にならないと思う?」
遊輔は押し黙る。甘瓜が醸し出す謎の威圧に一同言葉が出ない状況だった。そして甘瓜は言葉を続ける。
「それは幻想に過ぎないのよ。狼、蝙蝠、鳳凰、死神、そんな力、全ては誰かが創り上げた幻覚の一部過ぎない…それだけじゃないよ」
そう言って甘瓜は挙げていた右腕をそっと降ろす。すると、次は奥の闇からカラカラと金属質な音を鳴らせながら何者かが近づいてくる。
それは夢で見たあの巨人だった。白い面を付け角が生えたバケモノ、そのバケモノはゆったりと甘瓜に近づく。
「ザンベト様…」
僕は咄嗟に口にした。なんだろうか、"してしまった"と言う表現が正解なのかもしれない。しかし、甘瓜が被さるように言葉を放つ。
「それも違う。それも誰かが貴方に植え付けた記憶の断片に過ぎない。辻褄が合うような配慮を施された、とでも言っておこうかな」
そして甘瓜の側まで来たバケモノは突然、その白い面を自身の鎌で打ち砕いた。その光景もまた非現実なもの、驚愕だった。
白い面が割れ黒い顔面からヌルヌルと何かの液体に塗られ二人の人物が排出される。見ると、その二人は八島弘とロビン・ウィルソンだった。そして、巨人は少し身体を小さくさせた。恐らく中にはまだ、複数の人間が閉じ込められているのだろう。
「さて、このバケモノ、ロビン・ウィルソンとは関係がない。そして私も、この八島の姿をした者の末裔でもなんでもない。それどころか、各々の末裔の展開も誰かが視せた幻想に過ぎない。仮に…仮にだよ、貴方達がこのまま旧校舎に訪れなかったら、さっきも言ったように、また違う結末を迎えていたでしょう。私自身でさえ、数々の分岐からの枝分かれを経て辿り着いた複数の甘瓜美波の一人に過ぎない」
甘瓜はそう言いながらゆっくりと階段を降りて来る。その赤いドレスによく似合う透明なガラスの靴をコツコツと鳴らせ、僕達に歩み寄る。
「ねぇ遊輔くん?あの時のカボチャ、マズかった?」
そう問い掛けると階段の上にいたバケモノがぎこちない動きでこちらに近づいてきた。そして、バケモノが甘瓜の隣にまで来て止まった。先程まで白い面が被さっていた部位は真っ黒で何も見えない、闇のような空間が広がっていた。甘瓜はそこに腕を捻じ込ませた。ぐにゃり、と肉を削ぐような擬音を鳴らせながら奥まで腕を這わせる。そしてその中から何かを取り出した。
「そ…それは…」
遊輔が震えながら声を出す。そう、甘瓜が取り出したのは、あの時、遊輔が噛みちぎった残りのカボチャのマスクだった。
「貴方はあの時、誰と戦っていたの?今の貴方はもう狼でも何でもない存在、ただの人なのよ。いい加減それに気づいて、さようなら」
甘瓜はそう冷たい声で蔑んだ。そして僕は遊輔に目をやった。すると、遊輔はその場で意識を失い倒れ込んでしまっていた。
なんだ?なにが始まっているんだ…僕は只管息を殺した。今見えているこの人物は本当にあの甘瓜美波なのか…?どれだけ思考しても現状を全く掴めない。
そして次はアキラに目を向けた。
「貴方はちょっと気付いてるんじゃないの?今までからここまでに至る肯定の愚かさを。"生徒会長"という役が与えられた貴方は、その優れた頭脳で今まで上手く場をナビゲート出来ていたと思う。でも所詮それだけの事、結果としてこの結末に辿り着いたと言う事は哀れと言う他ないね。さようなら」
遊輔に続いてアキラまでも、言葉を放つ暇もなく一瞬で気を失う。
そして最後、僕の方へ近づく、匂いは相変わらず惹きつけられるような甘い香りが漂うが、やっぱり僕が知っている甘瓜とは雰囲気が異なる。そして、そっと耳元で甘瓜は僕に囁く。
「あの時、私は何で貴方をこの旧校舎に誘ったと思う?私の腕のアザを見てどう思った?そもそも貴方が最初に夢で見た殺されかけた少女、どうして助けられなかったの?助けていたらまた違った結末を迎えていたのに」
甘瓜は畳み掛けるように僕へ言葉を投げる。
「そ…それは…」
「うん。そうだよね。だって毎回忘れちゃうんだからね…仕方ないよね…」
「忘れる…?」
「そう。貴方がここに至るまで一体どれだけの貴方が分岐したと思っているの?それなのに、貴方達はここへ訪れた。このタイミングで、ここへ至るという選択肢が完全に間違っていると言うのに」
何だ?何を言っているんだ…甘瓜の発言に僕は疑問しか生まれない。甘瓜は静かに言葉を並べてる様子だが、その中にほんの少しの苛立ちが混ざっているように感じた。
「考えてみて欲しい。全ては分岐なの。そして今ここにある分岐は本来辿り着いてはいけない、ある種イレギュラーな分岐なの」
「分岐…?イレギュラー…?甘瓜さん、さっきから何を言っているの…?」
すると甘瓜は静かに被りを振った。
「違う。そう言う事を言わせたいのじゃないのよ。いい?落ち着いて聞いて。貴方がこの物語の主体。それは抗えない真実なの。では、貴方以外の物語は誰が知ってるの?貴方は他の人達の過去をどのぐらい把握している?結局貴方自身もこの物語の一部しか知らないでしょ?」
「物語…?」
「そう。それはそれは数々の根深いもの、言わば、怨念、のような記憶、でもそれは貴方達の為に造られた物語ではない。その物語達は誰かの為の、誰かの手によって造られた空想の産物達。例えば、文化祭という貴方達に都合の良いイベントでこの物語を終えていれば、貴方達は満足していたでしょう。それでもね、それを不服と捉える人物も複数存在する。貴方達は文化祭の決行を望んでいた筈、それなのに、あろうことかここへ来てしまった。つまり、貴方達はこの物語の希望に抗おうとしていると言っても過言ではないよ」
そう言って甘瓜は僕から踵を返す。なんだか今発した甘瓜の言葉全ては僕に向けられて発した言葉ではないような気がした。どこか、遠くを見据えるような甘瓜の仕草、僕はぼんやりとその姿を見ることしか出来ない。僕から背を向け、甘瓜は言葉を続けた。それはどうやら僕に向けられた言葉のような気がした。
「秋永君、貴方はさっきも私が言ったようにこの物語の主体、だから貴方には時間を掛けて言葉を発したの。勿論、貴方も感じていたと思うけど、私の言葉は貴方だけに向けた言葉ではないよ。この物語を創り上げた複数の誰かに向けて、或にはこの物語の全貌を知り得る誰か、そしてこの物語から更に生まれる複数の結末を彩る誰かに向けてでもある」
「甘瓜さん…ごめん、やっぱり僕は甘瓜さんの言っている事がよくわからない。遊輔とアキラは今眠っているの…?それとも…」
「心配しないで。遊輔君もアキラ君も死んでしまった訳ではないから。それぞれまた正しい道になれるように時間を戻しただけだから」
「時間を…?」
甘瓜は静かに僕の方へ身体を向け、質問に答える。
「そう。時間をね…そうだね…例えるならゲームで言うセーブデータ、みたいなものかしらね。どうやらこの世界はやり直す事が出来るみたいなの。何回でも。でも繰り返した人々の記憶だけはこの世界では忘れてしまってるみたいなの」
僕は遊輔、アキラを一瞥して淡々と言葉を並べる甘瓜の方を伺う。そして自分の中にある一つの疑問を甘瓜に投げかけた。
「それで言うと…甘瓜さんは…?甘瓜さんはさっき複数の自分の分岐を経てって言ってたじゃないか。それって甘瓜さんには分岐の記憶が残っている事になるじゃ…」
すると、甘瓜はどこか微笑みを見せ僕の疑問に答える。
「いい所に気付いてくれたね。そう…何故か私だけ、分岐の記憶が残っているの。断片的にね…全部ではない。そして考えたの。それってある一定の条件を獲れば可能なんじゃないのかって」
すると甘瓜は再び僕の方へ近く。そして手を差し伸べた。見るとそこには小さな緑色の双葉が甘瓜の掌に添えられていた。
「双葉…この旧校舎に舞っているなんの変哲もないただの葉っぱ…何度か旧校舎に出入りしている内にたまたま身体に付着したんでしょうね。この葉っぱが何か明確な答えになるのかはわからないけど、一応貴方に渡しておくね。なにかの役に立つかもしれない」
僕は首を傾げながら差し出された小さな双葉を掌に乗せた。
「私の思い違いかもしれないけどね。でも現に今の私のこの姿に至った時、たまたまその葉っぱが付着していた事が事実として存在する」
「甘瓜さん…本当に君は何者なの?」
僕がそう訊くと甘瓜は少し間を空け、渋い表情を見せた。
「さぁ…正直私にも検討がつかない。私が誰なのか、そしてこの物語での私の役割とはなんだったのだろうか…色々と思考したんだけどね、結局正解となる答えは思いつかなかったよ。でもね…」
また少し間が空いた。甘瓜はどこかまだ言葉が纏まってない様子だった。
「でもね…一度事実だけで考えたの。そしたら二つの事実に辿り着いたの。まず、貴方がこの物語の主体…私はそう決め付けた。何故ならこの物語の冒頭は貴方から始まった。それがまず一つの事実。でもその記憶が何故か私にはある。それも不思議な事だよね。でもそこに意味があるとしたらどうかな…私には私の役割が必ず存在すると思わない?」
僕がこの物語の主体…それは甘瓜の口から何度も出るワード、僕自身、今まで意識などした事がない。いや、そもそもそんな事意識する者など居るのか?でも甘瓜の表情はそれがいかに真実であるかのような表情を浮かべている。僕は一体…?それとも僕という存在自体、本当に誰かに造られた空想の産物なのか…?
そんな事を脳裏に反芻させながら僕は甘瓜に質問をする。
「で…もう一つの事実は…?」
「もう一つは…私がさっき遊輔君とアキラ君にした事、言わば"記憶の改善"の機会を与えられると言う能力がある。実際貴方にも幾度と同じ事やったの。けれど、何度行っても貴方にはその記憶がない。その事もまだこの物語では語られていない。どういう事なのだろうね…私には検討もつかないよ…けどね、着実だけどもこの物語は終わりに向かっているよ。その貴方に渡した葉っぱ…もう一度見てごらん」
そう言われ、僕は掌を広げた。すると緑色の双葉から淡い光が灯っていた。
「これは…?」
「私はこの物語のループを何度も体験してきたその時、そのように葉っぱが光っていてね。恐らくそれはこの物語の記憶をキープ出来る物らしい。私が持っていても物語が一向に終わらない。だとすると他の者にそれを渡したらどうなるのか、私はそう思考するようになってね。だからこの物語の主体である貴方に渡したの」
「でも…そうすると、甘瓜さんは…?」
「そうだね。貴方が次、目覚めた時の"私"の今までの記憶は消えているだろうね。それでも私はもうそれに賭けるしか方法が思い付かないんだよ。だから、貴方に託すね。この物語を…この世界の全てを…」
そう言うと甘瓜は僕の方へ歩み寄った。恐らく、遊輔やアキラのように"記憶の改善"を行おうとしているのだろう。しかし、僕は戸惑っていた。本当にそれが正解なのか…本当にその役割が自分で正しいのか、そんな不安で胸が押し潰されそうだったから。
「もし…もしもだよ…甘瓜さんの仮説が間違っていたら…?」
「その時は…そうだね…また最初からやり直すしかない…またこの壮大な時間を掛けて、私がこの物語の仕組みに気付く所から…時間は掛かるけど何度でもね…」
なんだろうか、甘瓜の表情から本心が少し浮かんだ気がした。甘瓜から、もう私にこんな役割を押し付けないでくれ、もう考えさせないでくれ、そう言われているように視えた。そして僕は腹を括った。
「甘瓜さん…わかった。やってみるよ。甘瓜さんの賭け、僕が担ってみせるよ」
「ありがとう…恐らく私の思惑が正しかったとしても、残る記憶はあくまで断片的で全てとまでいかないと思うけど、それでも主体である貴方で終わらせて…後は…」
「後は…?」
甘瓜は恐らく頭の中で言葉を探している。自分が今まで積み上げてきたものを最後、僕に託す為だろう…どれだけの時間を経て辿り着いた甘瓜かはわからない…けれどその壮大な時間は甘瓜にとって並大抵の努力ではないだろうと表情で思い知らされる。だから僕は待った。この分岐の甘瓜の最後の言葉を…
「秋永君…本当の事を言えばね、私は一人でこの物語を解決する予定だったの。どうやらループさせるという指揮権は私にしか出来ない事だから。だからその途中に貴方達が割り込んで来た時、正直苛立ってしまったの。何度やっても終わらない…本当に終わらないこの世界、もういいや、って投げやりになった事だって何度もある。今でも、貴方にどれ程の力があるか私にはわからない。けどこの物語の主体である事から託してみる価値があるのかなって考えたの…いや、言い訳かな…、"疲れてしまった"が私の本心かな…だから託すと言うより、押し付けようとしているんだと思う。それでも貴方は頷いてくれる…?」
僕は顔を硬らせた。甘瓜が今まで行ってきた苦行の数々、恐らく僕にはその一部すら視えていないのだろう…甘瓜の表情には一抹の陰りしか浮かんで来ない。恐らく今甘瓜が行おうとしている賭けの成功率は微々たるものなのかもしれない。
"物語の主体"、それだけが僕にある特権なのだろうとしみじみ思う。甘瓜にとってその特権だけが糧になっているのだろう。正直、自信を持って、胸を張って、大丈夫などと言う言葉は僕には言えない。それでも多少なりとも希望があるとすれば…と僕は甘瓜の魂の叫びにコクリと頷いた。
最後に甘瓜は現状の報告と可能性を口にした。
「この物語の舞台は旧校舎、それは皆がこの校舎にこぞって集まるから。まるで惹きつけられるように…それに魔夜中という空間、それもこの旧校舎が舞台。多分そこに終わりを迎えるカギとなるものが存在すると思うの。それに本来、魔夜中は夢の中でしか視れない空間、現実世界でそれを具現化出来るのは私の特権の一つなの。それを覚えておいて」
僕は集中して甘瓜を見据える。そしてゆっくりと甘瓜は僕に手を差し伸べ、言う。
「"月島聖良"という人物もどうやら私と同じでこの醜いループを経験して記憶を開花させた人物の一人みたい。だから彼女もこの物語で重要な存在なのかもしれない。それを出来れば覚えておいて。後は…後は…そうだね…恐らく今の私と貴方が今後遭遇する事はないと思う。だからもう私から貴方に何かを助言する事は決して出来ない。貴方は一人でこの地獄とも呼べる世界を彷徨い続けて結末を見つけるか、或いは月島と遭遇するのも一つの案かもしれない。まぁ…いずれにせよ、この記憶も一部しか確保出来ないと思う。だから、最後に私から言える事は…秋永君…さようなら…」
甘瓜が手を翳すと僕の視界はボヤけた…どうやらこれから時間が戻るのだろう…薄い視界からは甘瓜がどこか切なく微笑んでいる姿が見える…それは、今後の希望を表しているのか…それとも…
ーー
どことも知れぬ薄暗い廊下を一人歩いていた。窓の外を見れば、不吉に輝く赤い満月が時計塔を照らし出していた。
なぜ僕はここにいるのか。ここはどこなのか。
分からない。何も思い出せない。
ただ、なぜだろうか、少し違和感を抱く、僕は掌に何かを握りしめていた。そしてそれをふわっと広げた。
するとそこには小さな緑色の双葉がポツりと存在していた。
ーー 魅惑の旧校舎(仮)
エンド2(可能性)
○
画面の前の少年は首を傾げた。なんだか終わりとしてはどこかもどかしい。そう感じた。よく見ると画面下にエンド2とある。という事は…そしてプレイ中ずっと気になっていた『魅惑の旧校舎』というフリーゲーム、ずっと(仮)と名付けられている。その事も少し気掛かりだと感じた。


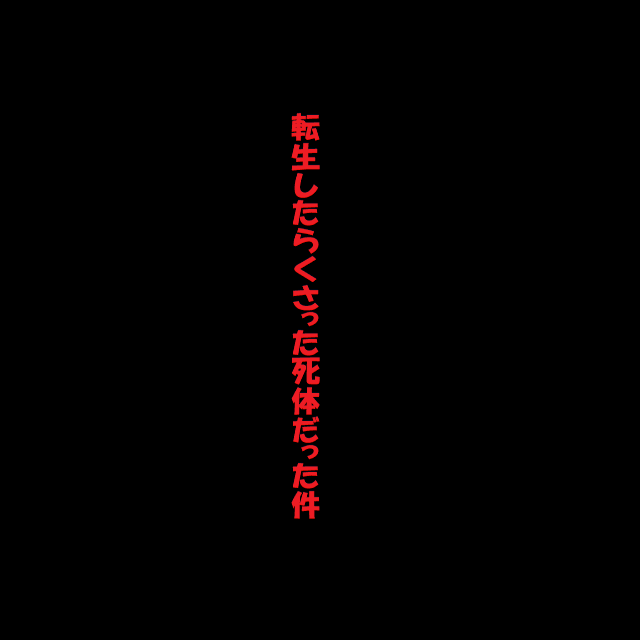
作者ゲル
本作品は、掲示板にて行われている第四回リレー怪談の第十話となります。
第一話 ゴルゴム13様(10/10投稿) https://kowabana.jp/stories/35392
第二話 五味果頭真様(10/17投稿) https://kowabana.jp/stories/35416
第三話 ロビンⓂ様(10/24投稿) https://kowabana.jp/stories/35444
第四話 rano_2様(10/28投稿) https://kowabana.jp/stories/35448
第五話 あんみつ姫様(11/7投稿) https://kowabana.jp/stories/35481
第六話 一日一日一ヨ羊羽子様(11/13投稿) https://kowabana.jp/stories/35497
第七話 綿貫一様(11/21投稿)https://kowabana.jp/stories/35514
第八話 珍味様(11/28投稿) https://kowabana.jp/stories/35523
第九話 車猫次郎様(12/5投稿)
https://kowabana.jp/stories/35534
以下、リレーに関する注意事項です。
注1、
本作の趣旨は、有志11名によるリレー形式でひとつの「怖話」をつくることです。
参加者多数のうえ、全体でかなりの長編になりますので、ところによっては怖さが控えめになる場合もあるかと思いますが、あくまで当初の目的としては「怖話」を目指すものであることをご理解いただけますと幸いです。
注2、
本作はアワードの対象からは辞退申し上げます。
また、リレー小説参加者は投稿作品に対して「怖い」ボタンを押すこと、およびコメントを書き込むことはいたしません。
注3、
企画に対してのお問い合わせやご質問につきましては、企画の窓口であるゴルゴム13様・ロビンⓂ様までご連絡ください。
本作の掲示板、およびリレー小説参加者個人のページでのお問い合わせやご質問は、ご遠慮下さいますようお願い申し上げます。